 |
●京都教育センター通信 復刊第 8号 (2007.1.10発行) |
川村 善之(京都市立芸術大学名誉教授)
憲法に基く教育基本法を、憲法存在のまま憲法に反する方向に改変することはその点だけでも筋が通らず、これは教育の観点ではない政治的意図を露骨にしたものである。
さて本題の、美術教育広くは芸術教育の個有の教育理念に関わる「人間観」と、その法的基盤でもある憲法の人間観について、今回の教育基本法改定の不当性、重大性を、紙数の範囲で述べる。
教育は人間の教育であることは言うまでもないが、その人間観は時代によって異り、現憲法以前と以後では革命的な変化があった。国あっての人間、国のために役立つ人間、「一旦緩急アレハ義勇公ニ報」ずる人間を育成する教育勅語時代の人間観から、人間あっての国、国民が主人公の国、人間のための国へ、国と人間の関係を転換したのが現憲法である。ところが今回、法律によって愛国心やその態度を国民に強制したことは、「人間観」を再び戦争の時代にひきもどす一歩をふみだすことである。
人間観についての表題の趣旨は、単に美術・芸術教育の問題にとどまらず、人間教育全体の問題であることは当然である。ただ日本の学校教育が主として教科主義教育によって行われてきたため、芸術教育は芸術教科だけのものに限定して見られ勝ちであるが、本来は画然と区別し切れるものではないこと前提とした上で、芸術と科学の本質の相違や、教育における人間との関わり方について、憲法の人間観が、美術教育の理念に強く結びつくものである点を強調したい。
科学を成立させる「知識」は、個々の知識を集めそれを体系づけ、積み上げてさらに高度な知識を獲得していく本質を持つ。科学的真実は、特定の人間が居る居ないに拘らず存在し、人間はそれを外から受け入れて学ぶ。一方美術は、ひとりひとり生きた人間が、内発的独自的な生命の自覚を、みずから形づくる創造活動であり、個々の人間が関わってそこにはじめて実現する。
また美術は人間能力の部分活動ではなく総合的で、個性的であり、はじめから全一のものとして本質を表現する。
人間が美術するとは、イメージの創造とその視覚的表現によって自己自身を再発見し、他者にも新しいメッセージを送る。美術の表現は、かけがえのない個々の、人間の主体が生み出す創造であるから、それはすべての人間に開かれた世界であり、そこでの個性の尊重はとりもなおさず人間そのものの尊重である。このような美術の特性を教育に生かすところが美術教育であり、美術教育が人間に直結する所以である。ただし誤解を避けたいことは、学習.指導の具体化では、表現を視覚化する素材や、技術や構成、それに関わる知識の教育を伴うことは当然であり、それは美術の本質をふまえて行われるのである。
美術教育が、人間の生きることを何にも代えられない尊厳とする人間観に成り立っていることを述べたが、入間は人と人の間即ち人間社会に生まれ、育てられたものであるから、社会と切り離した恣意独善の存在ではない。しかし人間を生かすべき国家が逆に人間をその心にまで立入り服従させ、支配できることになればそれは人間観の転覆であり、美術教育の理念にも相容れないものとなる。
生命を大切にする人間は戦争殺人に参加する人間にはならず、生命を軽視し、生命を省りみない国民をつくることは戦争の可能性を増大する。この意味で人間尊重を基盤とする芸術教育は平和の礎を築くものである。
かって国民が「忠君愛国、尽忠報国」の教育を受け、国のためとだまされ生命を軽んじたことが戦争を可能にした。
その十五年戦争の悲痛な反省から生まれた憲法の人間観を否定することは、平和に逆行することに他ならない。
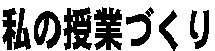
--『SATOBINのちょっとはずか史』--
佐藤敏正(京都府立乙訓高校)
「SATOBINのちょっとはずか史」は1995年4月、前任校の桂高校で発行し始めました。2000年4月現任校の乙訓高校転勤以降も同名で継続発行し続けることにしました。2007年1月7日付けのもので第12巻第17集通算№11,023までになりました。12巻というのは創刊12年目、第17集というのは2006年度の分が17冊目になったというこどです。冊子は約80から100号分で綴じ込むことにしています。
桂高校の後半から乙訓高校転勤以降約10年間は休みなく毎日発行してきました。 「ちょっとはずか史」は一言でいえば、私が担当してきた日本史・地理・政治経済・倫理の「教科通信」のプリント(B5サイズ)を冊子にしたもの、と言えます。桂高校で発行した当初は単発ものの授業補足用プリントのでしたが、量が多くなり、校内で大量に「生産される」裏白の紙を再利用して冊子にして配布するようになったのが今日の原型です。
現任校に転勤してからはB5サイズからA5サイズに変更し、自家製のA5サイズ専用版下用紙に直に手書きで書いていきます。これは気づいた時にその場で書き留めることがコツです。まとまったものを書く場合はパソコンを使います。
これまで私が書いてきたこと、載せてきたことを分類すると以下のようになります。
現任校での第六巻以降は、①授業の感想や要望・質問・「ちょっとはずか史」そのものに対する感想や意見、②担当する分掌(進路指導部)の関係で始めた放課後補習講座「乙訓小論文講座」に関係する新聞記事の紹介やマスコミ報道への問題提起、③筆者の日本史・地理などの教科に関する私の「研究論文」④筆者の日常や過去の出来事をエッセイ風に紹介する、などに力点を置いて書いています。
①はA5サイズをさらに半分にした専用の用紙を用意しておき、授業などで時々書いてもらい、回収してそのまま転載します。
なるべく本音に近いものを書いてもらうように促します。書いてもらう場合、一応テーマを提示し表しますが基本的に内容自由で書いてもらいます。事実でないこと、ひとを傷つけないこと以外は自由ということを明示します。書いてもらったものを転載する場合は、どんなに短いものでも必ずコメントを書き込みます。内容が「重い」ものの場合は、転載の可否を本人に問うことにします。またコメントでは言い足りない場合は本人への「回答」を別に書いて直接渡すこともと時としてあります。
「感想」他を書いてくれた生徒は私のコメントに興味があって自分のものが載ったものはよく読んでくれます。同時に、ふだんは仲良く付き合っている隣人たちの感想・意見に触れて、「そんなことを考えていたのか」と感じているようです。
これらは、生徒間および生徒と私の「キャッチボール」です。授業やふだんの学校生活だけでは触れあえないチャンネルでの接触です。
最近の生徒は討論らしいことができなくなり、自分の考え・主張を持てなくなっています。また仲良くしているように見えても「周囲に合わせているだけ」で本音の付き合いになっているかどうか怪しいと思う時があります。その意味で「ちょっとはずか史」は生徒間の貴重な交流の「ひろば」になっていると思います。
また、卒業生が学校に顔を出す時があります。出会えた場合は先ほどの用紙に在校生へのメッセージを書いてもらいます(シリーズ『卒業生来訪』というコーナー。連載進行中五六回)。これも好評です。OBとしての失敗談や後悔は下の学年の生徒にとっての「教訓」として読まれています。卒業生は「まだ続いているのか?」と言いながら書いてくれます。卒業生へのお土産に何冊か持ち帰っでもらいます。前任校の卒業生も時々登場します(なお現役・OBとも全員匿名です)。
②は日本史・地理などの授業にも資料として使用できます。また、時事問題の学習にも使えます。また小論文試験の予想対策としでも有効だったという受験生の声は何度か耳にしました。イラクでの高遠さん他の日本人人質事件での「自己責任論」や、最近の「ワーキングプア」「格差社会」などでの資料提供は好評でした。
③は、私自身の研究の報告であると同時に、生徒にはいわゆる「固い」文章や表現に少しでも接して欲しいことを意図しています。
山林の中で良木を探索しえ伐採し、椀や盆を轆轤(ろくろ)を使って製造する「木地師(轆轤師)」の文化と歴史を現地調査を踏まえて書いた「草刈義勇軍に行く」(100余回)、ティモールの独立までの動向を連載した「インドネシアウォッチング」(200余回)、最近では「安藤昌益のこと~不耕貪食から万人直耕へ」(現在進行中35回)、「マグロを買い漁る国」(同17回)などです。また、旅行その他で行く先々の地理的(?)「紀行文「冒険少年B ○○を行く」(同424回)などもあります。
④では、亡父の生き方や子ども時分の回想を述べる「土に生きる」(同485回)日常の出来事のエッセイ風「いつどこでそんなに」(同453回)、音楽と青春や社会を述べる「長くて曲がりくねった道」(同228回)、映画の話「映画三昧」(同65回)、現任校の校舎改築と40余年の歴史を述べる「乙高的惜春」(同四七回)などがあります。
生徒が持ち帰った冊子を保護者が読んでくれているということも耳にします。
以上のように継続ができているのは、私自身が負担にならない程度にしながら、前述した「キャッチボール」を楽しむことに徹しているからだと思います。「紙」で「生徒が変わる」などというだいそれたことは微塵も思っていません。生徒たちに対してこうして欲しいという私の「要求」は書きますが、それは結実することよりも霧散していくことのほうが当然なのだと思えば気が楽です。「紙」に過大な期待はしません。ただ、長い間継続し、考えるきっかけを提供していればずっとずっと先のいつかどこかで「なるほど」とか「そうだったのか」と思ってくれれば何かしら意味があるのかも知れない…。そう思います。軽く、長く書き続ける、これがいつまで続くかわかりませんが、私の密かなライフワークです。
|
[夏季から冬季に変更] 【集会テーマ】 ・改悪基本法の新たな情勢下で、人間を大切にする教育をいっそう推進しよう! ・「いじめ問題」「学力問題」など直面する教育課題を分析し、すべての子どもたちの豊かな発達を見とどける実践を交流しよう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【日 時】 2007年1月27日(土) 13:00~17:00 全体会 28日(日) 10:00~16:00 分科会 【場 所】 京都教育文化センター (京都市左京区 京阪「丸太町」下車東へ徒歩5分 京大病院南側、075-771-4221) *参加費(資料代として) 500円。(学生無料) 【日 程 ・ 内 容】 1日目 2007年1月27日(土) ◆10:00~12:00 プレ講座 教文センター302号室 「私の教育実践と支えた力」 藤原義隆(元京都市立小学校・教育センター事務局)
◆13:00~17:00 全体会 教文センター302号室 ○あいさつ 野中 一也(京都教育センター代表) 藤本 雅英(京都教職員組合執行委員長) 記念講演 「憲法・教育基本法とともに歩んだ私の教育:41年」 講師 野本勝信氏(元中学校長・京都府同和教育研究会会長) ○パネル討論 テーマ 教育改革の対抗構想を探る -教育の力で21世紀に平和と民主主義を再生するために- パネラーは、学校現場・研究者・地域運動の方々
◆17:30~ 交流懇親会 きびしい情勢に明るく展望してたち向かう2007年の抱負を語りあいましょう。どなたでも参加できます。 当日受付に申し込んで下さい。 2日目 2007年28日(日) 分科会 教文センター全館 ◆10:00~16:00 分科会(下記は予定)
|
京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。