 |
●京都教育センター通信 復刊第18号 (2007.12.10発行) |
教育センター高校問題研究会代表 中村 誠一
先日、宇治田原町でガードレールが百数十メートルにも亘って盗まれるという事件があった。鉄が値上がりしているのだ。それで思い出すことがある。
朝鮮戦争の頃、私は小学二年生。米軍からの軍事物資の受注が増え(いわゆる特需)、鉄や銅など金属の価格が高騰した。電線が盗まれるなどの事件もあった。鉄くずを売れば何がしかの現金収入になるとあって、大人に混じって子どもも河原や焼け跡に入り夢中になってくず鉄探しをした。私の家はガス会社の社宅だった。ある時、仲間の兄貴分が「ガス管なら高く売れるぞ」と言うので、倉庫に忍び込み、首尾よくガス管を持ち出した。くず屋は盗品と分かっていたと思うが、三十円ほどで買ってくれた。
そのうちくず鉄の値段が下がった。そんな時だ、知り合いのくず屋が、「またどこかで戦争してくれんかな」と言ったのだ。私は、「おっちゃんヘンなことを言うな」と思ったことを今も鮮明に覚えている。 鉄や銅が高騰する時、私はそこに戦争の匂いを嗅ぐ。あの宇治田原のガードレールはどこかの戦争で砲弾やクラスター爆弾になって子供達を傷つけるのだろう。
澤地久枝さんの本に「一九四五年の少女」という作品がある。その第二章「暮しの消えた日」に、戦争中、学校や家庭から金属製品が消えていく様が描かれている。山形県寒河江中学校の記録によれば、昭和十六年にはバケツ六五個、金火鉢大十個、同小十五個、溝蓋四個、窓格子(銃器室三十、物置四十)、日覆支柱(各教室十四、幹部室十一)、雨どい(職員自転車置き場)など、十七年度は、ラッパ、野球のマスク、ライン引き、庭球網張りハンドル、ワイヤロープ、引き幕用張り線など、十八年度には臨検が入り、校長室の金庫、鉄火鉢、鉄瓶、蛇口(生徒水のみ場、実験室)、講堂ドアの握り手、当直室カーテン金具、賞碑カップなどが回収されている。
実に寒々とした学校が眼に浮かぶ。臨検とはいつでもどこでも入れる権限を持つ役人の立ち入り検査で、拒否すれば懲役や罰金がある。各家庭では自由意志による供出とは建前で、臨検をちらつかされては、金盥から扇風機、花瓶まで供出を拒否できるはずもなかった。
新憲法発布の一九四七年の夏、文部省が作った中学生のためのテキスト「あたらしい憲法の話」の挿絵は感動的だ。軍艦や戦闘機、弾薬を戦争放棄のるつぼに投げ込んで鉄道や船、自動車にビルなどが次々に生み出されるあの挿絵。それを見た子供達はもちろんだが、教具や生活必需品をるつぼに投げ込み、弾薬や軍艦、戦闘機に変えさせられた教師や親たちはどんなにか感激し、うれしかったことだろう。
今また、鉄や銅が高騰している。しかし、学校や家庭から金属の回収などはない。他国の戦争だからだろうと、安心してはいけない。戦争をしたい人たちのやり方は狡猾だ。私には、病院や介護施設、障害者施設のベッドや設備を人間ごとるつぼに投げ込んで弾薬や戦闘機を作っている絵が透いて見える。歴史が巧妙に繰り返されようとしている。 軍事費を削って教育・福祉にまわせの声を今こそ大きくしなければと思う。
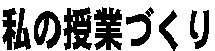
城陽市立富野小学校 片岡 真治
身近な自然を教室に持ち込んで
低学年の時期だからこそ多様な自然のおもしろさ・不思議さ・巧みさを五感を通して豊かにとらえることは、感性を育て、確かな認識力を育てるもとになります。それは、自然の事物にとどまらず、人や社会の見方や関わり方も含め発達の土台を広く豊かに構築していくことにつながります。一年生を担任したときは、入学式当日から草花や生き物を教室へ持ってくることを保護者にもお願いしています。
一学期には、親子で摘んだという草花やイモリやメダカ・ザリガニ・カブトエビ・カマキリ・ダンゴムシ・アゲハチョウの幼虫など様々な生き物が持ち込まれ、全員でさわったりえさをやったり、においを嗅いだり、食草を味わったりするとともに、絵や言葉、詩などで記録することができました。
卵から孵ったばかりの透き通った小さなメダカを見た子どもたちは、時間の経つのも忘れ見入りました。みんなの一言を集めて詩ができました。みんなで読み合って暗唱するとおもしろくなって次々に詩が生まれました。
食べることと結んで
春は、ヨモギを摘みヨモギ団子を、秋は収穫したサツマイモを使ってスイートポテトをみんなで作って食べます。お家へのおみやげにも大事に持って帰ります。お家でも家族と一緒に調理することが増えてきます。「サラダで元気」という国語の教材を学習したときも「元気サラダをつくったよ。」という子が数名いました。食べるものと言えば、イタドリ、ノビル、シイノミ、ムカゴ、学校にあるザクロ、カキ、何でも食べます。十一月には干し柿を作りました。渋柿を味わい「渋い」味を経験します。皮をむき、ひもを結んでつるして干すだけですが一年生にとっては難しい子もいます。でも、できあがると喜び勇んで干しに行きます。「何で甘くなるんやろ。」疑問は家庭や近所に尋ねるようにも進めています。
多様な自然に働きかける
動植物以外にも水や空気、磁石遊びを通して多様な自然、事物に触れることは大切です。生活の中でいろいろなところに使われている磁石の不思議さを取り上げます。磁石を使って学校中の「てつ」探しをします。磁石でもつかない物があることを知ります。砂鉄集めもします。
予想を持って探すことに熱心な子どもたちです。
作ることを取り入れて
物を作ることを通して、手と頭を鍛え、友だちと考え合うことや作る苦労、できた喜びを味わうことが非常に大切です。より長く廻るこま、よりよく飛ぶ飛行機、そこには作り直しや改良の工夫が必要です。教え合う中で、作ったぶんぶんごまが虹色に光り、廻り続けるのを満足そうに確かめる顔はすてきです。
毎日の学級通信で、これらの発見や取り組みを紹介したり作品を読み合ったりして家庭との連携も大切にしています。
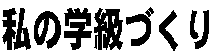
舞鶴市立岡田下小学校 水野 友晴
つい先日、十一月の授業参観日と本年度の岡田中学校ブロック人権教育研修会を兼ねた公開授業が本校で行われました。全学年が人権学習の授業公開をしましたが、私の担任する六年生では、昨年度岡田上小学校の五年生が取り組まれた『権利の熱気球』という参加型教材を扱いました。岡田上小学校の授業を拝見して、これは「グループの話し合い学習」にうってつけの高学年教材だと興味をひかれ、一年間心の隅に置いていました。案の定、子ども達はこのゲームに乗ってきました。そして、私の予想を超えて(いや、思春期前期の子ども達にとっては、この教材のもつ自然な、そして当たり前の結末だったかもしれないのですが)子ども達は真摯に考え合い、発表し合い、私の胸を「じーん」とさせてくれるような学びを展開してくれたのです。「こいつら、行動はあやふやなところがあるけれど、気持ち的には中学生になれるな。」という思いを抱かせてくれたのです。
ゲーム内容は、こうです。「グループで熱気球に乗って宝島を目指します。島を目前にして、ガス不足で気球が降下し始めます。眼下の海には人食い鮫がうようよしています。みんなの命を救うためには、荷物を捨てて気球を出来るだけ軽くして島まで持ちこたえるしかありません。さて、みんなに渡した十の権利を荷物としたなら、どれから順に捨てていきますか。グループでよく相談をして、協力して、制限時間内に捨てる順番を決めましょう。時間内に決められなければ、自分たちの気球は海に墜落したものとしてゲームオーバーとなります。」というようなものです。教材のねらいの中心は、「自分にとって捨てても良いと思う権利から捨てがたい権利までを選び、理由を述べ合い、意見を交わして、グループ内で一番ふさわしい(折り合いのつく)順番を決定しなければならない。」
授業の最後に「どのあたりから順番が決めにくかったですか。それはなぜですか。」をグループに問うたとき、どのグループも捨てがたい権利として選んだ権利が、「自分らしく生きる権利」だったのです。理由として「人にいわれるままに生きたのではつまらない。」との主張がなされて、私の胸を揺することになったのです。
さて、私たちの学校の重点研究(各学級の実態から研究テーマと教科を決め、「確かな学びにつながる授業を創る~学び合う子どもの姿を求めて~」を共通課題として取り組む。)や生徒指導、特別活動、読書活動、特別支援体制、その他多忙な中行われる学校行事の取り組みが、この『権利の熱気球』ゲームのように、「give and takeの精神」であり続けていきたいものだと日々願い、がんばっている昨今です。
--復活再刊18号を迎え、いっそう充実した紙面づくりに自薦・他薦の実践を--
1960年に設立された教育センターは、発足当時から学校現場と研究者をつなぐ「教育センター通信」を旺盛に発行していました。ところが事務局専従体制が崩れた1988年から、その発刊が見られず20年近い空白期がありました。昨年5月より復刊したのが今のスタイルです。往年の「深さ」には及びませんが、現場での教育実践紹介を中心に続けてきました。最近ではやっと「読んでるで!」といううれしい声を時々聞くようになりました。1面は研究者などの自由なテーマでの主張、2~3面は実践紹介、4面はセンターからのおしらせ。このスタイルでしばらくは続けるつもりですが、皆さん方からの「私の実践書いて」、「○○さんの実践載せて」の声を待っています。
| 年 | 月 | 1面(主張) 2面(授業づくり) 3面(学級づくり) |
| 2006年 | 5月 | 野中一也 久保 斎(京都市) 井上治夫(乙訓) |
| 6月 | 築山 崇 清水忠司(亀岡) 谷田健治(綴喜) | |
| 7月 | 室井 修 東 辰也(宇治) 大島辰哉(福天) | |
| 9月 | 市川 哲 仲西 亮(市高) 森本美枝子(府高) | |
| 10月 | 倉原悠一 和田 誠(丹後) 瀬戸亭明(与謝) | |
| 11月 | 春日井敏之 辻 信行(舞鶴) ―― | |
| 12月 | 高橋明裕 仁張美之(綾部) 三上 泉(船北) | |
| 2007年 | 1月 | 川村善之 佐藤敏正(府高) ―― |
| 2月 | 中須賀ツギ子 野村 治(綴喜) 堀 信子(京都市) | |
| 3月 | 勝見哲万 玉井陽一(福天) 三宅 匡(舞鶴) | |
| 4月 | 鰺坂 真 大八木賢治(京都市) 吉田義幸(船北) | |
| 5月 | 時田裕二 木村俊四郎(乙訓) 関口てるみ(福天) | |
| 6月 | 淵田悌二 小林幹弥(亀岡) 木村啓子(綴喜) | |
| 7月 | 藤本雅英 木村真留(宇治) 中野謙二(宇治) | |
| 9月 | 寺内 寿 後藤誠司(市高) 吉益敏文(乙訓) | |
| 10月 | 新谷一男 下田正義(乙訓) 松田森幸(相楽) | |
| 11月 | 関 民夫 中村雅利(京都市) 竹内明子(与謝) | |
| 12月 | 中村誠一 片岡真治(城陽) 水野友晴(舞鶴) |
12月22日(土)~23(日)教育文化センター(全館で)
【集会テーマ案】
「子ども・教育論不在の教育施策に抗し、未来をひらく教育を私たちの手で!」
――学習指導要領の改訂、学力テストの結果、PISA2006の検証を――
22日(土) 1日目は関西教育科学研究会が協賛:08年8月に教科研全国大会in京都 ▼10:00~12:00 プレ集会 「教師のよろこびと苦悩」 ▼ 吉益 敏文さん(第2大山崎小学校、京都教科研事務局長) ▼13:00~17:00 全 体 会 あいさつ:京都教育センター/京都教職員組合 ▼ 記念講演 佐貫 浩さん(法政大学・全国教科研副委員長) ▼ 「未来をひらく教育を私たちの手で!――教師の仕事と学力の形成」(仮題) ▼ ――学力テストシステムとどうたたかうか―― ▼ 実践報告 「子どもが輝く授業実践に学ぶ」 (小・中・高の現場教師から) ▼ ・野村 治さん(綴喜、田原小)・本庄 豊さん(宇治久世、木幡中) ▼ ・佐藤敏正さん(府高、乙訓高) ▼ ▼23日(日) 10:00~16:00 分 科 会 ▼ 〈教育センターの各研究会からの基調提起と実践報告〉 ――詳細は後日に―― ▼① 地方教育行政研究会 ▼② 生活指導研究会 ▼③ 学力・教育課程研究会 ▼④ 発達問題研究会 ▼⑤ 子どもの発達と地域研究会 ▼⑥ 民主カウンセリング研究会 ▼⑦ 高校問題研究会 ▼⑧ 教科教育研究会・国語部会 ▼ * 参加費(資料代として) 500円 |
||
教科教育研究会・国語部会[公開研究会]のご案内 11月25日(日)13:00~ 「第4回国語教育の危機、どうする!」 市内町屋「古武」にて ※「国語部通信」(年5回発行):定期購読希望の方は教育センターまで (無料で送付します) |
||
|
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。
特集 ◆検証 京都市の教育行政はこれでいいのか
◆養護教諭が担う役割--子ども理解と支援ネットワークの形成
●「ひろば 京都の教育」152号は、こちらをごらんください。
