 |
●京都教育センター通信 復刊第17号 (2007.11.10発行) |
京都市立高等学校教職員組合 執行委員長 関 民夫
九月三十日の京都新聞第三面下段に「ブルーベリーアイのわかさ生活」が「京都市の『子育て支援都市・京都』づくりを応援しています!」と称して大きな広告を載せました。「シリーズ『いま、京都から教育が変わる』全国をリードする京都市立高校改革」というもので、ご覧になった方も多いと思います。その広告のほぼ中央に「中学生のニーズに応える教育内容・入試システム」の見出しとともに「中学生の本来的な希望がほとんどない公立夜間定時制の定員を約三〇〇名相当減少」という記述があります。確かに、現役の中学三年生に進路の希望を聞けば最初から夜間定時制高校を希望する生徒はわずかしかいないでしょう。
しかし、それでは近年、複数の夜間定時制高校で、入学試験の志願者が募集定員を上回っていることを説明することはできません。特に、二〇〇七年度の入試では、洛陽工業高校での夜間定時制課程の募集停止を含めて、京都市内で一三〇名もの夜間定時制課程の定員が減らされ、その結果、桃山高校定時制普通科の一・六倍を筆頭に西京、伏見、朱雀の夜間定時制課程で志願者倍率が一倍を超え、二次募集でも一二六名の募集に対して一七五名が志願し、最終的には五五名の不合格者が生まれました。
このことは、「中学生の本来的な希望」がそのまま入学志願者数に結び付かないこと、ましてやそのことを理由にして夜間定時制課程の定員を減らすことなど許されないことを事実でもって示しています。
そもそも、戦後、新憲法と教育基本法が制定され、「教育の機会均等」が謳われる中で新制高校は発足しました。特に、定時制課程と通信制課程は「希望するすべての人たちに後期中等教育を保障する」ために、様々な理由で全日制課程に通えない人たちのために新しく設置されたものです。決して本来的な希望を持つ中学生新卒者のためだけのものではないのです。現に、今夜間定時制高校には、経済的な理由で昼間働かなければならない勤労青少年はもちろんのこと、小中学生時代不登校だったために全日制高校へ行けなかった人たち、引きこもりなど様々な理由で全日制高校を中退した人たち、若いときに十分な勉学条件に恵まれず子育てを終えて改めて勉強を始めたいと思った高齢者の方たち、などなど様々な人たちが学んでいます。このような人たちがこの広告を見ればどのような思いを抱くでしょうか。この広告の製作に携わった責任者の方たちに強い怒りを覚えます。
しかし、最大の責任は京都市教育委員会にあります。今、市教委がしなければならないことは、このような広告を使って夜間定時制潰しに狂奔したり、府教委と手を組んで恵まれた一部の生徒のためだけの高校入試改革を進めることではなく、戦後教育改革の原点に立ち返って、全ての生徒が高校教育を受けられるように行政の立場から制度保障をすることにあるのではないでしょうか。それができないというなら、もはや市政を変えるしかありません。
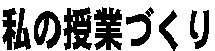
~保健「育ちゆく体とわたし」~
京都市立嵐山小学校 中村 雅利
水泳学習や一泊二日の野外活動を前にした子どもたちのつぶやきに、「自分の体がこれからどのようになるんだろう?」「お母さんって、どのように僕を産んだのだろう?」「僕の体、友達と同じなんかなぁ!」「みんなとお風呂に入るの?恥ずかしいなぁ」と素直な想いがみえます。
そこで、育ちゆく自分の体に関わって保健学習を行いました。授業のねらいとしては、性教育の年間指導計画をふまえ①体の発育と二次性徴 ②個人差と男女差 ③大脳の仕組み(ホルモン)に置き、四年でおさえる用語としては性毛・声変わり・月経・初経・精通・射精を展開の中で扱いました。
指導計画としては、第一次では絵本の表紙絵から見つけた子どもたちの姿について考えてみました。アフロの女の子、白杖をもつ女の子、松葉杖を使いながら歩く男の子、ラブレターを胸に携えた男の子など。自分たちの周りには、国籍や男女差を超えて、様々な子どもたちがいることを改めて考えました。「みんな、見た目の違いがあっても、いきているなぁ」と。
第二次では、担任の母子手帳を見せつつ、自分の生まれるまでの様子や生まれたときの状況を紹介しました。それを受けて絵本「あなたが生まれるまでに」(小学館)を読み聞かせました。その中で母体から聞こえる心音(テープ)を聞かせました。「すごい!心臓の音ってこんなん」「生きてる、赤ちゃん」などの声が。受精から、母胎の中で赤ちゃんがどのようにヒトとなってゆくのかをみていきました。
第三次は、子犬の誕生を扱った絵本「ぼくが生まれた」を読み聞かせ、母胎内の赤ちゃんの成育の写真をみせた後、男女の相違を外性器だけでなく意見交流しました。その展開の初めに男女の内性器を守る骨盤とその骨盤を扱いました。また、体つき、声変わりや胸のふくらみ、性毛などについて育ちと絡めて考えました。「性毛って、自分たちの体を守っているんやぁ、初めて知った」と。
第四次は、男女の内性器の名前とそのつくり、月経と射精の仕組み、自らの体に初めて訪れる精通と初経について考えました。「いつなるのか不安やけど、自分の体のこれからが分かっていい」と。
第五次では、自分の体や自分の内面を見つめる時期、思春期について、思春期を迎えた綴り方を読み上げてその想いについて考えました。授業の最後に「いのちのまつり」(サンマーク出版)を読み聞かせ、自らの命をどのように自分で守り、育てるのかを問題提起し終えました。
一連の学習の後、書いた想いある子どもの綴り方を紹介します。
「私は、この勉強で色々なことが分かりました。骨だけで女子か男子かが分かること。育ち方が違うこと。思春期は、誰もが絶対になること。やがて、自分の体にも絶対にそういう事が起きるんだと思いました。私は身長が少し伸びたのに体重が全然増えないので心配です。でも、保健で一番大切だと想わないとだめなのは命と命がつながっている事、命は一つしかないことです。命を粗末にしないで大切にしていきたいです。」
いつも子どもを真ん中にした学校づくりを
──そのキーワードは 〝つながる〟──
宮津市立由良小学校 竹内 明子
定年のゴールを1年余に控えた今、六つの小学校に勤務して学んだこと、考えさせられたことは枚挙にいとまがない。たくさんの子どもたち、保護者・地域の方々や仲間たちと共に歩んで、自分自身も励まされ、成長させてもらったと実感している。
◆一九七〇年に採用された私の新任校は、私の教師生活の土台となっており、京都新歓に参加してすぐに組合加入した。多くの青年教職員とともに公開授業や住民と共同するとりくみや運動を旺盛にやった。学校長も、戦前の軍国主義教育の反省と責任を果たすためにも民主教育をすすめる立場を標榜しておられた。
◆二つ目の学校は十二年間も在籍し、子育てをしながらも六年間は高学年を担当し、保育所づくりの運動などを今までとはちがう人びととつながり、母親教師としての立場を意識しながら頑張った。地域の主要産業である機業が不景気となり、生活上の困難を抱え込む子どもたちや親を励ましながら不安を隠して頑張る子どもの姿に私も励まされた。
◆三つ目の学校にも九年間お世話になったが、この頃には教育内容に及ぶ行政からの介入が露骨になり、到達度評価や算数での水道方式や平和教育などの項目にまでチェックが入るようになった。それでも父母・住民の学校への信頼は厚く、地区懇談会ではこうした教育をめぐる情勢についても率直に語り合い、子どもの立場で何が出来るかをいっしょに考えることができた。この学校で障害児教育を担当し、不登校の問題を含め課題を持つ子どものことを学校全体で考えてとりくむ「つながり」がここでも私を支えてくれた。
◆四つ目の学校では、主に障害児学級を担任し、軽度の発達障害を抱える子どもと歩み、「一人ひとりちがって当たり前」の視点で〝まるごとつながってとらえる〟ことの重要さを学校ぐるみで智恵を寄せ合い学んだ。しかし、この分野でも地域の障害児教育研究会を解体させいようとする行政からの圧力があり、私たちはこの研究会の存在価値の大きさを知っていただけに許し難いこととして頑張った。
◆五つ目の学校では、国・地方レベルでの教育政策の「様変わり」が激しく、文書提出などで多忙極まる日々を余儀なくされ土日もよく出勤し、最も大切であるべき授業研究やその準備は深夜か早朝にまわる実態にあった。若い先生も増える中で、ベテランの私たちがみんなの思いを代弁する立場で“もの申す役割”も担うようになった。多忙な中にあっても組合の学習会などにも参加し、週案ノートに勤務時間を書いたり、労働基準局を訪問するなどして行動することで打開を試みた。
◆そして今、六つ目の学校で子どもたちや職場の困難もたくさんあるが、子どものことでいつも話ができる職員室を心がけている。ここでもいつも希望をもって、ちょっとつらくなったら宮沢賢治の詩『私が先生になったっとき』を刻み込み自らを励ましている。
この三六年間を振りかえって、私は 〝つながる〟 ことで頑張ってこれたと総括している。
学びがつながって更に学びたいと/グチの声も含めて人とつながって/教科学習の中身もつながって/ひとつ一つの出来事もつながって。
12月22日(土)~23(日)教育文化センター(全館で)
【集会テーマ案】
「子ども・教育論不在の教育施策に抗し、未来をひらく教育を私たちの手で!」
――学習指導要領の改訂、学力テストの結果、PISA2006の検証を――
22日(土) 1日目は関西教育科学研究会が協賛:08年8月に教科研全国大会in京都 ▼10:00~12:00 プレ集会 「教師のよろこびと苦悩」 ▼ 吉益 敏文さん(第2大山崎小学校、京都教科研事務局長) ▼13:00~17:00 全 体 会 あいさつ:京都教育センター/京都教職員組合 ▼ 記念講演 佐貫 浩さん(法政大学・全国教科研副委員長) ▼ 「未来をひらく教育を私たちの手で!――教師の仕事と学力の形成」(仮題) ▼ ――学力テストシステムとどうたたかうか―― ▼ 実践報告 「子どもが輝く授業実践に学ぶ」 (小・中・高の現場教師から) ▼ ・野村 治さん(綴喜、田原小)・本庄 豊さん(宇治久世、木幡中) ▼ ・佐藤敏正さん(府高、乙訓高) ▼ ▼23日(日) 10:00~16:00 分 科 会 ▼ 〈教育センターの各研究会からの基調提起と実践報告〉 ――詳細は後日に―― ▼① 地方教育行政研究会 ▼② 生活指導研究会 ▼③ 学力・教育課程研究会 ▼④ 発達問題研究会 ▼⑤ 子どもの発達と地域研究会 ▼⑥ 民主カウンセリング研究会 ▼⑦ 高校問題研究会 ▼⑧ 教科教育研究会・国語部会 ▼ * 参加費(資料代として) 500円 |
||
教科教育研究会・国語部会[公開研究会]のご案内 11月25日(日)13:00~ 「第4回国語教育の危機、どうする!」 市内町屋「古武」にて ※「国語部通信」(年5回発行):定期購読希望の方は教育センターまで (無料で送付します) |
||
|
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。
特集 ◆検証 京都市の教育行政はこれでいいのか
◆養護教諭が担う役割--子ども理解と支援ネットワークの形成
●「ひろば 京都の教育」152号は、こちらをごらんください。
