 |
●京都教育センター通信 復刊第 6号 (2006.11.10発行) |
春日井 敏之(立命館大学)
奪われたいのちを悼むことから
いのちに関わる少年事件が起こるたびに、少年の生育環境、発達課題、人間関係、社会的背景などについて論議がなされる。他方では、何事もなかったかのように日常生活が流れていく。こうした中で、私たちがまず大切にすべきことは何か。それは、犠牲者が身近な人であればあるほど、かけがえのないいのちが奪われたことを、自分の五感の全てに今までの経験を重ねて悼み、子どもたちと共有していくことではないか。
また、加害少年について気になる点がある。それは、第一に、大人とのつながりの実感の乏しさと同世代からの深い疎外感を持っていること。第二に、よかれと思って親や教師がしてきた早くからの自立の勧めが、しばしば少年を追い詰め、孤立につながっていること。第三に、相手の気持ちが読み取れない、イメージできていないこと。第四に、受験・就職競争が激化する中で、様々な発達課題を持った子どもたちが追い詰められ、生き辛い状況が広がっていることである。
子育てと教育の原点を問い直す
不登校やいじめ、荒れや少年事件など、思春期の子ども達が成長の過程で起こす様々なトラブルは、一つの危機と言える。 同時にそれは、関わり方次第で、成長のきっかけになっていく。子どものトラブルは、大人へのSOSであり、子どもが誰にどんなSOSを求めているのかを考えることから、子ども理解と具体的な取り組みが始まる。
子どもの危機に際して、親や教師の姿勢で大切にしたい原点が三つある。それは、私たちは今まで何を大事にして生きてきたのかを確認していくことである。第一は、「いのちより大事なものはない」ということの再確認。第二は、「見返りを求めない愛」を注ぐこと。第三は、「どんな時もあなたの味方」という姿勢を伝え続けることである。
つながりの実感はどこから
子どもたちは、どんな時に大人や友達と「確かにつながっている」と実感しているのであろうか。
第一は、文句なく楽しいことを友達と一緒にしているときである。自分の身体と心を目いっぱい使い、汗をかきながら仲間と楽しく遊んでいる子どもの姿は、まさしく自己肯定感の塊ではないか。同時にこうした遊び体験には、みんなが楽しくなるために決めたルールがある。少年期から思春期にかけて、ぶつかり合いながら、何度失敗しても排除されたりすることなく、失敗付きの練習ができる集団を日常生活の中に作っていくことが、学校や家庭に求められている。
第二は、負の感情や体験が出し合えたときである。子どもたちは、気遣いや抑圧された日常生活を重ねる中で、「悲しい、つらい、腹が立つ、不安、いらつく」といった負の感情や体験に蓋をしながら過ごしていることも多い。その結果、少年事件といった形で不幸な暴発をしてしまうことも起きてくる。むしろ、日常的に親や教師に悪態をつきながらSOSを出し、見捨てられずに関わってもらった子どもは、早期にいい出会い直しとつながりを体験している。
その一方では、みんなの前では気遣いをしながら明るく元気に振舞い、辛いことは密かに「心の専門家」に聴いてもらい、また何事もなかったかのように日常生活に戻っていくような青年が増えてはいないか。誰にも相談できず、受け止めてもらえないときには、摂食障害やリストカットという形で、自分の身体を傷つけながら、必死にSOSを出している姿も見られる。
そんな時に、負の感情や体験を表出し受け止めてもらうことで、他者は共存的他者となる。同時に、それまで翻弄されてきた感情や体験を相対化し、自分にとっての意味を問い直したり、安心して悩んだり、一区切りをつけることもできるようになるのではないか。
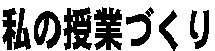
舞鶴市立高野小学校 辻 信行
本年度四月から、少人数授業を担当することになりました。一週間の授業時間数は、二十時間。毎日三年から六年の算数を四時間担当。三年は、二学級を三集団に、四年から六年は一学級を二集団に。集団の編成は、均質(これも変な言い方ですが・・・・)。つまり、習熟度に応じた固定的な集団編成をとらず、子どもの学力や学びの実態について学級担任と話し合い、集団を編成しています。
授業(学習)は、人格形成の場
わたしたちの学校でこのような集団編成をしているのは、「授業(学習)は、一人ひとりの子どもの学びを学習の出発点にして、子ども相互の学習で学びを広げる場」と位置付けているからです。学校の中心的な教育活動である授業では、子どもたちにある限定された学力を、効率的に獲得させるというのではなく、相互の学習での学びあいの中で思考力をつけ確かな認識をつちかうだけでもない、『人格形成』につながる多様な人間的な学びあいを育てたいと考えるからです。
少人数授業・制度の問題点
昨年度までは、学級担任の立場からこの制度を見ていましたが、今年度はその当事者になって改めて、多くの問題点がある制度だと思わずにはおられません。
まず第一に、授業でつまずきがあっても回復指導や家庭学習が機敏に取りづらいことです。担任ではないので、保護者との日常的な連携にも課題があります。
次に、従来から言われていたことですが、担任との打ち合わせの時間を勤務時間内にとることが困難で、多忙化に拍車をかけています。その他、言い出せばきりがないくらい様々な問題点があります。
少人数担当として
「少人数担当の任務・・・。」などと言われるのですが・・・。
『今日は、こんな学習だ、ぼくの考えをみんなに伝えたい。尋ねてみたいこともある。先生やみんながどんなことを言ってくれるか楽しみだ、先生はどんなよさを探してくれるかな。』
子どもたちが、こんな気持ちで教室にやってくるようにと願っています。まず、大切にしたいと思ったのは子どもとの信頼関係です。できるだけ声をかけ、様々な話題で話ができる関係をつくることを心がけています。教室には、絵本、皿回し、風車、化石と恐竜・・・何でもありの癒しの部屋。
そして、何より、自分で考え、友達からもいっぱい学べるような授業の工夫。一人ひとりの子どもの学びのよさを常に誉めることを心がけてきました。
学習に困難を抱えている子には、最後まで付き合い、個別に学び方や個人学習の課題を与え励ますことを続けています。
学校全体の算数科の教育課程や実践についても、提案しながら合意形成をはかっています。『学期・年間を通した習熟・定着のための家庭学習プリント』『学期末学力診断テスト』『発展的な取り扱いを生かした数と計算領域のカリキュラム』など。
やっぱり、子どもたちと
いろいろな研究会に行く機会が増えましたが、今だに「集団の固定的な習熟度別授業」で様々な「成果」が上がっているかのような報告を聞きますが、授業の中での子どもの学びの様子を見る限り、わたしには「成果」が、見えてきませんでした。どの子も、確かな主権者として育ってほしいという願いとかけ離れた「学力」「国語力」「・・・。」という声もむなしく聞こえます。
『今日も一番!』と元気よく教室に飛び込んでくる子どもの声を励みに、子どもたちとの日々を楽しみたいと思います。
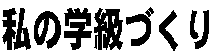
11・3円山集会で報告する鰺坂真氏 |
寄せられた賛同ハガキの数々 |
 (写真は9・23討論集会) |
日時 11月25日(土) 13:00~16:00 場所 京都教育文化センター 101号室 京阪丸太町下車東へ徒歩5分 講演 「フィンランドの教育から学ぶこと」 --父母とともにとりくむ学力保障実践 山口妙子先生(東大阪市立英田小学校) 実践報告 京都教研集会の「学力レポート」から 主催 京都教育センター「発達問題研究会」「学力・教育課程研究会」℡・Fax075-752-1081 |
|
 |
148号 発売中 (2006年11月1日発売) 特集テーマ 1 性と生を考える--現代の社会・文化といのちの教育 総論で小学校の現場からの実践報告があり、それを踏まえて、各論で今日の性教育にかけられている攻撃の特徴や、京都での性教育の取り組みを紹介する予定です。 2 中学校・高校生の進路選択・進路指導--社会他の出会い方 |
|
| ・購読希望者には見本誌を送付します ・定期購読者は年間会費2960円(4冊分)を年一回郵便振替で ・T&F075-752-1081かEmail:kyoto-kyoiku@asahi-net.email.ne.jp へ申し込んで下さい [氏名・学校名・自宅住所・電話を] |
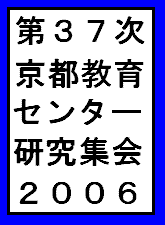 |
第37次京都教育センター研究集会[夏季から冬季に変更] 【集会テーマ案】 ・教育基本法の動向に注視しながら、教育基本法を生かした学校、教育のあり方を検証する。 ・「いじめ自殺問題」「学力問題」「高校未履修問題」など山積する今日的課題を解明し議論を深める。 ・すべての子どもたちの豊かな発達を見届けるさまざまな実践や運動から学び合う。 1月27日(土) 13:00~17:00 全体会 教文センター302号室 ◇ 講演 「憲法・教育基本法とともに歩んだ私の教育:41年」 野本勝信(元中学校長、京都府同和教育研究会会長) ◇ パネル討論 「今、改めて教育の役割を考える」父母・青年教師・学生・研究者のパネラー 1月28日(日) 10:00~16:00 センター各研究会の分科会 教文センター全館 ◇ 実践報告と討論 ①地方教育行政研究会 ②生活指導研究会 ③学力・教育課程研究会 ④発達問題研究会 ⑤家庭教育・カウンセリング研究会 ⑥高校問題研究会 ⑦子どもの発達と地域研究会 ⑧教科研究会・国語部会 ※ プレ集会:27日(土)10:00~12:00 藤原義隆氏(元京都市内小学校)「私の教育実践」 ※ 交流懇親会:27日(土)17:30~(会費制、場所未定) ◆この研究会は教育に関わる人、誰でも参加できます。今から来年のカレンダーにメモを! |
| 京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com ・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |