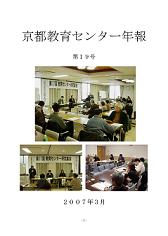 |
京都教育センター年報 第19号(2006年度) 第三部 京都教育センター 生活指導研究会 2006年度研究会活動の経過と概要 2007年度研究活動の方針 築山 崇(生活指導研究会) |
|
1.活動のまとめと方針 本年度の活動は、京都教研生活指導分会への参加、教育センター第37回生活指導分分科会の企画・運営が主で、研究例会については、年度内3月に「いじめ・自殺問題」の分析、子ども・保護者の意識分析などをテーマに予定している。 教育センター生活指導分会では、前回に引き続き「社会的排除」を視点に、生活指導実践のあらたな全体構想を探求していくことと、「いじめ・自殺問題」の第1次的な集中討議を行うことを課題に設定した。2006年11月の京都教研生活指導分会では、「いじめ・自殺問題」は実践報告や議論の大きな柱にはならなかったので、今回のセンター研究集会に位置づけた。 センター研究集会での、生活指導研からの問題提起は、次のような骨子である。
2. 「排除の力」に抗して「自律と自立」を実現する生活指導の実践・理論の探求 (1)子どものアイデンティティ(他者の存在との関係での自己確証)形成 (2)抑圧・排除されている他者との協同的・組織的な活動に取り組むことによる自治の力の形成(「学校における様々な集団づくりのとりくみ」) (3)地域づくり活動での子どもと大人の協同 2007年度は、この提案を基調にしつつ、「いじめ・自殺問題」の実態の客観的な分析と実践構想の探求を字愚に進めていくこととする。 なお、従来からの研究会の基本課題 ①今日の社会・経済状況が生み出す、子ども・青年をめぐる問題状況の分析 ②国の「教育改革」動向の分析、生活指導研究の課題の解明 ③研究会の組織強化 も踏まえ、また、教育基本法改悪後の教育関連法律の改悪、行政指導などによって現場に生じる問題の分析や対応にも力を入れていきたい。 国立教育政策研究所の「生徒指導体制のあり方についての調査研究報告書 規範意識の醸成を目指して」(2006.5)の内容は、「規範意識の醸成」に重点がおかれているが、その内容は、権力的強制の性格の強いものとなっている。 この点は、改悪された教育基本法が、学校教育における規律の重視を条文に含んでいることや、「教育再生会議」の提言を受けて、文科省が、「体罰の範囲の見直し」に言及していることなどとあわせて、生活指導(生徒指導)にかかわる重要な問題を含んでおり、今後の重要な研究課題である。 3.研究会体制 代表 加藤西郷(大) 築山 崇(大・事務局) 会員 浅井定雄(小・地域)、荒木巌(舞鶴教育センター)、石沢雅雄(小)、大平勲(教育センター)、小倉昭平(中高・大)、春日井敏之(大)、北村彰(中)、楠凡之(大)、倉本頼一(大)、近藤郁夫(大)、高垣忠一郎(大)、玉井陽一(小)、西浦秀通(高)、中井和夫(小)、中山善行(学童保育・地域)、野中一也(大、教育センター)、横内廣夫(中高)、吉田一郎(大)、山口高明(中高) 他 略 *なお、事務局強化のため、新たな研究者の入会についてセンター事務局でも協議を進めている。 |
||
|