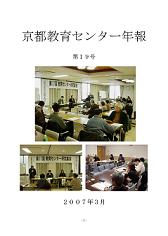 |
京都教育センター年報 第19号(2006年度) 第三部 京都教育センター 活動の報告 京都教育センターの活動・2006年度総括 大平 勲(京都教育センター事務局長) |
|||
1.第37回京都教育センター研究集会 今回から、全国教育研究集会が8月開催になったことなどにより、開催時期を8月末から1月末に変更しました。06年12月に教育基本法が「改悪強行」されたもとで、この間の運動の到達点に確信を深めながらも新しいステージでの運動と実践をどう構築していくかが課題となる時期での集会でした。
このふたつのテーマのもとにプレ集会・全体会・分科会をもち、二日間でのべ218名の参加があり10年ぶりに200人を超える研究集会として成功しました。[一日目の3企画にはのべ178名(実参加102名)、二日目の分科会には116名の参加] ◇ プレ集会[1月27日(土)10:00〜12:00]60人 ―センター研としては初企画― 藤原義隆氏(前教育センター事務局)が『私の実践を支えた力』と題して京都市小学校教員38年間をふりかえって感動的にその実践と教訓を語られました。A3判28枚(裏表印刷)の「ミニレポート」と模造紙びっしりの「教材」をもとに、「今、厳しい時代には違いないが、私の時代もそうであったように頑張れば展望を見いだすチャンスが来ている。情報や実践をセンターに結集して交流を図れば希望がみえてくるはず」と力強いエールを送られました。藤原氏自身が呼びかけられた教え子とその父母、同僚、先輩、後輩、研究会仲間など埼玉、岡山、大阪、滋賀からも参加され、エピソードや学んだことをコメントされました。 ◇ 全体講演[1月27日(土)13:00〜15:00]61人 センター野中代表、京教組藤本委員長のあいさつのあと、野本勝信氏(元城陽市立中学校長、京都府同和教育研究会長)が『憲法・教育基本法とともに歩んだ私の教育:41年』と題して講演されました。 野本氏は、戦後間もない頃から青年教師として平和憲法を礎にした授業や学級通信の実践を生き生きと語られ、また、自主的民主的な京都の同和教育を推進していく苦労話などを淡々と語られました。ここでも北城陽中学校長時代の父母や教員から野本氏にまつわるコメントがリアルに話されました。 ◇ パネル討論[1月27日(土)15:00〜17:00]57人 「教育改革の対抗構想を探る」テーマのもとに、この一年間の教育基本法闘争を総括しながら、教育の権力的支配が一層強まることが予測される中で新たなステージでの教育運動・活動を見通す議論を深めました。 パネラーの本田久美子氏(市教組左京支部)は、この間の左京におけるたたかいの前進や学校現場の課題、京都市教育委員会の独善的手法を具体的に話されました。江本佳世子氏(新日本婦人の会右京支部)は、新婦人としてのこの間の教育とりくみを報告され、小中学生の母親の立場から今の学校生活で気がかりなことを率直に語られました。コーディネーターを兼ねた築山崇氏(京都教育センター)は、研究者の立場から改悪基本法のもとで予測される問題点をはね返す新しい視点での展望がどこにあるのかを明快に語られました。フロアーからも6人の方が、報告や決意を述べられました。 ◇ 7つの分科会[1月28日(日)10:00〜16:00]116人 2.教育基本法改悪反対のとりくみ 改悪は強行されたものの、反対闘争は教育府民会議(センターも参加)をはじめ幅広い団体や個人でかつてなく大きく構えて、2回の円山集会(6/4:800人、11/3:4000人)の久しぶりの成功など府民的関心と盛り上がりを示しました。 教育センターとしても「改悪待った!5・27緊急集会」(63人)[野中代表の問題提起]、科学者会議京都支部と共催しての「改悪反対9・23討論集会」(54人)[石井拓児氏(名古屋大学)の講演]を開催しました。 また、9月18日に鰺坂真氏ら20氏を呼びかけ人として『現行「教育基本法」の理念を否定し、教育の目的を覆す「教育基本法改正法案」の廃案を求めます』との緊急アピール(別掲参照)を発信し、学者・大学人、教育研究者、文化人、宗教者、法曹界、元学校長、元組合役員、各種団体など京都の有識者1200余人に送付し、科学者会議京都支部の協力も得て、教育センターを事務局として、アピール賛同を求めるとりくみを一ヶ月半にわたって旺盛にすすめました。約半数の方々からの返信が寄せられ、回答者の98%を超える572名がアピールへの「賛同」を表明されました。また、二百数十名からの多額のカンパも寄せられ、それらを基金として教職員組合とともに11月3日付けの京都新聞に意見広告として発表しました。 3.公開研究会の開催 今年度から、各研究会とセンター事務局が共同して企画、宣伝・組織、運営などにあたる「公開研究会」を開催しました。各研究会の特性を生かしながらもテーマ性をもった内容で、幅広い層の参加を見ることができましたが、系統的な企画に不十分さがみられ今後の課題となりました。今年度は次の内容で実施しました。
4.教育研究集会への参加 第56次京都教研集会(11/11、12京都教育大)には、二日間でのべ55名の共同研究者の参加があり、各分科会での役割を果たしました。新しい研究者の参加で昨年まで配置できなかった分科会をいくつか克服しました。また、京教組の民主教育推進委員には20名(7/1)、22名(11/4)の参加がありました。しかし、埼玉での全国教研集会には共同研究者としての参加があったものの、センターとしての参加組織はできませんでした。第15回全国教育研究交流集会(10/8,9 東京)には代表、事務局長が参加しました。 5.季刊誌「ひろば・京都の教育」の発行
これらを特集にして今年度も季刊4回の発行をすることができました。定期読者は新規読者の拡大が数十部みられたものの退職者などの減誌分をカバーするに至らず引き続く課題です。 6.出版活動 ・ 「京都教育センター年報」第19号を2007年3月に発行し、京教組定期大会代議員、共同研究者、各県研究所などに配布しました。 ・ 今年度から20年近く休刊状態にあった『センター通信』を復刊し2006年5月より月刊ペース(8月は休刊)で発行し、全組合員、関係者に配布しました。[1面:研究者の主張 2面:「私の授業づくり」 3面:「私の学級づくり」 4面:センター報告]。 ・ その他、各研究会でのニュースなども発行。 ・ 討議資料として「学力テスト・学力問題」を提起(1/27)、各職場に配布。 7.研究活動 8つの研究会がそれぞれ独自に研究活動を展開しています。 8.資料室の整備・活用 この間、淵田前事務局長の尽力で資料室の整理がすすみ、センター関係の出版物や全国研究所からのレポート、雑誌「教育」「季刊・教育法」などのバックナンバーが整備された。また、昨年より連携を開始した歴史学大学関係者とのとりくみも深められた。8/5には関係者14名が集い、資料室の現状と活用についての研究会を開き、11/12には京都教研特別分科会として「1950年代の教育から学ぶ」を開催し15名の参加で戦後民主教育の変遷についての歴史的継承を確認した。また、鰺坂真氏、木村万平氏から貴重な文献・資料の寄贈がありました。 9.事務局体制 ・ 開設3年目に入ったホームページは管理担当者、浅井定雄氏の尽力により更新のテンポアップがはかられ、多くの関係者にセンターの諸活動を幅広く紹介している。また、メールの活用が一段とすすめられ「ひろば」や「センター通信」の原稿送付や連絡伝達などに機能している。 ・ 事務局会議(13名構成)は3週間に一回のペースで定例化され、毎回7割程度の出席のもとに議論を深めてきた。企画検討会議(月一回ペース)や拡大事務教会議(学期一回ペース)も計画的に開催されてきた。センターの体制や規約問題、長期的な展望などについて引き続き議論を深める必要がある。 [体制] ◎代表 野中一也(大阪電気通信大学名誉教授) ◎副代表 室井 修(近畿大学教授) ◎研究部長 築山 崇(京都府立大学教授) ◎「ひろば」編集長 春日井敏之(立命館大学教授) ◎事務局長 大平 勲(元公立中学校教師) ◎事務局次長 中西 潔(元公立中学校教師) ◎事務局メンバー 野中一也 室井 修 築山 崇 春日井敏之 市川 哲 高橋明裕 中須賀ツギ子 倉原悠一 淵田悌二 深澤 司 大平 勲 中西 潔 浅井定雄 事務活動担当として小田貴美子の協力を得ています。 ◎各研究会体制(略) |
||||
|