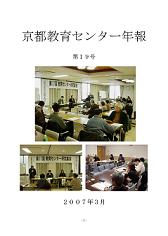 |
京都教育センター年報 第19号(2006年度) 第三部 京都教育センター 発達問題研究会 2006年度研究会活動の経過と概要 2007年度研究活動の方針 西浦 秀通(発達問題研究会) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2006年の活動経過 2003年には、インターネットや情報機器・道具の普及などと併せて「コンピュータ社会に生きる子どもたちを取り巻く環境」について検討、2004年は「インターネット時代と子どもたちの認識・発達」に関して、2005年は「ケータイ文化と子どもたちの発達環境」に関して、子どもたちの文化という視点から学習と議論を重ねてきた。2006年も、引き続き「子どもたちの発達課題と地域環境」に関して、研究と議論を継続した。 具体的には、月例の研究例会での学習や報告者を招いての「発達理論・発達を取り巻く環境」の研究を背景に、また、運営委員会での議論と問題提起を踏まえ、地域研との合同で7月8日(土)に公開研究会「地域で育つ子どもの発達を考える −「城陽生きもの調査隊」の活動から学ぶ− 」を開催、田中昭夫さんから「城陽生きもの調査隊」の活動や参加している子どもたちの様子について、具体的な活動・報告にもとづいた現状理解の討議を行なった。特に、子どもたちの活動を中心にしながら、親たちを組織していっている点に注目した。 公開研当日は、「城陽生きもの調査隊」の報告に加えて、<「子ども、発達、教育、地域」 棚橋啓一さん(地域研)>と、<「コミュニティにおけるアイデンティティの形成 ―格差社会の中でブラックボックス化する発達課題― 西浦秀通(発達研事務局)>の内容で、二つの研究会から主催者としての研究報告を行い、子どもたちがおかれている学校・地域社会という「生育環境」の視点から、実践・実態報告にもとづいて議論を深めた。 また、「発達の現代的課題」をより広い視点から俯瞰することを目的として昨年度秋から取り組んできた「北欧の教育」研究を継続し、11月には前年同様に学力研との共催で、「フィンランドの教育から学ぶ」をテーマとした教育研究会(第10回公開研究会)を開催した。山口妙子さんが「フィンランドの教育と教育基本法・私の教育実践」と題して講演、全教が実施したフィンランド教育視察団に参加した時の様子や、教育基本法を生かした学校現場での自らの実践を報告、続いて、後藤誠司さんが「フィンランドの学校を訪れて」と題して報告を行い、競争しないで学力世界一になったフィンランドの教育事情を詳しく紹介した。 その後の討論では、フィンランドの教育から学ぶべき点、日本の教育に生かすべき点などが話し合われ、その中で日本の現行教育基本法のすばらしさを改めて認識し、改悪を許さない決意などが話された。充実した研究討議を行なうことができ、今後の研究活動の展望を開いた。 昨年度の活動の記録は、以下の通り。
2 2006年のまとめ 2006年度も前年度に引き続き、研究の焦点を「思春期の子ども」に合わせ、さらに 1 認知的能力 2 身体的・運動的能力 3 現代社会の中の思春期 という3つのテーマに沿って研究活動を進めることを追求した。 また、「子どもたちの発達課題と地域環境」という前年に引き続いた研究から、子どもの発達の危機的状況が議論されるなかで、子どもたち自身の「様変わり」も指摘されてきた。子どもの内面の変容とともに、子どもたちの居場所(環境)も狭くなってきており、「どうして外で自然に触れて遊べなくなったのかをきちんと見極めること」が必要だという認識から、地域研に公開研共催を呼びかけ、共同での議論を重ねた。 その中で、地域での子どもの姿の希薄さが気になること、学校教育限定ではなく子どもの生活全体を見直すこと、与えられた「体験学習」ではなく子どもたち自身の好奇心や意欲を喚起する場をどうすればつくることができるのか、といった問題意識を踏まえ、公開研究会「地域で育つ子どもの発達を考える」を開催、田中昭夫さんから「城陽生きもの調査隊」の活動報告を通じて、学校外での子どもたちの様子や育ち(発達)についてもお話頂き、具体的な活動・報告にもとづいた現状理解の討議を行なった。 公開研当日は、地域研からの報告に続いて、発達研での研究経過や情勢及び運営委員会の問題意識などについて、<「コミュニティにおけるアイデンティティの形成 ―格差社会の中でブラックボックス化する発達課題―>と題して研究会事務局として研究報告を行い、議論の背景としての「モラトリアム心理の変化」や「無職者比率の増大」、また、傷つける・傷つけられるという関係の中で子どもたちが過ごしている状況があること、現状対策としての「学校のセキュリティの強化」「登下校時の監視」、「子どもの安全」というときの加害者である「大人」がどのような筋道を通って成長してきたのか、といった課題、あるいは、これまで検討してきた「最近接発達領域」「正統的周辺参加」について報告、「人のつながりの弱さ−地域がこわれている」また、「自然の生き物と子どもとの関わり」「地域でいかに学ぶのか何が育つのか」などの検討課題も提起した。 当日の議論では、活動や参加している子どもたちの様子について、特に、子どもたちの活動を中心にしながら、親たちを組織していっている点に注目した。公開研終了後も月例研究例会で堀井篤さん(元立命館高校)に「奥丹での地域活動から」の報告をして頂くなど、「地域で育つ子ども」に関しての議論を継続し、合同研究会、センター冬季研での合同分科会など、「人間発達の土壌としての学校・地域」について、地域研との共同の取り組みが続いている。 「子どもたちの成長発達と取り巻く環境」に関しては、「発達の現代的課題」をより広い視点から俯瞰するために、中山善行さん(学童保育連協)に「『子どもの権利とは』を深める−クラップ氏(国連子どもの権利委員)講演から」を、浅井定雄さん(教育センター)に「子どもの発達と憲法・教育基本法」を報告して頂くなど、テーマを絞り、あるいは研究テーマそのものを発展させる側面からも、定例の活動(研究例会+運営委員会、公開研、センター研)を軸に多彩な内容で原則的な研究を継続してきた。 また、昨年度より取り組んできた「北欧の教育」のシリーズでは、月例研究例会で小倉昭平さん(元同志社高校)に「北欧の教育にふれて−2005年夏、北欧訪問の報告」の内容で報告して頂き、北欧の制度などを検討しながら、子どもたちの発達と教育環境についての議論を深め、秋には公開研究会「フィンランドの教育から学ぶ」(学力研との共催)を開催した。こういった「教育制度」や「環境」としての学校や社会環境の影響の重要な意味も含めて、今後も認識・発達についての研究を発展させて、その課題を明らかにしていくことになっている。 【研究に関して】 研究を進めていく上で、以下の視点を確認してきた。 1 発達理論に基づいているか 2 社会的教育的な情勢・状況を把握しているか 3 子どもたちの実態に基づいているか 4 教育現場が求めているものになっているか 5 研究成果の活用の展望 そして、研究活動を今後どのように社会や教育現場に還元していくのか検討し、研究内容の記録・得られた研究成果を冊子か本にまとめて、組織的な研究を継続していくことになっている。 3 2007年の活動方針 2007年度も「思春期の子ども」研究を継続させていくことを確認している。当面「発達の現代的課題」、「人間発達の土壌としての学校・地域」について、定例の研究例会を学習の場として活用、すでに設定している。この間、この研究会のあり方を捉え直して発展させようと議論もあり、実務作業のための運営委員会についても、学習討議の場としての研究例会についても、「発達保障」の観点からの理論的な学習も含めて議論を繰り返してきている。また、前年までの「インターネット時代と子どもたちの認識・発達」「ケータイ文化と子どもたち」「子どもたちの発達課題と地域環境」「北欧の教育」に関する研究の継続も求められている。 今後も、「現代の子どものコミュニケーション」「自主活動と社会的発達」など、これまでの報告や研究を踏まえ、また会員の意見を広く取り入れながら、学校教育や社会環境など発達をめぐる問題を精力的に検討していきたい。 加えて、多忙化の中で月例開催を継続していくのかといった研究会運営や会員組織に関すること、あるいは研究会活動と教育センターとの連携など、改善・整理していく課題についても、活動の中から議論を深めていくこととなろう。 4 研究会組織体制と構成員 ・代表者 宮嶋邦明(京都府立大)、築山崇(京都府立大) ・事務局 関谷健(元田辺高校)、西浦秀通(伏見工高) ・運営委員 浅井定雄(教育センター)、伊藤晴美(嘉楽中)、小倉昭平(元同志社高校)、北村彰(東宇治中)、久保田あや子(音羽中)、中山善行(学童保育連協)、人見江利子(京都府立大院)、和気徹(向陽高) ・会員 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|