 |
●京都教育センター通信 復刊第19号 (2008.1.9発行) |
「スーパーのちらし」の読み取りで学力はつくのか!?
滋賀大学教育学部 倉本 頼一
1、「これならもう要らない」学テ結果発表
文科省は十月二十四日、四十三年ぶりに実施した全国学力テストの結果を発表しました。新聞では「得意の知識、活用は苦手」(毎日)「知識及第活用に課題」(朝日)と内容「A」(基礎)に比べて「B」(応用)が低かったと報道しましたが、これは予想通りの結果で、文科省の意図通りだったといえます。
全国都道府県の平均点の順位発表は、地域点数競争を煽ったものといえます。「地域・経済格差が影」「秋田・福井が好成績、沖縄・大阪低迷」(朝日)「最下位沖縄失業率離婚率も高く」(毎日)文科省の発表でも「就学援助を受けている子どもの多い学校の成績が低い傾向がある」等、今日の経済格差が教育格差、学力差を生み出していることは、学テを実施しなくても自明のことではないでしょうか。
これらの調査結果について、新聞の社説が「目的も活用も見えぬ」(京都)「これなら要らない」(神戸)と主張したのも当然といえます。
2、「スーパーチラシ」の読みで「学力」つくか
「次は、今村さんの家に配られたお店のちらしです。よく読んであとの問いに答えましょう」「一、今村さんはお店のちらしの内容を友達に説明しようと思います。その説明としてふさわしいものを次の1から4までの中から一つ選び、その番号を書きましょう」
これが学力テスト小学校国語「B」(応用)最後の問題です。結局「2.サンドイッチは、ふだんの一つぶんの金額で二つ買うことができる」を選べというのです。「B」の問題は全部で四題ありますが、1は「学級会記録」、2は「わくわく新聞」(かべ新聞)、3は「読書感想文二つの比較、4がこのスーパーのちらし」問題となっています。どこにも「物語文」「説明文」「作文」の教材も読みとりもないのです。このような問題で国語の学力がつくのでしょうか。
3、PISA問題と「学テ」内容は別物
文科省は、03年の経済協力会開発機構(OECD)の学習到達調査(PISA)の結果「読解力低下十四位」にショックを受け05年「読解力向上に関する指導資料」を発表し「読解力」に力を入れるよう力を入れてきました。今回の学テの国語内容「B」も「PISA型だ」と宣伝していますが、形は似ていても、その内容は違っています。
なる程小学校国語Bの3は二つの文を比較する問題ですが、PISAの問題が二つの「落書き」についての意見に対し読み手の考えを問うているのに対し、学テの問題は二つの「読書感想文」の「良い書き方」を求める問題です。PISAのいう読解力「リテラシー」は常に読み手の考えを文章で表現させますが学テは「二つの文」比較の形だけ真似ているのです。2の「わくわく新聞」のごみ問題も「わたしたちの身近なところからごみを減らす」「自分でもできる取り組みを書きましょう」と世界の紙・板紙の資料をあげておきながら「ごみ減らし」の「心がけ」に問題を矮小化しおています。PISAの問題は、常に社会との関わりを大切にした応用問題をテキストにするのと根本的に違っています。
4、学テ型学習内容重視の危険
現在、京都府下各地で学テ対策が「学力向上」という名で強化されています。「うちの学校は平均点より低かった」「学テ内容と結果を分析して成績アップの取り組みを」と圧力が教師にかけられてきています。
国語教育の学力は「文学教育」「作文教育」「言語・説明文教育」の積み 重ねの中でこそ培われるものです。
(図は、学テ6年国語「B」より)
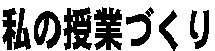
与謝野町立江陽中学校 太田垣 靖
文化祭で各学年20~30分程度の英語発表会を7年間取り組んだ。生徒達が日常の授業で取り組んでいる Small Talk, Short Speech, Show & Tell, Recitation 等の自己表現の力を総合的に高めていく場として、また共通の学習目標の達成に向けて生徒同士の学び合いや協働学習を創造していく機会としても大切な取組となっている。
内容は、英詩の朗読、構成詩、英語劇など多彩である。1年では助動詞 Can の学習を深めるために We Can Stand (水俣病を扱った教材)を学習する。この学習を通して生徒達は自作の構成詩を上演した。構成詩の最後は、 We Can Stand の合唱であった。 We Can Stand の作詞者へ上演ビデオを贈り、その後生徒との交流が行われた。
ある年の2年生は、神戸の中学生が書いた Cheer Up Kobe! (神戸大震災の惨状と復興への願い)を構成詩につくりかえて上演した。アメリカ同時多発テロの翌年、3年生が Mutchan (防空壕で死んだムッちゃん)を上演した。
教科書の平和を取り扱った読み物教材“ A Mother's Lullaby ”の授業では、吉永小百合さんの『第2楽章』の学習を通して、生徒達は広島の原爆投下がいかに非人間的な暴力であったかを学び、 Mutchan を演じる大きな足がかりを得た。 Mutchan を演じた男子生徒の“ I Want To Live! ”(もっと生きていたい)の言葉は、生きたくても生きることを許されなかった少女の平和を願う悲痛な叫びとして、また、平和な未来を次の世代に受け継いでいく私達大人への強烈なメッセージとして、6年経った今でも私の脳裏に刻み込まれている。
市販の脚本は時として語彙やボリューム等中学生が演じるにはレベルが高すぎる場合もある。 Run! Melost(走れメロス)や Toshisyn (杜子春)を演じた生徒達の場合もそうだったが、レベルの高さが生徒達の意欲や学び合いを高めたりすることもある。生徒同士の関わり合いや学び合いが深まることで、一見困難に見えるレベルの高さも克服され、彼らの達成感や次への学習の意欲につながる。
取組の中で生まれる生徒同士の信頼感や存在感が学習レベルを高める上で重要な要素であることをさらに確かめていきたい。11月の文化祭に間に合わせるために、1学期には脚本の完成、キャストの決定を終え、夏休みに自主学習も含めた台詞覚え、そして2学期からは当日に向けて授業や総合的な学習の時間を使った本格的な取組が始まる。
ALTも英語・演技両面からの援助を行う。時間も労力も費やし体力勝負の取組ではあるが、生徒達は英語力や演技力を高めながら、同時に学び合いを通じて学級集団のかたちもつくりかえていく。英語学習のスキルアップの面だけがもてはやされる傾向にある。英語学習を通してどのような学力を育てるのか、学習意欲をどのように高めていくのか等、授業論や教材論を実践的にとらえなおす研究活動の推進が求められている。
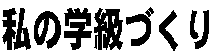
八幡市立八幡東小学校 内海 公子
「先生。本当は私、すっごく悪い人なんです・・・・略・・・この際全部言っちゃうけど(先生は全部お見通しだと思う)実は・・・最初内海先生のことがすっごく嫌いでした。でも今は違います。信じてもらえるかどうかわからないけれど、本当に感謝しています。・・・他の先生は、ストレスがたまるばっかりだったのです。・・・略・・・」(2007・6月 5年A子)
一昨年4月、始業式後の*年*組は、冷めた目で私を観察する女子とただ騒ぎ立てる男子、38名のクラスでした。親しげに声をかけてくれる子は空気の読めない子(KY)と言われていました。「だまれ!うるさい!ぼけ!」が中心メンバーの言葉で、私は毎日首にホイッスルをぶらさげて授業をしていました。毎日の日記や朝の会の歌や図工の絵にも「なんでせなあかんのや!嫌や!」ばかりでなかなか前に進みませんでした。先生なんて信じられない子どもたちが、そう簡単に心を開いてくれるはずがありません。
私の心もだんだん暗くなる中で、初めて描いた絵が「おじぞうさん」でした。私への慰めのために取り組んだのですが、これが信じられないくらい子どもたちに受けたのです。形も色も単純ですが、のり絵の具を指につけて描くと生き生きとした作品が生まれました。無意識の中に子どもの願いが絵に込められたのでしょう。この頃から少しずつ子どもたちが変化し始めました。あんなに嫌っていた毎日の日記も定着してきました。私はせっせと赤ペンを走らせました。事実の羅列の中にも子どもの姿が見えてきました。日記を載せた通信「よせなべ」を心待ちにする子どもが増えてきました。子どもたちも私という人間がわかってきたのでしょう。夏は泥戦争で夢中になって遊び、サッカー大会優勝パーティは保護者を交えてしました。
秋、紙粘土で自分の分身(顔)を作ることにしました。何時間もかけて、全て手作りの分身(顔)が出来上がったときの一人一人の表情は、一つのことをやり遂げた喜びで輝いていました。自分の再生産ができたのです。出来上がった自分と対面することで自分に対しての愛情がわいてきました。同時に友達に対する気持ちにも優しさがみられるようになり、いじわるやけんかも随分減りました。
3月はこの一年の絵本を作りました。C子は「*年*組が変わった理由」という題で、いじめがあったクラスの様子と自分の心の変化を絵と文で表現しました。
2008年から東小は八幡小と統合されます。その最後の年、私は念願の持ち上がりができました。東小での思い出をたくさん残そうと、体育館でお泊まりをしたり、東小の思い出の場所をたくさん描きました。私も子どもたちと一緒に校門の桜の木を描きました。秋の学習発表会と音の祭典に向けて、自分たちの姿を残そうと自分たちで歌を創りました。子どもたちが作詞・作曲した歌「今までのときを」を私は涙を流しながら指導しました。そんな私を38人の子どもたちがしっかり見つめてくれました。
子どもの「今」をしっかりつかみながら、子どもの持つエネルギーを引き出し、人や自然や物に豊かに関われる力として伸ばすこと、特に中学年(発達の節目)のこの時期は思考をくぐって「~する」ことを十分体験させることが大切だと思います。
様々な表現を学ばせることと芸術教育の力が大きいと痛感しています。友と心一つにして、声を声を重ねる喜び、自分の世界を自由に生き生き描いたり作ったりする喜び、全身で表現できる喜び、そしてそれらを仲間と共感できたら子どもはきっと変わると思います。表現そのものが子どもの人格であり、表現することは生きる力なのです。
「・・・・略・・・私は、こんな生活にうんざりなんだ。この一年で変わったと思う。それは自分と向き合えたからいろいろなことに取り組めたんだと思う。この一年間は私にとって大切な大切なときだったと思う。」(2007年3月 D子)
追伸、あと三ヶ月で私も子どもたちも東小を卒業します。
--第38回センター研究集会:二日間でのべ203人が参加--
夏季から冬季に変更されて二回目のセンター研が12月22~23日に開催。改悪教育基本法を後ろ盾に不条理で非教育的な教育施策を現実のものとしない展望を見いだすのが今集会のテーマ。参加者は学期末を終えた直後にもからずのべで200人(全体会85人、分科会116人)を上回り、今集会への期待が大きいことを伺わされました。
最近少なかった学校現場からの参加ものべ50人を超え、研究者や退職者・教育関係者などとの意見交流に新鮮さを受け止めました。また、今回は関西の教育科学研究会(来夏の全国大会を京都で開催)も協賛されたことで大阪、和歌山、兵庫、滋賀などからの参加もあり意気込みが示されました。
◇ 一日目の全体会では3つの企画があり、いづれも管理と閉塞を打破するエネルギーの所在を明確にしました。
Ⅰ.プレ集会:「教師のよろこびと苦悩」:吉益敏文さん
最近の教師なら誰もが一度は経験する「こんなはずではない」、子どもや父母とかかわる実践上の苦悩の体験を正直に語られたことが共感をよびました。そして、職場の同僚に胸をひらいて聞いてもらったことが支えとなりトンネルを抜け再起動する経緯をリアルに示されました。
Ⅱ.記念講演:「未来をひらく教育を私たちの手で」:佐貫浩さん
| 私たちの前に今大きく立ちふさがる「新自由主義教育観」に対抗する人格像や価値意識をどう押し出すのか、そうした視点に立つ実践のありようを明確に語られた。今後、強調されるであろう「コミュニケーション力」や「国語力」また、「習熟」のあり方についても歪んだ教育学を正面から批判しつつ我々の側からの概念の構成が求められている。その具体的実践についても紹介され、管理と閉塞の教育シフトを打破していくあれこれではない明快な筋道を示され、参加者に展望を指し示されました。 |
Ⅲ.授業実践報告:野村さん、本庄さん、佐藤さん:子どもの輝きが見える実践
3人の実践は吉益さんや佐貫さんの提起を裏付け、検証するリンクした報告として注目されました。楽しい授業であることを意識しながらも、子どもの実態分析や教育の科学性がはっきりしており、「子ども同士の学び合い」「受験に走らない面白さ」「生徒が自信を持つ学習展開」などをリアルに語られました。
◇ 二日目の分科会では教育センター各研究会の企画で8分科会が行われ、現職教職員、研究者、学校外の教育関係者などから28本のレポート報告がありました。分科会の詳細は「センター年報20号」(08年3月刊)で報告します。
教育センター顧問 室井修氏(73歳)ご逝去 今春より療養されてましたが薬石の効なく12月8日にお亡くなりになりました。 室井先生はセンター設立来のメンバーで半世紀にわたり教育センターの地方教育行政の分野を中心に学校給食の教研共同研究者など幅広くご尽力頂きました。 謹んでご冥福をお祈り致します。 |
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。
特集 ◆検証 京都市の教育行政はこれでいいのか
◆養護教諭が担う役割--子ども理解と支援ネットワークの形成
●「ひろば 京都の教育」152号は、こちらをごらんください。