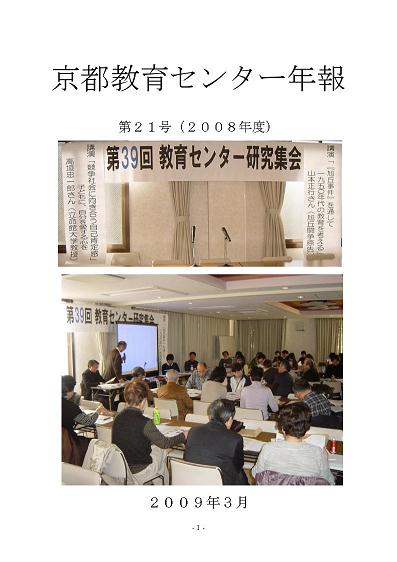 |
第8分科会 報告
国語教育の危機、その変質と私たちの実践 浅尾紘也(教科教育研究会・国語部会) |
|
|
||
「国語教育の危機、その変質と私たちの実践」 国語教育分科会で、何が提起され、何が論議となったか 2009年1月25日の第39回京都教育センター研究集会・国語教育分科会 は、「国語教育の危機、その変質と私たちの実践」をテーマに、府下からだけでなく、大阪や私学の参加者や、文学活動を進めておられる方の参加もあり、15名の参加でもたれた。 私たちは、これまで、「国語教育の危機」に対してどう考え、どのように理論的実践的にそれらに対していくのかの論議をふかめてきたが、「全国一斉学力テスト」、「改訂学習指導要領」など、その危機的な状況がより具体的に姿を現し、それの流れが大きなものになろうとしていることをより危機感をもって見、対していくことが大切だと考えている。 今年の国語教育分科会の提起と論議は、それをよりふかめるものとなり、国語教育の危機がより深刻なものとして進められ、決して子どもたちを人間的に成長させ、人格形成を進めていくものではないことが認識できるものとなった。 自己紹介から始まった分科会討議は、午前中、二つの提起をもとに論議が進められた。 提起1 最初の得丸提起は、「指導要領『国語』分析のために」と題しての、改訂学習指導要領・国語科がもつ問題点を端的に指摘した提起であった。 これまでのさまざまな審議会などの審議経過の資料や答申やまとめなどを丁寧に追いながら、その本質が、 ①指導要領全体に大きく貫かれている「愛国心教育」の観点から、国語科が「愛国心注入教科」としての任務を背負わされているものであること ②そしてこれまでにももっていた技能主義技術主義的が、PISA調査を意識しての、「哲学」も「理論」もない形で各教科にはそれが意識されたと思われる教材が正に「満載」という状況の中で、国語科にはより強くそれがさまざまに入り込んでいること が提起された。また、それがより具体的に「文科省のQ&A」や指導要領・国語科の文言の中にどう具体化されているか など、詳細に提起された。 また、現在編集が進み、来年度採択となる国語教科書が、昨年末に提示された教科用図書検定審議会の「報告」では、「学習指導要領に示された教材選定に当たっての留意事項に基づき、国語科及び外国語の題材の充実が図られるよう、検定基準上明確化する」と明文化し、国語教科書が改訂指導要領・国語科のもつ大きな問題点をそのままもつものとなる危惧を抱くと提起した。 提起2 続く浅尾提起は、「『PISA型学力』『PISA型国語力』とは何か」と題して、改訂学習指導要領・国語科がもつ問題点のひとつであり、それが「全国一斉学力テスト」の国語問題に具体化されていると考えられる「PISA型」と言われるものが、もともとOECD調査では、「読解リテラシー」として提示されたものが意図的にその本質が捨象され、その形式だけが強調されていく経過と、そ こでの情報操作や言語技術ばかりが問題とされていることを提起した。 そして、それが、 ①「言語の学習」をますます蔑ろにし、「ことばの力」の基礎をつみあげていくことを軽視して、「活用」の名の下に、国語教育における「基礎・基本」の崩壊をすすめている ②そしてそれが、「言語技術教育」一辺倒の指導となっていくことで、国語教育の構造と内容の崩壊をめざす方向となってきている ことなどを提起した。 論議の中で 二つの提起を受けての論議の中では、具体的に「研究指定校」の研究発表での「PISA型」についての発表が、参加者には理解できないものであったり、その批判が会場から発言された時に大きな拍手が起こるような状況があり、「PISA型」を先進的に進めているということがいかに軽薄なものであるかを実感したことなども出された。 また、現行の学習指導要領・国語科から言われ始めた「話す・聞く」が国語科指導の「基礎・基本」であることが、国語教育を技能的技術的にとられて、それをより強調していくためのものであったこと、「全国一斉学力テスト」の内容をもっと深く検討していくことが必要であることなどの質問や意見が出され、討議された。 また、国語教育がこのような状況にあること、このような大きな問題点をもつことをこれまでなかなか知ることはできなかった。それを、一人の市民としてどのように広げていけばいいのか考えたいという発言もあった。 提起3 論議に先立って、西条提起は、「国語教育の現状と課題」と題して、京都市内で1月に集中して開催された小学校での「公開研究会」などの参観や資料で、いくつかの国語研究発表で、何がどのように出てきているのかを提起した。 そこでは、「伝え合う」という語も残っているものの、「PISA型」という語が「PISA型読解力を高める指導を通して」などと用いられ、それを強く意識しての授業やとりくみが提示されてきていること、そしてそれらがこれまでのものと大きく変化してきていることが提起された。 たとえば、ある小学校では、文学作品「ごんぎつね」を教材として、その「読書会」のために、「登場人物の気持ちがわかる叙述」として、観念的なことばがあげられ、「心の距離」として、ごんと兵十の心の距離がハートマークを動かすことで表され、ごんの気持が何が何%(たとえば、寂しい気持○%、よかったという気持○%・・・等)として表すことをしたうえで、それを発表し合うというようなものがあったと報告された。 また、このように文学教育が本来の姿を変えていくことを強いられてきていることは、他の分野でも同じであろうし、説明文教育では、これから輝かしい「日の丸」が目立つこと、例えば、「スポーツ」や「海外協力」などなどが取り込まれていくことは想像に難くないことも指摘された。 現場よりの発言・・・・略 論議の中で 西条報告での京都市内の「研究」そして、その「発表」の状況が、これまでとはかなり進んだもの、改訂学習指導要領・国語科がもつ観点を忠実に具体化したものであることを再確認させられたものであることが論議された。 たとえば、「ごんぎつね」の実践は、「PISA」を強く意識したものであり、「読解リテラシー」としての出題項目である「情報の取り出し」「解釈」「熟考・評価」を、指導過程そのものに機械的に当てはめたものであることも指摘された。ここでは、文学作品を「形象として読む」ことは考えられて折らず、その表現は「情報」としてしか扱われていない。したがって、子どもたちに「ことばの力」としてついていき、それが「ことば」で人間や社会を理解し、自分に取り込み、自分の成長のエネルギーとしていくことはできないことが指摘された。 そして、このような状況の中で、現場では何にどのように取り組んでいくのかを考えていく大切さも提起された。ただ、それが「読書」や「補習」「宿題」などという、時間を増やすこと=量的対応ばかりではなく、国語教育として何にとりくむか=質的検討をふまえてのものであることの大切さも意見として出た。 このように、「ことばの力」の基礎となる言語の学習は教材として配列もされず、説明文論説文を「論理」として主体的に読まず、文学作品を「形象」として、「絵と感情」におきかえながら読む(形象・イメージとして読む)ことなく、さらに自分の実感・生活に根ざして表現するために書くのではなく、単に情報を伝えるために書く技術をつけるだけの指導で終わる国語科指導は、もはや国語教育ではない。 わたしたちがめざす「人間的成長をめざす国語教育・人格形成の国語教育」は、その構造と内容を、「言語教育(言語の学習・説明文教育)」「文学教育」「作文教育」の三分野でとらえ、そこでの「ことばの力」を「論理としてのことばの力」「形象としてのことばの力」「生活としてのことばの力」をつけていくことをめざしての実践を進めていくことである。 国語教育の危機的状況にあたって、それをさらに広く提起していきたい。 (詳細については「京都教育センター年報 21号(2008年度版)」をごらんください。) |