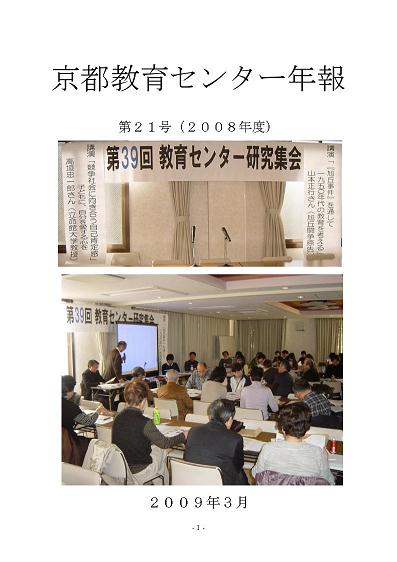 |
第5分科会 報告
子どもにとってはすべてが育ちの場 PARTⅢ -地域の教育力- 姫野 美佐子(子どもの発達と地域研究会) |
1 基調提案(姫野美佐子) 私たち「子どもの発達と地域研究会」は、今年もテーマを「子どもにとってはすべてが育ちの場」としました。家庭・地域・学校・塾・習い事・スポーツクラブ…さまざまな、子どもたちの行く場所に大人がいて、何らかの関わりをしています。その中から、「これは、ゆっくりお話をきかせてもらって、みんなで話し合いたい」ということを、私たちはいつも探しています。今日もふたつのレポートを通してみんなで学びあいたいと思います。 私自身、3歳の子どもの親となってからは、世の中のこと、とりわけ子どもを取り巻く環境に非常に敏感になり、また不安な気持ちも持っています。それは、昔の日本が持っていた「みんなで子育て」という習慣は年ねん薄れ、子育てに関わる多くのことが「自己責任」にされているからです。何かあったときに私個人の責任にされるのではないか、という不安もありますが、何より「人と人との結びつき」が薄れていることを感じるのが、悲しいのです。言うまでもなく、人は人との間で育つのですから、子どもたちには多くの体験や人間関係を与えたいと思うのですが、それがままならなくなっていることも、私を不安にさせます。 私のように感じている方、あるいはまた別の角度から不安や心配を抱えている方はいっぱいいらっしゃると思います。しかしまた、そう言った人たちが、新たな希望を見いだせるようにと願ってこの研究会を続けています。 研究会の名前になる「地域」ですが、私たちはこれは単に地理的な「地域」を指すのではなく、「子どもの発達の場」「生活の場」として、ひろい意味で使っていきたいと思っています。ですから、本当にいろいろなところで「子どもの発達」ということについて考えることができると思いますし、どなたでも参加していただけると思います。 一つ目は、森さんのレポートです。森さんは、ふたりのお子さんが不登校となり、ながい間学校と家との間でいろいろなことを考えてこられた、その率直な気持ちをレポートにされました。私たちに投げかけられるテーマが多いレポートだと思います。 二つ目は、上京区にある小学生とその親のグループ「メイク・ピース」について、お母さん達からのレポートです。「ちびっこプール」から始まったつながりの中で、子どもたちは毎週集まって勉強していますが、「学校の勉強」ではありません。でも、とてもいきいきしている子どもたちの様子が伝わると思います。 最後に、ご参考までに今日の議論の柱を提起させていただきます。 1.2つのレポートそれぞれから見えてくる、具体的な子どもの発達の姿について。どのような 関わり方によって、子どもがどのように変わってきているのか。 2.子どもの発達に、学校や地域はどのような役割を果たしているのか。「集団で育つこと」の意義について。 3. さまざまな場所で子どもたちと接している大人が今後、どのような形で つながりあっていけるだろうか。 もちろん、この3つに限らず自由に発言して頂いていいのですが、少しだけこの3つを頭にいれておいてください。 2 報告① 「学校って何なんだろう?」森明美・・・・略 3 報告② 地域の生活、人間関係とその育児力、教育力(棚橋啓一)・・・・略 4. 最後に 新しい参加者も迎え、2本の深い内容のレポートをたたき台に、今年も良い議論ができたように思います。感想文はありませんでしたが、参加者の討論での言葉にあるように、それぞれ「教育とは何か?」という問題をするどく突きつけてくれる内容でした。学校現場と地域がどうすればもっとつながれるのかについても、複数の方から発言がありました。現場の先生が忙殺され、主体性を失わされそうな状況で必死に働いていることに、深いため息がきこえてくるようでした。しかし、地域の側からの呼びかけももっともっと工夫して、できるかもしれない、とそんなことを考えました。みんなで知恵を出し合っていきたいと思います。 (詳細については「京都教育センター年報 21号(2008年度版)」をごらんください。) |