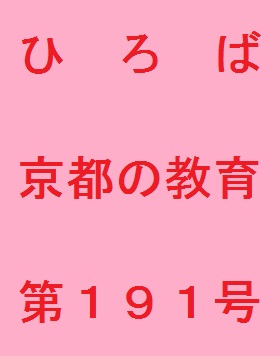
新しい学習指導要領、特別の教科「道徳」を考える
総論 ~検定で、教科書は どう変えられるのか?~
石山 久男
(子どもと教科書全国ネット21常任委員・元歴史教育者協議会委員長)
1.「道徳」の本来のあり方と「特別の教科 道徳」の問題点
小学校は2020年から、中学校は2021年から、高校は2022年から新学習指導要領が実施されるが、2年前倒しで小学校は2018年から「特別の教科 道徳」が実施されます。
1)「特別の教科 道徳」の学習指導要領で示された内容
「徳目」については一覧表になっておりますように、「特別の教科 道徳」の新学習指導要領では、こういう内容を学ぶということになっています。
| 小学校 | 中学校 | |
| A.自分自身に関すること | 善悪の判断・自律・自由と責任 正直・誠実 節度・節制 個性の伸長 希望と勇気・努力と強い意志 真理の探究 | 自主・自律・自由と責任 節度・節制 向上心・個性の伸長 希望と勇気・克己と強い意志 真理の探究と創造 |
| B.人との関わりに関すること | 親切・思いやり 感謝礼儀 友情・信頼 相互理解・寛容 | 思いやり・感謝 礼儀 友情・信頼 相互理解・寛容 |
| C.集団や社会との関わりに関すること | 規則の尊重 公正・公平・社会正義 勤労・公共の精神 家族愛・家庭生活の充実 よりよい学校生活・集団生活の充実 伝統と文化の尊重・国や郷土を愛する態度 国際理解・国際親善 | 遵法精神・公徳心 公正・公平・社会正義 社会参画・公共の精神 勤労 家族愛・家庭生活の充実 よりよい学校生活・集団生活の充実 郷土の伝統と文化の尊重・郷土を愛する態度 我が国の伝統と文化の尊重・国を愛する態度 国際理解・国際貢献 |
| D.生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること | 生命の尊さ 自然愛護 感動・畏敬の念 よりよく生きる喜び | 生命の尊さ 自然愛護 感動・畏敬の念 よりよく生きる喜び |
大きくは、ABCDと四つの分野に分かれており、小学校・中学校で多少言葉が変わっていますが、だいたい基本的には同じような内容です。教科書の中に、この徳目に関わるいろんな教材がずっと並べられています。
2)「道徳」とはなにか
この問題点を考えるにあたって道徳というのは、そもそも何なのか、ということを考えておく必要があります。「道徳」というのは本来、社会や自然についての科学的な認識、そしてその科学的な認識を身につけるための学習、それと自分のさまざまな生活体験が結び合わされた上に、初めて成り立つものだと言えます。
科学的な認識にもとづいた自主的判断力を育てていくのが、本当の意味での道徳教育ではないかと思います。
3)「特別の教科 道徳」の内容の問題点
それに照らして、「特別の教科 道徳」の徳目の内容を見ていきますと、いろんな問題が見えてきます。
① たとえば、「道徳」の内容のC「集団や社会との関わりに関すること」には、どういう項目がそこに並んでいるかというと、「規則の尊重」というところから始まります。中学校の方では「遵法精神」というところから始まっています。ここでは規則やきまりというものは、すでに完成し与えられたもの、これは守らなければならない当然のものとして、その上で規則というのは守らなければいけませんよ、というのを教えるのが「特別の教科 道徳」の中身です。ですから、規則とか法律というものができるには、本来何らかの必要性がありますが、そのことについては、一切問わない、というのが道徳の「徳目」の中身になっている訳です。
その反面、今みんなが幸せに、どんな人も等しく幸せに生きる環境をつくるということを考えたとすれば、本当に大切なのは、平和とか人権とか、民主主義とか、平等とか、自由とかだと思うのですが、ここには一切でてこないです。ここに象徴的に現れている訳で、その代わりにさらに出てくるのは「伝統と文化の尊重」「国を愛する態度」「国際貢献」、つまり今の政府が考えているある特定の考え方やその価値観、これが非常に尊重されていることになる訳です。この道徳の内容そのものが、そういった意味では非常に偏ったものになっていると言わざるを得ないと思います。
② 二つ目は教科書ができるということです。今まで「道徳の時間」というのはありましたけれど、道徳は教科ではなかったので、教科書はありませんでした。文科省はまず「心のノート」というのをつくり、今は「私たちの道徳」というのをつくって、国の費用で印刷して、全国のすべての小中学生に配付しています。これは、あくまでも扱いは「副教材」です。ですから、これを使うことを強制することは法令的には出来ません。今のところは使って使わなくてもいい。その代わりに教科書以外の県とか市町村とかでつくっている副教材とかがありますので、そういうのをとりまぜて使ったりしているというのが実情だろうと思います。
ところが、今度は「教科書を使わなければならない」というようになります。ですから、それ以外の自主的な教材、副教材は非常に使いにくくなる。教科書は全部やらなければならないという圧力が非常に強くなると思います。
③ 三つ目は教科書ですから、文科省の検定を受けて合格しないと教科書としては認められない訳です。ところが各教科、たとえば国語とか算数、理科、社会というのは、その教科の基になっている学問体系というものがあります。文学とか国語学とか、数学とか、自然科学、そして歴史学とか政治学とか経済学とか、そういう学問体系があって、それに基づいて教科の内容が形成されています。その学問的成果から離れて、勝手につくる訳にはいかないです。たとえば歴史の教科書の検定をやっていますが、ここに「神武天皇は実在していた」ということを「書け」というような検定意見は、これは絶対につけられない訳です。それは、事実と完全に違うということがはっきりしていますから。そいうことは教えられない訳です。
だけど、道徳というのはそういう基になる学問体系がないので、いわば文科省が先ほどの学習指導要領の徳目に合わせて勝手に検定意見をつけることができる訳です。そうすると教科書の中身というのは、いかようにも文科省・国の好みに合わせて作ることができる。結局、文科省あるいは政府が「正しい」と考える「国定」の道徳の押しつけということになる訳です。
2.小学校「道徳」教科書の検定
今年8つの教科書会社から発行された教科書が検定を合格しました。6学年分ありますから、48册ですが、8社の内の3社は「別冊」というのを付けたので、それを数えると66册ということになります。膨大な分量ですが、それに対してさまざまな検定意見が付けられました。
今回検定意見は、全部で244件ということです。各社6学年ですから、1学年1社あたりの平均にすると、検定意見は平均5つです。非常に少ないです。これはなぜそう少なくなったかといえば、その理由は2つあって、1つは、道徳というのは初めての教科書ですから教科書会社の方も、どういうふうに作ったら検定に合格するのかよくわからないので、余り独自の創造力を発揮して教科書を作って不合格になったら何千万円という損失になるので、そうならないように検定に合格するようなやり方で作った。だから、検定意見が少なかったということが一つあります。
そしてもう一つは、道徳の教科書に対する検定意見は、たった1行ぐらいの検定意見ですが、「その対象は、この教科書全体である」、だから1行の検定意見で、教科書全体を直さなければいけないのです。そういう検定意見があるのです。具体的に言いますと、どの教科書も、一応毎週1時間ですから、年間35時間、道徳の時間があることになります。それで教科書はだいたいどれも35の章でできている。その章全部に検定意見が付くのです。その一つの例が、それぞれ教科書にある35の章には、学習指導要領の徳目に関係する教材がはめ込まれています。それは創作した何かのお話だったり、文学先品であったり、あるいは会社の編集委員がつくった話であったり、何かの実話であったり、そのような教材としてあります。最初はそれに「徳目」との関係を書いていない教科書もあったんです。これに検定意見がついた。必ず道徳の教科書の各章の内容に、どの「徳目」をどう学ぶためにこの教材があるか書けという訳です。それを書いていなかった教科書は、全部にそれを入れなければならないということになります。
徳目が表示されていなければ、子どもはあまりその徳目とは関係なく、自由に読むことができます。それで読んでいろいろな感想を持つかも知れない。だけど、こうやって、徳目が見えることで、子どもは「あ、これはこういうことなのか」「こういうことを勉強するんだな。そしたらこういうことを感想に書けばいいんだな」と、全部裏が見える教科書になってしまいます。
3.「道徳」教科書の問題点
教科書を分析する3つの観点としてまず、「心の押しつけ」になっていないか、つまり「心のあり方、考え方」をある型にはめる、押しつけてしまう、そういう教材になってしまっていないか、ということが一つです。
それから、もう一つは、「科学の目」で見るとどうなのか、という観点です。「道徳性」というものがあるとすれば、やはりそれは社会や自然についての科学的認識に基づいていなければ、「うわべ」だけのものであって、役に立たないものだと思います。だから本当に子ども達が、何かを学んで考えを深めるとすれば、やはりその考えを深める材料というのはきちんとした事実に基づいていなければいけない。そういう教材になっているかどうかということです。
3番目の観点は、「人権」とか「平和」、あるいはジェンダー等々、これらは重要な観点だと思います。そういう観点から教科書を分析されてみたらいいのではないかと思います。
いくつか具体例を挙げておきたいと思いますが、「心の押しつけになっていないか」という点については、一つは光村図書の5年生のところ、「感想を表す時の言葉」という単元、これは35章の教材とは別に「特設ページ」みたいなのがあります。これは、発表や話し合いの場面や「学びの記録」を書くときにも役立てるため、「こういう言葉を使って書きましょう」と、ごていねいに47もの言葉が並べられています。それが教科書の1ページに書いてあります。そこに書いてある言葉は、「明るく、力強い、なごやか、さわやか、心打たれる、清らか、上手、明解、・・・・」、「悲しい」とか「苦しい」とかいう言葉はないのです。そういうのは自分の中にしまい込んで、表現してはいけないことなのか、というふうにさせられようとしています。
それから、「科学の目で見るとどうなるか」ということですが、光村図書の場合「通潤橋」という長崎県にある有名な橋の観光地だと思いますが、江戸時代に水不足で悩んでいた台地の村に、いろいろ苦労をして水路を引いて、ようやく作物が豊かに取れるようになったという話ですが、これは「感謝」という徳目です。ですから、この話自体は、たぶんその江戸時代の農民の暮らしや、その中でのいろんな苦しみや闘いがあったはずですが、そういうことを一切捨象して、この通潤橋をつくる中心人物になった人に感謝しましょうという物語にしたわけです。だから、全然科学的じゃない訳です。
それから、秋田県の「まげまっぱ」という話、これは都会に住む女の子が、遠足なんかの弁当箱で、たまたま家にあった「まげまっぱ」の弁当箱を持って行くという話ですが、それを機会に秋田県にいるおじいさんに電話をしていろんな話をするんですが、伝統工芸というのは、今いろんな困難がある訳です。だからその背景には、いろんな社会的な問題がある訳ですけれども、そういうことは一切捨象して「伝統工芸はすばらしいな」「日本はいい国だね」という所に結びつけようとしている。科学的ではないです。
「人権」「平和」「ジェンダー」の視点は、全体として、そういうテーマがないというのが大きな問題ですが、教科書を作った人達も、なんとかそういう問題を入れようと工夫をして下さったところも少数ですがあります。光村図書では、「同じでちがう」という項目ですが、これは「生命の尊さ」という徳目ですが、ここでは子どもの権利条約の意見表明権の条文を全部載せています。それから「世界人権宣言から学ぼう」をタイトルに掲げたのはなかなかすごいです。徳目の「規則の尊重」、人権宣言も国際的な規則ですから。谷川俊太郎さんが、世界人権宣言30条を全部訳したのをそっくりそのまま掲載しています。「この宣言が目指した世界が実現できていると言えるでしょうか」「この宣言には、皆さん一人一人が、クラスの中でかがやくための大切なヒントがあるのではないでしょうか」ということを呼びかけています。そういうなかなかいい教材を使っているところも、ごく少数ですがあります。
4.「道徳」の評価について
「評価」に関して文科省が出した通知がありますが、まず「観点別評価はしない」「個々の内容項目ごとに評価はしない」となっています。結局どういうふうに評価をするかというと、「指導要録」という学校での公的な帳簿がありますが、そこに文章で書くということになります。だからどういう観点で評価するかというと、その一年間の間に、その子どもの道徳性がどれだけ成長したかということに着目して評価を書きなさいという。だから、子どもの道徳性ということが評価の対象になり評価されるということは同じです。ただ上級学校の進路の時に出す「調査書」には、道徳の評価は記入しないというのが条件付きになっています。
これは私達の道徳の「教科化」に対する批判を、ある程度受け入れざるを得ないものがあって、そうなってきているのですが、評価されることには変わりありません。しかも、その評価の材料は別冊とか、子どもの記入欄とかを材料にして評価することにならざるを得ない訳です。先生自身も大変な作業だと思いますが、子どもの方も評価されるんだなということでわかるから、何となく先生に良く思われるようなことになって、いつのまにかそれが習慣になって、そういうふうな心の持ち方に育っていくというふうになりはしないかと危惧します。
道徳については、「教科」になることによってさまざまな問題点が出てきていますが、先生達が、国の方針に縛られないでやれるような環境をどうやって作っていくかということが、大きな課題だと思います。
それの一つの手段としては、今年の採択の時に、やはり道徳の教科書にはこんなおかしい所があるよ、これをこのまま授業しちゃうのはおかしいじゃないですか、という道徳の教科書に対する批判を、たくさん意見を出していくことが一つの手段にはなると思います。また改めて何かの機会に、学校に市民の立場からいろんな意見を言うことで、学校を地域のみんなでつくっていくということがこれからの課題になるのではないかと思います。
これは小中学校だけの問題ではなくて、幼稚園・保育園・高校に広がります。幼稚園の教育要領、それから文科省だけではなくて厚生労働省の保育所保育指針にも全く同じ内容が書かれています。「国旗に親しみ」それから「国歌に親しみ」ということが要領の中に書き込まれましたからこれも対応しなければいけないでしょう。