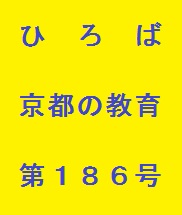
日記・詩・作文を通じて知る子どもの発達
川地 亜弥子(神戸大学)
一 子どもの表現から発達を学ぶ
子どもの自由な表現を大切にする日記や詩・作文教育について知りたい、という学生たちが、ここ何年か連続して私のゼミに来ている。「小学校の時の日記帳、大事においています」という学生もいれば、「自分が受けてきた作文教育と全然違う」という学生もいる。そのうちの何人かが、「忙しい中、指導時間も確保されていないのにどうして日記や作文に取り組むのか」と言って、指導の理由を尋ねるアンケートを実施した。「書く力がつくから」、「書く習慣がつくから」など、様々な選択肢をつくっていたのだが、先生方から一番多く選ばれた項目は「子どもを知りたい」だった。これには学生が驚いた。驚いた理由は二つある。一つは、学力向上・学習習慣確立のため、という回答が多いと予想していたのにそれを裏切られたこと。もう一つは、学生からすれば子どもの事を十分に知っていると思われるベテラン教師と言われる人たちも「子どもを知りたい」と回答していたことである。
しかし、考えてみれば、子どもはどんな先生の前でも本音を語り、書くわけではない。なんでも書いて大丈夫、そう思ってもらえる関係を築くことが大変なことであり、そこを乗り越えて、はじめて子ども一人ひとりの生活、思いを知ることができる。そうした困難を知っているからこそ、アンケートで「子どもを知りたい」が一番にあがってきたのではないかと思う。
ここでは、そうした先生方と子どもたちの生活の中から生まれてきた日記や詩、作文に学びながら、子どもたちの発達について理解を深めていきたい。
二 ありのままに書くことのおもしろさ
一年生の子どもたちは、学習にも意欲的である。子どもたちのつぶやいたことを黒板に書いていくと、「あ、それ俺が言ったことや!」と発見していく。
やっと覚えた文字で、自分の考えを書いていく。その内容は、したことや聞いた事、見た事だけではなく、こうなるといいなあという願いも含まれている。
ゆめ 小一 ちあき
わたしは きょうゆめを見た
わたしが 山ざきくんと
けっこんしたゆめを見た
だから そうゆうて
ほんとうに けっこんすることにきめた
そして 三十さいになったら
けっこんします
思わずこちらが笑顔になる作品である。一年生ではこのように、自分なりの筋道をしっかりと立てて話を展開することができる。三十歳になるまでの長い道のりを考えているわけではないのだが、だからこそ今の自分の考えをしっかり書ききることができる。
こうした力があるので、時には実際と違うことをまるで本当に経験したかのように書いたり話したりすることもある。例えば、「お父さんがそうめんゆでてくれてめっちゃおいしかった」と日記に書くのだが、それは事実ではない、という時がある。その時に「嘘をついてはいけない」と言うのではなく、「そうなるといいなあ」という願いを読み取っていかなくてはいけない。
三 自分の気持ちの変化がわかる、相手の考えをわかろうとする
書くと気持ちがすっきりする。二年生になると、そういう自分の気持ちの変化を、しっかりととらえることができる。京しろうくんの作文を読んでみよう。
いのこり 小二 京しろう
いのこり いやや。だってあそべへんから。先生もむっちゃ きびしくなるし いや。いのこり めんどい。そのとき なんで おれがこんなんしなアカンのとおもう。いや。なおし いやや。いのこり 先生と二人きりやし いやや。帰ったら ママに ださって いわれたことあるから 先生 やけに スイッチ入るから いのこり帰りみち同じ人 いいひん で 一人やしいやや。
いのこり いやや。先生うるさいしいやや。むっちゃ帰んのおそくなるし いやや。もんくいいたい。もんくいいたいし いまいう。先生のバカー。いいおわったらスッキリした。先生ごめん。
思いのたけを書きながら、「いいおわったらスッキリした」と気持ちの変化をとらえている京しろうくん。低学年の子どもたちでも、さまざまに気遣いしている現代では、こうして思いっきり表現できることの重要さが増している。読めばわかるが、京しろうくんは、先生が嫌いなのではない。「先生ごめん」の一言で、先生に寄せる気持ちが伝わってくる。
こうして自分の気持ちをいう事ができると、自分とは違う相手の気持ち、考えを分かろうとし始める。
おかあさん 小二 はやと
きのう
ひろし(弟)とけんかをしたから
おかあさんにおこられた
おふろでもけんかしたら
おかあさんにおこられた
なんでおこるんやろう
この「なんで」は、おかあさんの言うことわからへんわ!という拒否の「なんで」ではなく、文字通りなぜ怒るのか知りたい、という気持ちの表れではないか。大人が自分とは違う考えを持って判断していることに「なぜ」と考えている。こういうときに、「なんでじゃありません!喧嘩は悪いに決まってるじゃないの!」と叱ってはいけない。きちんと理由を伝えていくことが大事だ。すると、子どもも、他の人の考えについて丁寧に分かろうとする姿勢を持っていく。
逆に、「悪いことをしたからでしょ!」というような理由を述べているようで述べていない叱り方をすると、子どもたちはその答え方を他の子どもたちとの関係でも再現することがある。そのことが積み重なると、お互いを分かり合おうとする学級ではなく、監視して罰を与える学級に傾いてしまうことがある。大人が子どもの「なんで」と丁寧に向き合うことが求められる時期である。
四 相手の気持ちが分かる
やきもち 小三 ゆうゆ
まえ先生が、むっとした
それは、ゆうゆたちが
かわた先生(他の先生)ばかり、いっていたから
やきもちって、けっこう、うれしいな
だってゆうゆのことすきっていうことやもん
先生がむっとすることは、普通に考えると心配になることだが、ゆうゆさんは、「うれしいな」という。それはやきもちの表れで、やきもちをやいているということは、自分達のことが好きだからだ、と書いている。他の人の気持ちを分かり、その理由まで考えることが出来るようになり始めている。
ただ、まだ三年生の時期は、「他の先生のことばっかり言ったら先生に悪いから、今はやめておこう」と考えることは難しい。やってから、ああそうか、と分かっていく時期である。
なお、五年生頃になると、前思春期に入り、先生がどう思うか分かっていてシビアに表現してくることがあるが、この時期はそれとは違う。また、発達障害がある子どもたちが、先生から安定した反応を引きだそうとして、くりかえし先生が怒ることをしてくることもあるが、それとも別である。
五 九・十歳の節――相手の思いが分かるからこそ
九・十歳頃(つまり四年生頃)になると、論理的思考でも、社会性でも、さまざまな変化が如実に表れる。これを発達の節・壁などと呼ぶこともある。教科学習でも掛け算と割り算の関係が分かったり、金属と鉄のような上位概念・下位概念の関係が分かったりする。筋道を持った考えを、相手に分かるように表現できるようになる。相手に応じて表現や行動を変えたりすることもでき、自分の表現が相手にちゃんとわかってもらえたかを考えながら表現を修正することもできる。自分の思いをそのまま出すだけではなく、物事にそれを託し、比喩表現をすることもでき始める。
たんぽぽ 小4
いえのかどにさいたタンポポ
さみしそうにさいている
夏になれば
子とはなれる
一人ぼっちのおや
ぼくのお父さん
大阪でお兄さんとはたらいていはる
八月十一日は ぼくのたんじょう日
でも、三年前から
まっていてもかえってきやはらへん
お姉ちゃんのたんじょう日にも
かえってきはらへん
できたらたんぽぽぜんぶ
となりにさかせてやるんや
さみしくないようにしてやるんや
この作品を読むと、この子自身のさみしさが痛いほど伝わってくる。しかし、この子は自分のさみしさを書くのではなく、たんぽぽに父を重ね「さみしくないようにしてやるんや」と書くのである。なお、この作品は三十年以上前の作品であり、昔の子と今の子は違う、という意見もあるだろう。しかし、今の子どもたちも家族への気づかいに満ちた作品を書いている。
お父さん、お母さんへ 小四
お父さん、お母さん、妹と弟がいて大変なの、ぼくは分かっているよ。その中でいろいろな相談にのってくれてありがとう。
本当は、もっとゆっくりゆっくりしゃべりたいと思うことが時々あります。でも、お父さんとお母さんのことを見て、ぼくも自分で考える力がついてきたとぼくは思っています。もし、考えられない時は、また相談にのって下さい。
忙しいのに、今まで大事に育ててくれてありがとう。大人になるまで、どうかよろしくお願いします。
どの時期でも子どもたちにとって家族は重要だが、この時期には自分が甘えたい気持ちもありながら家族の大変さに心を寄せていることを理解しておく必要がある。こうした、もっと一緒に話したい、甘えたい、という気持ちをしっかり受けとめずに、もう四年生なんだから家族を手伝おう、というところだけが強調されると、子どもたちには息苦しい生活になる。筋道を立てて考え、説明し、見通しを持って行動していくことが出来る四年生だからこそ、ほっとできる時間が大切になっていく。
六 遊びまくることの大切さ
これまで述べてきたように、中学年になると、お互いの見え方や考え方の違いがよくわかってくる。「相手から見れば、こうだけど、自分はこう思ったんだ」と、その両方をわかって表現していく。しかし、それがすんなりできる子と、難しい子とが混在している。それがトラブルの原因にもなる。
こうした時期に、「遊びまくる」経験ができることは極めて重要である。さまざまなトラブルがある中で、それでも一緒に遊ぶなかまとしての経験が胸に刻まれる。一度のトラブルで全く関係がダメになるのではなく、グループが変わったりしながらも、何度でも関係を紡ぎなおす。「一緒に遊んで楽しかったなあ!」という経験が、その紡ぎ直しを助ける。
最近は集団で遊ぶ子どもが減ったといわれる。塾や習い事等で遊びにくい状況が遊び集団を減らしてきたのだ。現代では、学級や学童保育で、子どもたちの遊びを積極的に励ましていくことが重要である。
おこられたおふろ 小四 とおる
ぼくは、一日目、おふろはいるじかんになって、おふろのところにいったら、たこやき(高木くん)がいて、おふろにはいっていいのってきいたら、いいんちゃうとゆったので、ぼくとたこやきがはいったら、いっぱいはいってきて、およいでいたりしていると、田中先生がきて、フルチンでおこられました。五、六にんぐらいでおこられました。田中先生のメガネがくもっていました。メガネをふかはったけど、またくもりました。
ぼくは、フルチンで、一番前にたっていました。おこられたけど、みんなでわらいました。おこられたけど、おもしろかったです。
二日目のよるは、はいっていいと、とくまーる(得丸先生)にきいてはいりました。小よくじょうです。五人ではいっていました。きのうのことをおもいだして、またみんなでわらっていました。
おもしろかったです。
宿泊学習のおふろのことを書いている。おこられた場面だが、むしろ明るさが伝わってくる。実は四年生の当初、とおるくんはクラスで時々トラブルを起こしていた。しかし「遊びまくる」仲間の中で一緒に遊ぶ友だちができ、次第にトラブルが減ってきた。おこられても笑い合えるようになった。自分たちで判断していろいろやってみたい「集団的自己」(田中一九八七)が育つ時期に、失敗しても笑い合える仲間と生活があったことは彼の成長を励ましたと思われる。
紙幅がつきた。ここまで子どもの発達の話をしてきたが、大人が子どもと同じ地平に立ち、子どもを知り、共に生活を創造していくこと、また、子どもに、安心して本音で語り、遊ぶことができる仲間、大人がいること。これはどの時期にも重要な事であることは確認しておきたい。なお、作文教育を通じてさらに子どもの理解を深めたい人には、小松(二〇一五)、西條(二〇〇六)がお奨めである。乳幼児期から学童期を見通した人間発達と教育的指導については、白石・白石(二〇〇九)が参考になる。一読を奨めたい。
○参考文献
京都綴方の会(一九八四)『京都の生活綴方』駒草出版
小松伸二(二〇一五)『学級の困難と向き合う――子どもの〝持ち味〟を生かした学級づくり』かもがわ出版
小宮山繁(二〇一五)『京都市つづり方の会ハンドブック 詩の書かせ方①〜詩が生まれる箱の授業』
西條昭男(二〇〇六)『心ってこんなに動くんだ――子どもの詩のゆたかさ』新日本出版
白石正久・白石恵理子編(二〇〇九)『教育と保育のための発達診断』全障研出版部
田中昌人(一九八七)『人間発達の理論』青木書店
得丸浩一(二〇一一)『おもしろいけど疲れる日々』本の泉社
なにわ作文の会(二〇一六)『教室でいっしょに読みたい綴方 子どもたちの作文・詩』フォーラム・A