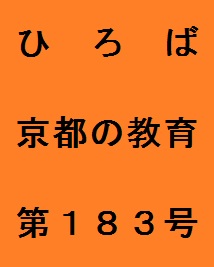
ドイツの「鏡」に映る戦後日本の70年
望田幸男(同志社大学名誉教授)
戦後の意味
「戦後」とはたんに戦争が終わったという意味なのであろうか、たしかに米英仏中などにとってはそうかもしれない。なぜならそれらの国々にとっては、戦前・戦後は政治も経済も基本的に同質の連続性のうえに立つ時期区分にすぎない。だが日本とともにドイツにとっては戦前は否定の対象であり、戦後は政治的にも社会的にも、さらには思想的にも新たな再出発であり、戦前とは断絶した非連続の関係にあった。したがってドイツと日本にとっては、「戦後」とは思想的にも特別に重い意味をもったものである。
(注)本稿でドイツとは、両独統一以前の場合は西ドイツに限定して用いる。東ドイツの場合には戦後日本とは異質の問題をふくみ、比較対象としては不適切であるからである。
「ワイマールへの復帰」と戦前との断絶
ところで、このドイツ・日本の「戦後」を考えるときに、前提として重大な違いを考慮しなければならない。日本の場合は、その戦後構想は明治以来の近代日本の政治・社会の否定のうえに、まったく新しい体制を考えなければならなかった。ところがドイツの場合には、ナチス体制の否定のうえに「ワイマールへの復帰」が考えられえた。第一次世界大戦の敗戦ののちのドイツでは、1919年「ワイマール憲法」という当時、世界で最も民主的な憲法のもとに新体制が発足した。だが、この新体制は、ナチスが議会第一党となることによって1933年に政権を掌握したことによって崩壊したのである。従って第二次世界大戦の終結によって、日本は明治以来の憲法体制の否定のうえに、新たな憲法体制の構築に向かわざるをえなかったのに対し、ドイツはナチス体制を否定しつつも、ナチス以前のワイマール体制に回帰することによって、戦後の最出発をすることができたのである。
しかし、このことは再出発にあたっての戦後改革の深度に影響した。日本の場合には、寄生地主制や財閥の解体をもともないながら新憲法体制が発足した。これに対して西ドイツの場合には、社会的にはワイマール時代のままの古い体制が継承されたのであった。たとえば教育体制である。日本の場合は旧制高校・帝国大学を基軸にした戦前のエリート・非エリート複線型体制は根本的に否定され、単線型の教育体制が導入された。だが西ドイツでは複線型エリート養成制度は存続し、それが大きく緩和に着手されるには1960年代中頃までまたねばならなかった。
戦後発足時のタイム・ラグ
加えて両国の戦後体制のあり様に影響したのは、戦争犯罪人を裁いた国際裁判(東京裁判とニュルンベルク裁判)と公然たる冷戦の勃発と新憲法体制の導入という三者の間におけるタイム・ラグ(時期の前後関係)である。以下の時系列表を見ていただきたい。
年表:日本・ドイツの戦後国家発足時のタイム・ラグ ( )内は月
| 西ドイツ | 日本 | 冷戦 | 国際軍事裁判 | |
| 1945 | ドイツ降伏(5) | 日本降伏(8) | ニュルンベルク裁判開始 | |
| 1946 | 新憲法公布(11) | 東京裁判開廷(1) ニュルンベルク裁判終了(10) |
||
| 1947 | トルーマン宣言(3) マーシャル・プラン(6) |
|||
| 1948 | ベルリン封鎖開始(6) | 東京裁判終わる(11) | ||
| 1949 | 基本法公布(5) | ベルリン封鎖解除(5) | ||
| 1950 | 再軍備の討議 | 朝鮮戦争勃発(6) | ||
| 1951 | ||||
| 1952 | 石炭鉄鋼共同体発足 | |||
| 1954 | ||||
| 1955 | 主権回復 NATO参加(5) |
|||
| 1956 | 徴兵制導入(7) |
ここからなにが見えてくるか。第一に注目すべきは1948年にベルリン封鎖が開始され、それまで反ファシズム戦争以来の共同フロントに立っていたかに見えた米ソが、公然たる激突(東西冷戦)へと突入したことである。そして、この公然たる冷戦の開始前に、ドイツ戦犯に対するニュルンベルク裁判と日本の新憲法制定が位置したのに対して、冷戦の開始後に一方で日本の戦犯に対する東京裁判の終結を迎え、他方で西ドイツにおいて連邦共和国の発足(憲法制定)が見られた。ここからどういう帰結がもたらされたか。
(1)冷戦勃発前に決着されたニュルンベルク裁判では、平和に対する罪とともに、人道に対する罪が裁かれ、その後の西ドイツにおける戦争責任論を深化させる礎石が築かれた。これに対し最終判決を冷戦開始のうちに迎えた東京裁判では、当初は人道に対する罪も訴因に考慮されていたが、最終的には独立の訴因とはならなかった。加えて昭和天皇とともに、日本軍の毒ガス・細菌戦(731部隊など)に対する免責が行われた。これらのことが、日本における戦争責任の所在をあいまいにする重大な要因となっていく。
ドイツと日本における戦争責任論に関して、今日、その深化と定着化の点でドイツのほうがはるか先を走っているといわれているが、その戦後史的要因をここに見ることができよう。
(2)日本国憲法が公然たる冷戦の勃発まえに制定されたという事情は、第9条という平和条項にその刻印を見ることができる。これに対し公然たる冷戦の開始後に発足したドイツ連邦共和国(西ドイツ)は、冷戦の最前線に立つ「戦争しうる国」として再軍備への道を初発から歩むことになり、やがて西側の集団防衛機構であるNATO(北大西洋条約機構)への参加、徴兵制の導入に至るのである。
戦後1950年代初頭、学生運動の渦潮のなかにあった私たち昭和1桁生まれにとって、当時の日本のほうが西ドイツよりも反戦平和運動の点で先んじていると映じたが、その背景には、公然たる冷戦の激化と両国の新憲法体制制定とのタイム・ラグが作用していた。
後のカラスが先になる
歴史においては後発国がいつまでもそうであり続けるとは限らない。後のカラスが先になることもある。冷戦の渦中でその最前線として発足した西ドイツも「戦争できる国」に安住することはできなかった。「ナチスの国が再軍備すること」には、ナチスによってじゅうりんされた近隣諸国の警戒心をかきたてた。加えて、これらの近隣諸国は、(戦後ほどなくの東アジアにおける日本の近隣諸国と違って)ポーランドをのぞけばすべて工業先進国であり、西ドイツなしでも経済発展をはかることができた。ここから西ドイツは以下の二つの課題をどうしても果たさなければ、ヨーロッパ国際社会に受け入れられることはきわめて困難であった。すなわち第一に、再軍備に着手しつつも、ナチス国家のような「侵略国家」とはならないことを、内外にむけて検証しなければならなかった。そして第二に、ナチスによる戦争犯罪(近隣諸国への侵略やユダヤ人大量虐殺など)への責任と謝罪・補償を果たさねばならなかった。
第一の課題における先駆けとなったのは、1952年のヨーロッパ石炭鉄鋼共同体の発足である。これは積年の敵対関係にあったフランス・ドイツ間における戦略物資=石炭鉄鋼の国際的共同管理の体制を中軸にしたものであった。これによって19世紀以来4度にわたって戦火を交えたフランス・ドイツ間の戦争が、もはや物理的にも不可能となったのである。この条約こそドイツと近隣諸国との友好と不戦共同体=EUの出発点をなすものであった。次いで注目すべきは、1970年代初頭の社会民主党政権のもとで展開された「東方外交」である。これによってソ連・東欧諸国などとの国交と交流の開始が告げられた。
第二の戦争犯罪への責任と謝罪・補償については、改めてここで再論する必要はないであろう。ただここで指摘しておきたいことは、戦後70年を貫くドイツの戦後補償の営みにおける法的基本的枠組みが、すでに1956年の連邦補償法で確立されたことである。
このように西ドイツが公然たる冷戦の激発のなかで誕生し、そのため当初から「戦争できる国」として出発した「ハンディ」は、近隣諸国との友好関係の確立を促し、はたまた戦争責任を果たしていくことに帰結した。この点で、日本をはるかに先んずることになったのである。ちなみに日本における戦後経済の発展は、近隣諸国との友好関係にもとづくものではなく、朝鮮戦争とベトナム戦争におけるアメリカの軍需的発注を「テコ」にしたものであった。そのため戦後日本は近隣諸国と向き合うことなく、経済再建の道につくことができた。そして日本が東アジア諸国と向き合う時期に至ったとき、日本はすでに高度工業国の道をたどりつつあり、近隣諸国はいまだ発展途上にあり、日本からの経済的援助を期待する地点にとどまっていた。これらの近隣諸国が、日本の戦争責任を力をこめて迫ってくるのは戦後も30有余年を経てからのことであった。西ドイツが戦後補償の法的基本的枠組み(連邦補償法)を確立したのが、1956年であったことを想起すると、その落差はあまりに大きいといわざるをえない。
第二の戦後=「新しい社会運動」
ドイツを「鏡」に見立てて戦後日本を眺望したとき、日本では敗戦直後の戦後改革から以後、これといった目立った民主的改革に着手されずに今日に至っているのに対して、西ドイツでは60年代後半から70年代前半にかけて、「新しい社会運動」と称せられる「第二の戦後改革運動」が展開された。それは反核・脱原発の平和運動、環境保護=エコ・フェミニズム運動、複線型エリート養成の教育システムの打破の諸運動の波であった。これによって社会の隅々にまで根を張っていた戦前的な古い体質が破られ始めた。
ひとつの事例を挙げよう。1991年に京都で記録映画『日独裁判官物語』が上映された。ここに登場するドイツの裁判官は、政治活動の自由も結社加入の自由も、裁判官独自の団体の結成(一種の組合)も認められていた。「良き裁判官たるには、良き市民たれ」といわれ、彼ら裁判官たちは、平和や環境保護の運動に市民とともに参加できるのである。日本の裁判官とのコントラストはあまりに明瞭である。日本の裁判官の場合には、一般の市民に認められている諸権利さえも制限されている現状がある。ドイツのこのような姿容は、既述の「新しい社会運動」の成果の一端である。
すでに述べたように戦後ほどなくの民主的改革は、西ドイツよりも日本の場合のほうが、徹底性をもっていた。だが戦後70年を通して眺めてみると、西ドイツでは60・70年代における第二の戦後改革によって、「古いドイツ」から脱皮してきたといえよう。今日の日独における原発政策の落差も、同様のことをさらに裏書きしているといえよう。
新しい社会の胎動と新しい課題
過日6月27日付け『朝日新聞』にこんな記事が載った。19歳の高塚愛鳥(まお)さんは札幌の繁華街すすきのでデモをやろう、とフェイスブックでよびかけた。「いいね!」が三千を超えた。デモの名は「戦争したくなくて震える」だ。人気歌手西野カナの歌詞「会いたくて震える」にかけた。参加者は700人ほどだったという。このことは、デモが特別の人びとでなく、普通の若者によって、彼らふうのやりかたで結構の人数でやる、やれる社会が、日本にもやってきたことに気付かせてくれる。それというのも、こうした類いの話は、あちこちで聞かされるからだ。
しかも同時に、彼ら彼女らのなかでは戦争法案反対や原発反対の声も、人間と地球を守れ!の叫びとか、大量生産・大量消費の成長主義とたもとをわかつ願いとかと合流して広がっている。さらには女性同士、あるいは同性同士の共同生活もさしたる気負いもなく行われ始めている。そこには理屈でいえば環境保護・エコの思潮、そしてフェミニズムの思潮が明らかに胎動している。こうした思潮は、日本でも論壇の一角には登場したことがあったが、社会的には定着しえなかったものである。安倍政権による「戦争する国」への暴走との闘いのなかで、日本のなかに「新しい社会の胎動」がたしかに聞こえてくる。だが、そこにはまた新しい課題・難問も待ち受けているだろう。ドイツでもそうだ。EUのリーダー的存在になったドイツは、ギリシャ問題など南欧諸国との困難なトラブルに直面している。そこには経済の国境をなくしたけれども、政治的には国民国家が厳存するという厄介なパラドックスを解かねばならなくなっている。古い社会を脱皮して、新しい社会が胎動するとき、そこではまた新しいアポリアに直面する。