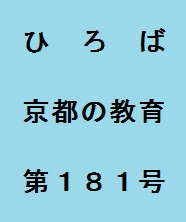
���W�Q�@�q�ǂ��̌���������������
���{�̉^���͎q�ǂ��̌��������ǂ��~�ߔ��W�����Ă����̂��H
�\�q�ǂ��̌����������^����30�N���ӂ肩����|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����R�@�m��i�V����w�j
�͂��߂�
�@1989�N�ɍ��A�q�ǂ��̌������i�ȉ��A�K�X�A�������܂��͏��j�����A����ō̑�����Ă���25�N�A�����āA1994�N�ɓ��{���{���{�����y���Ă����N��20�N���o�����B��x���Ƃ͂Ȃ邪�A�̑�25���N�A��y20���N���@�ɁA�{����A�ɂ����ċN������Ă��������炷�łɎn�܂��Ă������{�ɂ�����{���̎����̂��߂̉^����30�N���ӂ肩����A�^�����ǂ��܂ŗ��āA�����ۑ�ƂȂ��Ă���̂����������Ă݂����B
�@���A�̐l���Ɋւ�����͌����m�Ɉ�`�I�ɋK�肵�Ă���̂ŁA�����y�������ɂ�����^���̖����͍��ƊԂō��ӂ��ꂽ���Ƃ𐭕{��������Ǝ��{����悤���������邱�ƂɌ��肳��Ă�����̂Ɨ������ꂪ���ł���B�������Ȃ���A���Ɛl���Ɋւ�����ɂ��Č����A���̂悤�ȗ����͐������Ȃ��B���ɋK�肳�ꂽ�����̓��e�����łȂ��A���S�̂̈Ӗ����������A�����y�������ɂ�����^���Ɛ��{�Ƃ̊W�A�����āA���̎��{�Ď��ɂ����鍑�A�̑g�D�|�������̏ꍇ�ɂ́A���A�q�ǂ��̌����ψ���iThe Committee on the Rights of the Child�j�i�ȉ��ACRC�j�|�ƍ����̉^���c�̂Ƃ̑Θb�̒��ő傫���ς���Ă�����ł���B
�@���������y����Ƃ��̍��̐��{�͒���I�ɏ��̎��{�Ɋւ��鐧�������A�ɒ�o���ACRC�ɂ��R�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��ACRC���R���̌�ɍ̑�����ŏI���������Ђ��镶���Ƃ��Ď~�߂Ȃ���������{���Ă������Ƃ����߂���BCRC�͐R���̃v���Z�X�ւ�NGO�Q���A��̓I�ɂ́A���{���ɏ�����Ă��Ȃ������Ɋւ�����̒��d�v�����Ă���B���̂���CRC�ɂ�鐭�{�̐R���́ANGO�Ɛ��{�Ƃ̊Ԃ̑Θb�݂̂Ȃ炸�ANGO��CRC�Ƃ̊Ԃ̑Θb����������@��ƂȂ�̂ł���B
�������̓��{�ɂ�����^���̗��j��U��Ԃ��Ă݂�Ɖ^���̒S����Ɖ^�����f���闝�O�A�����āA�������瓱�����^���̃X�^�C�����A���{�Љ�ɂ����錠�����̊�{�I�ȈӋ`�����肵�A���A�ɂ����̗��������W�����Ă��������Ƃ������ł���B
�P�D 1980�N��ɂ�������{�ɂ�����c�_�̏�
�@���{�ɂ����錠�������������邽�߂̉^���̗��j�͌�������A����ō̑������ȑO��1980�N�㒆�Ղ���J�n����Ă���B���A�ɂ�������̋N����1979�N�̍��ێ����N���_�@�Ƃ��Ďn�܂��Ă���A���{�ɂ����Ă͌����҂̊Ԃŏ�ĂɊS���W�܂�A�N���̐i���̕��͂��s���A���̐��ʂ��������p�I�Ɍ��\����Ă����̂ł���B���̌����҂̓������x���Ă����̂́A�����̓����g�Ɏ��������\���Ă����u�q�ǂ��̐l���A�v�ł������B
�@�l���A�𒆐S�Ƃ��鍑�A�̓����������������{�ɓ`���錤���҂����S�̉^���́A���̗��_�ʂ�����ƁA���{�̓����̏ɑ傫�ȉe�����Ă������Ƃ��킩��B
�@1980�N�㏉������u�Ǘ���`����v�A���Ȃ킿�A���\���A�Z���A�̔����u�O��̐_��v�Ƃ��Ďq�ǂ��̊w�Z���O�̍s�����ߓx�ɋK�����邱�Ƃ���莋����钆�ŁA�q�ǂ��ŗL�̌����A���Ȃ킿�A�q�ǂ����q�ǂ��ł���Ƃ������R�����ŔF�߂��錠���\�ȉ��A�q�ǂ��̌���(�E�E)�|�ł͂Ȃ��A�q�ǂ�����l�Ɠ����l�Ԃł��邱�Ƃ���F�߂����l�Ɠ��������\�ȉ��A�q�ǂ��̐l��(�E�E)�|�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����咣�������Ȃ������Ƃł���B1980�N��ȑO�ɂ�����q�ǂ��̌����ƌ����A�q�ǂ����q�ǂ��ł��邱�Ƃɒ��ڂ����q�ǂ��̐������B���Ǝq�ǂ��̐l�ԂƂ��Ă̐������B�ɕs���Ȋw�K�������Ƃ���q�ǂ��̊w�K�����Ӗ����Ă����B�����āA���R�Ȑl�ԓI��̂������q�ǂ������R�Ȏ�̂ւƈ�Ă邱�Ƃ��ł���Ƃ̏𗝂Ɋ�Â��A���t���u�����ۏ��́v�Ƃ��Ĉʒu�Â��A���t�̋���̎��R�����q�ǂ��̌����̎����̂��߂Ɏ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl�����Ă����B
�@�Ƃ��낪�A�Ǘ���`����̂��Ƌ��t�ɂ��q�ǂ��̎��S�E���E�������邢�͎q�ǂ��Ԃ̂����߂𗝗R�Ƃ��鎩�E�������N����ƁA�q�ǂ��̐l��(�E�E)�A�Ⴆ�A�����Ɋւ��錠���⎩�Ȍ��茠�|�ւ̒��ڂ������Ȃ�A�������A�q�ǂ��̐l����N�Q���Ă��鋳�t���u�l���N�Q��́v�Ȃ����́u���͎ҁv�Ƃ݂Ȃ��ׂ��Ƃ̋c�_�𑣂����ƂɂȂ����B���̂悤�ȋc�_�̏̉��A�q�ǂ��̐l��(�E�E)�����ɏ�Ă𗝉����钪�������ݏo����A��ĂɎq�ǂ��̕\���̎��R�Ȃǂ̎s���I���R�����荞�܂�邱�ƂɂȂ������Ƃ̈Ӌ`���������A���邢�́A���12���ɋK�肳�ꂽ�ӌ��\���������Ȍ��茠�ł���Ƃ���c�_�܂ł����o�ꂷ�邱�ƂɂȂ����B�����āA�����g��1989�N�Ɋw�K�w���v�̖̂@�I�S���͂�F�߁A���t�̋���̎��R�̎����A����ɂ́A�u�q�ǂ��̌����v�̎����������I�ɂ͉^���̉ۑ肩��~�낵�Ă��܂������߁A���̒������܂��܂������Ȃ��Ă����Ă��܂����̂ł���B
�Q�D DCI���{�x���̓o��
�@1989�N�̍��A����ɂ����錠�����̍̑�i�K�ɂ����ĉ^���ɂ����Č����ł������u�q�ǂ��̐l���v����Ƃ��钪����ς��镪��_�ƂȂ����̂́A���{���{�����������y����3�����O��1994�N2����Defence for Children International�iDCI�j���{�x�����ݗ����ꂽ���Ƃł������B
�@DCI�{���i�W���l�[�u�j�͏��N���ɓ������Đ��E��NGO�̈ӌ������A�ɃC���v�b�g���邽�߂̑����ƂȂ�A���N���ւ�NGO�Q���̗v�ƂȂ��Ă����B�����ē��{�x���́u�q�ǂ��̐l���v�ł͂Ȃ��A�q�ǂ��̌���(�E�E)�ɑ���u���A�������̈Ӌ`�́u���E�̎q�ǂ����ׂĂɖL���Ȏq�ǂ�����v���������悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃɂ���Ƃ̍l������W�J�����B���{�ɂ����ēƓ��̔��W�����Ă����q�ǂ��̌���(�E�E)�_�̉^���̎M���o�ꂷ�邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@DCI���{�̓o��ɂ��A�^���̃X�^�C�����ς���Ă������ƂɂȂ�B�܂��́A���A�̐l���S������CRC�̈ψ��Ƃ̂Ȃ��������A���A�̓�����`���邾���łȂ��A���A�Ƃ̑��ݓI�ȑΘb�Ɋ�Â��Č������̈Ӌ`��T�����Ă����Ƃ����X�^�C�����m�������Ƃ������ƁB���ɁA�ݗ���������̎����������]�T�^�I�ɂ͍����\�͂̕n�コ�ɂ�������炸�Ɨ��������������\���Ă������Ɓ|�A1996�N�Ɂu�����ЂƂv�ɂ�����֓I��������{�̍���NGO�ɑi���A�u�q�ǂ��̌������s���ENGO���������v�̗����グ�ɑ傫���v���������Ƃł������B
CRC�͂���܂ł͖������ɓW�J����Ă���NGO�̐��{�R�����^�����Ă����B��I�ȏ������NGO���W���l�[�u�ɏ������A�\���R���ɂ�����NGO�Ƌc�_�����A���{�R���ɂ����Ď��グ��ׂ������m�肷��Ƃ����葱�����̗p���Ă����̂ł���B�������A�l���S�����ł������t�B�I�i�E�u���C�X�E�v�ۓc����́uNGO�Q�����ł����ʓI�Ȃ��̂ɂ�����@�́ANGO�̐����ЂƂɂ��邱�Ƃ��B�v�Ƃ̃A�h�o�C�X�ɏ]���A��̂悤�Ȓ�N�����A�����̗����グ�ɑ傫���v�������̂ł���B
�R�D �����ɂ�闝�_�̓W�J
�@������1997�N�A2003�N�A�����āA2009�N��3��ɂ킽���đ�֓I����CRC�ɒ�o���Ă���B�����̊����̍ł��傫�ȓ����͉^���Ɨ��_�̉����^�����������悤�Ƃ������Ƃɂ������B���̍�����̃��|�[�g���L����W���āA���{�ɂ�����q�ǂ��̌����̏Ɋւ�����𑐂̍����x��������W����̂Ɠ����ɁA�����҂⊈���Ƃ����̏��͂��A1�̃X�g�[���[�ɂ܂Ƃߏグ��Ƃ����葱��������ĕ������s�����̂ł���B�����āA���̃X�^�C���͗��_�̉���I�Ȑi�W�������炷���ƂɂȂ����B
�@��1���֓I���̃^�C�g���́w�L���ȎЉ���{�ɂ�����q�ǂ����̑r���x�ł���A���҂ւ̒����Ȃ����͂�����ƈ��������Ɏ�҂ɗ��v���z���������{�Љ�̂��Ƃɂ����Ďq�ǂ��͂���̂܂܂Ɏ~�߂���l�ԊW���l�Ƃ̊Ԃőr�����Ă���A�q�ǂ��͖L���ȎЉ�ɂ����Ďq�ǂ�����������Ă��邱�Ƃ��咣����Ă����B��2����̃^�C�g���́w�L���ȎЉ���{�ɂ�����q�ǂ����̔��D�x�ł������B�u�r���v����u���D�v�ւ̕ύX�́A21���I��������{�i�I�ɊJ�n���ꂽ������u�\�����v�v�̂��Ɖ����ɂ���Ďq�ǂ����オ�D���Ă���Ƃ��������悤�̂Ȃ����Ԃ��W�J���Ă��邱�Ƃ��������̂ł������B�����āA��3����̃^�C�g���́w�V���R��`�Љ���{�ɂ�����q�ǂ����̔��D�x�ł���A�����Ɏ���悤�₭�A���{�Љ���u�L���ȎЉ�v�Ɛ��i�t���邱�Ƃƌ��ʂ��A�������A�q�ǂ����D���Ă���Ɛl���u�V���R��`�v�A���Ȃ킿�A�����Њ�ƒ��S�̎Љ�ƍ��Ƃ���낤�Ƃ����l�����ɓ���ł����̂ł���B
�@3��̕����̒��Łu�q�ǂ��̌����v�_�́A�@�q�ǂ��̎�̐��A���Ȃ킿�A�q�ǂ������ɓ��������A�������牞���������o���͂������Ă���䂦�ɁA���Ƃ������I�Ȏ�̂łȂ��Ƃ��q�ǂ��ɂ͌������F�߂���ׂ��ł���A�A�q�ǂ��̎�̐��́A�q�ǂ��̗v���ɉ������l�Ƃ̐e���ȊW�̂��Ƃł��������������̂ł���A�B���̂悤�Ȏ�̐�����������ď��߂Ďq�ǂ��̐l�ԂƂ��Ă̐������B�������ł���Ƃ����l�����ɂ܂Ŕ��W�������Ă������B�����Ă��̍l�����́A�������12���ɋK�肳�ꂽ�q�ǂ��̈ӌ��\�����̈Ӗ��́A�q�ǂ��Ɏ�̐��Ǝ�̐����ł����l�Ƃ̊Ԃ̐l�ԊW���`�����邱�Ƃ������Ƃ��ĔF�߂����Ƃɂ���Ƃ̃��j�[�N�ȗ����Ɍ������邱�ƂɂȂ����B
�S�D ���A�ɂ���e�Ɖ���
�@�q�ǂ��̌���(�E�E)�_���q�ǂ��̎�̐������ɂ��Ĕ��W�����Ȃ���A�q�ǂ��̌����������Ԃ����̂���肵�Ă��̉��v�����߁A����ɂ́A�q�ǂ��̌��������Ƃ����Љ�Â�����ӎ���������̉^���́A���A�ɂ��傫�ȉe����^���A�傫�Ȑ��ʂ������炵���B
�@�܂��́A2005�N��CRC���̑������u��ʓI���ߑ�7���@���c�����ɂ�����q�ǂ��̌����̎��{�v�ɂ����āA�q�ǂ��̎�̐������ɂ���q�ǂ��̌����ɂ��Ă̍l��������e���ꂽ�Ƃ������Ƃł���B�����͂Ȃ邪���̒��߂̑�16�p���O���t���ȉ����Ă��������B
�@���c���́A����̐����A�����A����ѕ����̂��߂ɕK�v�Ƃ���ی�A�������A����ї������A�e����уP�A�҂��狁�߂�\���I�ȎЉ�I��́iactive social agent�j�ł���B�V�����͏o�����ォ�玩���̐e����уP�A�҂�F�����邱�Ƃ��ł��A��I�R�~���j�P�[�V������ϋɓI�ɍs�Ȃ��B�ʏ�̏ł́A�e�܂��͑�1���I�P�A�҂Ƃ̊Ԃɋ������ݓI�������`������B�����̊W�́A�q�ǂ��ɐg�̓I����ѐ��_�I���S�A�Ȃ�тɁA��т����P�A����ђ��ӂ����B�q�ǂ��́A�����̊W��ʂ��āA���Ȃ̃A�C�f���e�B�e�B���`�����A�����I�ɉ��l�̂���X�L���A�m������эs�����l������B���̂悤�ɂ��āA�e�i����т��̑��̃P�A�ҁj�́A�����ʂ��ē��c���������̌������������邱�Ƃ̂ł����v�ȉ�H�ƂȂ�B
�@���ɁA�����W�J�����V���R��`�ᔻ���قڑS�ʓI�Ɏ�����A���{�̌������{�ɏZ�ނ��̂��������Ă���ȏ�ɐ��m�ɕ`�ʂ���ŏI�������A��3�{�R���Ɋ�Â���2010�N��CRC�ɂ���č̑����ꂽ�Ƃ������Ƃł���B���̍ŏI�����ł́A�q�ǂ����A�ߋ�2��̍ŏI�����Ŏw�E���ꂽ�u���x�ɋ�����`�I�ȋ��琧�x�v�̂��Ƃŕs�o�Z�⎩�E�Ȃǂ̍���ɒ��ʂ��Ă��邾���łȂ��A��I�K���x�̒Ⴓ�Ƃ����V���ȍ���ɒ��ʂ���悤�ɂȂ������ƁA���̑�1���I�������q�ǂ��Ɛe�����Ďq�ǂ��Ƌ��t�Ƃ̊Ԃ́u�W�̍r�p�v�ɂ��邱�ƁA�����āA���̑�1���I�������A�J���K���ɘa�A���c���A�q�ǂ��ɒ��ɐڂ��Ďq�ǂ��̂��߂ɓ�����l�̒n�ʂ̒ቺ�ȂǍ\�����v���\������{��̑��ɂ���Ĉ����N������Ă��邱�Ƃ��w�E����Ă����̂ł���i��p���O���t50�A51�A61�A66�A67�p���O���t�j�B
�@CRC�́A2010�N�̍ŏI�����ɂ����āA�����̎咣�����V���ȉۑ����N���Ă����B��́A��1�{�R���Ɋ�Â��ŏI�����̒��Ŏw�E���ꂽ�u���x�ɋ�����`�I�ȋ��琧�x�v�̉��v�Ɋւ���āA�����ɂ��w�͂̌���ł͂Ȃ��A�u�q�ǂ����S�̔\�͌`���v���������A����ɔ����A�w�Z��ʊԂ̐ڑ����܂ޑ�w�܂ł̊w�Z�̌n���v���s���ׂ��ł���Ƃ̊������Ȃ��ꂽ���Ƃł���B��1��̐R�����s��ꂽ1998�N�ȗ�10�N�ȏ��������CRC�ɂ���Ď����ꂽ��̓I�Ȗ��̑ŊJ��ł��邪�A�ܒ~�ɕx��ł��邤���A���ɍ��{�I�ȉۑ����{�̋���W�҂ɓ�����������̂ƂȂ��Ă���i��71�p���O���t�j�B
�@������́A�q�ǂ��̌����̎����̂��߂Ɋ�Ƃɑ��鍑�Ƃ̋K��������ׂ����ƁA���Ȃ킿�q�ǂ��Ɛe�A�����āA�q�ǂ��ɒ��ɐڂ��ē����Ă����l����Ƃ���ی삷�鍑�Ƃ̋`���̗��s����{���{�ɋ��߂����Ƃł���i��27�C28�p���O���t�j�B���Ƃ��g���Ďq�ǂ��̌������������邽�߂̃o���A�[����Ƃɑ��Đݒ肷��B�V���R��`�ւ̑R���Ɋ�{�������ł͒[�I�Ɏw�E����Ă���̂ł���B
�܂Ƃ߁|����10�N�̉ۑ�|
�@����30�N���{�ɂ�����q�ǂ��̌��������������邽�߂̉^�����ӂ�Ԃ�Ə��Ȃ��͂Ŏ��ɑ����̐��ʂ��グ�Ă����Ǝ�������B�������Ȃ���A30�N���I���������10�N�̃`�����W�ƂȂ�V���R��`�Ƃ̑S�ʓI�Ȋi���Ɏ��g�ނɂ͂������̃n�[�h�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��BCRC����V��������������ꂽ�ۑ�̂ق��A�����ł͎���2�̂��Ƃ������w�E���Ă��������B
�@�܂��́A�q�ǂ��̌����̓����Ɋ֘A���āA�q�ǂ��̐����I�~���ł��鈤���`���ɒ��ڂ��A��7�����߂Ȃǂ̐��ʂĂ������A�v�t���ȍ~�̎q�ǂ��̊l���I�v���A���Ȃ킿�u�Ӗ�����l�����Љ�̒��ʼn߂��������B�v�Ƃ����v���ɐ��ʂ�����g�܂Ȃ��Ă͂����Ȃ��B
�@���ɁA����܂ł̉^�����x���Ă����g�D���o�[�W�����E�A�b�v����K�v������Ƃ������Ƃł���B��ٓ��̃{�����e�B���S���Ă����^�����A���̐��_���ێ������܂܁A���g�D�I�Ȃ��̂ւƉ��v���Ă����A���{�Љ�̒��ɍL�����݂���q�ǂ��̌����������������Ƃ������l�ȗv�������悭�~�߁A���A���L�������ł���悤�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�ȏ�̎G���ȕ��͂��A����10�N���x���闝�_���Ƒg�D���ɎQ���������Ƃ̋C�����������N�������̂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��F���ďI���Ƃ������B