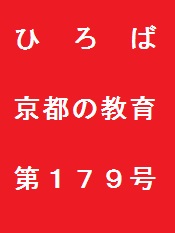
特集テーマ 1 憲法と教育
「憲法の力」と「教育の力」
出口 治男(弁護士)
1 文部科学相の「教育勅語」礼賛という愚行
2014年4月26日の朝日新聞によると、25日の衆議院文部科学委員会で教育勅語をどう評価するかに関する議論が交わされ、下村博文文科相は、①勅語の徳目について「至極真っ当。今でも十分通用する」と述べた。②教育の理念を示す「よく忠に励みよく孝を尽くし、国中の全ての者がみな心を一つにして代々美風を作り上げてきた」(現代語訳)との文言を、「日本の国柄を表している」と評価した。③「万一危急の大事が起こったならば、大義に基づいて勇気を奮い一身を捧げ」(同上)の部分は「わが国が危機にあった時、みんなで国を守っていこう。そういう姿勢はある意味では当たり前の話」と述べた。④一方、勅語で使われる「我が臣民」「皇室国家につくす(同上)」などの表現は、「現憲法下における国民主権を考えると適切でない」などと指摘した、とされる。
改めて言うまでもなく、教育勅語は、天皇が勅令によって、1890年(明治23)10月30日に発布し、1945年(昭和20)8月15日の降伏に至る迄、日本の教育の基本法であった。その中心的思想は、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無 窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」という点にあり、これは日本の国を肇めた「皇祖皇宗の遺訓」であり「子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所」とされた。教育勅語は「天皇のために一身を捧げよ」と命じたのであり、「みんなで国を守ろう」という思想は微塵もない。
又1946年(昭和21)10月18日文部省が教育勅語奉読廃止を通達し、1948年(昭和23)6月19日、衆参両院で教育勅語の効力を否定する決議を行っていることを、文科相は知らぬ訳はあるまい。教育勅語の思想が戦前の苛烈な軍国主義的又は極端な国家主義的傾向を帯びた教育の源泉となっていたことは周知の事実であり、その反省に立って日本国憲法、教育基本法が制定され、教育勅語に基づく教育体制を完全に否定したところから戦後の教育の歩みが始った。
文科相の教育勅語の読み方は、このような戦前の歴史を忘却したか、又は甚しく歪曲するものであって、教育の衝に当たる閣僚として失格と言う外ない。しかし、翻って考えると、文科相が敢えてそのような歪曲をしようとするのは、集団的自衛権を憲法解釈の変更によって行おうとすることと無関係でないと思われる。防衛研究所長や防衛省教育訓練局長等を務めた小池清彦は集団的自衛権の行使にひとたび道を開いたら「日本に海外派兵を求める米国の声は次第にエスカレートし、近い将来、日本人が血を流す時代が来る。自衛隊の志願者は激減するから、徴兵制を敷かざるを得ないだろう。」と述べている(朝日新聞2014年6月25日)が、少なくとも集団的自衛権が現実に行使されると、日本の若者が、海外へ派兵されることは必至であり、それらの若者が海外の戦場で殺すか殺されるかという環境に投げ込まれるのであるから、若者に対して、自らの命を捨てることを覚悟する教育を行うことが、どうしても必要になる。こうした文脈の下で文科相の発言をみると、教育勅語に仮託しながら、子ども達に対して生命を捨てることを覚悟させる教育の必要性を述べていると解することができる。
集団的自衛権の行使を可能とする憲法違反の閣議決定を強行した安倍政権と与党の常軌を逸した態度を見ると、文科相の教育勅語礼賛という愚行は、教育に対する「不当な支配」として教育現場にその姿を現わす可能性を有していると危惧されるのである。
2 「不当な支配」をはね返すために
(1)学力テスト最高裁判決による縛り
現教育基本法(以下「現教基法」という。)16条12項は、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」と規定している。旧教基法10条1項は「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」とされていたが、改定によって現教基法16条のように規定された。改定法案の審議の過程において、上記現教基法が「この法律及び他の法律に基づきさえすれば「不当な支配」に該当しないということになるのか、それとも旧教基法10条1項と同じく、法律に基づく教育行政の行為であっても「不当な支配」に該当する場合があるのか」が重要な問題となったが、政府は、現教基法16条1項の「不当な支配」は旧教基法10条1項と同じであり、法律に基づく場合であっても「不当な支配」となる場合があることが確認された。旧教基法10条1項の「不当な支配」禁止は、現教基法でも旧法と同じ意味で引き継がれている。この点は極めて重要なものとして再確認しておく必要がある。そして、旧教基法の下で、10条1項の「不当な支配」について示された学力テストに関する1976年(昭和51)5月21日最高裁大法廷判決(以下「学テ最判」という。)の判断も又、現教基法の下で厳然とした効力を有し、教育行政を拘束しているのである。
(2)以下、学テ最判で示された重要なポイントを指摘する。
ア 憲法26条の「教育を受ける権利」規定の背後にある観念の宣明
学テ最判は、憲法26条の規定の背後には「国民各自が、一個の個人として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる。換言すれば、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられている。」と述べる。教育は、何よりもまず、子どもの成長発達、人格の完成実現のために必要な学習をする権利に対応するものであり、教育を施す者の支配的権能ではないとする。旧教基法も現教基法も、教育の目的の冒頭に、「教育は、人格の完成を目指」すことを掲げているが、そのことを学テ最判は更に明確にしている。子どもの教育を受ける権利に関する学テ最判の宣明は教育の本質理解に関する極めて重要な内容であり、子どもを戦争に駆り立てるようなことをしてはならないということが、この解釈から導き出されると考える。
イ 教師の教授の自由及び教育の本質的要請の確認
学テ最判は、普通教育における教師に、大学教育と同じような完全な教授の自由は認められないけれども、「憲法の保障する学問の自由は、たんに学問研究の自由ばかりでなく、その結果を教授する自由をも含むと解されるし、更にまた、専ら自由な学問的探究と勉学を旨とする大学教育に比してむしろ知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育の場にいて、例えば教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべき」とする。ここでは、例えば教師が、文科省等教育行政当局から、子どもを戦争に駆り出すための教育を行うことを強制されないという自由を有していること、子どもの教育が教師と子どもとの間の「直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならないという本質的要請」を有していることからすると、子どもの個性を無視した画一的な軍国主義的教育又は国家主義的な教育を教育行政当局から押し付けられることは、憲法23条の教授の自由に反し許されないと解される。
ウ 旧教基法制定の理念の確認
学テ最判は、この点について次のように述べる。「教基法は、憲法において教育のあり方の基本を定めることに代えて、わが国の教育及び教育制度全体を通じる基本理念と基本原理を宣明することを目的として制定されたものであって、戦後のわが国の政治、社会、文化の各方面における諸改革中最も重要な問題の一つとされていた教育の根本的改革を目途として制定された諸立法の中で中心的地位を占める法律であり、このことは、同法の前文の文言及び各規定の内容に徴しても、明らかである。」「教基法は、その前文の示すように、憲法の精神にのっとり、民主的に文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献するためには、教育が根本的重要性を有するとの認識の下に、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的で、しかも個性豊かな文化の創造をめざす教育が今後におけるわが国の教育の基本理念であるとしている。これは、戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れ、時に軍国主義的又は国家主義的傾向を帯びる面があったことに対する反省によるものであり、右の理念は、これを更に具体化した同法の各規定を解釈するにあたっても、強く念頭に置かれるべきものである。」「戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れ」「軍国主義的又は国家主義的傾向を帯びる面があったことに対する反省」から、旧教基法が制定されたという歴史認識を示しているが、この認識は、現教基法の下でもいささかも変わらない。したがって、学テ最判の歴史認識に基づけば、教育勅語が礼賛される余地など全くあり得ず、子ども達を戦争に駆り立てる教育行政の動きは許されないのである。
エ 「不当な支配」とは何か
学テ最判は、「旧教基法10条1項は、(中略)教育が国民から信託されたものであり、したがって教育は、右の信託にこたえて国民全体に対して直接責任を負うように行われるべく、その間において不当な支配によってゆがめられることがあってはならないとして、教育が専ら教育本来の目的に従って行われるべきことを示したものと考えられる。これによってみれば、同条項が排斥しているのは、教育が国民の信託にこたえて右の意味において自主的に行われることをゆがめるような「不当な支配」であって、そのような支配と認められる限り、その主体のいかんは問うところではないと解しなければならない」とし、「他の教育関係法律は教基法の規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関が他の教育関係法律を運用する場合においても、(中略)教基法10条1項にいう「不当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けているものを解される。」と述べる。これによれば、教育が自主的に行われることがゆがめられるような支配が「不当な支配」に該当し、教育行政機関は、他の教育法律関係法律を運用する場合においても、「不当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けている、というのである。したがって、もし教育行政機関が、教師や親達の反対にもかかわらず、教育勅語を礼賛し、子ども達を戦争に駆り出すような教育をさせようとするならば、それは、教育本来の目的に従って教師が自主的に行おうとする教育をゆがめるもので「不当な支配」であるから許されない、と言わざるを得ない。
更に、学テ最判は、「本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとして、党派的な政治的観念や利害によって支配されるべきでない教育にそのような政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する右のごとき国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない。」とする。教育勅語を礼賛することは歴史的事実のうちの重要な部分を無視若しくは改竄するもので、誤った知識ないしは一方的な観念を植えつけるものと言わざるを得ず、上記の観点に照らせば許されない。子ども達を戦争に駆り出す教育も、同様に許されないものと言わねばならない。
オ 世取山洋介は、以上のような学テ最判に示された「不当な支配」禁止に関わる判断、つまり「政治目的の教育内容への介入は許されないこと、一方的な見解の教授の強要も許されないこと、教育活動に深く介入し、あるいは強制力の強い手段を用いて教育活動に大きな影響を与え、教師の教育の自由を萎縮させるようなことは教育行政はできないことなどの判断も現在に引き継いでいる」と述べている(日弁連第55回人権擁護大会シンポジウム第1分科会実行委員会編「教育統制と競争教育で子どものしあわせは守れるか?」所収の基調講演「新自由主義教育改革と憲法・教育法」)。
カ 以上の、教育勅語礼賛に対する憲法、教基法の観点からの批判的検討の外に、子どもの権利条約の視点からの検討も重要である。字数の制約で内容は割愛せざるを得ないが、さしあたり、同条約前文、第3条、第6条、第12条ないし第15条、第28条、第38条等が引照されるべきものであろう。
3 おわりに
憲法26条は国民の教育を受ける権利を有する規定する。この簡潔な条文から、学テ最判は、教育に関する極めて豊かな内容を導き出している。学テ最判は憲法のコトバの中に思想・理念・精神・歴史認識等を注ぎ込んでその内容を豊かなものとしたのである。憲法は、簡潔なコトバで成っている。私達は、その簡潔なコトバの中に、自らの思想・理念・精神・歴史認識等多くのものを注いで、いま眼前に展開している事態を法の問題として取り込んだり、それを阻止するための論理を組み立てねばならない。憲法の条文は、そのような作業を通してはじめて力を持つに至る。学テ最判は、教育の目的は子どもの人格の完成を目指すことにあり、教育は、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、個性に応じて行わなければならないということを明らかにしている。教育についての本質をこのように述べていることは、教育を考える上で極めて重要である。教育についての憲法の力を自らの中に取り入れた教師が、子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、子どもの個性に応じて教育を行い、子どもが一個の個人として、また、一市民として成長発達し、自己の人格の完成実現のために必要な学習をする権利を実現させること。これが教育の力の源泉である。特定秘密保護法の強行、集団的自衛権を容認する憲法解釈の変更、亡霊のような教育勅語の礼賛等憲法の原理をゆるがせる事態が相次いでいる。しかし、こうした違憲の動向に対する国民の批判、反対は強固である。本稿は、憲法と教育の力を、教育勅語礼賛という小さな窓から見たものであるが、教育現場においては、現実の社会で日々生起する憲法的事象を取り上げて、生きた憲法状況を学習する機会を持つことを、一法律実務家として願ってやまない。