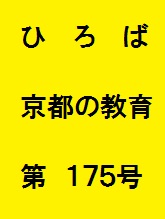
特集2 学校統廃合と地域
学校統廃合と地域
― 新自由主義教育下の学校統廃合、第3のピーク
山本 由美(和光大学)
学校統廃合が各地で急増している。表1にみるように、平成の市町村合併がピークを迎え、首都圏で学校選択制を利用した統廃合が急増する2002年頃から廃校数が増えている。選択制は、00年頃から08年頃までに集中的に導入された制度であり、その後は、小中一貫校による実質的な統廃合も出現していくことになる。
これまでは、自治体ごとに設定された「適正規模」である「12〜18学級」などや、「最低基準」の「150名」などを下回ることが、統合の根拠とされてきた。しかしながら、この間そのような基準を下回らない規模の統廃合が出現している。例えば、施設一体型小中一貫校を開校するために中規模校が統合され、全校児童生徒1000人以上の規模の“巨大”な学校が出現している。他方で、自治体レベルでの画一的な「公共施設の統合」施策による統廃合も出現している。これは、多くの場合中学校区を単位としており、小中一貫校の施策と連動する傾向がある。
そこでは、第1に、新自由主義的な地域の再編を進めるために、言い換えれば、活力のなくなった地域を切り捨てるために統廃合政策が用いられているといえよう。平成の市町村合併について、経済学者の岡田守弘は、地域の“グローバル国家への再編”すなわち「『住民の生活領域としての地域』と『資本の活動領域としての地域』とのかい離を後者の論理によって強制的に再編統合するもの」と定義づけた。学校統廃合は、まさに、その第2段階であり、生活領域を具体的につぶしていく役割を果たす。
さらに第2に、地域の小規模校を競争的な関係ができる大規模校に再編していくことにより、従来より早い段階からの子どものエリートと非エリートへの選別、およびエリートへの資源の集中を容易にする条件が整う。これは、安倍政権の目玉の1つである“平成の学学制大改革”がまさに行おうとしている改革である。教育の機会均等を保障する6・3・3制を見直し、序列的に再編していくことが目的とされる。
これまでの学校統廃合施策を振り返った上で、新自由主義的な再編としての学校統廃合が地域に何を及ぼすのか、具体的なケースに即して述べてみたい。
戦後の統廃合政策の変遷
統廃合の第1のピークは1950年代に自治体数を約1万から約3千に減少させた昭和の大合併に伴うものであるが、廃校状況は自治体によってばらつきが大きかった。社会学者の渡辺敬子によると、市町村合併は戦後資本主義の農村支配・地方行財政機構の再編整備のために打ち出されたものとされる。53年の町村合併促進法により、町村はおおむね8000人以上を標準とするとされたが、それは新制中学1校を効率的に設置管理していく規模と設定された。56年の新市町村合併促進法により、統合校舎の建築費の国庫補助率が従来の危険校舎改築などの3分の1から2分の1まで引き上げられ、校舎建築が自治体合併を誘導する政策が確立する。その直後、中央教育審議会は「公立小・中学校の統合方策についての方針」を公表し、具体的な学校統合の基準として「小規模校を統合する場合の規模は、おおむね12学級ないし18学級を標準とすること」および通学距離の基準として「小学校児童にあっては4キロメートル」中学校生徒にあっては6キロメートル」という今日まで継続する基準を提起した。行政効率性から導き出され、教育学的根拠はない「12〜18学級」および「国庫補助率2分の1」は、さらに58年の義務教育施設費国庫負担法によって固定化される。
それに続く第2のピークは、1970年の過疎地対策振興法によって、統合校舎建築の国庫補助率が3分の2にまで引き上げられたことにより統合が誘導されたものだった。高度経済成長のもと生みだされた過疎地の小規模校がターゲットとなったが、急激な統廃合の増加に伴い各地で統合反対紛争や裁判が続出する。そのような状況下で、1973年、国会議員の山原健二郎(日本共産党)による国会での追及から「12〜18学級」に教育学的な根拠はなく、「小規模校には教職員と児童・生徒との人間的な触れ合いや個別指導の面で小規模校としての教育上の利点も考えられる」ので「小規模校として存置し充実する方が望ましい場合もある」とする、いわゆる“Uターン通達”を文科省は出さざるを得なくなった。この基準は今日も有効性を持つ。文部省は、さらに74年度から危険校舎改築の負担率も統合と同じ3分の2にまで引き上げたため、安易な統廃合による校舎改築に歯止めをかけることになった。その結果、全国における統廃合数は74年から減少に転じていった。
その後、過疎地化に続く人口ドーナツ化現象に伴って、次第に都市部でも統廃合が実施されていく。例えば、1975年に公表された京都市の統廃合計画に対して、保護者、住民らによる銅駝中学校統合反対紛争(1978年〜)の中で同盟休校が行われたケースなどは典型例である。
この時期以降、このような保護者、住民による統廃合反対運動が裁判で争われるケースが多く出現する。特に、通学距離が遠くなることによる寄宿舎やスクールバス利用が子どもの教育権を侵害するという論点が多く用いられたが、採用されることは少なかった。しかし、1976年6月の名古屋高裁金沢支部決定は、統廃合によって児童生徒が徒歩通学する機会が失われることにより「人格形成上、教育上の良き諸条件を失う」といった、通学が子どもの人格形成上に果たす役割という問題を捉え、廃校処分の無効を認める画期的なものだった。今日、各地で実質的統廃合である大規模小中一貫校でスクールバス通学が多用されるケースが出現しているが、この論点は見直されるべきであると思われる。
新自由主義教育改革のもとでの統廃合
90年代から始まる新自由主義教育改革のもとで、保護者の選択行動を利用した統廃合は、まず、都道府県への地方交付税削減の影響をダイレクトに受ける高校段階で開始された。2001年の地方教育行政の組織および運営に関する法律の改正により、都道府県教育委員会が学区を定める義務が削除され、2003年の東京を皮切りに、学区を撤廃し全県一学区にする、もしくは学区を拡大する自治体(現在、47都道府県中23都県が学区撤廃)が増加した。さらに、教育学的根拠がない高校「適正規模」として「学年4〜7学級」などが自治体レベルで設定され、都市部の進学校などへの生徒の集中と競争の激化、山間部などの高校の生徒減および「適正規模」以下校の統廃合が導き出される。また先行的に、東京、神奈川、大阪などでは、製造業からサービス業・情報産業などへの産業構造の転換に応じて求められる“人材”育成のための多様化と称した高校制度のスクラップ・アンド・ビルドが行われた。そこでは非エリート層向けの定時制高校や旧来の職業高校、およびいわゆる“底辺校”が多数廃校された。
義務教育段階では、英米の教育改革をモデルに、学力テスト達成率による自治体・学校を競わせることによって統制し、公教育制度を経済目的に応じて序列的に再編していく政策に、学校選択制とリンクした学校統廃合も位置付けられていった。東京都においては、品川区を皮切りに学校選択制(23区中19区、26市中9市)が導入され、同時期に「適正規模(多くの場合、12〜18学級)」および「最低基準(150〜180人が多い)」が設定された。行政は、小規模校では“切磋琢磨”ができない、社会性が育たない、といった俗説を利用しながら、地域や保護者との合意形成の手続きを省略化し、学校維持費や改修費などコスト削減を図るためのみならず、跡地を民間に売却するなど経済目的の統廃合を行った。しかし、地域の教育力低下、伝統校の廃校を批判する町会長など地域保守層の反対もあり、東京では2008年以降導入はなく見直し・廃止が増加している。現在、橋下市長の大阪市のみが区ごとの選択制導入、及び統廃合をトップダウンで推進しているが、保護者、地域住民の反発は大きい。2014年度からの何らかの形での選択制導入は24区中11区にとどまっている。
選択制の全国的後退と平行して、小中一貫カリキュラムを根拠とする小中一貫校による実質的な統合が、2006年の教育特区制度を利用した品川区の日野学園を皮切りに全国に急増してきた。子どものために学習効果が上がる、小学校からの英語が充実するといった、検証されていない教育的効果が謳われ、さらに保護者が反対しにくい状況が生まれている。現在、全国で50校以上の施設一体型小中一貫校が開校し、中には市内の小中学校をすべて施設一体型にした佐賀県多久市のようなケースも出現している。このようなタイプの小中一貫校のモデルは英米では見られず、日本のオリジナルな改革の1つといえよう。(アメリカの場合は、大規模中学校進学に伴う安全面などのリスクを避け、9年間地域の小学校にとめおく「K〜8」スクールは一部の自治体で導入されているが、日本とは理念も異なり例外的なものである。)
また東日本震災後、耐震工事のための校舎建築への補助金交付期間の延長に伴う駆け込み統廃合が増加し、さらに隣接する2校の老朽化した校舎の片方を改修し、もう片方で児童・生徒を収容した後、新校舎へ戻すタイプの統廃合も出現している。統合する必要性の根拠が薄く、子どもへのダメージなど統合に伴うリスクへの配慮がないことから保護者に抵抗感が強く、東京都足立区などで裁判に至るケースも出現している。
コミュニテイの核としての学校
新自由主義教育改革は地域を軽視するが、地域が子どもの成長・発達にとって果たす役割は大きい。特に家族や学級集団や狭い地域など身近な人間関係の中で生活している小学校児童にとって、徒歩圏に家族的な関係の延長の小学校が存在することの意義は、成長・発達上軽視できない。また学校はコミュニテイの核として、地域住民の活動拠点や防災時の避難拠点としての役割を果たす。そこで形成されたコミュニテイの人間関係の中で、子どもの思春期の葛藤と自立も果たされていく。
統廃合によって子どもが慣れ親しんだ地域から無理やり引き抜かれ、新しい集団を形成していかなければならないことに伴うダメージなどについて、丁寧な配慮が求められよう。