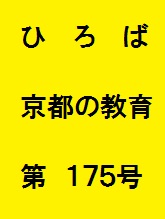
特集1 学力テスト体制について考える
現実の問題に向き合うための力と教育評価
― 学力・学習調査の功罪と子どもたちにつけたい力
川地 亜弥子(神戸大学)
調査そのものに対する評価を語る
今年は、「全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)」(小6、中3悉皆調査)の実施・結果発表だけでなく、PISA(日本語訳「国際生徒の学習到達度調査」)2012年の結果が公表される。結果公表時のマスコミの大々的な取り上げ方、一喜一憂する大人の様子を見て、子どもたちは何を感じるであろうか。
こうした学力・学習についての調査は、教育政策改善のためのデータとして重要であると考える人もいよう。一方、教育実践改善のデータとして生かすためには様々な問題があること(結果の返却の問題等)、議論が順位の上下を中心に語られていることなどに対して、これでよいのか、と感じている人もいるだろう。こうした、調査に対する大人の冷静な受けとめ方を伝えていくと同時に、そもそも、この調査では何が分かり、何が分からないのか、調査問題に偏り、改善すべき点はないかなど、「調査そのものに対する評価」を子どもたちと語ることを大切にしていきたい。これをしなければ、不自然な問いでも答えられるのが優秀な人間であり、違和感をもってしまい解けない人間は不器用で劣っているという、誤ったメッセージが子どもたちに伝わってしまうだろう。
教育目標から教育評価を考えるという大原則
さて、日本における近年の学力低下論は、1999年頃から活発化した。議論を加速させたのは、PISA2003の結果発表(2004年)である。読解リテラシーが平均並みの結果だったことで激震が走った。その後、学習指導要領改訂(2008年)が行われた。ただし、学力低下への問題意識から「教科の時数増」「言語力重視」の方針に変更されたと捉えるだけでは不十分である。
ここで問題にしたいのは、調査問題の構成が学習指導要領の改訂に影響を与えていると考えられることである。2007年、全国学力・学習状況調査が実施された。問題が、A問題「習得的な学習指導」(知識・技能)と、PISA調査問題に似たB問題「探究的な学習指導」(活用)によって構成された。その後、2008年版学習指導要領で、教科で「習得」と「活用」の力を育てることが示された。国際調査(PISA)→国内調査(いわゆるPISA型問題の導入)→学習指導要領の改訂、という流れが見える。端的に言えば、外部の調査問題が、学習指導要領の改訂に影響を与えていると推察できるのである。これは目標と評価の関係の転倒である。
本来、学童期・思春期・青年期における全面的な人格発達を保障する上で重要な役割を果たすものとして、学力保障が行われる。教育目標は、子どもたちの全面的な発達を期して構想されるべきものだ。しかし、外部の調査問題が教育目標に影響を与えるという関係の中では、調査で「よい結果」を出せる指導、「よい結果」を出すための目標が求められることになる。この異常な事態を打開し、本来の学力保障、発達保障に向けての議論へ転換させなければならない。
PDCAシステム下における「目標に準拠した評価」への批判
近年、佐貫浩氏が今日の指導要録体制下の「目標に準拠した評価」批判を展開している。管見の限り、佐貫氏が最もまとまった形で批判を展開している論考が、佐貫浩「評価論をめぐる論争点の検討(No.Ⅰ)――田中耕治氏・中内敏夫氏の評価論の検討」(『法政大学キャリアデザイン学科紀要 生涯学習とキャリアデザイン』vol.9、2012年2月、pp.87-110)である。(※以下のアドレスで読むことができる。 http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/7040/1/12_cdg_9_sanuki.pdf)。
佐貫氏は、「『目標に準拠した評価』は、教師の教育実践の自由の下においてこそ、初めて教育実践全体に対する自己反省的、科学的仮説検証過程の一環として機能するが、今日のPDCA システムは、教師と教育実践から、与えられた『目標』に対する批判の自由を剥奪したものである」(佐貫、前掲論文、p.87)として、教師の実践の自由がないところでは、目標に準拠した評価であっても評価は権力化していくと述べる。さらに、パフォーマンス評価(とくにルーブリック)に対して、「教育実践=学習過程は子どもが自らの課題に取り組むということを意欲とし目的として展開されている。その学習過程をオリンピックの体操競技やフィギュアスケートの評価のように、詳細なルーブリック(細分化された詳細なパフォーマンス内容についての評価尺度の一覧表)にそったパフォーマンス評価に曝して良いのだろうか」(前掲論文、p.89)として批判している。
鶴田敦子氏は、とくにパフォーマンス評価、真正の評価批判を通じて、目標と評価が教師に独占されていることに対して疑義を投げかけている。「ここで、真正な評価は誰にとってリアルなのかを検討しなければならない。/『真正の評価』ではっきりしているのは、『オーセンティック』な課題を設定するのは子どもは無理で教師がするということである」。「教育の専門家である教師が高次であるために考え抜いた課題に取り組む――すなわち教師の手にある学習――ことが、自分の学びを再構成していく主体として位置づける教育論と合致していると言えるか否かが検討されなければならないと思う」(鶴田敦子「家庭科教育の立場から--リアルな課題を問う」『教育目標・評価学会紀要』第22号、2012年11月、p.14)。鶴田の批判は、目標と授業づくりへの子どもの参加を具体的に議論してくこと(前掲論文、p.14)を求めている。
科学的な概念と生活との往還――数学教育の立場からの提起
このときに参考になるのは、石井英真氏の指摘であろう。「[従来の生活との結合論は]科学的概念への実感を伴った飛躍を実現する手段として、生活に密着した素材や活動を用いるものであり、ひとたび飛躍を実現したならば、抽象的・形式的な数学の世界のみで学習が展開することもしばしばあった。これに対して、銀林[浩「桎梏と化した指導要領体制」汐見稔幸・井上正允・小寺隆幸編『時代は動く!どうする算数・数学教育』国土社、1999年;川地補)らが提起するのは、実感を伴って把握した科学的概念を現実生活において総合的に活用するとともに、生活文脈や現実世界の問題に即して科学的概念そのものを再構成するような、科学と生活とのよりダイナミックな往復と対話のある学習なのである」(石井英真「算数・数学教育の立場から――『数学する活動』を軸にした目標と評価のあり方――」『教育目標・評価学会紀要』第22号、2012年11月。下線は川地)。
ここでは、実感を伴って科学的概念を把握することと、科学的概念そのものの再構成が生活文脈や現実世界の問題に即して行われるような学習の構想を重視している。例として挙げられているのが、小寺隆幸氏の関数を使って地球温暖化問題を考える授業である(小寺隆幸「カリキュラム構成の視点――数学教育を現実世界に開くために」汐見稔幸・井上正允・小寺隆幸編『時代は動く!どうする算数・数学教育』国土社、1999年)。地球温暖化防止京都会議の直前に行われたこの授業では、二酸化炭素濃度が地球温暖化の危険ラインになるのはいつかを予測した。その後、生徒たちは自分たちの予測が専門家の予測とほぼ一致していることを知った。自分たちが学んだ関数で、専門家と同様の予測が行えることを実感し、子どもたちは学習内容に対する認識をより深め、数学という学問そのものに対する認識も変えていったのである。科学的概念の再構成のときに、子どもたちの問題意識が反映されることが期待され、これまでに得た知識、価値を再評価していく可能性が示されている(ここには、その内容を吟味し、批判的にとらえることも含まれる)。
現代では、このような学習を行う単元として、原子力発電、放射線に関する内容を含むものが構想されるべきだろう。3.11以降、原子力発電、放射線についての学習の必要は、親も子も強く感じている。さまざまな情報がある中で、確かな情報を分かるようになりたい、というのは共通した願いである。京都教育センター編『子どもたちに確かな判断力をつけるために 原発・放射線をどう教えるか』(2012年6月)では、現実世界での誤った情報を読み解き、現実生活での判断を支えるような科学的概念の学習が可能となるように、子どもたちにも分かる原発・放射線のテキストを作成している。このようなテキストの開発・活用は重要な取り組みである。
与えられた問いをひっくり返す力
佐貫、鶴田、石井が重視している、子ども自身が主人公となり、問いを立て、学びを構成していく力は、いつごろ誕生するのだろうか。人間発達に関する「可逆操作の高次化における階層-段階理論」(田中昌人)では、大人の発する問いをひっくり返し、自分なりの答え方をするのは、生後第3の発達の原動力の発生の頃(通常5歳半ごろ)である。赤と白の積み木で構成したモデルを見せられ、「同じのを作ってね」と言われても、色や配置を入れ替えたものを作り、「(赤白・位置を)反対ニシタラ同ジヤ」と答えたり、5つの積み木をまっすぐ積んだものと、がたがたにずらして積んだものを見せて、「どっちが高い?」と聞かれても「5個ト5個ダカラ同ジ」と答えたりする。与えられた問いを吟味し、自分なりの根拠を持って応え、相手にも分かるように説明する力が備わってくる。この「理知り初めし力」によって、9、10歳ごろの発達の飛躍的な移行を成し遂げていく。
しかし、規範意識が強調されると、このような問いを発する子どもについて「どうして言うことをきかないのだろう」と考え、「素直に答えなさい」「まじめにやりなさい」と追い込んでいくことなる。あるべき姿を大人が規定し、そこに子どもを合わせさせていく関係ではなく、共に学び合う存在としてお互いに問いを発することのできる関係を築くことが重要になるだろう。
たとえば、3年生から不登校だった子どもが5年生から徐々に学校に来られるようになり、授業で俳句をつくろうという要求に対して、「思いつかん こまつはいつも むりを言う(6年5月)」と答えられるようになったとき、担任の教師は「実にうまく逃げるなあ」(小松伸二「不登校の子どもとかかわって」『作文と教育』2012年2月、p.71)と温かく受けとめている。学校を休み、休んだことでまた自分を責めていたBくんが、要求に対して自分なりの応え方ができるようになったとき、それを大切な力の獲得だと受けとめてくれた教師の存在は大きい。
このような安心の中で、試行錯誤をし、問いを立てながら学ぶ自由な学びが保障され、その中で先人が発明・発見してきた方法や知識のよさやおもしろさを実感しながら学ぶことが重要であろう。効率や強い指導が求められる現代では、そのような指導ができる環境や人間関係が築けているか、つねに振り返ることが必要である。
生徒と教師の関係の弱さの改善を
PISA2009では、生徒質問紙(日本では高校1年生が調査対象)において、「日本ではOECD加盟国中最も教師との関係が弱い」という結果が指摘されている(経済協力開発機構(OECD)編著、渡辺良監訳『PISAから見る、できる国・頑張る国2――未来志向の教育を目指す:日本』明石書店、2012年、p.86。同書、図2.19、p.88)。この中で特に肯定的な回答の割合が低かった項目は、「多くの先生は、私が満足しているかどうかについて関心がある」である。「とてもよくあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した生徒の割合が、日本では28%(OECD平均では66%)であった。日本では、教師が子どもに関心を持って関わっているつもりでも、生徒の期待とずれているのではないかと考えられる。また、「たいていの先生は、こちらが言うべきことをちゃんと聞いている」は日本63%(OECD平均67%)で、「助けが必要なときは、先生が助けてくれる」については日本64%(OECD平均79%)であった。先の結果と合わせると、こちらから言わないと関心を向けてくれない、と感じている生徒が一定存在することが推測される。
一方、同じ生徒質問紙の回答によれば、日本ではOECD加盟国中最も規律ある雰囲気で国語の授業が行われている。これらの結果からは、「まじめにしているのに先生は私を見てくれていない」、という子どもたちの声が聞こえてくる。教師が子どもと向き合える授業づくり、生活指導ができるような基盤整備が求められている。多忙さや教員評価体制の中で、良心的な教師ですら困難を感じる状況を打開しなければならない。