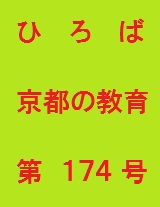
■特集テーマ 2 子どもの居場所としての学校のあり方
総論 子どもの居場所としての保健室を考える
三浦 正行(立命館大学スポーツ健康科学部教授)
はじめに
「学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健にかんする措置を行うため、保健室を設けるものとする。」と、「学校保健安全法」第7条に定められている。
しかし、こうした制度的な保証以上に、学校における保健室の存在は極めて大きいということが、多くの教育実践とその議論の中で確認されてきている。それは、学校に通う子どもたちの「居場所」としての価値を為すものでもある。なぜ、どのように「居場所」であるのか。専ら、この間の教育研究集会などで実践報告され、議論されてきた事柄を介して検証しておきたい。
1.「貧困・格差」の中での健康問題から
健康には、「いつでも、どこでも、誰にでも」あてはまる普遍妥当的な性質が強調されるが、現実は決してそうではない。多くの養護教諭が健康づくり支援の教育実践に取り組む時避けて通れない「貧困・格差」の問題がそのことをよく示してくれている。
イチロー・カワチ、ブルース・P・ケネディ/西信雄、高尾総司、中山健夫監訳、『不平等が健康を損なう』(日本評論社、2004年)が、拡大しつつある不平等は、資本主義の成功にともなう副産物であるとしてかたづけられるものではなく、むしろ私たちはそれが経済発展によってもたらされるはずのさまざまな自由を脅かしていることに目を向けなければならない。その自由とは、貧困からの自由、病からの自由、民主主義的選択を行なう自由、そしてすばらしい余暇活動を追及する自由のことであると語っているのが印象的だ。
世界的なレベルで見れば、「飢餓からの解放」、「清潔な水の供給」、「よりすぐれた衛生施設」、「子どもへの予防接種」、「医療技術へのアクセス」などは、「お金で健康を買うことができる」ことの反映である。それは、身近なところでも無関係ではない。そして、「身体が元手(資本)」の論理の中で、人々は、健康でいることが「身を守る」上で最重要の要件であると実感している。「稼ぐに追いつく貧乏なし」で表されるように、元気で働いてさえいれば、何とか食うに困らない状態を維持できるからである。しかし、一旦健康を害してしまうと、途端に「貧乏」への戸口に立たされてしまうし、さらに「貧乏」は、不健康を増幅させてしまう。そうした状況の中で、人々はひたすら「健康の私事性」よろしく「自己責任」の論理のなかで、健康でありたいと欲求し、不健康から脱しようと試みるのである。
健康の問題は、結局は人々の「からだとこころ」の問題として降りかかるものであり、それだけに「私事性」にもとづく「自己責任」が貫徹しやすい領域である。しかし、一人ひとりの個人の問題に閉じ込められない広く深い問題である。だからこそ、S.レフ・V.レフ『健康と人類』(岩波書店、1962年)が、「・・・健康問題は、・・・政治問題である。」と語っているし、それに限らず、多くの書物が、文化的・社会的・経済的など諸側面から健康について語ることになる。そして、保健室にやって来る子どもたちは、それら諸側面を垣間見せてくれることになる。
2.保健室の存在意義が問われる中で
保健室が、かつてその存在意義が捻じ曲げられ、喪失し兼ねない危機に立たされたことがある。それは、1997年の「保健体育審議会答申」に至る諸答申の下で、次のような具体的な構想が練られたことに関わっている。(1)これまでの学校を「基礎・基本教室」にまでスリム化する、(2)その外回りに企業も参加する「自由教室」をつくる、(3)さらにその外回りに企業も参加する「体験教室」をつくり、これら三つの教室のネットワークを「合校」と呼ぶ、というものだった。こうした「学校スリム化」は、「肥大化」した学校の機能を縮小させ効率化を図るための論理であった。学校が単に「学習の場」でなく、地域・社会そして家庭でのさまざまな教育的活動を一身に抱え込んできた経過をもつことは否めないし、「社会に開かれた」ものであれば当然ともいえる。しかし、そのことが逆に「公教育の否定」を導き出す道具として使われたりした。その典型を保健室・養護教諭の活動にみることができるかもしれない。
現実には、1日に40-50人(さらに学校、時期によってはもっと多数の)もの子どもたちが保健室に殺到し、年間では延べ3000人もの来室者がある実情が報告されたりする。そのような中では、「本来の養護教諭の仕事とは何か」と苦悩する状況が生まれてくる。
実際に、養護教諭の中からは、日々保健室での子どもたちとの対応の中で、散々なくらいの悪態をつかれて、「何で、こんな子に付き合わなければならないのか」「私は、あなたのためだけにいるのではない」と、対応自体に「忌避感」をもつこともある。しかし、その一方で、「今、子どもたちはとても心を痛めている。保健室にふてくされたようにやって来る生徒も、ゆっくり話を聞いてあげるだけですっきりして帰って行く。」「小学校から大変な子どもはたいてい、家庭の貧困な問題を抱えている。不登校で、何とか保健室に来れるようになった女子生徒が、教室に戻って行くまでになった。」「私は生まれてきたらあかん子やったと話す女子生徒が保健室に来て自己肯定感を回復させていく。」等々、子どもたちが「変わる」姿に接してもいる。
「ヤンキーが好きになれない自分がいる一方で、子どもたちの成長・発達の姿に感動を覚える自分がいる。」というように、養護教諭は、日々、保健室を拠り所としながら、そこにやって来る子どもたちと真正面から向き合っているのである。
こうした喜び・苦悩もする養護教諭と学会での「ケアをめぐる実践報告」の内容吟味の際に交わした筆者の「メモ」の中から紹介しておきたい。
・・・結論的に言いますと、一人の養護教諭ではもちろんのこと、一つの学校での取り組みだけで、あるいは教育現場だけでの取り組みで解決できるような状態ではありません。子どもたちは「荒んだ社会」の中に放り出されているということだと思います。貧困の問題は、経済的な部面だけではなく、人間の意識・精神の部面での「貧困化」をもたらす問題として改めて捉え直す必要があると思います。私は、「精神の荒廃」をもたらすことが、貧困問題の中でも、大変重要なことだと思っています。そして、この「精神の荒廃」の問題を克服していくヒントが「ケア」の発想の中に潜んでいるのではないかと思っています。
人間的なものではあっても、法的基準、倫理的基準など現状の「ものさし」だけでは計り知れない広くて奥深い「関係性」の中で、いろいろな事柄の「善し悪し」が推し量れなければならないような状態にあるのかも知れません。・・・
また、30数年中学校で一貫して子どもたちと向き合ってきた擁護教諭の場合には、その時々に様々な「エピソード」が充満している。例えば、荒れた子どもたちがキャリア付きの椅子に乗って「暴走」する中学生の前に立ちはだかって、寸でのところで急停止させるという一見すると「無謀な」行為も敢えてやってしまうのである。「暴走車」の前に敢然と立ちはだかる養護教諭も養護教諭だが、一方、直前で急停止した中学生の心情は如何ほどのものだったのだろうか。先に紹介した養護教諭の吐露する中学生への思いとダブって、子どもたちの成長・発達の筋道の問題として思い起こされる。
こうした姿に見られるように、厳しい競争の教育の場になっている学校にあって、保健室は子どもたちにとって「癒しの場」となっているのだが、一面では「逃避の場」でもある。その限りでは、今日の厳しい学校環境、教育危機の状況の中では、それを補完するものでもある。しかし、根本にあるのは、「なぜ、そんなにも多くの子どもたちが保健室に殺到し、養護教諭と接することを望んでいるのか」ということである。そのことによって、養護教諭・保健室業務が肥大化してしまっているということの分析とその真の解決策を見出すことこそが必要なのである。業務が煩雑になる中で、保健室に殺到する子どもたちを排除し、保健室業務を「整理・縮小」するだけで、今日の問題が解決されるわけではない。
3.「保健室の意義」を問う実践に引き寄せて
「保健室は子どもが”みえる””つながる”出発点」と題する、直接的に保健室の意義や価値に迫ろうとするレポートがあった。
保健室は、「学校保健安全法」第7条で規定されていて、制度的に設置が保障されている。しかし、そのことが、本来もっている保健室の「役割・機能」を十分に果たすこととイコールではない。この実践報告者が3年間勤務した中学校では、長年にわたり保健室は閉鎖されていて、必要な応急処置などは職員室で対応していたし、現在もそうだと言う。
そして、「保健室閉鎖」の理由が、数人の男子生徒が常時居座って「たまり場」になってしまい、担任等の積極的な対応や関わりもないまま、養護教諭が耐え切れなくなり、孤立もしてしまったことにあったという。確かに、「荒れた子どもたち」が「占拠」するような保健室は閉鎖を余儀なくされる。
しかし、鍵がこじ開けられたり、窓から侵入して保健室が荒らされたりすると、「何のための保健室閉鎖なのか」の疑問が頭を過ぎる。「これが本当に小学校なのか」と思わせるほどの荒れた状態を作り出す状況さえ生まれる。
保健室は、荒れて行き場の無い子どもたちの「たまり場」であると同時に、本当に診てほしい子どもたちにとっての「居場所」。存在そのものが意義あるものだと言える。その点からすれば、「保健室閉鎖」は、保健室を必要とする子どもたちにとっての重大事だ。但し、「保健室閉鎖」の本当の重大さは、養護教諭という、本来そこに居るべき人の存在を打ち消すことにあるということを忘れてはならない。つまり、子どもたちは、単に「空間・場所」としての保健室に来るということではなく、養護教諭のいる保健室にやって来る。そして、実践を介して語られるのは、養護教諭が「居座って」いる保健室では、荒らされることが少ないということである。
レポートでは、異動した現任校でも「保健室閉鎖」がされていた状況を変革して再開室にまで至った経過が詳細に語られ、それにもとづく討論がなされた。
参加していた何人かの養護教諭から、自身の学校ではないけれども、子どもが通う中学校で「保健室閉鎖」の実態があることが語られた。同様のことは、全国の至るところで散見される。「保健室が開いている」ことが必ずしも「当たり前」なのではない。荒れて教室に留まれず、行き場を失った中学生たちにとっての「たまり場」としての保健室からは、本当に必要に迫られながら、行きたくても行けない中学生たちが排除されてしまう。「保健室閉鎖」は、そうした止むを得ない状況で現実のものとなる。
おわりに
学校保健の中核に位置づくのが、養護教諭・保健室だ。学校における教職員との共同はもとより、地域・社会、家庭との「つながり」を図りながら、子どもたちの成長・発達に寄り添い、健康づくりの担い手として豊かな実践を地道に行なっているのが養護教諭であり、その拠り所となっているのが保健室だということへの確信を持つことこそが必要である。
また、「保健室登校」の子どもたちが「こころを開き」、教室に戻っていく足掛かりをつくるのも、もちろん保健室である。学級担任や一般の教諭の中には、保健室についての無理解が存在し、「養護教諭が甘やかすから保健室はダメになる」と言ったりもする。しかし、「いつでも、誰でもが入れる」のが保健室だ。「ヤンキーも来るし、保健室登校の子どももいる」中で交流が生まれるという「学びの場」が保健室でもある。結局、子どもたちの成長・発達を見守り、どのように寄り添って行けるのか。保健室が決定的に重要な場となっている。