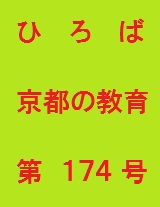
■特集テーマ 1 体罰について考える
体罰・暴力の再生産の仕組みと体育・スポーツ指導
石田 智巳(立命館大学産業社会学部教授)
はじめに
今年の1月に起こった体罰による自殺事件報道と,2月の女子柔道選手の暴力告発が引き金となって,各種スポーツ団体,体協,学会,行政機関などから体罰根絶の声明やアピールが出され,緊急シンポジウムなどが開催されている。私が所属する学校体育研究同志会でも,いち早く1月26日に常任委員会の名において「体罰を苦にした運動部員自殺事件に対する『私たちの見解』」を表明している(体育同志会HPにも掲載)。
とはいえ,表面上の直接の暴力行為に対する批判だけでは不十分なのであり,指導者の個人的資質の問題にとどめてはならないのである。そこには暴力や体罰を赦す雰囲気や時代的制約,さらには暴力や体罰が再生産される仕組みや構造があることに目を向けて,その問題への対応こそを課題としなければならないと考える。そこで,本稿では,体罰・暴力が再生産される仕組みについて述べる。その後,子どもの体育・スポーツ指導について述べてみたい。
1)体罰再生産の仕組み1−卒論での調査から
3月に卒業した学生の一人が卒論で体罰問題を扱った(山根秋穂「学校の運動部活動における体罰・暴力観について〜アンケート調査に基づく体罰・暴力に対する大学生の意識〜」)。この論文は,体罰・暴力の再生産について扱った先行研究をもとに,競技水準と暴力経験の関係を中心課題として調査を行ったものである。
結果としては,調査対象とした大学生116名のうち64名(55.1%)が,体罰・暴力を受けたあるいは見たことがあった。また,中学・高校時代に全国大会出場以上であった群では,体罰・暴力を受けた経験のある割合が54.7%,全国出場以下の群では体罰・暴力を受けた割合は26.9%であった。そして,全国大会出場以上の学生のうち,体罰・暴力を「必要」もしくは「場合によって必要」としたのは63%であり,全国大会出場以下の群では35%であった。さらに,全国大会出場以上で,体罰・暴力を受けた経験があった場合の83%が,「必要」もしくは「場合によっては必要」と回答した。先行研究にもあるように,暴力を受けた学生の多くは,成果として「精神的に強くなった」「技術の上達」をあげ,また指導者に対して「感謝している」「尊敬している」という感情をあげていた。
考察としては,体罰や暴力を受けた学生の意識は,やはり体罰・暴力を容認する傾向にあり,それは競技レベルが高いほどその傾向が見られるというものであった。つまり,競技成績の高さを担保にして,自らの閉ざされた経験的情報にしがみつき,新たな知見を受け入れられないということを表している。柔道界をはじめとする一部のスポーツ界では,こういった考え方が支配的だといえよう。
2)体罰再生産の仕組み2−体罰という公的な教育法
では,なぜ日本のスポーツ指導者の多くが体罰や暴力に頼ることとなったのだろうか。というのも,「日本」を考察した内外の文献のうち,古い部類に入るルイス・フロイスの『ヨーロッパ文化と日本文化』(岩波文庫)によれば,ヨーロッパでは「普通鞭で打って息子を懲罰する。日本ではそういうことは滅多に行われない。ただ(言葉?)によって譴責するだけ」とある。これは16世紀の記録である。また,明治初期に日本に滞在したイザベラ・バードも日本人が子どもを大切にする文化を持っていることを指摘している(『日本奥地紀行』,平凡社)。にもかかわらず,体罰が行われるようになる歴史的経緯はなにか。
それが軍隊に関わっていることは想像に難くない。明治初期の兵学校では暴力と無縁であったが,その転機は日露戦争にあったという(片山杜秀,「朝日新聞」2013年2月19日)。西欧列強のロシア相手に,「持たざる国」日本が挑み,かろうじて負けずに済んだ。しかし,今後どうなるかわからない。そこで軍事力の不足は精神力をもって補うべく「大和魂という名の下駄を履かせ」,「やる気のない者には体罰を加える」という動物のしつけ的な指導が行われるようになったというわけである。
明治以前は,日本の国内は封建社会であり大名や封建領主を中心とした階層的秩序があった。それが,明治維新とともに封建時代は終わりを告げるが,国外的には欧米列強と不平等条約を結んでいたため,国外の秩序を換えるために,富国強兵政策を進め,天皇を超越的な存在と頂き,国民皆レベルで内的な階層秩序を形成した。
軍隊内は等級によって差別化されており,下級が上級に服従することで,軍の秩序が保たれている。この秩序を保つためには,下士官であれば兵を,上等兵であれば下等の兵に「私的制裁」を加えて,全人格的服従も行われた。城丸章夫は,「この私的制裁こそが軍紀を維持する道だと,公然と信じられていた」(城丸章夫著作集第10巻,青木書店)と述べる。そして,日本の学校では明治の初め頃より兵営化が目指され,小学校でも「管理規則や生徒心得を作り,細部にわたって教員ならびに児童・生徒の行動を規制し,処罰を濫発し,軍隊的一斉動作と軍隊的服従とを強調するようになった」(城丸,同7巻)。そのなかで,軍隊的な秩序維持の方法として下級生いじめも行われたという。いわば,国を挙げて体罰・暴力を奨励したのである。
3)精神主義的スポーツの再生産
ルース・ベネディクトは『菊と刀』(社会思想社)において,戦時中の日本人の「無降伏主義」という特徴を指摘している。無降伏主義とは「戦陣訓」にも書かれているように,負けるときにいかに被害を少なくするのかという問いの立て方はなく,そもそも負けを考えずに最後まで戦い抜くことを美徳とする。そこにあるのは物質主義を凌駕すると信じる精神主義であり,「神の国」や「カミカゼ」的な神話主義である(「頑張れ」という声掛けは,まさにこの流れに位置づく)。だから,負けが許されない,あるいは勝たねばならないという勝利至上主義に結びつきやすい(負けることをどう教えるのかというのも今日的な課題の一つである)。
まさに,日清,日露戦争の頃に日本にスポーツが輸入されることになるが,その需要もまた「精神修養の手段」であり,野球においては,「武士的野球」や「一球入魂」(飛田穂洲)なのであった。体を痛めつけるような練習によって精神を修養するというのは,今でも「気力で打った」だとか,「最後は気持ちの勝負」という言い方に端的に表れている。そして,体育教師やスポーツの指導者が好んで使うのが「人間形成」という言葉であるが,この言葉が持ち出されるところに体罰が行われやすいという指摘もある。また,対戦相手を「敵」と呼んで倒すべきものと位置づけることも,戦争時代の残滓だといえるだろう。それらが戦後の高度経済成長時代の「モーレツ」やスポーツにおける根性主義となって,ぞれぞれの発展のための一定の役割を果たしたために,精神主義への信頼が残るのである。
保健体育科の教員採用試験にも,精神主義的スポーツの再生産の仕組みがある。まず指摘できることは,採用試験で重視されるのは「スポーツができる」ことである。さらに,全国の26都道府県でスポーツ特別選抜(要するに,一流のアスリートの優先採用)が行われ,国体要員の採用もある。ここにはスポーツの論理と教育の論理の混同がある。最初に述べたように,多くのアスリートが暴力を受けてきたわけではないだろうが,少なくともアスリートだからといって,教師に必要な資質としての多様な能力を持つ子どもたちを教えることがうまいわけでもないし,子ども集団を組織する力量を身につけているとは思われない。ここにも,再生産の仕組みがあるのである。
4)子どものスポーツと大人の関与
杉本厚夫によれば,子どものスポーツが確立するのは,コマネチが登場した1976年のことであるという(『映画に学ぶスポーツ社会学』,世界思想社)。これは象徴的な言い方であるが,要するに子どもが子どものスポーツをするのではなくて,この頃から子どもが大人のスポーツをする,あるいは,子どもがスポーツを大人にやらせられることになるのである。このことは,スイミングクラブやスポーツ少年団など,大人がお膳立てをしたスポーツを子どもがやることにもつながっていく。スポーツをするということは,プレイの場面のみならず,チームのメンバーを集めること,連絡すること,そして団体に登録すること,さらには練習や試合の場所を確保するなどが同時に必要になる。大学の部活動は主として学生自治でそういった活動すべてが行われている。子どものスポーツにおいては,指導者が子どもに替わってやることで,子どもは大人のスポーツをさせられることになるのである。
さて,スポーツは資本主義社会において自由主義的な性格を持って生み出されてきたため,かつてのアマチュアリズムに見られるように身分差別も内包していた。また,フットボールなどはプレイ中に暴力行為を許す荒々しいものでもあった。問題は残しながらも,それらを民主的な中味に作り替え,大衆が享受できる方向に発展させてきた歴史がある。私たちは,子どもたちがスポーツの主人公になるためには,技術習得はもちろんのこと(プレイ),民主的な組織運営のあり方や(組織),スポーツ要求の組織と訴え,あるいは,スポーツの継承と発展の主体者にふさわしいスポーツ教養(社会)などをあわせて教えるという考え方に立っている。今では,「三ともモデル(ともにうまくなる,ともに楽しみ競い合う,ともに意味を問い直す)」を実践課題として取り組んでいる。
実践事例を挙げるならば,「このクラスではどんなバレーボールがしたいのか」という問いから始まる実践がある(矢部英寿『たのしい体育・スポーツ』2010年2月号)。「楽しい」「仲良く」などとならんで運動が得意な子どもは「スパイクを決めたい」という。そこから,バレーボールがそもそもラリーをつなぐことを一方で目的とし,他方でスパイクによってラリーを切ることを目的とするように矛盾関係にあることや,競技のルールもこの二つを振り子の両極のようにして発展してきたことに目を向けさせていく。そして,子どもたちは「自分たちがやりたいバレーとは何か」,「それを実現するためにはどんなルールを採用するのか」,さらに「どんな練習を行うのか」をそれぞれ考えていく。最終的には,子どもたちの間で「きれいなラリー」の追求が行われるようになっていく。この実践でも,技術・戦術の学習,ルールの学習が行われるが,それらは「目指すバレー」に対する意見表明の保証(要求の組織)がされているからこそ可能になるのである。
スポーツの民主的発展とは,スポーツをやる者の要求がどれだけ汲み上げられ,実現に向けた努力がなされるのかにかかっているのであり,その指導こそが体罰・暴力のオールターナティブと考えるのである。
おわりに−構造的,文化的暴力の克服を
私が子どもの頃,すなわち70年代から80年代の前半は,社会に暴力がまだ満ちあふれていたといってもいい。今は,目に見える暴力はその根絶の努力によって表面上は少なくなってきているが,暴力を生み出す仕組みは遺伝子のレベルでまだまだ残っている。問題なのは,新たに暴力の仕組みを増大させようとしていることである。学校の教員組織も,行政の長の権限の増大も,民主的な話し合いではなく,組織を上下に明確に分けて,上からの命令に下が従うような組織作りが進んでいる。道徳の教科化の政治主導的な推進や,小泉構造改革による格差拡大などのように,政策がエリートの復権という新自由主義(デヴィッド・ハーヴェイ『新自由主義』)によって,上下関係=服従関係を生み出そうとしている。つまり,体罰・暴力再生産の構造を保持しようとしたまま,いじめや直接的暴力の排除・排斥を上から降ろそうとすることは,背馳にほかならないのである。