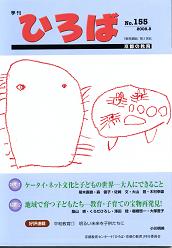
−−教育・子育ての宝物 再発見!
"子どもの世界"を地域につくる
築山 崇(京都府立大学・教育学)
何が人の心を荒廃させているのか
6月8日に秋葉原で起こった事件は、今日、何が人の心を荒廃させているのかを否応なく知らされるものであった。ケータイ。派遣。人の顔の見えないコミュニケーションの世界。人をモノのように使い捨てる派遣労働の実態。いずれも、人が人との直接的なかかわりの中で、その尊厳が守られないとき、人の心が非人間的な暗闇に閉ざされてしまうことを物語っている。
「癒し」ということばがキーワードとなって、すでにかなりの時間がたつように思うが、現代社会のどこかに心のオアシスを求める人びとの思いは今なお強い。しかし、時代はさらに、「癒し」から「蟹工船」へと進んでいる。身も心も丸ごと支配する現代社会の非人間性に、子どもたちもまたその感性を大きく傷つけられ、ゆがめられている。
"子どもの世界"はいま
ビー玉、メンコ、ゴムとび、おはじき、馬とび、鬼ごっこ、これらは、1960年代前半の子どもの世界を物語る遊びの道具・姿であり、モノ、人の肌触りをリアルに感じながら、技を磨き、競う子どもたちのいきいきとした表情が浮かぶ。このような子ども期を過ごした世代は、今祖父母世代となりつつあり、孫世代の育ちに大きな憂いを感じている。
今どきの子どもたちの遊びの世界の代名詞は? 次々と新製品が作り出されるコンピュータゲーム(身体を動かすものや、インターネットを通じて対戦ができるものなど)、○○カード、TV、ビデオ(DVD)、子ども世界の商品化は猛烈な勢いで進み、子どもの世界を浸食している。これまでにも、テレビ番組やゲームの内容が、暴力性や過剰でゆがめられた性情報などを焦点に問題視され、メディアに対する子どものアクセスを規制するなど、いわゆる健全育成、"子どもの世界を守る"ための手立てが様々に講じられてきた。しかし、一方で、インターネットの普及を背景に、新たな"有害情報"が氾濫し、そのコントロールが困難をきわめる中で、「学校裏サイト」など、より陰湿で深刻ないじめのスタイルも生まれている。
このような、子どもの世界の危機的状況のもとで、正にその危機感ゆえに、一層積極的に、子どもの世界にかかわり、子どもたちが心身ともに健康で豊かに育ちゆくよう、人間的なかかわりや活動の世界をつくっていこうとするおとなたちの努力、これに呼応する子どもたちのチャレンジもその流れを太くしつつある。そのような取り組みの一つに、創造的で、仲間とのかかわりを大事にする活動を展開してきた、学童保育、児童館の活動がある。そこには、楽しさの追求という遊びの本質を大事にしながら、手芸やお菓子づくりのような"つくる"活動、スポーツなど協力しつつ競い合う活動、ダンスや演劇など表現する活動など多彩な取り組みがあり、夏のキャンプなど自然と触れあう貴重な体験の場もつくられてきている。
子どもたちの放課後の生活を見ると、従来の塾やお稽古事に加えて、子どもが被害者になる事件が増えていることなどによって、安心して過ごすことのできる自由な時間が、一層少なくなりつつあり、おとなが用意する"安全・安心なプログラム"の比重が増す傾向にある。その際、活動の内容が、型にはまったものではない、子どもが自分たちの力とアイディアでつくっていくものになるようにしていくことが、子どもの人間的発達(人やモノと多様にかかわりながら、身体と心を育んでいく過程)にとって重要である。本特集2で紹介されている4つの活動は、そのような"おとながかかわりつつ、子どもたちが主人公となって活動を発展させていく取り組みの好例である。
特集2の導入にあたる本稿では、以下、今日の地域社会の変貌と子どもたちの世界の諸現象をとらえる視点、子どもたちの世界を、人間がその可能性をゆたかに実現していく場として、再創造していこうとする大人たちの試みについて、さらに、子ども、おとな、それぞれの世代内・世代間の関係をつむぐ地域のあり方について論じていきたい。
地域に注がれる視線
かつて、「地域に根ざす教育」は、民主教育の共通のスローガンであった。「地域の教育力」への着目は、資本による乱開発によって破壊される地域環境を守る取り組みや、地域住民の連帯・共同の力に依拠して、教育と子どもたちの発達を展望する文脈の中にあった。
しかし、今日では、「安全・安心のまちづくり」が、自治体が全国いたるところで進めるまちづくりのキャッチコピーとなり、危機管理、「ご近所の底力」、暮らしの支えあいなどが、少子高齢化社会の課題として、様々な観点で、様々な機会にくり返し語られている。そこには、競争原理を軸とした新自由主義思想のもとで拡散する国民意識を統合する手段としてまちづくりを考える流れ、あるいは、行政のスリム化による事業・サービスの削減・縮小を、「民間活力」の導入と住民の地域活動の組織化によって補おうとする行政経営の手法なども濃い影を落としている。
地域をめぐるこのような背景と地域社会の構造は、1970年代までの革新自治体建設の住民運動が拠って立っていたそれとは、質的に大きな変化を遂げている。同時に、国や自治体の施策の拡大・充実を求め、それを実現していった当時と違って、各種のボランティアグループや法人格をもったNPOなどが、教育・福祉・環境などの分野で、大きな役割を果たし、市民・住民の手による暮らしの創造の輪が広がっている点は、今日の時代を特徴付けるもうひとつの大きな変化である。
このような、地域を取り巻く大きな社会環境、地域自身の構造の変化によって、自覚的に生活を創造していこうとする実践の質も新たな内実を求められており、実践における人びと相互の関係づくりにも新たな視点からのアプローチが必要になっている。
「子どものための地域づくり」によって、子どもの世界に差し入れられる大人の手はどのようにあるべきなのか、子どもたちの世界は、どこまで可視化され、大人の手の内にあることがふさわしいのか、時に大胆な発想の転換もいるのではないだろうか。
近年、子どもの権利条約の理念にもとづいて、子どもの権利に関する条例を定める自治体が増えてきている。それらは、まちづくりへの子どもの参加・参画を位置づけていく志向をもっている。権利条約は、なにより、子どもを権利行使の主体として認め、その市民的権利を保障することで、子どもを社会の一員として位置づけている。「子ども議会」「子どもタウンミーティング」など、イベント的な子どもの意見表明の場づくりも行われているが、身近な地域に子どもの遊び場やたまり場をつくっていく取り組みなどに、もっと子どもがその計画段階から参加し、"つくる"活動の担い手となっていくこと、子どもたちの話し合いをリードし、仲間の声と力を集めて、日々の遊びや行事をつくっていく試みなどを拡げていくことが大切である。少年団活動や「冒険遊び場」づくりの試みなどから学ぶところも大きい。
子どもの目に映るおとなの世界
ここで、今日、子どもたちの目には、現代の社会やおとなの世界が、どのように映っているのかということに注意を向けてみたい。おとな社会がもっているゆがみを批判しつつ、子ども社会をその有害性から守り、子どもが人間として本来備えている発達の可能性に依拠し、これを実現していこうと、我々おとなは通常発想する。しかし、果たして子どもたちの目に、大人たちは、自覚的批判集団として、批判的創造の主体として映っているのであろうか。
京都教育センターの取り組みに参加した高校生が、「ここにいるようなおとなの存在を知って心強く思った」という趣旨の発言を聞かせてくれたことがあった。しかし、「こんな、おとなもいたんだ」という、"味方"の存在に意を強くする子どもたちは、残念ながら、チャンスに恵まれたごく一部に過ぎない。おとなは、子どもたちに届く発信をもっと強めていかなくてはならない。子どものために何かをしようとすると同時に、いやその前に、おとなたちは、なぜそのことをさせたいのか、そうすることが子どもたちに何をもたらすのかについて、もっとていねいに、粘り強く語りかけねばならない。
他人のことなどかまうことなく、私的利害に明け暮れ、嘘ばっかりでちっとも信用できない、表と裏の間に途方もないギャップがある、おそらくそのようなおとな社会の否定的側面を、子どもたちは敏感に、感じ取っている。おとなが現代の子ども世代の危うさに、不信と不安を募らせているように。
筆者がかかわったある都市における子どもを対象としたヒアリング調査でも、次のような結果が出ている。
子どもたちが「うれしい」と感じるのは、「褒められる・認めてくれる」「サポートしてくれる・話を聴いてくれる」といったときで、反対に「納得がいかないこと」は、「話を聴いてくれない・一方的な行為」「大人にとっての都合のいい使い分け」「不公平な扱い・比較される」といった内容で、おとなの「マナー・ルール違反」「モラルの低下」への批判の声もある。おとなの全体的イメージについても、プラスイメージより、犯罪や子どもへの暴力、自己中心性などのマイナスイメージが強くなっている。
このような子どもたちのまっとうな批判の声に、おとなは真摯に向き合っていかなくてはならないし、弱さや未熟さをもった存在として、子どもと共におとなも成長しようとするようなあり方が求められている。
表現・創造の世界と子どもの育ち
さて、今日の子どもたちが熱中する、あこがれる世界を見てみると、ダンス・音楽・漫画・ファッションと、いずれも創造性と表現に縁取られた世界であることがわかる。サッカーや野球など少年スポーツの世界も、競技そのものの面白さとともに、ファッション性が強く意識されているように感じられる。また、これらにかかわる情報は、インターネットを含むマスメディアを通じて流れているため、冒頭で述べたように、商品化の波に常に洗われている。
劇団や少年団、学童保育・児童館での活動などは、表現の世界を求める子どもたちの人間的欲求に、自然や歴史的文化、そして何より生身の人間の存在によってこたえていく可能性をもっている。
その際、ダンスは硬く萎縮させられている子どもたちの心と身体をほぐし、多様で豊かな表現の可能性を持った自らの身体に気づいていくことに、音楽は、競うことではなく、何より歌うこと、演奏することの楽しさを実感できる世界であることに、ファッションは流行という虚構を身にまとうのではなく、心地よく自分を包むことにむけられたものでありたい。
子どもの表現・創造を励ます大人(社会)の役割・課題
ここまで語り綴ってくると、"地域"というステージで、子どもの育ちを考えていくにあたって、私たちが今あらためて踏まえるべき、原理・原則も明確になってこよう。それは、子どもの主体性の尊重、子どもと大人との相互性の確認、子どもと子ども、大人と子ども、大人同士を"つなぐ活動"、世代内・世代間をつなぐ活動の全体像づくり、今私たちが未来へ向かって描く社会像づくりである。ひとことで言うなら、"子どもの世界"をその懐深く擁する地域社会をつくることである。
先日、大学での生涯学習論の講義の際に、受講生から「先生の理想の生涯学習のかたちについて教えてください」という注文を受けて、はっとした。各種の議論の批判を展開し、原則的な考え方について解説する一方で、目指すべき理想像をリアルに語れていなかったのである、「先生の・・・」という言い方で、一人の人間の固有の表現としてのそれを求める19歳の青年の感性は、非常に新鮮であった。
こんな町になったら、子どもたちも楽しく毎日が過ごせて、親たちも安心して見守っていられる、そんな町の具体的なイメージを描いてみたい。大きなキャンバスに、思いっきりいろんな色を使って、子どもとおとなが入り混じって、「夢のまち」を描いてみたら、そこから、たくさんのアイディアが生まれてくるに違いない。