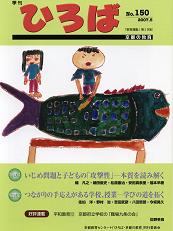
つながりの手応えがある学校−学びの道を拓く
佐伯 洋(立命館大学・千代田高等学校)
つらいとき悲しいときここへおいで
寺石くんが学校へ突然訪ねてきたとき、僕は職員会議の最中だった。廊下へ出ると寺石くんが立っていた。僕の顔を見ると寺石くんは泣きだした。うっうっと喉で声を押さえて、顔をゆがめて、涙が目からあふれている。(なにかつらいことがあって訪ねてきたんだな)と僕は思った。「よく来たなぁ」と声をかけると、にぎった拳で目のまわりをこすりながらうなずいている。「ごめんけど、いま職員会議でな・・・。待ってられるか」と尋ねると寺石くんは「待ってる」とちいさい声で言った。
二年前に僕の教室から卒業していった寺石くんは、いま中学生活の折り返し点あたりだ。小学校を卒業後、大阪港区を離れて奈良生駒のあたりへ一家転住したと聞いている。弟と妹のいる長男の寺石くんは責任感のつよい生真面目な性格だ。五年、六年と担任した僕は彼の人柄をずっと好きだった。
職員会議が終わると、運動場に出てみたが寺石くんの姿は見えない。思いあたった僕は、寺石くんと過ごした六年生のときの教室へ足を急がせた。予想的中で、寺石くんは教室の椅子に座り机に頬づえをついていた。背中は中学生の背中になっていた。
もう夕暮れもいい時間で、なにか食べに行こうと誘って並んで歩いて商店街の食堂に入った。僕はうどんの上に乗っているカマボコを一枚、ぽんと寺石くんの食べているどんぶりの中に投げこんだ。すると寺石くんはにっと笑って、そのカマボコを口の中にいれてうれしそうに食べた。なにかつらいことがあってやってきたのだろうが、とうとう寺石くんは言わなかった。僕も問いただしたり、聞きだそうとはしなかった。灯りのついた商店街をぬけて地下鉄の方へ歩きながら寺石くんは小学校のときの思い出話をひとつした。「修学旅行の晩、僕らはみんなで見せあいをしたら、タケマサなんかもうチン毛が生えてたけど、僕はまだつるつるで一本も生えてなかったんや」といった話だった。「そうか、いまは生えてるか」と僕が言うと、「そら、あたりまえやんか」と結構あかるい声だった。
改札を入ってから、ふりかえって、ちょっと手をふってホームの階段を昇っていった。訪ねてくるために費やしたと同じほどの二時間近くの道のりを電車を乗り継いで、もう一度もとの現実へと寺石くんは帰っていく。なんだか僕は涙ぐましい気持ちだった。
その後、幾か月かして、寺石くんのご両親が離婚して、妹や弟とも離れて暮らすこととなったことを僕は知った。
あの僕を突然訪ねてきた日の夕方は、寺石くんにとって何だったのだろう。きっと、小学六年生のときの教室の空気を体いっぱいに吸いこんで、家庭がそれなりにうまくいっていた頃の自分をふりかえり、確かめたかったのだ。いまある現実との折り合いをつけるためには、僕の前で泣くことも、彼の胸のうちが必要としたのだ。
「おまえ、よう生まれてきたなあ!」の拍手につつまれて
僕はいま「子どもの未来はあなたとともに−あたらしく教職員になられたあなたへ」という冊子を編集している。新着任の一人ひとりにこの冊子は全大阪府下で手渡される。執筆していただいた二十余人のうちの一人、北村孝子先生(羽曳野市・羽曳が丘小学校)の実践にもつよく心をうたれた。タイトルは「父母は子育てのパートナー おそれずに父母の力をかりましょう」だ。ここに紹介させていただく。
| 「・・・お父さんとお母さんは、結婚したらすぐに子どもは生まれてくるものだと思っていました。ところがそうではなく、六年目にしてやっと、病院であなたがおなかにいることがわかりました。その時は、もううれしくてうれしくて、すぐに会社にいるお父さんに電話して「赤ちゃんできたよ!」「ほんとかー!やったなー!」「うんうん」と今思い出しても涙が出るくらいうれしくて、感激し、その後どのようにして帰宅したかも思い出せません。そのくらいあなたの誕生を待ち望んでいました・・・」。 「・・・十年前丸二日にわたる難産の末、結局帝王切開であなたは生まれてきました。首にへその緒を二重にまいた状態で・・・もし江戸時代だったら、母もあなたも命をおとしていたことでしょう。生まれてきてくれたことがうれしくてうれしくて、毎日『生まれてきてくれてありがとう』と話しかけていたことを思い出します。でも、今はどうでしょう。母はいつのまにか、あなたに多くのことを求めすぎていたのかもしれません・・・」。 「・・・○○は、阪神大震災の日、私のおなかをけって、地震を教えてくれたお母さん思いの息子です。赤ちゃんの時は熱とひきつけをおこし、夜、救急病院に車をとばすことなんか、月に何度もあったし、一歳で入院して、病室の○○の寝ているベッドの下で寝たこともありました。そんな赤ちゃんだったからかはわかりませんが、本当に優しい、素直な子に育ってくれたと思います。・・・」。 「・・・もう十歳になるんですね。長かったような短かかったような十年間でした。ふりかえれば、○○の命が芽生えてすぐのころ、お医者様に『命の危険があり、あとは赤ちゃんの生命力にかけるしかありません・・・』と言われ、お母さんはお腹にいる○○に『がんばってね。お母さんもがんばるから、無事に生まれてきてね』と毎日話しかけ祈っていました。だから、無事に生まれてきてくれたときは、うれしくてうれしくて、お父さんと手をとりあって泣いてよろこんだんだよ。・・・」。 文集「1/2(にぶんのいちいち)成人式おめでとう」の「家族からのメッセージ」のコーナーには、クラス三五人全員の家族から、B5用紙ビッシリにメッセージが寄せられました。右はそのメッセージの一部です。私が全員の分を読み上げたのですが、私自身何度も胸にこみあげるものがあり、涙声になってしまいました。ファミリー全員が寄せ書きしてくださった家、お母さんが書いてくださった家、お父さん・お母さん合作の家とさまざまでしたが、期日までに三五人全員がメッセージを寄せてくださったことは、本当にありがたいことでした。 読み上げると、顔を真っ赤にしている子、照れて身体をどこかに隠そうとする子などもあり、教室があたたかい拍手につつまれ、とても幸せな気持ちになりました。 以上は、四年生を担任していたとき、性教育の学習と結んで「1(に)/(ぶんの)2(いち)成人式おめでとう」の文集を作ったときのものです。 子どもたちに「命の尊さ」を深く学ばせたいと思い、クラスの保護者全員に、お願いのお手紙をつけて依頼したのですが、全員のご家族からメッセージが寄せられてとても良い学習ができました。教基法は改悪されましたが、私たちは憲法に則り、保護者とがっちり手を結んで実践を深めていくことが、今とても大切になっていると思います。すこ〜しだけの先輩から−。 |
子どもは「大人からの愛着」を胸のうちにたくわえながら、「ほんとうの自分」をつくっていくのだ。
「評価の客体」として、競争のなかで、「良い子仮面」をかぶらなければ見捨てられるのではないか、という心の境地に立たされる子どもが「生きづらさ」を抱えこむ。そうした背景に起因する「少年事件」はいくつもある。北村先生の、僕たち編集部に届けてくださった実践の骨格は、「子どもの存在のうれしさ」だ。その「うれしさ」を父母があらためて自覚する場をつくったのだ。子ども一人ひとりの、かけがえのない存在としての、あたたかさと重みで、父母と教師と子どもがつながり合うのだ。
僕の身近な中学二年生の男の子。この子の名前を仮に"良太"くんとしておこう。良太くんは、中一の秋から学校に行って(行けて)いない。濁った大和川の流れを見ながら、良太くんは死にたいと思う。川を見つめてじっと立ちすくんでいる良太くん。その良太くんの背中にすっと近づいてきた自分の母親の気配にむかって、良太くんはつぶやいた。
良太「ぼく、生きてるねうちあるんやろうか」
母 「・・・だいじょうぶや、良太あんたはいま生きなおしをしているんやから」
良太「生きなおしをするんやったら、いっぺん死ななあかん・・・」
母 「あんたは、ねうちあるんやで」
良太「ねうちって、なんぼぐらい?」
母 「あんたは非売品やから値段はつかんよ」
こんな会話を交わすことのできる母と子。母と子の間を流れる時間は、せわしく忙しい時間ではない。ゆっくりと心のひだに染みこむ。ぬくもりのある時間なのだ。ほんとうの〈生きることの味わい〉とはなにか。相談室で、良太くん、良太くんのお母さんと向きあって、僕は目の奥が熱くなった。そして、早くて効率が良くて、強くて競争に勝ってというがんばれがんばれの風潮に、ふと立ちどまることの大切さを胸の奥におさめた。
ほんとうのことを知る大切さ
人格の発達とは、自分にとっての自分を選びとる、そのくりかえしの過程そのものだと考える。二月末、卒業を前にして、僕との最後の授業で学くんは「将来の夢」を僕に告げて卒業していった。人は、心の中に棲む人(人々)を支えとして、"納得"の自分を探すのだ。
| 私の将来の夢 小澤 学 私の将来の夢は、学校の先生になるということです。これはこの千代田高校に来てできた夢です。先生方の雰囲気やこの学校の生徒会活動など、この学校は本当にあたたかい学校です。中学生の頃は勉強するという意味が理解できず、ただ先生の板書をノートに写すだけでした。でもこの高校はそういう考え方を取り除いてくれました。KGノート(家庭学習ノート・筆者注)や充実ノートをしていくうちに、どんどん勉強が楽しくなり、勉強は大切なものだという考えに変わってきました。こういう考え方にしてくれたのには先生方の明るさあたたかさも関係あると思います。本当にいい先生ばかりで、すごく尊敬しています。 そういう先生に自分もなって、将来を担う子どもたちに、ほんとうのことを知ることの大切さや、勉強することの意味、楽しさを伝えていくことができればいいなと思っています。 |
高校を卒業する直前の、最後の授業で、学くんが僕に告げてくれたこと。それは「ほんとうのことを知ることの大切さ」だ。学ぶことを通じて、楽しいこととわかるということの統一が生きるちからの土壌となるのだ。
