 |
●京都教育センター通信 復刊第21号 (2008.3.10発行) |
西條 昭男 (京都教育センター)
映画『母べえ』(山田洋次監督)を観にでかけた。母べえ役の吉永小百合、学生の浅野忠信もよかった。子ども役の女の子は泣かせる。監督の思い入れが随所にみられる秀作だ。
ところで映画では鶴瓶が演じるところの吉野のおじいちゃんが登場する。母べえのおじで、しばらく東京に滞在する。これが、なんとも型破りで厄介なおじいちゃんで、その無神経な言動のせいで女の子を泣かせてしまう。
大っ嫌いなおじいちゃん、どうして、あのおじいちゃんが家にいるの、と母べえに泣いてつめよる女の子に、吉永小百合が演ずる母べえは、でもあのおじさんがいるとなんだかほっとするのと言う。
また、このおじさんは、贅沢は敵だと、街頭でキャンペーンをはる婦人たちに食って掛かり、贅沢はステキだと言い返して、官憲に連行され、絞られたりもする。普段はおじいちゃんには、いささかうんざりしていた周りの者も、そのときばかりはおじいちゃんに意気投合し、溜飲を下げるのである。
いっしょに生活していると、厄介なおじいちゃんではあるが、どこかほっとさせる何かを持ち合わせているまことに貴重な存在として描かれている。
さて、私は教室の子どもたちを思うのである。ミニ吉野のおじいちゃんはいないかと。
いるいる。立ち歩く、突然大声で歌いだす、その上教室を飛び出す大ちゃんは手がかかる子だが、これがなんともおもしろい。
月曜日の朝の健康観察。頭が痛いとか、ちょっとしんどいですとか、みんな、ぐだーとして元気がない。今日の体育はドッジボールしようと思っていたんやけど無理みたいやねえ、みんなしんどいみたいだから、センセイがそう言ったとたん、「もう、なおったあー」。大ちゃんが叫ぶ。つられて、あちこちから、「なおったあ」「もうすっきり!」口々に笑いながらの合唱。センセイもはははっと笑って、教室はいっぺんににぎやか。元気を取り戻す。大ちゃんのおかげ。
四時間目後半、音読の調子がいまひとつ。センセイいわく、今日の給食はカレーうどんやから、早めに終わろうと思ってたんやけど、この調子では終われへんなあ・・・。すると、すかさず、大ちゃん、「みんな、本読み、ちゃんとがんばりや。カレーうどんですよー」ときた。その一言でみんなははっとして、本読みの声に勢いと張りがでるから愉快だ。大ちゃんのおかげ。
掃除をさぼって大ちゃんが大目玉。ボクらはセーフ。大ちゃんのおかげ。
そんな子はどこの教室にも一人や二人はいるものだ。教室は「よい子」ばかりではつまらない。「よい子」のふりをしているとすれば余計に始末が悪い。職員室だって「よいセンセイ」ばかりが幅をきかせているとしたら子どもが不幸だ。もともと世の中はいろんなタイプの人間が集まって出来上がっているのだから。
文科省『心のノート』は「よい子」量産路線だ。いつも、やさしく、明るく(暗くなく)、規律正しく、秩序を乱さず。疑問をもったり、疑ったりせず、素直に(従順に)人の意見を聞く(人の意見に従う)。
息がつまる思いで現代を生きている子どもたちに、さらに追い打ちをかけるかのように「よい子」になれと。そして最後は愛国心を持て、である。 国を愛せよ、お国のために銃を取れ。オレ、そんなん嫌やあ!と大ちゃんが大声で言って、はっとしたみんなが、「嫌です!」「かなんわ!」と声を上げ出すかもしれない。
ミニ吉野のおじいちゃんは大切にされねばならないのである。
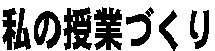
京都府立洛東高校 松村 啓一
担当する日本史A・Bで「映画」を教材に活用しています。
【なぜ映画?】
生徒の関心・興味、学習意欲を引き出し、歴史の理解を深めるためです。昨今の生徒の状況から判断して、全部見せることを基本にしています。なぜなら、その方が学習意欲は高まるからです。
【「映画学習」の留意点と教材選択の基準は?】
次のような点に留意して、教材選択の基準にしています。 (留意点)①年間プランの中に適合的に設定する。②目標やねらいに到達する手だても必要。③編集に工夫のあるものを選ぶ。④史実をふまえたものを選ぶ。(教材選択の基準)①歴史上の人物の生き方が描かれたビデオ。②歴史の謎を推理したビデオ。③解説的でわかりやすくイメージのもてるビデオ。④「歴史ドラマ」ビデオ。
【どんな映画を?】
日本史Aのラインナップは次の通りです。数字は視聴時間です。「たそがれ晴兵衛 3」「北の零年 4」「あゝ野麦峠(部分)1」「バルトの楽園 3」「戦争と人間第三部(部分)1」「さとうきび畑の唄(TVドラマ)4」「硫黄島からの手紙 3」「ALWAYS 三丁目の夕日 3」「パッチギ LOVE&PEACE 3」。かつては世界史に比べて 品数が少ないのが悩みでしたが、ここ十年で充実してきました。これらの作品は生徒の関心の外にあるようで、生徒の多数が観た映画は案外少ないのが現実です。その点でも見せる価値はあると感じました。
【授業との関係は?】
映画のシーンの中で、歴史の「事実」として確認してほしい事項(問い)を、普段の授業プリントに挿入して記入させています。授業の進度に疑問を感じるかもしれませんが、二〇〇六年まで進みます。そういう授業計画を作っています。
【具体的には?】
歴史の科目は時間軸に沿って、社会(地域)の変化の様子と原因を理解し考えることに目的があります。一九五八年の東京を舞台にした「ALWAYS」の場合、高度成長開始期の日本社会を知るシーンが具体的に登場します。農業(農村)から工業(都市)への大規模な移動は冒頭の集団就職のシーンで、企業社会の成立以前に多く存在した自営業や増大する「核家族」の姿は鈴木オートの工場や家族で、消費中心の社会への移行(三種の神器)は鈴木オートに入るテレビや冷蔵庫のシーンで、安保闘争と戦争の記憶の関係は医師宅間先生が家族を東京大空襲で失ったことを知るシーンで、というように設問を通じて確認させていきます。五十代教師にはノスタルジアの対象ですが、生徒にとっては未知の過去であり、現在を相対化し客観化する教材となります。
【誤った史実やイメージを与えないか?】
教室の授業では知識不足の生徒にイメージをもたすのは困難が多いです。映画を使った授業の史実やイメージに関するリスクは、教室の授業でも向じように発生します。映画の感動は映画の中に見られる「史実」とは無関係なことが多いですが、それでもいいと思います。その感情は映画を通じて歴史に関心をもち歴史を少し深く知ることに役立っていますから。授業アンケートでそれがわかります。
(日本史Bの授業の全体像は拙著『新・日本史授業プリント』(地歴社)をご覧下さい。)
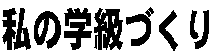
京都市立松ヶ崎小学校 安達 淳子
今ほど私達の仕事がむずかしいときはありません。実践をベースに学級づくりができ、子ども達がどんどん伸びていった若い頃の実践では、親も教師も子どもを伸ばそうと一生懸命でした。今でも、悩みながら実践しているのですが・・・・。
上からの学力っていったい何でしょうか。点数で計れる学力はいったいどこへ向かうのでしょうか。競争することでしか私達の仕事は計れないのでしょうか。子ども達にとって、学校は一日のうちで一番長い大切な時間です。できるだけ子ども達どうしがかかわり合う時間をたくさん持ちたいものです。
四月、新しい学年を担任すると、初めに『さくらのさくひ』という絵本を読むことにしています。この本は、もう年老いた桜の木が花を咲かせなくなり、地下のもぐらが、友だちである桜の木の根に水を運ぶのですが、手で運ぶことができなくて、「ぼくは君の友だちだったよね。」と言って涙を流し力尽きてしまうのです。でも、その涙のおかげで桜の花を咲かせることができるのです。私はこの本が大好きです。今は、四年生を担任していて『ごんぎつね』を学習しています。ごんはいたずらばかりしています。でも、ひとりぼっちになった兵十をみて、次の日もまた次の日もつぐないをするのですが、最後に兵十に撃たれるのです。その時、兵十はごんのやさしさに気付くという物語を読み合っています。最後まで読んだ時、何人かの子ども達のすすり泣きが聞こえてきます。その声を聞くと私まで悲しくなります。相手を思いやる気持ちは簡単ではないけれど大切にしたいと思いながら学級づくりをしています。
学級づくりは、日々の学習の中で「自分を出すこと」であり、クラスのみんなが「自分を出し合う」ことです。さらに、書くことは「考えること」であり、「考え合う」ことです。書くことでさらに学習が深められていきます。書くことの一つに、細々と続けている一枚文集があります。日記や作文や詩を書いてくる子の生活に心を痛め、その子どもたちに後ろを向くことができずに悩んでいる自分がいます。でも、それが、今の私を支えてくれています。言い換えれば、何度も負けそうになる自分を子どもたちの綴り方によって励ましてもらえているのだと思います。 また、親が誰にも言えずに心を痛めていることが表に出せるような、「わが子が大切にされている」という実感がなければ、親のかたくなさは溶けないのではないでしょうか。
お母さんやお父さんと語り合いながら、時間はかかるけれど、私達は子ども達に励ましとやさしさを送り届けたいものです。
| 1.第38回教育センター研究集会 | 「子ども・教育論不在の教育施策に抗し、未来をひらく教育を私たちの手で!」をテーマとして1 2月22日~23日と教文センターでのべ203人が参加して開催。プレ集会「教師の喜びと苦悩」(吉益敏文氏)、記念講演「教師の仕事と学力の形成」(佐貫浩氏)、授業実践報告(野村治氏、本庄豊氏、佐藤敏正氏)。分科会は8つの研究会企画で28本のレポート報告。 | ||||||||
| 2.公開研究会の開催 | 各研究会が企画委実した研究会(のべ13回)以外に全体企画として次の二つを開催。 (1)6月9日 41人参加 講演「新たな教育統制施策にどう立ち向かうか」八木英二氏(滋賀県立大)学力テストに関する報告(深澤司氏、魚山栄子氏、淵田悌二氏) (2)9月9日 70人参加 講演「PISA型学力の検証と学力テストの問題点」松下佳代(京都大学教授)報告(小野英喜氏、浅尾紘也氏、西原弘明氏) |
||||||||
| 3.教育研究集会への参加 | 京都教研にのべ39名の共同研究者を配置、民主教育推進委員会(6、11月)には41名の参加。 全国教研や全国民研には代表参加 | ||||||||
| 4.季刊誌「ひろば・京都の教育」の発行 |
|
||||||||
| 5.出版活動 | (1)「京都教育センター年報」第20号を3月に発行、配布。
(2)「センター通信」は2年目に入り、月刊ペースで発行し、全職場組合員、「ひろば」全読者、関係者に配布。 (3)その他、各研究会作成の会誌や通信、ニュースなどを配布。 (4)討議資料として「学力テスト問題」「学校づくりの課題」を提起。 ※センターHPの公開、更新 [http://www.kyoto-kyoiku.com] |
||||||||
| 6.研究会活動 | 8つの研究会がそれぞれ独自に研究活動を展開しています。 | ||||||||
| 7.資料室の整備・活用 | この間、関係者の尽力により資料室の整備がすすみ、全国の定期刊行物のバックナンバーが整理された。 | ||||||||
| 8.事務局体制 | ・事務局会議は(12名構成)は3週間に一回のペースで下記の日程で15回開催され、毎回7割程度の出席のもとに議論を深めてきた。企画検討会議(月一回)や拡大事務局会議(学期一回)も計画的に開催された。
・「研究員」の登録 退職教職員を中心に依頼し、センター企画のとりくみなどを案内し、希望により各研究会のメンバーになっていただく候補者として登録する制度。今年度より開始し、27名の方々に登録していただきました。 |
◇詳しい年間報告は「京都教育センター年報20号」(166P)に掲載。[希望される方はメールにてご連絡を下さい]
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。
テーマ「京都市・乙訓通学圏再編で、高校はどう変わるか?」
2008年3月20日(木、祝日)13:30~
教育センター室にて(別館2階)
報告:府立高教組、市内・乙訓の高校現場、山城地域の中学校現場より