 |
●京都教育センター通信 復刊第16号 (2007.10.10発行) |
京都市教職員組合 執行委員長 新谷 一男
「何でも日本一」、「全国に先駆けて」と全国どこへ行っても吹聴している門川教育長。
巨額の費用を投じて一点豪華主義の学校を作り、一方、窓も開けられないような老朽校舎が放置されている。統合された新しい豪華主義の学校には、北山杉の特別仕様の机やいすをすべての生徒が使用している。 給食に使う食器まで校章入りの特別製が使われている。その一方多くの学校では、卒業生が使っていた古い机やいすを新入生に使いまわしているところや、それだけでは足らなくて統廃合された学校から、まだ使えそうな机やいすを貰い受けて使用している学校もある。公立学校でこのような格差はあってはならない。
教育内容も、前の取り組みの総括も反省も不十分のまま、次から次へと新しいことが押し付けられてくる。そして、テストの点数を上げるための「学力向上」の取り組みが、矢継ぎ早に押し付けられてくる。日本の気候風土に合い、学校教育の中に完全に定着している三学期制をいっせいに二学期制へと移行してきた。学校・教職員に研究の名の下に膨大な研究紀要の作成や指導案の作成、研究発表に次ぐ研究発表。そして、父母や子どもへの対応がうまくいかなくて思い悩み、信頼を崩しかけている教師を、不適格教員として退職へと追い込む。一方、表彰や認定の基準があいまいなまま、優秀教員の表彰やスーパーティーチャの認証を行っている。ひとり一人の教職員を評価して、学校の中に一層競争主義を持ちこみ、教師も子どもたちも勝ち組・負け組へと追い立てている。
社会情勢の急激な変化の中で、子どもたちや父母の現状の厳しさからその対応で苦慮し、多忙を極めているのに、報告文書作成や事務的な仕事量の増大で、過労死ラインを超える長時間過密労働が強いられている。また、土曜・日曜日などの行事や部活動での出勤もあり、学校へ行かなくても持ち帰り仕事を行っており、まったく休日や休養もない状態が常態化している。現状の打開の方途と、市教組組合員が、超過勤務を強いてきた市教委に対して、超勤是正に向けて現在損害賠償請求の訴訟を起こしている。
教育は競争ではない。同じ市立学校で格差があってはならない。また、学校で働く教職員に長時間過密労働の強化でなく、ゆとりと教育の自主性と自由の保障、そして何よりも子どもとふれ合う時間の確保こそ必要である。この秋、京都市長選挙の勝利を展望しつつ、京都市の教育の困難な現状を少しでも改善するために、教育大運動に取り組んでいる。
第37回京都市教育研究集会 (市教組教研) 変えよう学校 ゆっくり楽しく学びあう場に〜今こそ憲法の精神に基づいた教育実践を〜 全体会 10月26日(金)6:00〜8:40 京都教育文化センター 記念講演 「今こそ語ろう、子どもたちに憲法を 〜平和を守る主権者を育てる〜」(仮題) 森英樹さん(龍谷大学法科大学院教授) 分科会 京都アスニー・社会福祉会館にて 10月27日教科別分科会9:30〜12:30 課題別分科会 1:30〜4:30 |
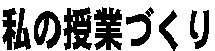
長岡京市立長岡第九小学校 下田 正義
(1)なるほど算数 数年前、4年の子どもたちの中に、3年で習った2桁のかけ算の筆算で、部分積をずらして書く事を、納得していない子どもたちがいた。そこで、面積の学習のあと、2桁のかけ算の筆算を長方形の面積の問題で、考えあったことがある。21×23のような筆算を、長方形の面積を使って考えたのである。1cm方眼のプリントを用意し、たて21cm横23cmの長方形を書いた。1cmがその中に何個あるかを数えることと、かけ算で出すことは、一緒のことである。21cmをはっきりさせるために、10cmの所に線を入れていく作業した。すると、図のようになる。 ここには、21×23の筆算の部分積が見事に現されている。 何問か、一緒にやった後、自分でやっていたE子が「先生、合ってた!」と思わず大きな声をあげた。私はそのことが強烈に残っている。 かって、私たちは、タイル図を使い、筆算の部分積の意味を具体的に図で視覚的にも理解させてきたことは、間違いではなかった。 |
|
(2)子どもと創る算数 昨年、計算のゆっくりなN男が、2けたの筆算で、一の位のブロックを並べて計算して いた。 N男に必要なことは、2けたの数で表されている数量の大きさを実感しながらの筆算の習得のはずなのに、私は、そのことを丁寧に教えてこなかったと反省している。 幸い、今年、また二年生の担任になった。そこで、昨年ははしょってしまった、ブロックの図と、数字の対応を丁寧に教えることに気をつけている。全員が楽しみながらできるように、クリアシートを使い、ブロックを使いながら、2人で協力しながら学習をしている。現行学習指導要領の改訂が具体的な日程になりつつあるが、お母さんお父さんたちが二年生のときにならった3桁の加減の筆算も扱うことにした。 幸い教科書には、何百・何十の計算が載っている。「200+300や300+50のような問題を筆算に表わすことができる?」と水を向けると、元気に「そんなの簡単!」と返ってくる。現行の教科書で扱われている、2桁+2桁=3桁、3桁−2桁=2桁の計算は、3桁の加減の計算の中でこそ、確かに理解できると私は考えている。 子どもたちは、3年の教科書に載っている問題をすらすら解ける自分たちが、カッコよく見えるようである。その続きでやった虫食い算も楽しかった。単に計算問題を解いているのとは、ちがう感覚である。答えの丸付けをしたとき「やったあ!」「よっしゃ!」の声が上がるのである。 こんな授業が、いま求められていると思う。 中学年から高学年にかけて「少人数授業」の中で、「なるほど」「子どもと創る」ことが少なくなっていると危惧する。子どもたちは、学びがいのある授業を待ち望んでいるはずだ。 |
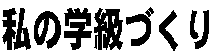
木津川市立南加茂台小学校 松田 森幸
運動会の前日、高学年の子ども達は激しく議論していた。高学年の表現「ロックソーラン2007」の入場の仕方についてである。静から動への変化をつけようということで、それまでの練習では太鼓のリズムに合わせて歩いて入場をしていた。ところが最後の通し練習の後で、一人の児童が「どうも歩いての入場は気合が入らない。駆け足の方がいいのでは。」という意見を出したのである。
早速全員で考えることにした。多くの子が同様の意見を出し、「駆け足で入場」と決まりかけた時、ある子が「ちょっと待って。」とストップをかけた。「駆け足で入場ということになったら、S君はどうするの。みんなから遅れるし、自分の場所もわからなくなるんじゃないか。それではS君がつらい思いをする。」というのである。
S君は重い障害を持ち、みんなと同じように判断し、行動することができない。またいろいろと意見が出、結局、S君の両隣で踊る子がS君と共に先頭を歩きみんなが走って配置につくときにはS君も自分の場所に立っていられる方法をとってみようといったが入場だけやってみることとなり、結果、何の違和感もなく踊りに入れることが確認できた。翌日の運動会本番、満場の拍手に包まれた子ども達は、満足しきった顔で退場門に向かった。
些細といえば些細なエピソードであるが、私達は、この小さな出来事の中に、自分達がつくっていこうとしてきた学校、子どもの姿を見る思いがしている。
この学校に転勤してきて三年目。「授業をつくる」ことを核に学校づくりを進めてきた。「自分の考え・思いを豊かに表現する児童を求めて」をテーマにし、文学的教材を中心に深く追求し合う授業をみんなで模索してきた。国語という教科は全ての教科の基本になっている。文章を読み取っていく力とか、また国語教育の中で培われた想像力とか追求力とか、集中力とか人間の幅とか深さとかが、そのまま他の教科での追求力とか想像力とかに波及していくと考えてきたからである。
これまでに、各学年での研究授業はもちろんのこと、節目節目では理論的学習や演習、模擬的授業などを行い、「教師が学び合い、力量を高め合う」ことを大事にしてきた。一年半程の間に学習しあったテーマは「どのように文学の授業をつくるか」「個人学習の内容と方法」「追求ある授業形態」「追求し合うに必要な力をつけるための具体的指導」「授業づくりと学級づくり」「追求ある授業のために」などである。
冒頭の場面。本番直前であってもみんなの前で自分の思いを率直に表明する児童、それをしっかり受け止めみんなの課題として返す教師団、困難な立場の友達に思いを馳せ、その立場で発言することのできる児童。そしてみんなの合意で一つのものをつく出すことができた。学校の一つの姿があるのではなかろうか。
この学校へ転勤してきた教師達は、「この学校は圧迫感がなく、居心地がいい」と言う。子どもを真ん中に据え、教師が納得いく実践に励めるような、そんな学校であればと願っている。
| 「流行」の兆し? 「PISA型学力」を検証する ―― 9・9公開研「松下佳代講演」に 70名参加 ―― 6月9日に開催した教育センター公開研(八木英二講演:41名参加)を継承した第2弾! |
||
9月9日(日)の午後、教文センター301号室で開催され、資料の追加印刷を余儀なくされるほど予想を超える70名の参加者がありました。「全国学力テスト」に「PISA型」といわれる問題が出されたことで、学校現場の関心も高く過半数が現職の参加で最近のセンター企画では珍しいことでした。松下先生は、PISAショックを受けた文科省の動きを分析しながら、4月に実施された「全国学力テスト」はPISAの“傾向と対策”として作成されたものでPISA型学力とPISAリテラシーは似て非なるものであることを具体的に示されました。 また、「全国学力テスト」結果はその「説明責任」を求められ、学校評価や教職員評価に連結するハイステイクスなテストになる危険性を指摘されました。 講演に先立って小野英喜氏(立命館大学、センター学力研事務局)から基調提起があり、学力問題をめぐる状況を評価方法の再転換や学習環境の視点から解明されました。 講演を受けての実践報告では、「学力テスト国語問題の分析・批判」が浅尾紘也氏(センター国語研事務局)から、「中学校における学習評価」が西原弘明氏(洛北中)から提起されました。 12月の「教育センター研究集会」では、この公開研のテーマを深め発展させる構想を練っています。 |
||
|
12月22日(土)〜23(日) 教育文化センター(全館で)
日程
22日:午前 京都教科研と協賛したプレ集会
(08年8月に教科研大会を京都で開催)
吉益 敏文先生(乙訓小学校、京都教科研事務局長)に教師のよろこびと苦悩を語ってもらいます。
午後 記念講演 佐貫 浩(法政大学) 「ブレる文科省に抗し、私たちの手で教育再生を!」(仮題)
実践報告 子どもが輝く授業実践に学ぶ (小・中・高の現場教師から)
23日:全日 8分科会
地方教育行政研究会/生活指導研究会/学力・教育課程研究会/発達問題研究会/子どもの発達と地域研究会/家庭教育・民主カウンセリング研究会/高校問題研究会/教科教育研究会・国語部会
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。
特集 ◆検証 京都市の教育行政はこれでいいのか
◆養護教諭が担う役割−−子ども理解と支援ネットワークの形成