 |
 |
●京都教育センター通信 復刊第15号 (2007.9.10発行) |
京都府立高等学校教職員組合執行委員長 寺内 寿
7月の参議院選挙で、安倍政権と自民・公明与党は歴史的大敗を喫し、参議院での与野党逆転という、新しい政治状況が生まれた。国民はこの選挙で〝二つのこと〟― 貧困と格差拡大の「構造改革」路線と、「戦後レジームからの脱却」を標榜する憲法改悪路線― に対する〝ノー〟の審判を下した。それは、国民の悲鳴にも似た怒りの審判であり、これまでの自民・公明政治に代わる新しい政治を求めたものといえる。
またこの結果は、「教育再生」を政権浮揚の「最重要課題」とした教育基本法改悪と教育改悪三法を強行した安倍「教育改革路線」の企てに大きな打撃を与えることになった。その一端は、選挙直後の世論調査(7・31~8・1FNN)で安倍政権の「教育改革」を「評価しない」が55%をこえたことでも明らかである。これは教育政策の転換にとっても大きな条件と可能性をもつものに他ならない。
参議院での与野党逆転は、私たちの予想を超えて、政治を現実に動かし、要求実現を迫りうる新しい可能性をはらむことになった。
はや、改憲のための憲法調査会の発足は事実上先送りされ、今後の憲法闘争前進の新しい条件を拓きつつある。テロ特措法延長をめぐる攻防、ホワイトカラーエグゼンプション導入断念、障害者自立支援法見直し、消費税増税計画の沈静化など、安倍政権の重要政策が少しずつきしみ始めている。
今、私たちの改悪教育基本法の下での学校・教育づくりもまた、この新しい政治状況を生かすとりくみのとば口にある。教育改悪三法案の国会審議で教職員の働き方が追及され、管理統制強化と教育予算・教職員を削って暴走する安倍「教育改革」への不安と批判が専門家やマスコミを含め大きな世論となり、伊吹文科大臣をして「(教員が)子どもと向きあえる時間をつくることが大事」「年末の予算編成で努力したい」と、答弁せざるをえなかった。すでに、中教審では少人数学級の検討が始まり、文科省は、〇八年度概算要求として、一万人の定数純減の政府既定方針(行革推進法)を承知の上で、2万1000人(三年計画)の教職員定数増を決定した(その内容には重大な問題点を含む)。府教委もまた、子どもと向きあう時間の確保を目標に、庁内にワーキンググループを立ち上げ、教職員業務の見直しの検討を開始した。国民と共同した私たちの運動が政治を動かしうる状況が、学校・教育づくりをめぐっても始まろうとしている。
学校・教育づくりをすすめる上で、今、大切にしたいことの一つは、教育基本法闘争やこの参議院選挙で発揮された父母・国民の見識とたたかうエネルギーであり、父母との共同の条件を限りなく広げていること。二つには京都のすべての学校に〝職場九条の会〟を立ち上げるなど教職員の〝九条改憲ノー〟の多数意思をつくり、子どもと教育を守る決意を内外に表明することだと考えている。 (2007年9月3日 記)
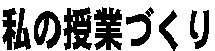
京都市立日吉ヶ丘高等学校 後藤 誠司
いまどきの教師の「三つの病」があるそうだ。①授業のファストフード化、だれがやっても同じような授業をしている、②同僚性の欠如、ヨコのつながりを持たず孤立している、③公共的な課題への鈍感さ、広く社会に目を向けようとする意欲や関心が薄くなっている。
現在進行中の政府の「教育改革」のもとでこのような現象が指摘され、教師の仕事の「脱専門化」がますます進行して教師は単なるサービス提供者としてしか見なされないようになっていこうとしている。 しかし、そうならないように努力している教師たちもいる。長崎県の中学校で国語の教師をしている友人に、彼の学校での様子を教えてもらった。東京大学教授の佐藤学さんが中心となって全国で取り組まれている「学びの共同体」パイロットスクールに参加している学校の様子である。それは、授業と学校の「再生」をめざす学校をあげての「下からの改革」の動きでもある。(「現代思想」2007年4月号、青土社、参照)
友人が語るには、生徒の学習意欲を敏感に感じとり授業の改善をめざす教師と、生徒の学習意欲に鈍感で授業の改善に無関心な教師どうしの乖離が年々増大していることが、生徒の学力格差と連動している。教育改革は、畢竟、教師の一時間一時間の授業改革であり、教師と生徒の関係性の改革である。さらに彼は言う。OECDのPISA国際学力調査の結果にもあるように、生徒が他者と関わりながら学べるようにすることが最も「実を上げる」学力向上の取り組みであると。こうして彼は国語の授業での様々な創意、工夫に挑戦していく。「改革はすなわち自己の破砕と再生を循環させる営みなのだ」。まさに彼の言うとおりである。(「日本語学」2005年6月号、明治書院、参照)
ということで私の授業づくりの要諦も、「三つの病」に罹らず、教科(社会科)の「専門性」を維持し高めていくことにある。定年までの十年、授業の形と中味をどう変えていくことができるか、さらなる挑戦である。子どもたちが伸び伸び過ごせ、教師たちも楽しんで仕事に打ち込める学校であればどんなによいことか。そのような学校の環境づくり、職場づくりのための条件整備とともに、教師は「教える専門家」であると同時に「学びの専門家」でもなければならない。そのような教師の専門性回復の鍵を握っているのが、自発的なサークル・研究会活動であり、校内での公開授業や事例研究の取り組みであり、研修時間の確保である。教育が非教育的な効率にふりまわされ外面的な基準で評価されるようなことに対して、教師の自律性と専門性を回復することこそ、授業の「再生」と教師としての「誇り」を取り戻すことにつながるはずだ。子どもの頃よく聞いた言葉を思い出す。「よく遊び、よく学べ」。教師もまた生活を楽しみ、多くのことを学びたいものだ。
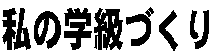
大山崎町立第二大山崎小学校 吉益 敏文
はじめに
学級づくりは、教師の指導性と包容力にかかっている。このごろ、いろいろなところできまったように語られる。教師の集団を動かす指導力と、一人一人を大切にする指導力、この二つの統一が大切だと力説される。メリハリのあるクラス、楽しく明るいクラスを作るということなのだろう。私は今まで、そのことを念頭に学級づくりをしてきたつもりだが、うまくいったといえる状況はあまりない。しかも学級崩壊的な状況に遭遇し、四苦八苦したことがある。
ただ新任以来、ずっと続けていることが一つある。それは、子どもたちの詩や作文を読みあい語り合うということだ。
詩や作文を読み合うおもしろさ
今、国語の読解力、国語力の大流行である。いかに短時間に自分の考えを○字以内に書きあげるということが要求されている。それは大切なことだが、まず子どもたちの書いてきた作文や詩を教師が楽しんで読む。それをゆっくり読み聞かすように子どもたちに読んであげる、ということを大切にしたい。
子どもたちは、虫を取ったこと、友達と遊んだこと、家族のことなど、実に多彩に、ある日あるときのことを書いてくれる。それはうれしかったり楽しかったり,やったーという思いであったり。時に悲しいこと、つらいことを書いてくれたりする。作品によってみんなの前で読めない作品もあるが、子どもたちの作品を読んでいると、子どもたちがかわいくなってくる。教師である自分が知らない子ども達の一面を知ることになる。
私の場合は読みきかせとあわせて一枚文集にして、朝の会や終わりの会、時には授業の中で読み合っている。その子の作品で思ったこと、同じような体験を語り合うということを続けている。
お互いをすこしずつ理解しあっていく
子どもたちは、クラスという集団の中で、お互いを知っているようであまり知らないことが多い。高学年になってくると、気を使いあって本音を語らないという場合も多い。ゆっくりと作文や詩を書かせ読み合っていくと、実にゆっくりだがお互いを理解しあって、やさしくなっていく。もちろん、これだけで学級づくりが完成するものではないし、人間関係がすっきりいくというものでもない。ただ子どもたちは、「読まんといて」「載せんといて」といいながらも自分の作品を読みあうときの表情は穏やかだ。1枚文集を配ったときなどの静けさ、集中はなんともいえない瞬間である。ただ最近は個人情報の関係で、なんでもかんでも読みあえるというわけにはいかなくなった。なんでもいえる、安心して語り合えるクラス作りの基礎がそこにあるように思う。今、私は3年生を担任しているが、その子どもたちに読んであげた、昨年の四年の子どもの書いた詩がある。
| ○○家 4年女 今日もみそしるに 味そをいれてるお姉ちゃん そこへ お母さんがさわり 「なに どこさわってんの」 と 姉 「えっ よく育ってるかたしかめてんの」 と 母 「なんで」 と姉 「農家の人が かぼちゃのできぐあいをたし かめてんの」 と 母 これが毎日のようにある。 さわがしすぎる |
子どもたちと一緒に笑った。ただそれだけだけどホットした時間だった。
終わりに
子どもたちの詩や作文を書かすとあとが大変ということもあり、多忙化した現場の中では、文集にしたり通信にするということは、なかなか手間ひまのかかる仕事で、敬遠されがちである。以前であれば父母の中から自分の子ども以外の子どもたちの様子がよくわかるといった感想があったが、今はどちらかというと否定的な意見も少なくない。
「もっと、けじめのあるピシッとしたクラスにしてください。」
「作文や詩もいいですが、漢字や計算がしっかりできるようにしてください。」
父母の当然の願いに真摯に答えなくてはならない。そのことを前提としつつ、やっぱり子どもたちの作文や詩を楽しく読みあっていきたいと思う。
自己表現が自由にできて安心して受け止めてくれる仲間がいる。その上でメリハリのついた行動ができるように。
楽しみながら続けていきたいと思う。
注目される地域、家庭での発達・学力保障の二つのとりくみ
次期の学習指導要領改訂を前にして文科省は、小・中学校の「総合学習」の時間を削減し「主要教科」の授業時間を1割程度増やすことを示しました。この間の文科省のぶれる学力政策や、少子化での塾の加熱を懸念する立場で地域や家庭から子どものまともな発達や学力づくりをめざす注目すべきとりくみを二つ紹介します。
[報告]
京都家庭塾交流集会:「子どもの学力、今親ができること」 藤原義隆さん講演
| 8月25日の午後、南青少年活動センターで開催。「家庭塾」では、「受験塾」とは異なり学習習慣を身につけるために親子でとりくむことを重視。藤原さん(元市内小学校教師、教育センター「学力研」)の実証ずみの学力形成の話は定評があり、京都で家庭塾をしておられるお母さんを中心に、遠くは東京、岡山、愛知などからも25名が参加されました。藤原さんは、今の教育情勢や財界の「思惑」にもふれながら、科学としての教育を確立していくことの重要性を語られ、自然・社会を科学の目で見抜く力と学力が中枢を形成する言語力形成の重要性について強調されました。主催は、「京都子ども勉強会」などでつくる京都家庭塾交流集会実行委員会です。併行して行われた児童講座には15名の小学生が参加し7名のスタッフから、鉛筆の正しいもちかた、電気パンづくり、腹話術と人形作りなどにとりくみました。 (「子ども勉強会」澤田 稔) |
[案内]
京都教育センター子どもの発達と地域研究会 「公開研究会」
どなたでも参加できます
| 9月15日(土) 13:00~16:00 教育センター室(別館2F) ・ 「4日間のキャンプでこんなにお~きくなりました」 左京少年少女センター 指導員 浅野明香さん ・ 「地域社会で育つ子どもたち」 地域研 棚橋啓一さん |
「非行」と向き合う全国ネット学習会IN京都
子どもの“荒れ”と向き合う―――ひとりで悩まないで!
9月22日(土) 13:00~16:30
教育文化センター [体験報告]
①「自らの荒れを体験して」藤岡克義さん
②「我が子の荒れと向き合って」母親Aさん
③「子どもたちに寄り添うなかで」能重真作さん [交流]
主催:「非行」と向き合う全国ネット(京都教育センター後援) 連絡先:親と子の教育センター 勝見さん
京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。
特集◆教育再生会議で学校・教育は良くなるのか-現場からの提言
◆保護者に開かれた学校づくり-教師と親がつながり合うとき