 |
●京都教育センター通信 復刊第14号 (2007.7.10発行) |
京都教職員組合執行委員長 藤本 雅英
日本の未来、子どもと教育、くらしに関わる重大な参議院選挙、投票日7月29日が目前に迫っている。 「消えた年金」、「住民税などの大増税」、「貧困と格差の拡大」、「政治と汚れた金」の問題、さらには、自衛隊による国民の平和活動などへの「スパイ活動」や防衛大臣の原爆投下「しょうがない」発言などに対して国民の怒りの声が燎原の火のように広がっている。安倍内閣の支持率が急落している。自民・公明党の悪政の本質が浮き彫りにされつつある。参議院選挙は、自民・公明の暴走政治をストップさせ、悪政の転換をはかる絶好の機会であり、きわめて重要な国政選挙となっている。
憲法9条を改悪し、アメリカとともに世界で武力行使出来る態勢確立、そして、「従軍慰安婦」への軍関与の否定発言や、沖縄戦に関わる教科書書き換え、DVD「誇り」の普及策動など「戦前社会」への回帰の動きを止めなければならない。改悪教育基本法の具体化、「教育再生会議」による「教育破壊」ともいうべき政策の具体化を許さず、今こそどの子にもゆきとどいた教育を推し進めなければならない。安倍首相のいう「美しい国」づくりをすすめる従順な「モノ言わない」公務員、教職員づくりにむけた公務員制度改革や公務・公共サービス切り捨て、人件費削減は、公務員、教職員にとどまらない国民的な大問題である。教職員の長時間過密勤務問題も深刻な問題である。サービス残業分の人件費も増やさず、新しい職を設けて賃金差別を広げ、教職調整額の差別支給をおこないさらに教職員の分断・管理強化さえ強めようとしている。このような教育破壊につながる動きを許してはならない。
この間の教育基本法改悪、「教育3法案」反対のたたかいは、その反動的なねらい、本質が明らかになり、子どもと教育を守る共同が大きく広がった。「全国一斉学力テスト」が教育格差をいっそう拡大することへの国民の懸念が広がっている。教育予算を減らしながら教育反動化と格差拡大に暴走する安倍内閣の「教育再生プラン」への疑問と批判が広がっている。京都府教委の教育長は校園長会議で「国レベルで提起される教育改革に振り回されずに、地域に根ざした教育改革をすすめるべき」と言い、「教職員を疲れさすような無駄なことをさせるな」とも述べた。そういわざるを得ないところにも安倍内閣の「教育改革」の矛盾の深刻さがあり、府民、国民的な運動の反映がある。
そうした運動の到達点をふまえ、改悪教育基本法の具体化を許さず、憲法に立脚して、子どもたちの豊かな成長を保障する教育、教職員が「誇り」をもって立ち向かえる教育を進めるために参議院選挙に関わる政治論議、政党選択の論議を職場からおおいに広め深めなければならない。
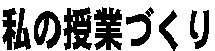
──音楽の授業から──
宇治市立御蔵山小学校 木村 真留(すぐる)
私は、京都音楽教育の会で、二十七年以上、学び続けています。
毎月、合宿例会があり、みんながピアノを弾き合って歌い、そして教室の音楽の授業の実践テープを持ち寄り、聞き合って話し合います。夜は、おいしい物を食べながら、ピアノと友達となって、音楽の広場をつくりだします。
その六月例会の夜の音楽の広場で、工藤吉郎さん(元・京都市立中学、音楽教師)は、御自身が作曲された いす という曲を、弾き歌いして下さいました。その曲が、私の心に、引っ掛かりました。
| 「い す」 この うつくしい いすに いつも 空気が こしかけて います そして たのしそうに 算数を かんがえて います まど・みちお 詩(詩題は「かいだん」) |
二年生を、今年は担任しています。
とても素直な三十五人のこどもたちで「つくしがでたよ、たんぽぽひらいた」(こばやしけいこ 詩、丸山亜季 曲)の歌を、いっぺんに好きになって歌ってくれました。
音楽の授業は、教科書教材の他に、サークルで歌ってきた、たくさんの教材の中から、今、目の前にいるこどもたちと歌いたい曲を選んで歌っています。
その曲の一つにしたいと、私の心に引っ掛かったのだと思います。
「いす」のうたの、「そして、たのしそうに算数をかんがえています」のフレーズが、なんともいえず、教室で算数をたのしそうに勉強しているようすが浮かんできました。
教室で、一つの問題を、みんなでたのしそうに考え合っているという空気が感じられます。
そんな空気を感じて、こどもたちといっしょに歌ってみたいなと思ったのです。
そして、実際の算数の授業も、そんな授業でありたいなと思ったのです。
――「実験場」の山城から市内・乙訓通学圏の「改革」批判――
宇治久世教組・木幡中分会 中野 謙二
今、京都府・市教委による「京都市・乙訓地域公立高校入試選抜に係る懇談会」が異例の頻度で開催され、六月末に出された「まとめ」をもとに「規則を改正」し、来夏に新制度要項を発表し、〇九年度入試から実施しようとしています。その内容は総合選抜制度を部分的に残すなどの「歯止め」がみられるものの、多くは三年前から山城地域で「実験した」制度を下敷きにしています。 私は一昨年までの三年間、宇治市の中学校で三年生を担任し、〇四年度より府教委のトップダウンで変更された山城地域での「新制度」下で大変な苦労を強いられました。「百害あって一利なし」と言ってもいい「山城方式」を市内・乙訓地域に持ち込もうとしている今、実験場となった山城通学圏でのリアルな実態を限られた紙面で伝え、「山城の二の舞を許さない」声が各所で上がることを願います。(詳しくは山城地方の高校統廃合問題を考える会の「黒書」を参照して下さい)
「三原則つぶし」の名の下に八五年から強行された「京都方式」(九通学圏での類型制度)は多くの矛盾と困難を拡大しながらも、今や全国で唯一残るⅠ類での総合選抜制度を残し、ささやかながらも混迷の歯止めになっていました。ところが、四年前の〇四年度入試から山城地域で強行された「新方式」は①山城北・南の二通学圏を一つに統合 ②総合選抜から単独選抜へ ③三段階(前・中・後期)入試で受験機会を複数化 ④Ⅰ・Ⅱ類の一括募集 ⑤内申点を全学年から採る。というのが主な内容。
「希望する高校を選べるバラ色のプラン」(四十一中学校から十二高校の志願が可能)というのが「売り」で、生徒も保護者も私たち教師もその新方式に「バラ色」を垣間見た。しかし、三年間その入試最前線で携わってきて、「バラ色」はトゲのある「灰色」であったというのが今の実感です。その問題点は、①単独選抜により予測しがたいバクチのような志望校選択(併願増) ②中期(一般)入試では毎年二〇〇~三〇〇名の不合格者が出る(市内の2倍超) ③通学圏の拡大で遠距離通学となり地元の高校は存在しない ④高校間格差が増大し、生指上「問題なし校」の一方で一年間で中退者一クラス分を生み出す高校が発生。そして、この進学状況が中学校の評価・格差に。単独選抜ではなく、「総合選抜制」が維持できていればこんな学校間格差はおそらく生まれなかったでしょう。
中三生の多くは「専門学科より普通科」「遠い高校よりも近くの高校」「いい(悪い)高校より普通の高校」を望んでいます。その思いを大切にして「学ぶよろこび」と「生きる力」を見通せる進路実現をはかるのが私たち中学校教師の願いです。塾などがつくる偏差値をもとに振り分けざるをえない「指導」はもううんざりです。「選べる自由」は実のところ「選ばされる不自由」につながることを、すでに「実験場」となった山城地域から告発し、市内・乙訓の中学校の先生に知ってもらいたいと切に思っています。
--6・9公開学習会に41人が参加し、熱い議論--
改悪基本法下での教育統制施策が3法改悪や再生会議などの手法で矢継ぎ早に出される中で、教育センターは表記をテーマに6月9日学習会を開催しました。講演頂いた八木英二氏(滋賀県立大)は次の点を強調されました。
| ①教育政策は「改悪基本法」のもとでの4・24全国学力テストを起点に、深刻な矛盾を引きずりな がら新たな段階に踏み込んだ。 ②文科省は深刻な実態のもとでぶれる学力形成をめぐって、今度は「PISA型学力」指向を打ち出 そうとしている。 ③そのもとで岐路に立たされている学校現場にあって「子どもの全体を育てる学校と教師」の新しい 役割を教師観の社会的変化にも着目しながら実践集約を手がかりに模索すること。 ④新しい国家主義の下での困難克服には時間がかかるが、共同のネットを張り積極的に問題提起して いく事の重要性。 |
特別報告として次の3つの内容がありました。
・淵田悌二氏(元中学校教師):60年代の学テ闘争を当時のテレビ報道も交えて、理科授業の楽しさを語られました。
・深澤司氏(京教組教文部長):今回の学テの問題点と氏名を明記させないたたかいの成果を報告されました。
・魚山栄子氏、江上由香里氏(新日本婦人の会):学テの中止を求める仮処分の法廷闘争の教訓と次年度への課題を。 その後、5人の方からの発言があり、ぶれまくる文科省の学力観に対峙した私たちの学力形成実践の重要性が語られ、次の機会にその議論を深めることを確認しました。
[感想]
毎日が「その日の授業の生徒の自己評価の整理」「翌日の授業プリントの作成」「部活動メニューの作成」「清掃場所の点検」などに馬車馬のごとくに追われています。校内では、校長、教頭、生徒指導加配、特別教育支援加配などが毎時間校内パトロールしており監視されているようでストレスが貯まりっぱなし。疲労も蓄積されて病院通い!そんなせせこましい日々から離れて、「大きなうごき、大きな観点の教育的刺激」を求めて「元気をもらう」ために参加しました。「反省する実践家」の八木先生の言葉は私の思いと一致するところが多く印象に残りました。私たちのよく見えないところで子どもたちのために奮闘されている教組や新婦人の話はまさに「元気をもらいました」。(乙訓・研究員 岡本幸男)
鈴木史朗(東光小) 西村嘉夫(田辺高) 白根俊之(莵道第2小) 阪田 剛(間人中) 松岡博之(長岡中) 浜野利夫(長岡3中) 北村 茂(雲ヶ畑小) 累計 27人
●[民主カウンセリング研究会]
7月21日(土)10:00 教育文化センター203号室
「民主カウンセリング・ワークショップ」
グループ・エンカウンター
【京都教育センター 公開研究会のご案内】 『PISA型学力』を検証する:「リテラシーと学力」 松下 佳代 (京都大学教授) 2007年 9月 9日(日)13:00 教文センター301号室 4月の学力テストは「PISA型」の出題がひとつの特徴だと言われた。文科省はこの間、ゆとり教育を見直し新たな「詰め込み」に傾く一方で、「思考力」「読解力」を重視する次の学習指導要領を目論んでいる。こうした動向を批判的に分析し、リテラシーと学力形成について議論を深め、実践を対置していく内容です。 今から、日程を手帳に入れて下さい。 |
京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。