 |
●京都教育センター通信 復刊第13号 (2007.6.10発行) |
「教員免許更新制度」許せぬ!
元中学校理科教師 淵田 悌二
「人材の育成」ではなく、「人格の完成」をめざすことを教育の目的(第一条)とする教育基本法は、その第六条(学校教育)に「・・・教員の身分は尊重され、その待遇の適正が期せられなければならない」とある。
しかし、憲法の理念を具体的に実践するための教育基本法は、二〇〇六年十二月、その改悪案を審議不十分なままの「自民・公明のみによる強行採決」というフアッショ的なる行動がとられた。そして、その改悪法を具体化していくための悪法「教育三法」の一つに「教員免許更新制度」があり、これらもまた強行しようと恐るべきことが進行中である(〇七年五月)。定年退職後十年以上にもなるとはいえ、この悪法に対して「文科省教育制度改革室」宛抗議も送付したが、再びこの機に批判をしておきたいと思う。
一、「教員免許更新制」なるものは、教育の条理・本質にも反するばかりか、憲法九条の理念を学校教育の場において否 定することと連動しているもので許せな いものである。また、学校教育の場は子 どもたちと先生がともに活動する場であ り、未来への希望と人間としての連帯、そのための安全・安心が保障されなければならないものである。
現行の教員免許は大学での単位修得による一種の資格としての性格を有するものであり、教員の能力は子どもや保護者たちとの豊かなふれあい、教職員集団の中での学び合い励まし合いなどを通じて、その実践の中で育まれていくものである。「十年」でその「資格」が「一方的に取り消される」という性格のものではない。この制度は教育の本質をごまかすものである。
二、①教育懇談会の自由を保障すること。このことは、多様な意見・教育要求の合意を得るためにも、教育実践への協力・支援を得るためにも必要なことである(しかし、そのための時間保障、内容・意見の自由さえない現状)。 ②職員会議での発言の自由を保障し、合意形成のための十分な時間の保障、民主教育における絶対条件である。 ③教育実践の自由・研究の自由を保障。教育行政の「研修」のみではなくて、自主的なる研究が可能なる時間・研究費・体制の保障を。「十年ごとの更新制」ではなくて、「十年ごとの自由なる研究・学習の時間をこそ保障」すべきことだ。教員の専門性である。
今日の「教育再生」にとって必要なことは、「教育三法」ではなくて、以上の三点ではないかと思う。
教育にとって必要なことは、「強行採決」による政治的介入ではなくて、国民的合意の形成である。日本最古(一六六八年)といわれる「閑谷学校」では、「藩主の公門は狭く」「庶民と武士の子弟、他領の者も入学させ」「藩財政からの独立」と掲げられ、今日の教育行政さえ学ぶべきものがある。今日の教育における競争主義と管理体制という最も不適切なる行政は許されるべきでないと思うのだが、いかがなものか。
(二〇〇七・五・末)
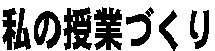
亀岡市立つつじヶ丘小学校 小林幹弥
昨年の四月、専従休職を終えて、現場にもどりました。もどって驚いたのは、低学年を担任するということでした。その理由は低学年(二年生)を担任するのは、初めてだったからです。
低学年を担任するにあたり、どんな教室(学級)をめざそうかと考え、「一人ひとりを大切にする教室」にしていこうと考えました。それにはまず、自分の子どものように接し、その子どもたちの願いを感じることからはじめました。それは、①安心できる先生であってほしい。②自分を認めてくれる友だちがあふれている学級であってほしい。③友だちと遊びや活動をいっぱいしたい。そして、何よりも④楽しく、わかりやすい授業であってほしい。ということだと考え、それらを満足させる取り組みを軸にして、自分の子ども三十六人に接するように教室(学級)づくりをすすめていきました。
①に対しては、教師の指導姿勢「ひいきしない」「自分の子どものように愛する」をはっきりとしめし、大いに学級通信を活用し、伝えました。②に対しては、月一回のお誕生会をリーダーとともに作り上げて行い、誕生日カードを教師、子どもから送ってみんなでお祝いしました。そして、終わりの会では『今日のホームラン』と題して、一日の中で友だちががんばったこと、やさしくできたことを出し合い、拍手を送りました。また、日記を週に一回書いて、それを一枚文集にして読み合い感想を交流しました。③に対しては、クラス遊びを係り活動としてすすめ、手・足・体でふれあうゲームを終わりの会でもして、「明日も楽しくがんばろう。」と感じながら帰れるようにしました。また、「ハイタッチ」をして、笑顔でしめくくりました。④に対しては、こだわりをもってする教材(文学教材、かけ算の九九、体育)においては、プリントを作成して取り組みました。
担任が変わることがわかり、春休み中にお腹の調子が悪くなって、始業式の当日、遅れて暗い顔でやってきた女の子がいました。不安な気持ちが体の変調を起こしたみたいでした。でも、クラスづくりをしていく中で、その女の子は少しずつ変わってきました。
| こないだかみの毛を切りに行きました。かみの毛を切りに行ったところはなでしこでした。わたしはほとんはかみの毛を切りたくなかったのにお母さんが、「切りなさい。」といったから切りました。お母さんもかみの毛が長いのにお母さんが、「かみの毛をのばしているから切らない。」と言いました。プールがおわったらのばします。 |
年々学校は多忙になっています。特に午後からはもっと余裕がなく、安全のための学年下校に間に合わすために、どうしても「早くしなさい」「ちゃんとしなさい」と注意することが多くなります。そんな中でも、時間割りを書くのを五時間目始まる前の五分間にして、帰る用意の時間も確保しながら、十分間の終わりの会をしっかりと保障し、しっかりとほめて気持ちよく帰れるようにと心がけました。
八幡市立中央小学校 栄養教諭 木村啓子
本校に転勤してから五年目になります。途中城陽市へ五年間行きましたが、採用されて約三〇年ほとんど八幡市で勤務しています。食育が注目されていますが、八幡市では以前から給食に対する思いが一貫しています。(栄養士の力に負うものが多いと思いますが) 手作りのものを提供する。食材の安全性を最優先させる。各校にあった給食も実施できる。楽しい取り組みを取り入れる。アレルギー食にも配慮する。など子どもを大事にする給食が展開されています。
給食は、その学校の実態に即したものでないといけないと思っています。本校に勤務した当初は食事を大切に思っていない子どもたちの現状におどろきました。食事は提供された食べ物(料理)とそれを食べる場の雰囲気です。食べる姿勢、マナー、よい材料で心を込めた献立すべてが教育です。はじめに取り組んだのが手作りのクッキー、ケーキでした。当初は「まずい」と言っていました。手作りの味に慣れていないからです。
調理員が大皿に盛り付けるパーティ給食、考えて選ぶ栄養バイキング、そして冬場の鍋給食、六年生への松花堂弁当やテーブルマナー給食など、目で見て楽しく、手をかけてくれていることがわかる給食を心がけました。子どもたちに自分は大事に思われているということがわかってほしいと調理員と一緒にいろいろアピールをしました。調理員には、集会の場で話をしたり、普段の結びつきを強めるように子どもたちに声をかけてもらうなど、一歩前に出る姿勢をとってもらいました。
また、栄養士としても、参観日にテーブルマナーの授業をしたり、本物のだしの味をしってもらおうと校区の料亭「松花堂 吉兆」との連携授業などに取り組みました。本物のだしと地場でとれた旬の野菜の煮物に子どもたちは素直に「おいしい」と言ってくれます。
そこから学んだことは、食べる人のことを考えて作る料理です。どのようにおいしく食べてもらうか心配りします。そういう姿勢は必ず子どもたちに伝わります。本物は確かに「おいしい」と言う力を持っています。 そうして五年目、確実に成果は上がっています。まず、残菜の少なさと「ごちそうさま」の声の多さです。自分たちが大事に思われているということをわかってくれています。
この前、兄弟学級で食べる給食をランチルームでしているときです。特別にとクッキーを出すのですが、やはり一年生が「先生このクッキー固いしまずい。」と言いました。そうしたら六年生が「何言うてんの。こんなにおいしいものないのに。ゆっくり食べてみ。」と言っていました。本物はおいしいというのが、子どもの舌を通じてわかっていくのです。 大人になってもきっと手作りの味は覚えてくれていると信じています。そして、子どもたちが親になったとき自分の子どもにそれが伝えられたらなどと思っています。
京都教育センターでは、団塊世代の退職時期を迎えて、退職教職員を対象にして「研究員」の委嘱・登録を今年度からはじめました。多くの方々は民主府政下で採用されながらも、その後の京都の教育の反動的変遷の過程を意気高く歩んでこられました。民主的な教育実践や運動の体験・教訓を引き継ぎながらも今に生きる研究を推進するために、教育センターの一翼を担っていただくための組織化です。今後希望により、共同研究者にも登録いただくことも考えていますが、研究員の任務は「センターが行う公開研究会などに参加いただき、提起や討論に参画していただくこと」です。その委嘱を開始しましたが、5月末現在で要請に応えて登録いただいたのは次の方々です。( )は最終勤務校です。
| 大塚富章(大宅小) 新庄祐三(洛東高) 清水忠信(勝山中) 平田庄三郎(第2向陽小) 布川庸子(大久保小) 酒井弘一(木津中) 原田省造(鶴ヶ岡) 坪 健治(南加茂台小) 秦 保恵(鳥羽高) 福井波恵(青谷小) 武尾正信(男山第三中) 中村誠輝(洛水高) 井上正則(岩滝小) 平本喜美代(東宇治中) 安本俊昭(嵯峨中) 中路清種(槙島小) 千賀 繁(山田小) 齋藤哲雄(嵯峨野高) 岡本幸男(長岡第二中) 田中吉照(高の原小) |
| 昨年の12月15日に教育基本法か強行改悪されて半年が経過しようとしています。この間、改悪ステージのもとで新たな教育統制と競争管理をシフトした国民不在の教育議論が展開され、新学期早々の4月24日には46年ぶりの「全国一斉学力テスト」が「粛々と」実際されてしまいました。今国会には教育3法案が上程されており、「教育免許更新制度」「賃金格差に連動した教職員評価」「学校選択制の拡大」などが画策されています。コロコロ変わる「学習指導要領の改訂」も日程に上っています。 こうした子ども・父母・教職員にとって新たな困難を導く情勢下で、すべての子どもたちの生き生きとした豊かな発達を願う立場からどう立ち向かうのか、議論を深める機会として企画しました。 どなたでも参加できます。(参加費:資料代として300円) |
●[高校問題研究会]
6月16日(土)13:00 京大会館
「こんな高校なら行きたい、働きたい――学校ストレスはどこから来るのか――」
第8回高校教育懇談会 民主教育推進委員会分科会を兼ねた研究会として
●[発達問題研究会]
6月23日(土)13:30 教育センター室(教育会館別館2F)
「奥丹での地域活動」
・講師:堀井 篤(元立命館高校)
・報告者 和気 徹(向陽高校)
・棚橋啓一(教育センター地域研:要請中)
●[民主カウンセリング研究会]
7月21日(土)10:00 教育文化センター203号室
「民主カウンセリング・ワークショップ」
グループ・エンカウンター
・日時 2007年 6月16日(土)10:30~
・午前:全体会 /午後:分科会
・場所 京大会館にて
京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。