 |
●京都教育センター通信 復刊第11号 (2007.4.10発行) |
鰺坂 真(関西大学名誉教授)
教育基本法が無理やりに変えられて、「国を愛する心」という文言が入り、子どもたちにこれが押しつけられようとしています。教育全般にわたって国家統制を強めようとしていることが問題だと思いますが、子どもたちの心の中にまで踏み込んで、国を愛せよと押しつけようとしていることは、さらに問題だと思います。
「郷土や国愛する」のはあたりまえではないかと自民党の政治家などが言っていますが、それは本当かということ、そこに疑問はないのかということを論じておきたいと思います。
まず「国(くに)」とは何かということを明らかにしなければなりません。「くに」という日本語に二義性(あいまいさ)があるということです。「あなたのおくにはどちらですか」と聞かれて、「土佐です」とか「紀州です」とか言う場合で、ここでいわれる「くに」は、生まれ育った「郷土」のことです。ところが「日本という国」と言うような場合の「くに」は「国家」のことです。つまり日本語の「国(くに)」という言葉には、郷土という意味と、国家という意味と二重の意味があります。
日本は島国なので、こういうことになっていると思われますが、ヨーロッパのような大陸国家では郷土と国家とは明確に区別されています。郷土は、それが都会ならば city であり、田舎なら town であり villege です。これは生まれ育った町であり村です。国家は state であり、国家権力が時代の都合で人為的に国境線を引いて作った統治機構です。ヨーロッパなどでは郷土でもあり国家でもありうるような二義性をもった「国」という言葉は使われていません。
郷土を愛する気持ちを持つことは、市民としての、町民としての、村民としての自然の気持ちであるといえましょう。権力的な統治機構という意味を含めて国家を愛する気持ちは、これとは全く別のものです。郷土を愛する心はかなり多くの人々の自然の心でしょうが、国家を愛する気持ちを今の日本でどれだけの国民が持っているか、かなり疑問です。
日本という国家が、本当に民主主義的な国家となり、福祉も医療も充実し、社会的弱者に対して思いやりのある国家となり、平和主義的な国家として、過去の戦争責任を真摯に反省して、アメリカのような戦争国家の同盟者とはならない立場を明確にしたならば、この国家を国民みんなが愛する気持ちを持つであろうし、そうなったらいいと切に願うものですが、現状はそれとはほど遠いと言わざるを得ません。
日本語の「国(くに)」というのは極めて特殊な言葉だと言わねばなりません。この言葉をいわば悪用して「国を愛する心」を子どもたちに押しつけようとしているのが政府・自民党ではないでしょうか。
むしろ国民から愛されそうもない国家だから、その支配層は「国を愛する心」を子どもたちに注入しようとしているのではないでしょうか。
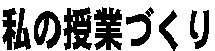
大八木賢治(京都市立勧修中学校・子どもと教科書京都ネット21)
十五年戦争についてこれまでもいろいろな実践があるが、やはり日本史中心の発想が強い。八〇年代以降「戦争の違法化」など世界史的展開の意義を強調しているが、必ずしも実践的には定着していない。
そこで「第一次世界大戦とその後の世界」の学習を日本との関連で把握することを重視した。第一次世界大戦の学習で、映画「西部戦線異常なし」を取り上げ、「祖国」の名の下に青年が戦争に駆り立てられていく場面や壮絶な陣地戦を見て、生徒たちから「これ実際の戦争?」という質問が出るほど、戦争の恐怖と戦争で死んでいく姿に驚きの声を隠せない。この戦争の経験が国際連盟や不戦条約、ワシントン体制下の軍縮という形で「戦争の違法化」を生み出したことを学ぶ。しかし生徒にとって「戦争が違法」という意味が十分理解できないところがある。その理由は戦争とは国家間の問題で、戦争は「国家の権利(主権)」であるという、国家中心の戦争のとらえ方に陥らされているからである。しかし実は人民なくして戦争はできない。人民(国民)は「祖国のため」という美名で、国家に戦争に動員されるのである。そして最終的に一番大きな被害を被ってきたのも人民(国民)なのである。この矛盾に始めて気づいたのがロシア革命やドイツ革命であり、こうした革命を背景に高まった人権意識が女性参政権や労働者の権利などの社会権や、植民地支配に抵抗する民族自決権を生み出したのである。「戦争の違法化」を単に国家間の主権の調整としてとらえ、第二次世界大戦を阻止できなかったことで大きな意味がなかったという意見もあるが、「戦争の違法化」は「人民(国民)の人権と主権者意識」の向上との関連でとらえることなくしてその意味はとらえられない。なぜなら人民が主権者としての意識を高めることなくして、戦争をする「国家」の手を実際にしばることはできないからである。
「戦争違法化」の学習は「満州事変」や日中戦争(「日華事変」)に対する批判を明快にさせる。しかも戦争を肯定する世論の動きや「戦争熱」への異常さに驚くのである。リットン調査団の報告や国際連盟の決議は日本の中国侵略に対する「戦争の違法化」を確認した国際社会からのまともな批判であることがわかる。結果として第二次世界大戦が起こるが、この戦争がそれまでのたんなる帝国主義戦争ではなく、「民主主義とファシズムの戦争」という新しい性格を形成する根拠を形成できたのも、「戦争違法化」という国際社会の形成という前提があるからである。日本の場合、「戦争違法化」という国際社会の形成の意義をとらえきれなかったといえる。それは日清日露戦争以後のアジアへの帝国主義的な侵略で形成されてきた日本のアジアに対する支配者意識が背景にある。このように「戦争違法化」の意義を十五年戦争学習と戦後の歴史に位置付けていけば、憲法第9条は国際社会の発展のなかで、日本の戦争責任の取り方の一つであることが学習の発展の中で見えてくるはずである。
子どもの意見表明権は、子ども自身の問題の決定に際して、広く子ども自身の意思を反映させる適正手続きを求める権利であり、自分の生活や社会の条件に対して、子ども自身の意思を尊重することを求めた権利であると思います。
その一つとして全国各地でも取り組みが進められている「子どもアンケート」を実施しました。統合間なしの学校施設に対して「アンケート」をとることには少しはばかりもありました。しかし三年経っていろんな施設等にも不具合もでてきはじめ、校長は難色を示しつつ高学年のみ、かつ持ち帰らないことで実施しました。子どもたちの声の中で「エアコン設置」がとくに多くありました。次年度の予算要求に向けて「教室の温度調査」も実施しました。残念ながら要求実現とはならず、扇風機の設置に終わってしまいました。他にも、校舎のちょっとした修繕箇所など大人の目からは見落としたり不便を感じていない所などにしっかりと目を向けた内容が「アンケート」には記載されていました。アンケート結果は廊下に張り出し、要求のあったものを「できるもの」と「できないもの」にはっきりと区分し、その理由も表示しました。新鮮な子どもの声を聞くことの大切さを学びながら、子どもたちにも徐々にいろいろな事に気づくようになり自分の意見を持って「自分の学校」を創っていくという考えを育てていけるようになればと思っています。今後も子どもの意見にも積極的に耳を傾け、その意見を尊重していけるよう心がけたく思っています。
また、学校設備などについて保護者からの率直な意見などが聞ける場についても設けられないかと思っていました。いろいろ考えた末に、夏休みの「PTA合同清掃作業」の時に、「アンケート」をとることにしました。当日のアピール不足などから回収率は低いものでしたが、引き続き保護者・地域住民の声を聞く機会を持ち続けていきたいものです。
例年より多くの図書購入費(四〇万円)が予算化され、その機会に図書の購入について、子どもたちの意見をもっと取り入れられないか、少しでも「本」に対する興味を持ってほしいとの思いから「子どもたちによる図書選定」を行いました。図書担当教員とともに業者の協力もえて、選定用の本を二~三〇〇冊お借りし、閲覧用の部屋を用意して中間・昼休みに開放するようにしました。子どもたちの中には、毎日のように通って新しい本をむさぼるように読んでいる子もいました。三年生以上で一人三冊まで順位をつけて買って欲しい本を投票する方式をとりました。投票結果は、図書室前に張り出しました。
子どもたちが選んだ本も含めて約二百数十冊購入しました。「いつ選んだ本は来るの」「私の選んだ本は○位だったよ」など子どもたちにはたいへん好評だったと思っています。
「学校ホームページ」はほとんどの学校で作成されているのですが、「事務のページ」についてはあまり見受けません(横浜市では全校予算公開)。学校事務職員の仕事について、少しでもアピールできる機会になればと思い取り組みました。学校事務についても、多くの学校で取り組まれているものを参考にしながら、「事務のページ」を作成しました。完成後、予算額について校長・町教委との協議も重ね、ようやく全てクリアとなり公開となりました。(一七年度 前任小学校)。
2007年度も、日本と子どもをめぐる情勢は重大な局面を迎えています。新しい教育基本法下での関連法案の策定や教育振興基本計画の具現化(学力テスト、学校・教職員評価、免許更新制度など)が狙われ、学習指導要領改訂案が発表されようとしています。また京都市の教育をめぐっての検証が必要ですが、こうした中、京都教育センターは「学校現場・父母住民からみえるセンター活動を!」を合い言葉に、下記のようなさまざまな取り組みを進めていく方針です。
(1)第38次センター研究集会 2007年12月22日(土)~23日(日)(予定)
(2)事務局企画による情勢に適った学習会・シンポなど (6月下旬、9月上旬、11月下旬)に予定
(3)各研究会による公開研究会の実施(その都度案内します)
・地方教育行政研究会
・生活指導研究会
・学力・教育課程(学校づくり)研究会
・発達問題研究会
・家庭教育・民主カウンセリング研究会
・高校問題研究会
・子どもの発達と地域研究会
・教科教育研究会 国語部会
*各研究会は、それぞれ定例の研究会や運営委員会を開催しています。
(4)他の研究団体との共同をすすめ、父母・地域住民との懇談・交流を広げる。
(5)発行・出版 ・季刊「ひろば 京都の教育」の発行
| 2007年度 季刊「ひろば 京都の教育」特集 ●150号(07.5.1発行) ①いじめ問題と子どもの攻撃性 ②こんな学校、授業があった! ●151号(07.8.1発行) ①保護者に開かれた学校づくり ②教育再生会議で学校・教育は良くなるのか ●152号(07.11.1発行) ①「京都市の教育」はこれでいいのか ②保健室・相談室から見た子どもたち ●153号(08.2.1発行) ①専門機関とのネットワーク支援 ②「大学全入時代」と進路指導 |
・昨年復刊した「センター通信」は今年も毎月はじめに発行し、全組合員に配布します。
(6)情報開示
・インターネット、ホームページの活用
・資料室の整備・活用
(7)京都教育センター諸会議の開催
・教育センター室は(月)(水)に常駐しています。
・事務局会議は3週間に一回のペースで土曜日の午前に開催しています。
【事務局メンバー】
野中(代表)、室井(副代表)、築山(研究委員長)、大平(事務局長)、中西(事務局次長)、春日井(「ひろば」編集長)、他 計14名
京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。