 |
●京都教育センター通信 復刊第 7号 (2006.12.10発行) |
―歪みを正して学習指導要領の根本批判を、教基法改悪阻止を―
高橋 明裕(京都教育センター)
高校をはじめとした未履修問題が波紋を呼んでいる。しかし、履修科目の「読み替え」や、普通科高校における二年次以前の段階からの文系・理系分けによる必修科目の選択科目化などによって、「未履修」状態が起こっている現場の教員にしてみたら何をいまさらという感が強いのではないかと思う。
マスコミにしても例えば毎日新聞二〇〇五年四月二十日付け(東京朝刊)が教育特集でとりあげていたように、新しいニュースであるわけではない。それが教育基本法「改正」の国会審議の局面でニュースにされたことは、教員、校長、教育委員会への不信感を醸成し、「改正」の機運を後押ししようとする意図が感じられる。もちろん履修していない科目を履修したとして調査書に虚偽記載した行為は許されることではない。しかし、そうまでさせて高校を受験競争にあおり立てている今日の教育をめぐる構造、「教育改革」こそ非難されるべきだろう。
受験実績による学校間競争が今回の問題の背景にある。とりわけ地方の公立高校にそうした傾向が強いことは、未履修状況の数字が表している。
「学力」を全国一斉テストによって判定しうる領域にしぼり、競争を通じて「学力」向上を目指すという、歪んだ教育改革が進行中である。未履修問題で槍玉にあげられたのは世界史であった。報道によれば、今回のニュースの発端となった高校の校長は、「日本史のなかに世界史の内容も含まれていると思った」と発言した。不見識な発言ではあるが、今回の世界史未履修の問題は、受験偏重のために世界史履修を忌避している現実に対して、どのような日本史・世界史の学力を保障するのか、という教育課程の内容に踏み込んだ議論が必要である。
さらに懸念されるのは、この問題によって学習指導要領は厳密に遵守されるべきものとの観念が教員や保護者に植えつけられるのではないか、ということである。しかし、現行の学習指導要領においてさえ、学校ごとに「地域や学校の実態、…生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。」と明記されている。指導要領は全国的な「基準」にすぎないのであり、教育課程づくり、学校づくりは生徒、教員、保護者の自主的な共同によるべきものである。
それを規定しているのが「教育は…国民全体に大使直接に責任を負って行われるべきものである。」と定めた教育基本法第十条である。政府案ではこの教育の直接責任制がそっくり削られている。教基法の改定を許せば、今以上に指導要領の拘束力が強まることとなる。
未履修問題をめぐる議論を教育不信に結びつけるのではなく、教基法改悪阻止にむけて組み立て直すことが緊急に求められると同時に、どのような学力を生徒に保障していくのか、自主的な教育課程づくりの努力が不断に求められているのだと思う。
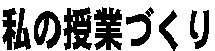
綾部市立志賀小学校 仁張 美之
子どもたちとのあいさつが楽しい朝
私は毎朝、担任する全ての子どもたちを教室で迎えます(教材準備のため教室にいるのですが)。「先生!お早うございます!」と元気なあいさつがとんできます。「はい!お早う!」と返していると、「さあ、今日もやるか!」という元気が出てきます。私には、教室がとても居心地がいいのです。さて、つたない私の授業は、次の様な内容です。
全ての子に自己肯定感と「凛とした授業規律」を
年度初めに、学級の目標は「昨日よりも今日、今日よりも明日の自分を」としました。つまり自分を鍛え、毎日少しでも前進しようということです。そのために取り組んできたことは、毎日の百マス計算(単純計算)・小漢字テスト・国語教材の音読です。他の子どもとの競争ではなく、自分の進歩に注目させ評価しました。当初はその点を特に強調して指導し、毎日子どもたちの少しの進歩でも、目に見えるように評価してきました。毎日しっかり鍛え、少しでも自己肯定感のもてるようにしています。
そして、平行して徹底してきたことは授業規律の確立です。授業の中では当然、私語や立ち歩きは厳禁としています。一方、討論する時には全員が発言します。討論の中では言葉を大切にしながら、子どもたちが意見をまとめ、必ず「先生、いかがですか?」と問うようにさせています。教師と子どもたちの関係をハッキリさせています。この自己肯定感と学習規律は、相乗効果をもたらしながら発展してきました。
現在、子どもたちの中には、緊張感のある「凛とした授業規律」が定着し、落ち着いた中で学習課題に立ち向かっています。
新たな課題に
このような授業ができるようになった今、子どもたちと次の新たな授業に立ち向かおうと、手探りで研究し実践しています。その中心課題は発達の後追いではなく、発達の前を行き、発達をうながす毎時間の授業をどれだけ実現するかということです。その為には、言葉たらずですが「発達に応ずる科学的な『概念』の体系」をいかに子どもたちの中に発生させていくか、真の賢さをどう実現していくか、目新しいことではないのですが、そのような授業をめざし模索しています。先輩諸氏の民主教育の実践に学びながら、自分のものとして実現していきたいと思っています。
仲間や保護者からの激励が
このような授業づくりを実現し、新たな課題に挑戦するにあたって、研究サークル(綾部では『授業改善研究会』)関係の仲間の存在と、その激励は欠かせません。そこでの討論は、導入から最先端までとても自由で刺激的です。産声をあげて間もないサークルですが、教育を科学的に分析・研究し、教育の未来を見据えようとしています。
また、前年度末の学級懇談会で保護者方々からは、「凛とした授業ですね。」「子どもは、充実した一年間を過ごすことができました。」等、前向きの激励をいただきました。上記の「凛とした授業」は保護者の感想で、決して私の自己満足ではないのです。 これからも、全ての子どもたちを伸ばすため、健康を大切にしながら、しっかりとがんばろうと決意しています。
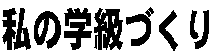
南丹市立八木小学校 三上 泉
(1)「唯物論と弁証法」を実践に生かすこと
私は、青年教研などで若い人たちに、唯物論と弁証法にもとづく教育実践~「観念にとらわれず、事実をありのままに見つめる」「物事はすべて変化・発展することを前提に実践を組み立てる」ことを勧めています。若い世代はこんな言葉は初めて聞くという人ばかり。この理論を知っている人でも、自分の実践に意識してとことん生かしている人が少なくなっているのではないでしょうか。
一九八六年中学校の体育教諭として採用され、五年間中学校で勤めたあと、小学校に異動し五年間、そして、一九九六年から七年間、教職員組合の専従役員として現場を離れて、二〇〇三年に再び現任校に戻ってきました。
私は、ある人から教わった言葉を自分なりにアレンジして、子どもたちにこう語っています。 「自分よりもうまくできる人もいれば、そうでない人もいる。でも、それはすべて自分が歩む道筋の中のどこかの姿だ。自分よりうまくできる人は自分の『未来の姿』であり、自分もやがてたどり着く姿だ。だからコツややり方をよく見て取り入れたり、アドバイスをもらったりしよう。また、自分よりうまくない人は自分の『過去の姿』であり、自分もかつて通ってきた道にいる人だ。だから自分がどうやって乗り越えたか、どうすればうまくなるかを積極的にアドバイスしよう。人に教えられるようになることで、自分の技もよりよいものになるはずだから。」
(2)「ムリムリ!」から始まり「できた!」 まで──学級みんなで支えあい磨きあった「跳び箱運動」の授業
いま、担任している学級は、発達上の課題を持つ子や、障害児学級から体育の時間に学習に来る子、体格・体力、健康上の理由から配慮の必要な子がたくさんいます。
でも、この子らも必ず伸びるしできるようになる!と信じ、跳び箱運動「ヘッドスプリングからハンドスプリングへ」に取り組みました。 最初に私が、ヘッドスプリング、ハンドスプリングの見本を見せたとき、子どもたちは口々に「ムリムリ!」「すごいけど・・・」「こわい!」と、予想通り一気にひいてしまいました。「いきなりこんなことはできないのは当たり前。でもちゃんと道筋を通ればみんなたどり着くんだよ。」と笑顔で語りかけ、授業をスタートさせ、いくつかの技術的アプローチを自分なりの系統性をつけて指導していきました。子どもたちがお互いにアドバイスをしたりされたり、人の技をじっくり見たりすることを大切に、授業カードも毎時作って、気づきやふり返りを記録させていきました。
「ムリムリ!」と叫んでいた第一時。でも次からは、子どもたちの目つきも態度も徐々に変わってきました。自分の体がふわっと浮いて起き上がる感覚が気持ちよくて、しり込みしていた女子もどんどんマットに突進していきました。カードの書かれている内容も、「できてよかった。」「まだよくわからない」という文章から、「○○さんのを見ていると△△すればいいのかなと気づいたから今度やってみよう。」「◇◇くんが、今日初めてできはった。アドバイスしてきたぼくもとてもうれしかった。自分もがんばらんと!」という文書が増えてきました。
(3)科学の眼をもって、他人の成長を自分の喜びにできる子どもに
授業を終えて、障級の二人も含め、ほとんどが跳び箱でのハンドスプリングまで到達しました。できなかった子もいたが、「やり方はたぶんわかったと思う。きっとできるようになる!」「いっぱいアドバイスをもらってうれしかった。いっぱい人の技を真剣に見た。」という感想を残してくれました。 ますます、忙しくなる職場ではありますが、ささやかでもこのようなこだわりのある授業をしていきたいと思っています。
-- 京都教育センター06公開研究会 Ⅵ --
京都教育センターでは、2006年度に各研究会と共に「公開研究会」を開催していますが、その第6回「フィンランドの教育から学ぶ」が、11月25日(土)午後1時から4時まで、京都教育文化センター101号で行われ、30名が参加しました。この公開研究会は、発達問題研究会と学力・教育課程研究会が共同して、準備をしたものです。 はじめに、発達問題研究会の西浦事務局長が挨拶を行い、「教育基本法改悪がが重要な局面に入っているが、だからこそ、日本の現行教育基本法を参考にしたと言われるフィンランドの教育を学ぼう」と話しました。 続いて、東大阪市立英田南小学校教諭の山口妙子さんが「フィンランドの教育と教育基本法・私の教育実践」と題して講演。山口さんは、この夏、全教が実施したフィンランド教育視察団に参加した時の様子や、教育基本法を生かした学校現場での家庭科専科教員としての実践を報告しました。 また、京都市立日吉ヶ丘高教諭の後藤誠司さんが「フィンランドの学校を訪れて」と題して報告を行い、競争主義を排し学力づくりを重視するフィンランドの教育事情を詳しく紹介しました。 その後の討論では、フィンランドの教育から学ぶべき点、日本の教育に生かすべき点などが話し合われ、その中で日本の現行教育基本法のすばらしさを改めて認識し、改悪を許さない決意などが話されました。 |
第37次京都教育センター研究集会[夏季から冬季に変更] 【集会テーマ案】 ・教育基本法をめぐる新たな情勢下で、人間を大切にする教育を一層推進しよう。 ・「いじめ問題」「学力問題」など山積する今日的課題を分析、検証し、すべての子どもたちの豊かな発達を保障する実践を学び交流しよう。 |
1月27日(土) 13:00~17:00 全体会 教文センター302号室 ◇ 講演 「憲法・教育基本法とともに歩んだ私の教育:41年」 野本勝信(元中学校長、京都府同和教育研究会会長) ◇ パネル討論 「今、改めて教育の役割を考える」父母・青年教師・学生・研究者のパネラー 1月28日(日) 10:00~16:00 センター各研究会の分科会 教文センター全館 実践報告と討論 ①地方教育行政研究会 ②生活指導研究会 ③学力・教育課程研究会 ④発達問題研究会 ⑤家庭教育・カウンセリング研究会 ⑥高校問題研究会 ⑦子どもの発達と地域研究会 ⑧教科研究会・国語部会 ◇ 参加費 500円(資料代) ※ プレ集会:27日(土)10:00~12:00 藤原義隆氏(元京都市内小学校)「私の教育実践を支えた力」 ※ 交流懇親会:27日(土)17:30~(「十両」にて) |
| 京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com ・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |