| 事務局 | 2016年度年報目次 |
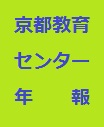 |
京都教育センター第47回研究集会 分科会報告 |
|
第8分科会 「京都障害児教育研究センター5年間の活動から考える教育実践で大切にしたいこと」~学習指導要領の改訂にどのように臨むのか~ 京都障害児教育研究センター |
||
Ⅰ あいさつ 木下博美 京都障害児教育研究センター代表 Ⅱ 報告1 京都障害児教育センター5年間の活動を通して京都の教育実践で大切にしてきたこと 西城信幸 京都障害児教育研究センター 1.京都障害児教育センターはなぜ発足し、何をめざしたか 2.5年間の活動 3.大切にしてきたこと 4.学びの要求を実践・研究から運動へ 5.教育課程から 6.教育目標について 7.発達は集団によって組織される 8.教育内容、教材、方法について Ⅲ 報告2 学習指導要領改訂の目指すものとこれからの授業づくりでの論点 (1)特別支援学校学習指導要領の改訂の論点 安井 芳幸 京都障害児教育研究センター 1.学習指導要領の本質は「社会に適応させる教育」、その改訂のキーワード 2.特別支援学校 学習指導要領改訂の論点 (1) 「インクルーシブ教育システム」の内実は、教育課程の円滑な接続 (2) 教育目標と評価の一体化で縛りのきつい窮屈な授業に (3) アクティブラーニングと観点別評価 (4) 「自立活動」、「合わせた指導」をどのように考えるのか (5) 本来の「キャリア教育」は、自分らしい生き方を目指して発達すること 3.これからの授業を考える「5つの論点」 (2)中教審「特別支援教育部会における審議のまとめ」から、次期学習指導要領の目指すものはなにか 西城 信幸 京都障害児教育研究センター 1.はじめに 2.中央教育審議会「特別支援教育部会における審議のまとめ」より考える (1)通常の学校の学習指導要領を基軸に教科の目標・内容の整理を行う (2)目標に準拠した評価 3、まとめ~新学習指導要領に基づく取り組みはすでに始まっている~ Ⅳ 実践報告 実践報告1 イメージで集団をつなぐ「13びきのねこ」のとりくみ―自閉症児の創造的なあそびをつくるー 京都府立宇治支援学校 今泉 祥子 この実践報告は、1歳半までの子どももいて、2歳から4歳までが中心で、4歳以上の子もいるという幅の広い集団の報告でした。 1.「子ども理解」は障害特性、発達検査の結果だけではない。行動だけでなく内面を 2.「つもり遊び」や「ごっこ遊び」の教育的な意味 3.友だちと一緒にすることで分かってできる 4.道具や音楽があれば、何をするか分かる 5.友だちのことを気にかけれるようになる 6.集団へ参加は、その子の参加のしかたをみんなが分かるように 7.自制心、自己コントロールの力 8.自我が拡大するにつれ、内面が豊かになり、イメージが広がる 9.自分のイメージやつもりが大事にされる授業や生活を 実践報告2 水遊びの実践「びしょぬれ大作戦」 京都府立南山城支援学校 万野 友紀 この実践報告は10ヶ月から1歳半の自閉症の子どもの水遊びの授業が報告されました。 1.感覚にとらわれても、待てなくても、こだわりがあっても・・・ 2.友だちを観る、自分もやってみる、一緒にする 3.集団参加が難しい子どもも、みんなの中でできることを一緒に 4.まず、安心できる人を支えにやってみて、しだいに人との関係を広げ、友だちが加わる・・・ 5.道具を持つとより目的的に遊べるようになり、因果関係を楽しめるように 6.1つのことを繰り返してすると同じようでも質が変わり、遊びが広がっていく 7.試行錯誤し、自分の目的のために伝え、動機にもとづいて要求でき、自分のやり方で遊ぶ Ⅴ グループ論議 論点 ① 子供から出発した授業作り ② 実践を通しての教職員集団の大切さ ③ 遊びの指導、遊びを通しての授業作りの論議の視点を置く。 Ⅵ 各グループより報告、全体論議、感想のまとめ 改訂される次期「特別支援学校学習指導要領」対する「これからの授業づくり」の「5つの論点」は、2つの実践報告を受け、話し合いの中で枝分かれし、醸成され、焦点化されていったように考えます。 1 「できる・できない」だけでない子ども理解を 「観点別学習状況の評価」で授業はどのように変わるのか(論点②) 今回改訂される学習指導要領の中心は「目標に準拠した観点別の学習状況の評価」にあります。文科省資料の「教育課程の総体的な構造の在り方」はこのことを中心に「スクールマネージメント」を行い、教育課程に対する教職員の批判の自由を奪い、管理し、子どもたちの人格を丸ごと適応、順応させようとしています。 教育評価とは「教育実践の成否を判断する価値的な行為」で、その結果は教育計画の改善や子どもたちの学習活動に見通しを与えるために活用されるべきです。つまり教育目標や教育課程を改善するために行う教育評価がその教育目標と一体化・固定化しているということが最も問題です。 かつて、1980年に国連で示された国際障害分類( ICIDH ~ 疾病、機能障害 → 能力障害 → 社会的不利)のように、「障害を理由とした社会的不利を打開する」という学習目標を中核に持つ教育課程(授業)は、「できる」、「わかる」をどんどん積み重ね、能力・スキルを高めるために訓練的に「頑張る」授業となります。このような授業は現在、学習指導要領の研究者などから次のように反省されています。 ・「キャリア教育」の名の下で学校教育が訓練化している。 ・スキル獲得(「~ができる」、「~の能力を高める」)の授業展開が多い。 ・「 ~はダメ・・・」など、教員の指示や制止が多い授業となりやすい。 ・「できさせる」ことが目標で教員が常に横にいて子どもに介助している。 ・先生の「講義」が多く、待ち時間が多い授業、導入とまとめが長い授業は、実際の活動が損なわれている場合がある。 2001年に示された新しい国際障害分類(ICF)は、「個人の頑張り」のみならず「障害者をとりまく社会環境」によって社会的不利が左右されることの重要性に着目しました。このような国際的な障害者理念の発展が、2014年に日本でも発効した「障害者権利条約」の理念を生み出しているといえます。 分科会の中で「どのような教育課程(環境)の中で、どのような物や場所(資源)で実践を考えるのか。この背景のようなもので実践の生まれ方が関係があるのかなと考えました。」という報告がありました。 そして、話し合いの中でも「できた、できなかったの評価がダメではないが・・・、一定必要だと思うが、その周りの評価も大切だと思った。」 また、「子どものアセスメントをしっかりとらえ、わずかな変化を気づき喜べるようになりたい。」、「アセスメントをていねいにし、子どもが伸び伸びと楽しくできる実践をしていきたい。」などというものがありました。「評価」と「教育アセスメント」は違う意味合いで使われますが、教育評価は「教育アセスメント」のように使われるべきものです。 2 トップダウンの教育とボトムアップの教育 本来の「キャリア教育」とは (論点⑤ ) 改訂学習指導要領では、「キャリア教育」の実践について、「地域協働活動」としての防災学習やメンテナンス、介護サービス、クリーニングなどの実習、高齢者のグループホーム等にでかけ、カフェをサービスする学習、小学部や障害が重度の子どもたちでも取り組めるように段階的に級を定めた「技能検定(大会)」など、ワークキャリアに傾斜した実践を例示しています。これが共生社会のアクティブラーニング、カリキュラムマネージメントの典型とされます。 話し合いや感想の中で「高等部を卒業したら企業就労につなげなくてはならないということで、高等部ではこの力、中学部ではこの力、小学部ではこの力と、上から下へのトップダウンでなく、小学部や中学部段階から子どもの可能性をどんどん広げていくという考えで、指導者も子どもを見るというボトムアップも大事なのではないかと話しました。」、「子どもの実態から出発することを前提に、生産的活動もトップダウンも大事だということを一応知っておくことが大事。」などという意見が出されました。さらに、遊びの中に労働につながる力があり、「遊びから労働につながる」という視点が大切だという内容もありました。 そもそもキャリア教育は、「それぞれの時期毎に社会との関係の中で自分が果たす役割を知り、自分らしい生き方を見いだす過程(キャリア発達)」であり、「仕事」や「労働」という事柄でもライフキャリアの前提に立った実践の考え方が重要です。 ワークキャリアに偏重した考え方は、過去の「学校工場方式」のように固定的な学習目標に子どもを合わせ、「できる」ことを強く求める指導になりかねません。話し合いの中でも、「(授業づくりは)子どもから出発して子どもと一緒に探し続けることが大事。」、「子どもの姿から出発した授業づくりが大事」、「トップダウンの視点もあって良いが、ボトムアップの中で可能性(縦の発達、横の発達)の幅を広げていくのも大切だと思う。」などという意見が出されました。 3 仲間とともに学び合う集団づくり 子どもに合わせた「集団の編成」と「学習目標」(論点③) 全国の支援学校の圧倒的多数が「学年制クラス編成」を行っている中、京都府の支援学校は歴史的に「障害別・発達別クラス編成」を行っています。このことは、京都府下の支援学校の子どもの「基礎集団」と「学習集団」の考え方によっています。当然、学習指導要領は全国の圧倒的多数の「学年制クラス編成」の学校のためのものです。その記述の中には障害別の部門制で「肢体障害(学校)クラス、自閉症クラスなどの考え方はありますが、「障害別・発達別クラス編成」を前提としていません。前掲のように「障害、発達がバラバラのクラス」でもできる教育課程や授業を提案しています。 その典型が「合わせた指導」の授業ではないでしょうか。東京都教育委員会が昨年(平成27年度)出した「合わせた指導の充実」というパンフレットに「授業づくりのポイント」は「どの児童・生徒でもできる状況をつくる」だとしています。つまり、「障害、発達がバラバラのクラス」でも「一人ひとりができる活動を選択でき、活動量を確保し、繰り返しを用意する。そのために道具や補助具を工夫する。」そして「できた!をほめる」、つまり、「できた!」は「自信」を育む、ほめられると「喜び」につながり、自信と喜びは次への「意欲」を引き出すというものです。 障害別・発達別クラス集団で実践を積み上げてきた京都府の先生たちが、他府県のような「合わせた指導」の授業を見て、「何か物足りない・・・、よく分からない・・・」と感じるのは、このためではないでしょうか。 4 発達の観点で子ども理解を進め、授業を創る 「各教科の目標・内容を踏まえた授業づくり」の内実は何か(論点④) 「各教科の目標・内容を踏まえた授業づくり」の視点は、「インクルーシブ教育システム」の中心的な課題である「知的障害のある児童生徒が通常学校と障害児学校を行き来すること(「多様な学びの場」)の保障です。このため、「教育課程の円滑な接続」が必要と、「各教科の目標・内容の連続性に留意し、分かりやすく示す」としています。 「発達の視点と生活年齢の視点を入れつつ、授業をつくっていくことが大事と話し合いました。」、「子どもから出発して実践を創るには、子どもを見る確かな目とそれぞれの教員の子どもを共有する力必要だと思う。そこに発達の視点・観点が大事で子どもをどのようにとらえていくかにつながっていく。」、「子どもの姿から出発をベースに、発達の視点、生活年齢、家庭、性格、障害が含まれる。」などなど、授業づくりには「発達の観点」が大切というものが多くありました。同時に、子ども理解を進めるために教職員の集団づくりも大切だと話し合われ、「実践報告では、教師集団づくりがうまくいくとこんなに素晴らしい実践ができるのだなと思った。」という感想もありました。 5 子どもたちの人格形成につながる力を育てる 「卒業後の視点から」教育目標を設定する(論点①) そもそも教育目標とは、教員が子どもたちの中に実現しようとする価値を意味します。これは教員の教育実践の方向性を示し、授業内容や指導方法を規定する決まり事のような文言です。 学習指導要領は「障害のある子供たちの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する」することを教育目標としています。これを「変化の激しい不透明な社会に適応して参加し、社会の人材としての自立の力をつける」と固定的に読むことは間違いだということは話し合いの中や感想で述べられた通りです。 日本でも実効した「障害者の権利に関する条約」は、教育について、 「人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を充分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること」 【24条の1(a)】 とされ、障害者を社会に適応する人材として扱うのではなく、全面発達の可能性を持つひとりの人間として、その多様性が尊重されながら生きることを目標として教育されることが国際的に示されています。 中教審の答申案でも、子どもたちに育てたい資質・能力を語る際には、教育基本法の「人格の完成」、「平和で民主的な国家の形成者」ということに言及せざるを得ない矛盾があります。「卒業後の視点から目標を設定」することについて、私たちの主体性や構想力が問われています。各校の学校教育目標を全教職員で再確認することが求められています。 6 子どもから出発する授業づくりを教職員集団でつくる 教職員集団として、発達の観点・視点で子どもたちをとらえ、楽しい授業を目指して教材や教育内容、指導方法を考え合う授業づくりとは、具体的にどのようなことなのでしょうか。 2つの実践報告に共通することは、子どもたちの学校生活での具体的な姿を複数の教職員の目で観て、話し合いを大切にしたことです。「できる・できない」という目に見える行動だけでなく、「どのようにしたいのか」、「なぜできないのか」、「友だちや先生(人)との関係は・・・」など、発達的な視点で理解しようと話し合いを続けたことです。 Ⅶ 終わりのあいさつ 木下博美 京都障害児教育研究センター代表 |
||
|