| 事務局 | 2016年度年報目次 |
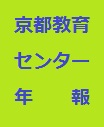 |
京都教育センター第47回研究集会 分科会報告 |
|
第6分科会 家庭教育・民主カウンセリング・ワークショップ “いきいきした、温かい人間関係をつくるために” 芦田 幸子(民主カウンセリング研究会) |
||
過労自殺、相模原市の障害者殺傷事件、深刻ないじめなど耳をふさぎたくなるような事件や地震などの災害、国民を馬鹿にしたかのような安倍政権の自衛隊の海外活動の拡大、辺野古基地問題、オスプレイの容認、そして生活を一層困難に陥れる年金や介護保険制度の見直し、消費税率の増加などますます生きにくさを感じることが多い社会になっています。 こんな世の中であるからこそ、人が人として尊重されるようにしたい、お互いが尊重し合う人間関係を築いていきたいと、私達は今回もエンカウンター・グループを開催しました。 今回も日々感じていることや生活していく中で生まれる喜び・悲しみ・怒りや不安、今まで生きてきた歴史の中で積もった思いやその場で動いてきた感情などいろいろな思いを言葉にしてみる、言葉にしたことを聴いてもらう心地よさや他の人の話しを共感的に聴き、自分の中で反復してみてまた新しい発見をするよろこびや驚きを味わいました。 やや観念的なエンカウンターだったのですが、参加者全員が話をし、聴きあうというみんなが主人公になる日常とは違う時間を過ごすことができ、次の日からの生活の糧や心の支えになるようなエンカウンターになったと思います。 全体で参加者は10名。男性5名女性5名でした。当日の案内文に心惹かれて参加してくださった初参加もおられて、とてもうれしく思いました。 ●あいさつ・オリエンテーション 自衛隊に“かけつけ警護”という新たな任務が付与され戦闘地域で自衛隊員が「殺し、殺される」危険が現実のものになった。まさに戦争前夜のような情勢、私達はそれを肌で感じている。 今こそ「平和的共存」と「個人の尊厳」の大切さを改めて選びとりたい。私達の目指すカウンセリングは「基本的人権」を尊重し「個人の価値と尊厳」への敬意に裏付けられたもの。国家ではなく個人に基盤を置いている。物言えない学校や企業があるが、ここでは自由に話せる。人と人との温かいつながりが大切にされる時間を感じ、他の人や自分に出会う時間にしていきたい。 ●話しあい、聴きあいから ★午前のワークショップは「“いい子”でいたいという人が多いのではないか、みなさんどう思いますか」という投げかけの問いから始まりました。 “いい子”と何か、“自分とは何か”という話やそんな自分が他人とどう接して、コミュ二ケーションをとっているのか、とろうとしているのかということが主な話題でした。 ・“いい子”でいたいから喧嘩しないのではないか。人間だからすれ違うことあるが、すれ違いを修復できないこともある。それが怖くて喧嘩できない。“あるがままの自分”でいたいと思うが、そんな自分だと“いい子”にはいられない。 ・もめることも大切と認める事が大切ではないか、違いを認め合うことも大切。おおらかな議論すればいいのでは。 ・学校では生徒の様子を見ていて痛感している。生徒は周りに気を使い、みんないい子でいたいと思っている。いい子でいようとすると変調をきたして、行きしぶりや不登校、精神疾患などになってしまう。以前はおおらかな議論できたが、今は職員同士も子どもとも話す余裕ない。学校という管理社会になり、校長の一言ですべてが決まってしまう。議論しても仕方ないというむなしさがある。わずらわしいことを避けて、その分個人で心安らかな時間をもとうとする傾向があると思う。学習指導要領がかわるとをますますその傾向が強まるだろう。“カリキュラムマネージメント”が実施され、2018年から教えることも校長が管理することになった。ますます“いい子”が求められ、病気になる生徒、教師が増えるのではないか。安心感も持てるクラスを作りをしていきたいと思い努力しているのだが・・。 ・“いい子”になろうと人の期待に応え、親のいうことを聞き、自分を抑えつけている。どんないい子になろうとしているのか、なぜそう思うのかを自分で気づくこと大切。 ・“いい子”はその人の1面。だから他の1面でネットに書き込んだりする。教育委員会ではネットの書き込みをチェックしていて、「〇〇校は〜という書き込みがあるが本当か、問題あるのか。なんとかしろ」と言ってくる。自分のいろいろな面を出せる場があれば、無理にいい子出なくてもいいし、ネットに書き込むこともないだろう。 ・いじめたいという思いは誰にでもあるのではないか。その自分の思いを認めること大切。教師間でもいじめあることを認めて、教師もいじめたい思いある、生徒の中にもあると話すと生徒も正直に話せるのではないか。いい、いじめをしない先生ではなくて、自分の心の声を聞く、自分のいじめたい気持ちを認める先生であってほしい。 ・関係性の貧困を変えるために、話を聴きたいと思う。相手の話も聴きたいし、自分のことも話したい。相手のこともっと知りたいと思う。そのことでもっと人間が豊かになると思う。 ・建前の関係ではなく、本当の関係を持ちたいですね。 ・コミュ二ケーションを阻害しているものは自分。自分をさらけださないといけない。こんな自分ではだめだなあと思っていると本当にコミュニケーションできないと思う。自分を隠していては相手も本音で話せないだろう。 ・すべての人にさらけ出すのは無理、でも1部の人にはさらけだせるのではないか。 ・ぼくは好きな人でも嫌いな人でも同じ接し方、違う接し方はしない。職場の人全員に自分からあいさつする。相手によって言い方を変えることはあるが。 ・挨拶を返さない人に対して気にかかることないか? ・なんとも思わない。楽しくいきたいと思っている。黙っていると楽しくない。 ・ヘッドライト理論というのがある。自分のライトを付けると相手の車から確認できる。自分のことを伝えている人、オープンにしている人には話しやすい。けれど職場はいろいろな状況があるので限界があると思う。 ・幼いころいい子であろうとした。自分に値打ちがないから外側からとり入れようとしていた。今でもありのままの自分ではだめという思いは消えない。ありのままの自分を表現することこわかった。外から知識などを持ってきてもだめ。自分を尊重できないとしんどいままだと思う。 ・ぼくはそうではない。いろいろな人の意見を吸収して生きていくことで自己確立していけると思う。 ・知識や意見は鎧、鎧で自分が見えなくなっている。本当に付き合いたい人と接することができないと思う。 ・すべての人に全身全霊でつきあいたい。だからしんどい思いもする。1回目は無理でも2回、3回と重ねる中で付き合えるようになる。 ・自己確立でれば、付き合いたい人がわかるのではないか。自己確立できているか問うていくことが必要ではないか。 ・人はすべて信頼できると確信している。 ・僕は、人は信頼できるところもあるが、できないところもあると思う。信頼できない人を出会ったら離れる。それを判定できる自分でありたい。 ・人を信頼するためには、自分を信頼できないといけない。信頼できない自分があるが信頼する為にここにきている。人とのコミュニケーションの中でわかっていくと思っている。 ・人はそれぞれ・・・やっぱりひとりで生きていかないと。 ・無理しなくていい。自分が楽しいと思うことをしていく。人と接しているとウキウキする。その感情が大切で、そのことの積み重ねで自己確立出来ると思う。 ・私は学生時代生徒会長などをする積極的は性格だった。けれど、社会にでると人間関係のトラブルが多い。私はいいなあと思うこととよしやろうと思うことが一致している、人も同じだと思っていたが、違っていた。そのことがトラブルの原因だった。 ・心の健康はむつかしい。自分を認めることやありのままの自分を受け入れることが健康だと思う。温かい人間になりたいなと思っても自分の中に問題あるとなれない。 ・温かい人間になりたいと思っているわけではない。けれど温かさを実感していと思っている。あの時、あの人が支えてくれたな・・とかいう経験は糧になる。 ・自分とその助けてもらったり助けてあげたりした人と一体感があるから、自然とそんな行動がとれる。“助けてあげるんだ”と思うのは自然ではなく、よそいきの自分、“いい子”の自分。一体感は同じように生きているという実感や体験からくる。だからお互いに感謝の気持ち湧いてくる。 ・コミュニケーションの原点だと思う、してもらいしてあげる。自分の非を認めて自分からあやまることが関係性が深まる原点だと思う。 ・自分より下と思う人には言いやすいのは当たり前。対等で言いやすいと思われることが大切。 ・対等と違いの区別は認識が必要だと思う。男と女、平社員と上司、違いを認識して話すことが大切。すべて対等にといわれると少し違うと思う。 ・同じ人間という対等感、同じ人間として尊重しているという対等感の話だと思う。 ★午後からは午前の流れをうけて“自己肯定感”や親や教師など関係性の中で育つ“自己”。また他の人、主に家族との関係性をどのように作っていくかという話が出されました。 結論が出るような話し合いではなく、またこのワークショップの性格からも、話しあいのまとめはしていません。色々な話をして、聴いて、それぞれが自分や家族、他人との関係性について向き合え、考える時間であったと思います。 ・幼い頃から自分に向き合う教育をしていたら自律性が育つのではないかと思う。自分に自信がないから外側に目標を設定してしまう。小学生の時「好きなものを描きなさい」と言われて困った経験ある。今思えば、自分がなかったのだと思う。 ・実際の子育ての中ではどういう声かけをしていったらいいのか。母親も父親も自由にしたらいいいと思っているが、現実の生活や社会のなかではそうはいかないことも多い。子ども2人が楽しく生きてくれたらいいと思っていて、2人の楽しい様子を見るとうれしく思い、将来にたいする焦りが無くなる。 ・2歳半の孫はたくましく育ってほしいと思っているが、祖父母参観の出し物の練習ははりきってしていたが、当日熱を出したり、家では「オムツがいい」と紙オムツをはいてオシッコをしているのに、保育園では失敗したことがないなどデリケートな子どもになっている。たくましく、自己肯定感をもって・・と思っているが不安、どうしたらいいかわからない。 ・“よい親であるよりも、よい人間であれ”と子どもが思っているとい話をきいたことがある。 ・親が、確かによい人間でなければ心を充たしてくれないと大人になってから思う。ぼくは子ども時代から親に人間として共感してもらうことがなく、それが不満だった。 ・ぼくもなんかうちの親は尊敬できないなと思っていた。人間同士のふれあいに物足りなさを感じていた。 ・自分は母親を尊敬している。すきなようにさせてくれたので好きなようにやってきた。失敗したら怒られたが。“育ててもらった、”という思いがある。できれば倍返ししたいと思う。けれど、父親にはそういう思いない。殴られたこともないし、あまり何も言われなかった。陰で心配してくれていたと言う話はきいたことあるが。 ・小学校3年生の時の先生の影響が大きい。とにかく話をきいてくれ、きちんとほめてくれる先生だった。全てに真剣にむかってくれた。すごく憧れて、ぼくも人の話しをきちんと聴きたいと思った。 ・子どもは感覚的に人を判断する。聴いてもらった経験していると違う。聴いてもらうことの喜びを知っていると自分が聴く側になった時にその経験が生きる。自己を見つめる作業はしんどいが自分の内面を聴いてもらって受け入れてもらったら違うと思う。 ・聴いてもらった経験のない人はカウンセラーにはなれないという。反面教師は崩れやすい。なぜなら頭で行動しているので身体で温かいものを感じないから。自己肯定感からの行動、つまり“あんなふうになりたくない”というネガティブな所から行動してもだめだと思う。 ・母親にありがたいという思いではなく、自分がきちんとしたいという思いがある。母親に直接何かしてあげたい、例えばよろめいたらサッと支えてあげるとかしたい。恩返ししたいが返しきれないと思う。 ・以前「わかってもらいたかったのですね」と言われたことが嫌だった。これだけ話をしていても誤解はあるのだと思った。わかってもらいたい、もらえない残念さが人の話を聴く原動力になっている。 ・人間そうそうわかりあえない。だからこそ確認しあわないといけない。人間への信頼が根底にあるから言葉で確認できる。 ・家族のほうが言葉で確認すること難しい。 ・しがらみがある、役割や願いなどの関係性もあるから一層難しいのだろう。 ・子どもが自殺した。それを受け止める為に生きてきた。生きていく。家族も含め、他人を理解することは難しく、難解なこと、でも重要なことだと思う。人との出会いすばらしい、人生を変えることがある。人を理解したいと思う。 ●感想文から ・いっぱい話ができて、いっぱい聞いてもらっていっぱい聞くことができました。ちょっと成長したような気がします。次回開催されれば参加したいと思います。 ・グループとしては少人数だったが、話し合いにはちょうどよく、ゆっくり話し合うことができた。初参加者の心の深い所での感情もあって、心の持ち方、自分の本音の所のことや人との関係性など掘り下げて話しあうことができました。参加者の安心感も伝わってきました。変動する世の中での貴重な時間でした。 ・時間がゆっくり流れるようでした。城陽にすむ友人が年末で忙しく参加できなと残念がっていました。 ・参加者があまり多くなくて、ゆったりとした安心できる1日だったと思います。 言葉で伝える、聞く、わかる、理解する、確認する・・・とってもむつかしくて誤解も多いけれど、すてきだなぁと再確認。日常生活や家族・職場での人間関係がすぐに変わるわけではありませんが、毎日毎日の出会いや関係を大切にしたいなぁと思いました。何回も例会など出会っている方々の意外な面やすてきなところ、新しい面も見られとても有意義な1日でしたf。 ・新しい方が参加してくださり、真剣な話し合いができてよかった。人と人とのコミュニケーション、大事だと痛感する日々だが、なかなかスムーズにはいかない。特に親子や親しい間でかえって気を使いあってしまうなと思う。自己肯定感を子どもにも育てたいが教えようと思ってできることではない。話の中で自分自身が自己肯定感を持って、自分を大事に生きる姿を見せることが子どもにも伝わることになるのだと思った。じっくり、ゆっくり、それぞれの思いが出せて学ぶことの多い1日だった。 |
||
|