| 事務局 | 2016年度年報目次 |
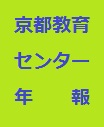 |
京都教育センター第47回研究集会 分科会報告 |
|
第5分科会 「私たちの暮らしと育ち」 姫野美佐子(子どもの発達と地域研究会事務局) |
||
Ⅰ.基調報告 子育てのこと、職場のことを率直に話し合える生き生きとした場があることに感謝している。今日のテーマは「私たちの暮らしと育ち」です。子どもだけでなく、大人も集団の中で育ちあうということがあると思います。子どもも親も育ち合える場とは?それは地域のなかに見つけられるか? Ⅱ.報告 ① 自己紹介より ・退職教職員。現在の教職員組合を援助することはとても大事だと思っている。地域を見渡すと、一人でさみしく暮らしている人がたくさんいる。こういう人たちとつながっていきたいと思っている。 ・より良い教職員採用制度を求める会で役員をしている。障害児を育ててきた親でもある。普段、ぼんやりと考えていることも、こういう場に一年に一度でも来ると、いろんな人にあえて意見をきけるので嬉しい。 ・児童館で働き、子育てネットワークを担当している。 ・少年団の事務局をしている。11月、少年団の全国集会に行ったとき、「子ども組織を維持していくことが大変になってきた」という話になった。子どもたちが年々、年のわりに幼くなってきていると感じる。 ・今、89歳。教育会館建設に関わるなど、教育に関していろいろなことをしてきたが、今の時代は「ものをつくっていく」ことが難しく混沌としていると感じる。障害児と関わってきたが、彼らは「枠にはまらない」地域も、いろいろな人がいて学校とは違う、枠にはまらないところがある。 ・高3、中3、小6の子どもがいる。けんかは絶えないが、手がかかることは減ってきた。小学校の先生になりたかったが厳しかった。でも今その、夢に近づくためがんばっている。 ② 〈安本俊昭〉「左京朝カフェ世代間交流グループの実践」 ・朝カフェに登録した人々が「この指止まれ」方式で、やりたいことを出し合って3人程度が中心となって呼びかけて実施。文化を通した世代間交流となっている。子どもたちも参加。 ・子どもたちが大原の自然を描く「大原絵巻」や、折り紙、紙飛行機、和凧など地域在住の在野専門家の協力。 〈質疑・意見〉 ・子どもの活動のためには何もない単なる広場(宝ヶ池公園のような)が必要。 ・「つながる・広がる」ことを意識的に追求することが大切。 ・軸になってすすめているのは3人とのことだが、意見が違う場合はどうしている?→まず3人でやりたいことを言い合い、出し合うと10個ぐらい出てくる。その中からひとつかふたつならやれそうだと絞っていく。 ③ 〈神谷潔〉「地蔵盆の今〜写真から学ぶ〜」沢山の写真を見ながら解説。 ・下鴨・左京・下京地区の地蔵盆の調査・訪問 ・一カ所を4,5年おきに訪問するので、変化がわかる。手作りの行燈、プログラムなど地蔵盆には既製のグッズがないことが良い点。 〈質疑・意見〉 ・かつては地蔵盆に学生班が存在したこともあったが、中高生が関わることがない。ふらっと現れる雰囲気がよい点でもあった。 ・子どもが少なくなり、高齢者だけでも地蔵盆を続けられるようにすることも必要。 ・地蔵盆は父親のデビューの場でもある。 Ⅲ 全体を通しての質疑・意見 ・朝カフェの活動には不登校の中高生でも準備に関わることができる自由さがある。外部の大学生は4年でつながりが切れてしまう面がある。子ども−中高生−大人の参加が大切で、少年団への期待は大きい。 ・学校教育は進学対策など上からの注入だけの教育となっているのが現状。地域の力を引き出すのに地蔵盆に期待できる。 ・少年団でも子どもたちの多忙化が進んでいて、集まりや祭りそのものを楽しめない状況がある。学力や部活のための時間ではなく、休日・安息日が子どもたちには必要であり、子どもの権利条約第31条にもよく遊ぶことが求められている。少年団の中の文化として、中高生の成長を位置づけることが大切で、かつては中学生会のような存在があった。子どもたちにとって自分たちもそうなりたいというあこがれ的な存在が必要で、そうした年代の青少年が少年団の活動を引き継いでいく道筋が見えていることが必要だ。 ・少年団が大切にしてきたことは、子どもたちだけでなく親も参加していること、そして青年の存在だ。取り組みを進めていく専門性とともに子どもたちの自発性を引き出すことが大切だ。地蔵盆には商品化の論理、経済の論理に引き込まれない地域の論理が存在している。学校以外に子どもたちが地域で活動できる時間を保障することが必要だ。 ・障害を持つ子どもたちが地域で過ごす時間を持つことは難しいが、専門性をもった支援学校の先生たちが自主的にソフトバレーなどの機会を親と一緒に作ってくれている。しかし、このような活動が若い先生たちに継承されない問題と、親も新しい世代が入ってこないという課題がある。福祉が契約化され、親同士、先生(専門家)同士のつながりがなくなっている問題がある。 ・朝カフェの良いところは「どうしたらいい?」と話すところからグループができてくる良さがある。それを活かして起業でつながり合い、互いの自立を助け合うこともできてきて、シェアし合う文化の可能性を感じる。 ・少年団の必要性が示しているのは子育ての危機であり、若者が安心して語り合う場がないという問題である。退職教員が若い先生の率直な相談を本当に受け入れられているのか、取り組みを検証する必要がある。 ・少年団において青年は指導員として子どもと一緒に悩んでもらう存在だ。子どもたちにとって青年はあこがれの存在であり、青年自身もやがて子育てをする際に自信につながる。その子女がまた少年団に加入するというサイクルが存在した。青年が子育てに関わることの大切さがここにある。 ・経済の論理、競争、サービスとしての「福祉」とは異なる、人間の主体性・つながりが重要。地域の本質は人間どうしがつながりをもつ暮らし・生活の場だということだ。 Ⅳ.感想より ・地域に根差した取り組みを続けていくことは、とても大事なことですが、難しさもあるなと皆さんのお話をきいてあらためて思いました。でも、地域の中には志をもって、いろんな取り組みに関わっておられる方がいらっしゃることも分かり、そういう方々ともつながっていきたいと思いました。この分科会も、いろんな立場とつながりがもてる貴重な場だと思います。参加して良かったです。また地域で発信しつつがんばろうと思えて励まされました。ありがとうございました。 ・現在の教育統制体制のもとで子どもと親、教職員が苦しみ、かつ希望へと前進させる上で、地域の役割がとても大きいと実感しました。「学校づくりは箱庭づくりではない、民主的地域づくりである」という与謝海養護学校建設時の教訓がますます輝いてきていると思います。 ・子どもと地域のかかわりについて具体的な報告を元に様々な意見をきくことができた。自分自身が現在の職場で課題としている中高生の力を発揮する場づくり、保護者同士の交流、グループづくりなどについても話を聞くことができ、とても有意義でした。 ・朝カフェを出発点に、子ども・子育て世代も楽しんで参加できる行事を継続している。行政を上手く利用しているとともに、起業などで自分たちの自立を互いに助け合う、シェア社会の可能性を感じた。地蔵盆のレポートでは、少子化で段々、オリジナルな地蔵盆行事が衰退しているように見えるが、関西独自の文化で資本主義の商品化が比較的浸透していないところに親―子どもの行事がまだ残っており、地域の活動の子育てにおける重要性がよく実感できた。中高生の参加や子どもがいなくても高齢者だけでも続けていくことの大切さが指摘されていた。共通しているのは、子ども・青年の多忙化。学校スタンダードや学校体制に巻き込まれ、商品化の論理、サービス化によって地域で子どもの育ちが奪われている点だと思う。 (11名参加) |
||
|