| 事務局 | 2015年度年報目次 |
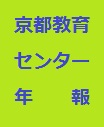 |
第46回京都教育センター基調報告 京都教育センター運営委員会 |
|
Ⅰ.はじめに-《集会テーマ》 について考える 今回の研究集会のテーマ「戦後70年、戦争と平和を考える~戦争をくぐった生き証人から学ぶ~」および記念講演のテーマ「戦争責任をどうとらえるか~学校・教師の戦争責任を問う~」を設定したことの理由、その意味について考えてみたいと思います。 * なるほど、現在の日本の人口の8割以上が戦後生まれであり、敗戦時15歳以上だった85歳以上の世代は3.8%にすぎません。徴兵・招集を経験した世代は、90歳以上になっています。安倍首相は、戦後70年の「安倍談話」で「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。」と言っています。「戦後レジームからの脱却」をめざす現政権ならではの歴史認識ですが、これでよいのでしょうか。 戦前の教育への反省に立脚した戦後教育改革 70年前の敗戦を画期とした戦後教育改革は、戦前の教育への反省に立脚したものでした。戦前の教育の過ちへの反省から、戦後においては教育を政治の手段としてはならないこと、教育は子どもの成長・発達を保障するものとして、それ自体固有の価値をもつものであることが確認され、出発したはずでした。 戦前と戦争に対する反省という課題はもう終わったのか 今回の研究集会で記念講演をされる佐藤広美さんは、「現代は、果たして、戦前と戦争に対する反省という課題はもう終わったと済ますことができる時代なのだろうか」「戦前に対する痛切な反省をどこまで行い得たのか、それは徹底した反省であったのかどうか」を問い、教育にとって「国家に屈服した罪の自覚という戦争体験の思想化」という課題の重要性を一貫して主張されてきました。それが欠落した時、「教育の危機的現実を読み解き批判する拠り所を失い、現状への追認になりかねない。それでは、貧困と格差を呼び起こし、教育統制を強める新自由主義的改革を断行する国家の教育行政犯罪を見損ない、免罪してしまう。」という佐藤広美さんの指摘は鋭い。 根本的問い直しを求めている 戦争体験とその後の70年の歩みは、日本社会と教育のあり方に対する根本的問い直しを求めています。私たちがどう生きてきたのか、どう生きるのか、今の現実に向き合い、教育を政治の手段となることを許さない思想性をどう引き継ぐのかを考え合う研究集会にしていきましょう。 Ⅱ. 子どもと教育をめぐる情勢 1. 全体情勢 「自分の言葉で」 戦後70年目の夏。 特定秘密保護法反対に続いて安保関連法案(戦争法案)に反対して主権者として立ちあがったSEALDsの若者たちのスピーチで特徴的なのは、「自分の言葉で」というこだわりにあり、何よりも政治課題を日常生活と切り離さないかたちで、徹底的に「自分自身の問題」として言葉を紡いでいる点にあると指摘されています(*注1)。 大澤茉実さんのスピーチを手がかりに 「空気を読んでいては、いつまでも空気は変わらないんです。」―10月25日に法政大学で開催された安保関連法案に反対する学者の会主催のシンポジウムで発言したSEALDs KANSAIの大澤茉実さん(立命館大学2回生)のスピーチ(*注1)を手がかりに、今を生きる子ども・青年の発達の可能性や学校教育への課題を考えてみたいと思います。 「引きこもり」体験 大澤さんは高校時代の「引きこもり」体験を次のように語っています。「…私は2年前ぐらい、半年間、もうちょっと、ずっと布団の中にいて、なんか『こんな社会で』とか思って、ずっとアニメとアイドルとかばっかり見て、人と話したくなくって。」 新自由主義が浸透する「現実社会」で「よい子」を求められ 「引きこもり」へと至る大澤さんは、新自由主義が浸透する「現実社会」で「よい子」を求められてきました。(それはまた、競争と評価によって管理される「よい教師」の内面とも重なっています。) 「…この社会には、『自己責任』という、見て見ぬフリ、自分だけを責めることが美化される姿勢、他人を傷つけることで解消する鬱憤や、弱い者に皺寄せの行く『仕方のなさ』が溢れています。常に何かに追い立てられるように、数字で、金で、ノルマで、自分を語ることが求められています。飛び交う言葉には中身がなくなり、それは誰かを傷つけ、言葉で傷ついた人は言葉で傷つけることで自分を守ろうとします。その感覚が、私には痛いほどわかります。私も、小さい時から『よい子』を求められてきたからです。(中略)私は、言葉を自分の中に押し込めて、黙ることを覚えました。そうやって、ひたすら教室に、この社会に順応することが普通やと思っていました」。 友だちとの出会いとその存在 そして大澤さんは、「私を支えてくれる大切な女の子たち」と出会います。貧困の中で家族が崩壊している友だち、家が安心できる居場所ではない友だち、しんどい時にしんどいと誰にも言えなかった友だち…こうした友だちとの出会いとその存在は、それまでの友だちとの関係性を質的に大きく転換させると同時に、自分を対象化していく重要な転機になっていきました。 空気を読んでいては いつまでも空気は変わらない 大学に入学して一年後、大澤さんたちのSEALDs KANSAIは東京を中心にしたSEALDs と同じ日に活動をスタートし、勉強会と並行しながら地元関西で6月から毎月デモを行い、7月からは毎週金曜日に街宣もおこなっていきました。「言葉を自分の中に押し込めて、黙ることを覚え」、「ひたすら教室に、この社会に順応することが普通や」と思ってきた大澤さんが、「この夏、普通だったことは、どんどん普通じゃなくなりました」。「『当たり前』に順応するのではなく、何を『当たり前』にしたいのか、常に思考し行動し続けること。どうやらそれだけが未来を連れてきてくれるようです。空気を読んでいては、いつまでも空気は変わらないんです。そのことを、デモをするたび、街宣をするたび、一緒に声をあげる名前も知らない人たちが、その勇気でもって教えてくれました。」「おんなじ街に住んでいても、自分とは違う国籍や経済状況にある人のスピーチは、私に、自分とは違う誰かと生きていくことへの想像力をくれました。もうすでにこの街で一緒に生きていたんや、って気づかせてくれました。それは、誰かに死ねというよりも、自分が明日どう生きていくか語る方がよっぽど未来を変える力を持っていることを教えてくれました」。「私はほんの数年前まで新聞の中にだけあった『沖縄』を、『東北』を、こんなにも近くに感じたことはなかった。彼らの息遣いが、怒りの声が、今の私には聞こえます。」、と。 主権者として、普遍的価値を日常生活からとらえ直す 生きることに絶望しかけていた大澤さんが、「こんなにも自分が生きていることを噛み締めた夏はなかった」と確信させていったのは何だったのか。「人権」や「平和」、「民主主義」などの普遍的な価値がうさんくさく、嘘っぽく受け取られる土壌がヘイトスピーチの背後にあることが指摘される(*注3)今日、SEALDsの若者のこだわりとして最初に紹介したような、主権者として普遍的価値を日常生活から「自分の言葉で」とらえ直すという思想、彼らのスピーチやサウンドデモの「コール」にみられる他者にひらかれた「声」や「怒り」の表出、身体の解放など、今日の社会と学校が子どもたちから奪い、抑圧してきたものを取り戻すかのように展開していった彼らの思想と行動に「憲法を教育の中に生かす」ということの具体化、教育課程づくりの大きなヒントがあるのではないでしょうか。大澤さんのスピーチには、今日の学校教育と学校関係者への本質的な問いかけが内包されているのではないでしょうか。 *注1:南出吉祥「政治における身体性―奪われた『声』を取り戻すために」(『教育』2015年11月号) *注2:9月19日未明、戦争法が国会で通過した直後の国会前での大澤茉実さんのスピーチおよび10月25日に法政大学で開催された安保関連法案に反対する学者の会主催のシンポジウムでの大澤茉実さんのスピーチの全文はネット上に掲載されています。 *注3:大澤真幸・木村草太著『憲法の条件/戦後70年から考える』2015年、NHK出版新書 いま、憲法の大きな危機に いま、日本は戦後の平和と民主主義を支えた憲法の大きな危機にあります。 「戦争立法」は国会を通過しました。だが、それは危機ではあるが終わりではありません。危機とは峠であり、分岐点です。 危機が新たな生き方へのチャンスになることを私たちは知っています。現にいま、どんな時代と社会に生きているかにめざめて立ち上がり、新たな生き方を模索する若者たちがどんどん増えています。 敗戦から戦後への転換を示す「国民から個人への解放」 『奈々子に』の詩人・吉野弘さんは19歳で敗戦を迎えました。吉野さんは自分たちの少・青年期は「国のために生きること以外は考えないように教育された」「自分の幸福について考えた記憶など全くなかった」「敗戦によって初めて私は、自分が国民から個人へと解放され、自分のことを自分で考えてもいい時代になったのだと漸く思うようになっていた」といいます。 これほど、わかりやすく敗戦から戦後への転換を示してくれる言葉はありません。それは「国民から個人への解放」だったのです。この言葉のなかに、「すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」(憲法第13条)という新しい憲法の掲げた根本理念の大事な意味が端的に示されています。 憲法9条が最大の抑止力 この理念を実現するために憲法9条があります。軍隊に個人の尊重、自由、幸福追求の権利があるでしょうか。戦争を始める国に、平らかで和やかな心があるでしょうか。集団ヒステリーに巻き込まれない精神や心の自由があるでしょうか。自分の頭で考え、自分の心で決める個人としての自立があるでしょうか。 攻撃的になっている人間に対する最大の抑止力は、平らかで和やかな心です。敵意や攻撃心は、相手の敵意や攻撃心を煽るだけだ。だから憲法9条が最大の抑止力です。問われているのは、この考えを一人ひとりが、どれだけ自分のものとしているかということです。そのことが、戦後70年のいま、安倍政権による安保法(戦争法)が国会で強行可決されたいま、これまで以上に深く国民に問われています。 憲法を教育の中に生かす運動を大きく どんな国をつくるかは、どんな国民をつくるかに反映されます。だから、平和と民主主義と立憲主義の国をつくるためには、憲法の根本理念の生かされる教育がなにより大切なものになる。 憲法を教育の中に生かす運動や取り組みがこれまで以上に大きく、高くかかげられなければならなりません。 2. 当面する課題 1 現代の子どもをめぐる状況と課題 厳しい現実を越えて、どの子にも夢と成長の未来・発達保障を 「いじめ防止対策推進法」実施から2年が経ちました。法律を厳しくしたり、数値目標で指導強化しても子どもの問題は簡単に減少したり、いっきに解決するものではありません。いじめ、不登校、体罰、虐待、暴力、子どもをめぐる事件は その背景に、過度な競争主義、格差、貧困問題等、深い社会的原因があります。 「いじめ問題」と教育行政・学校・教師 ―「小学校いじめ最多」報道― 「いじめ防止対策推進法」は「厳罰主義・道徳主義」の傾向があり、学校現場では、「報告文書」が増え、集団論議・対応以上に教育委員会への報告が優先される傾向があります。「いじめ最多、低年齢化」と文科省の調査結果・府県別数が発表されました。しかし全国的には岩手「いじめ・自殺事件」で示される「学級担任責任論」「取り組みの形骸化」が指摘されています。京都では9月3日に4月~7月の「いじめ調査結果」「重大事例」が発表されました。「いじめ件数減らし」よりも学校全体でどう取り組んだかを大切にして、一人ひとりの子どもと集団の成長と発達に繋がる実践が出来たかが問われているのです。 不登校・登校拒否2年連続増加、小学生割合最高、大切な「親の会」の存在 文科省は5月調査で2年連続不登校が再び増加、とくに小学生の割合は過去最高と発表しました。これは行政の「不登校対策」が強化されている一方で、「学力テスト点数競争」「管理主義教育」が一層進んでいることの現われでもあります。不登校対応の「多様な教育機会法案」は今国会提案では断念されましたが、何が不登校の子どもと親に大切か充分論議されることが必要です。不登校の「親の会」との連携を大切にし、学校現場の集団的な取り組みが期待されています。 まだ残っている「体罰」、中学「部活問題」課題 大阪の「桜宮高校体罰自殺事件」以降学校内外で体罰問題は関心を呼びました。生徒指導における「体罰」には「ゼロトレランス」指導が背景にあり、「部活・クラブ活動」での体罰には「勝利至上主義」「スポーツ推薦入試競争」が背景にあります。厳しい体罰批判が寄せられる反面、「体罰肯定論、根性論」も根強く残っています。「部活と体罰」には「中学校教師超過勤務問題」解決と「部活指導のあり方」等、課題として残っています。また新たに養護施設や地域のスポーツ少年団における虐待・体罰も問題に上がりました。 小学生の暴力が過去最多、中高生前年より減少、指導困難は深刻 「きしょい、きもい、ガイジ、死ね、ぶっ殺す」等の暴言が、日常化している中で子どもの暴力問題行動が増えています。子どもの暴力が集団化し「恐喝・傷害事件」になった場合は警察との連携は仕方ないとしても、中学校現場に 日常的に警察が「指導」に入ったり、小学校に「いじめ」「万引き」指導で直接警察官が授業・学年指導するのは、行き過ぎで「教育の放棄」ではないかと批判されています。子どもの暴言・暴力の背景には、自分の感情・思いを言葉で表現する力が弱くなっていること、集団活動での話し合い・討論の場が減っていることも考えなくてはなりません。 児童虐待通告は上半期1.7万で過去最多、背景に親の経済状況、貧困格差 生活保護家庭数は最高になり、虐待件数も年々増え続け最多になっています。生活におわれ子供を育てる余裕を失った親が増えているのです。「指導困難」と言われる子どもの背景には「虐待経験」があります。また「勝ち組」といわれる「経済的」に恵まれた子ども中にも、親のその地位を守りたい願いから子どもに精神的虐待とも言える過度な進学競争を強いる犠牲も増えています。 学校は地域や福祉の援助を得ながら、共に子育てをする姿勢で親に接することが大切になっています。 深刻化する「子どもをめぐる事件」増加、子どもの豊かな成長と安全を守る課題 「川崎中一少年事件」と「寝屋川中二男女殺害事件」は子どもをめぐる事件として注目されました。背景に加害者・被害者共に経済的に厳しい中で、家庭が安心出来る居場所になっていない現実と、携帯やスマホでつながり、夜中に徘徊する子ども・少年が増えていることがあります。一方「佐世保高一同級生殺害事件」、「名大女子学生事件」等は、どちらも「学力優秀」な子どもが起こした事件です。親が経済的、社会的地位が高い中で「勝ち組の競争」に晒された子どものゆがみ、苦悩から来ています。かけがえのない一人の人間として子どもが本当に大切にされ、家庭と学校が 安心して生活できる居場所となっているかが問われているのです。 京都の学校現場や地域では課題を持った子どもの「勉強会」や「居場所」づくりの実践も取り組まれています。「苦しみ悩む」子どもたちが「ここに生きて存在していても大丈夫なのだな」と共感と安心を得られることが大切なのです。厳しい生活現実に晒されている子ども達に将来に対する夢と希望を与える福祉と教育の充実と 子ども・父母・地域の期待に答える学校づくりが課題になっています。 2 学力の問題と「道徳」の教科化 学力をめぐる新たなステージ 学力をめぐる問題はその定義を含めて戦後揺れ続けていますが、この20年近く根底で支配する考え方は「競争」にシフトされた学力観です。「全国一斉学力テスト」や競争入試などによって企業にとって有能な「人材養成」が主流になり、人間らしく成長するために「生きる力」となる学力形成が後方に追いやられてきているといえます。そのもとで今、強調されているのが「アクティブ・ラーニング」の手法です。 これは大学などで、大教室での一方通行の講義の改善に端を発したものですが、受動的な学習スタイルから「書く・話す・議論する」活動で認知を深める手法で、小学校でも国語や社会を中心に展開されてきています。「総合的な学習の時間」での探求的な学習の推進や「PISAショック」(2004年)を受けて強調された読解力向上のための「言語活動の充実」の流れがあります。 また、学校と学習塾との連携が進み、塾講師が常駐して授業も行うという「官民一体型」の小学校が出現するなどの異常な事態もあります。深刻化する「学力格差」問題が「経済格差」に起因するといわれる実態がある中で、こうした新たなステージがすべての子どもたちの学習意欲の向上に繋がるのか、実践的な検証によって見極めていかなければ子どもの実態を横に置いた「試行錯誤」の繰り返しになりかねません。 次期学習指導要領改訂の方向 新指導要領は小学校では5年後の2020年度から、中学校は2021年度から、高校は2022年度以降に全面実施される予定で、文科省は「大幅改訂」といわれる骨格素案を8月に、諮問機関「中央教育審議会」に示しました。教育課程上の大きな変更点は小学校英語の強化で、2011年度に必修化された小学5~6年で週1コマの外国語(英語)活動が3年生まで広げられ、5年生からは週2コマの教科として評定されるようになりました。 もう一つは、前回の改訂で殆ど手が付けられなかった高校段階で、18選挙権での政治教育や規範意識を意図する「公共」科や現行必修の「世界史」に加えて「日本史」の近現代を軸に統合した「歴史総合」科などが新設されたことです。小中学校では前回改訂で学習内容を大幅に増やしたため、授業だけの履修では分からないままに置き去りにされた子どもを多数生みだし、塾に依存しなければついていけないという深刻な問題を引き起こしていますが、小学校英語の拡大で拍車がかかることが危惧されます。 そして何よりも大きな問題点は中教審の教育課程部会「論点整理」で出されている「カリキュラム・マネジメント」(教育課程経営)の考え方で、「教育目標・内容と学習・指導方法・学習評価のあり方を一体として捉える」点で教育課程を品質管理のPDCAサイクルで統制しようとしていることです。また、「新しい時代と社会に開かれた教育課程」と打ち出しながらも最も「開かれる」べき現場教師が視野に入っていないことも致命的と言わねばならなりません。 広がる「全国一斉学力テスト」の弊害 2007年から実施された文科省の「全国一斉学力テスト」は9回目の今年も新学期早々に小6、中3生を対象に実施されました。 当初は犬山市の不参加表明などがあり、民主党政権下では悉皆ではない抽出実施もありましたが、今では「年中行事」のように粛々と実施されています。結果の公表や活用の圧力から、テスト内容が日常の学習内容をコントロールし、過去の問題練習での授業の遅れ、年度当初の行事の変更などが公然と行われ、問題の難易度も年によって違うために学習内容の検証にならず、ランキングだけがひとり歩きしている状況があります。毎年60億円もの巨額をかけて全員対象に行う必要があるのかマスコミなどもその改善を主張しています(「朝日」8/27社説)。また文科省は、「英語力向上推進プラン」の一環として平成一九年度から中三生を対象にした「英語全国統一テスト」の実施を目論んでいます。 そして、大阪府・市教委では学校別平均点や個人成績を来春の高校入試の内申点にリンクして活用するという由々しき事態になっています。文科省は「目的外使用」との見解を示しているものの、こうした「悪用」が全国的に広がる可能性が心配されます。 高校でも将来的には大学入試や就職へ活用するとした「高校基礎学力テスト」を2019年度から高2、3年生を対象に年2回実施すると文科省の有識者会議で打ち出しています。また、2020年度からは今の大学入試センター試験に代わって「大学入学希望者学力評価テスト」を実施する方向で検討していますが、その運用については高校での履修問題との関連で不透明です。 「道徳」の教科化をめぐって 昨年10月に出された「中央教育審議会答申」で、安倍内閣の求める「道徳の教科化」が盛り込まれ、記述式とはいえその評価が強引に導入され、2018年度以降に小中学校で実施されます。また、今年2月に出された教科化に伴う学習指導要領の改定案では小1~2年生で「わが国や郷土の文化と生活に親しみ、愛着をもつこと」と明記され、初めて「わが国」が明記されました。そして、教科書検定の基準となる「学習指導要領解説」では「国とは、政府や内閣などの統治機構ではなく、歴史的・文化的な共同体を意味する」と明示し愛国のイメージを表しました。「子どもの発達に即し、深く考えられる教材」「自分の考えをもとに討論したり書いたりする言語活動に配慮」などを強調するものの、教師が評価することと相まって国定の規範や理念が子どもの内面に浸食していくことが懸念されます。 こうした動向に対して「道徳性規範は個人と社会の両方にあって、個人の側だけに求められるものではなく、社会の側の規範の低下や道徳性の退廃こそが問われるべき」(佐貫浩教科研委員長)など教育学者の指摘もあります。競争の中で尊厳を奪われても自己責任を問われるのが当たり前の社会で、子ども達のプライドや居場所を確保するために、道徳教科書の徳目を順々に教え込むのでなく一般教科や生活指導の中で豊かな人格を育む道徳性の涵養こそが私たちに求められています。 3 教科書・歴史認識問題 ポツダム宣言を肯定することができない安倍首相 第二次世界大戦終結から70年目を迎える今年2015年、ナチスを打ち破った対独戦勝記念式典、中国による対日戦勝記念パレードが行われましたが、10年前と異なり、欧米の首脳と中露の首脳が式典に同席することはありませんでした。ロシアのクリミア併合、シリア内戦などの影響により西欧とロシアの亀裂が表面化している状況にあります。第二次世界大戦は日本がポツダム宣言を受諾したことにより終結し、国際連合など戦後国際社会の出発点となりました。ところが、日本の安倍首相はポツダム宣言を肯定することができないでいます。 ポツダム宣言は日本の指導者が「国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出づるの過誤を犯させしめた」とし、カイロ宣言と併せて満州、台湾及び澎湖諸島は「清国人から盗取した」と断罪しているのであり、第二次世界大戦はいうまでもなく日清戦争からして侵略戦争と認定したものです。 21世紀有識者懇談会の20世紀の歴史認識 しかるに安倍内閣は21世紀有識者懇談会を立ち上げ、その報告書において次のような20世紀の歴史認識を是としています。 20世紀は帝国主義と国際協調のせめぎ合いの中で、第一次世界大戦後は国際協調の下、戦争違法化が進められる段階に至っていたが、世界恐慌によって各国が自由貿易体制を閉塞させる経済ブロックを推し進めた結果、第二次世界大戦に突入した。そこから引き出される歴史の教訓は国際協調と自由貿易を堅守することであり、戦後の日本は日米同盟と平和的・外交的解決による平和国家として道を歩んできたものとする。 安倍談話の歴史認識の歪み 8月14日、閣議決定された「戦後70年総理大臣談話」は、「我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました」と村山談話を継承するように見せながら、土台は報告書の内容とその歴史認識を下敷きにしたものです。日露戦争がアジアの人々を鼓舞したなどと述べ、この戦争が中国東北地方・朝鮮半島を戦場にした点や日清戦争が植民地獲得をもたらしたことにも言及していないなど、アジアの国々に対する植民地化と侵略戦争への謝罪と反省の点で村山談話から明らかに後退しています。 これは日清・日露戦争までは栄光の歴史であり昭和に入って国策を誤ったという明治維新と明治憲法を讃美する歴史観です。昨今のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」及び世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産―製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業―」に松下村塾が入っている異様さ、11月3日「文化の日」を「明治の日」にしようとする右派の祝日法改正運動とも共通する歴史認識の歪みです。 中学校教科書の検定結果の問題 安倍内閣は教育政策、とりわけ教科書を通じてこうした歴史認識を強制しようとしています。4月に公表された2014年度中学校教科書の検定結果は、昨年の『学習指導要領解説』改訂の影響で全社にわたって領土問題が記述された上、政府見解を記述することを求める検定により、学び舎の教科書がその従軍慰安婦記述のためにいったん検定不合格になるなど、学問の自由と子どもの学習権を侵害したものとなっています。教科書検定基準の改悪により、通説、「正確性」を求めると称して、関東大震災の虐殺者数、北海道旧土人保護法の記述が書き替えられました。 せめぎ合う中で行われた今年の教科書採択 今年の教科書採択は、新教育委員会制度の下、教科書採択のあり方をめぐってせめぎ合う中、行われました。文科省は1月の政令指定都市教育委員会・教育長会議の場で「(教科書)調査員からの報告等を鵜呑みにしたり、教職員の投票によって」採択されることは不適当との資料配付を行いました。これに対し、衆院文科委員会で畑野君枝議員が教科書採択における教職員の専門性が否定されない旨の初等中等局長の答弁を引き出しています(4月)。 育鵬社の教科書の問題点 安倍政権と右派が推奨する育鵬社の教科書は、歴史教科書が明治維新と戦争の歴史を美化し、公民教科書では明治憲法をアジア初の憲法として強調することで日本国憲法を貶め、改憲へ誘導する内容となっています。全国的な反対運動のなか、9月に強行採決された戦争法(安全保障関連法)を先取りした内容となっており、この教科書が教育現場に持ち込まれれば、今日の情勢において極めて危険な役割を果たすことが明白です。 採択結果の特徴 採択結果は、京都府下において育鵬社・自由社の歴史・公民教科書を採択することは阻止できました。しかし、全国的には現行の大田原市、横浜市、東大阪市、呉市などに加えて新たに金沢市、加賀市、松山市、大阪府下では大阪市、四条畷市、泉佐野市、河内長野市などが育鵬社を採択しました。ほかに千葉県立、宮城県立、山口県立、福岡県立の特別支援学校、中高一貫校などでも採択されています。これらの自治体では、首長の関与が疑われる事例や、教育長が育鵬社を推薦した例、教育委員会議で選定委員会答申を全く無視した事例などが報告されています。 京都市の採択においても選定資料「選定の観点」に新たに「伝統と文化の尊重、我が国と郷土に対する愛情」という前回よりも踏み込んだ表現が盛り込まれました。答申においても育鵬社の歴史教科書を「我が国の伝統文化への関心を高めるための工夫が優れている」、「神話について詳しく記述される」と評するなど、各社ともに領土問題の記述が評価されるなか、育鵬社・自由社教科書に有利な採択環境となっており、警戒が必要です。教育行政の公正な運用、瑕疵の有無などを監視・チェックするとともに、改悪された検定・採択のあり方を是正していくことが必要です。 侵略戦争を美化する教科書を採択させない運動の前進 今回、地道な住民の運動によって東京都大田区、神奈川県立、益田市、今治市では育鵬社から他社の教科書に取り戻すことができました。攻撃されていた実教出版の高校日本史A・Bの教科書を採択する高校が大阪府下では8校から12校に増加するという前進も見られています。 京都においても各地で学習会、街頭宣伝が積み重ねられ、教科書展示会にも多くの市民が出向きました。京都教科書問題連絡会は危険な教科書を採択しないよう府・市教育委員会への申し入れを複数回実施するとともに、採択決定後も採択過程の公開・傍聴、教科書展示会の改善、教職員の教科書研究の機会を保障するよう要請行動に取り組みました。 4 高校教育を巡る状況と課題 「18歳選挙権」に伴う新たな文科省通知 本年6月公職選挙法が改正され、18歳・19歳の青年が新たに選挙権を手にすることになり、これに伴い文科省は「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」を出しました。その中で有権者としての権利が行使できるよう、教員の「政治的中立」確保を念押しした上で、具体的かつ実践的な政治的教養の教育の重要性を強調するとともに、生徒による政治活動等には様々な制限があることを列記しています。高校生の政治活動を禁止した1969年通達の廃止も明記しています。 憂慮される主権者教育の形骸化 今後学校現場では、公民科の授業のみならず、特別活動や総合的な学習の時間などでの主権者教育が推進されることになり、文科省は早くも「副読本」を作成し、在籍生徒への確実な配布と学校における有効活用を要請する文書を発出しました。 一方、自民党は7月8日に政務調査会名で「選挙権年齢の引き下げに伴う学校教育の混乱を防ぐための提言」を公表し、この中で「高校生の政治活動は基本的に抑制的であるべき指導を高校が行えるよう政府としての責任ある見解を学校現場に示すべき」「教員の日々の指導や政治活動については政府としてその政治的中立性の確保を徹底すべき。政治的行為違反に罰則を科す」と記しています。 こうした中で学校現場では戸惑いが見られます。特に、「政治的中立」を具体的な教育実践の中でどう考えればいいのか、生徒達の政治的活動をどう考えどう向き合えばいいのか、大きな課題となっています。 高校統廃合計画の焦点となっている丹後-求められる府民的論議 高校統廃合計画の今年度内発表も予想されます。府教委は今年の8~9月に「生徒減少期における府立高校の在り方検討会議」を三度開きました。目的は、生徒数が減少するにあわせて府立高校減らしを進めることです。議論の中心は府北部(口丹、中丹、丹後通学圏)で、その焦点になっているのが丹後です。会議資料では2013年度の中三生の数を100とした場合、2028年度には京都市・乙訓(87.7%)、山城(83.2%)、口丹(70.6%)、中丹(79.3%)、丹後(56.1%)となるとされています。 会議では北部は「独立した高校の最小規模は3学級(1学年)」等の意見も出され、5学級学校と3学級学校を比較した府教委の資料では3学級校のディメリットが示されました。丹後地域では全校が1~2学級減って3学級校になるだけに、丹後での府立高つぶしが懸念されます。この他にも口丹では農業関係学科の再編、中丹では定時制(分校・夜間)と小規模校の整理も予想されます。 「検討会議」という狭い場所での議論ではなく、地元高校の消滅は地域にも大きな影響を与えるだけに、十分な時間をかけた府民的論議が必要です。 鴨沂高校の夜間定時制を募集停止に 府教委は8月21日に2016年度公立高校の募集定員と入学者選抜要項を発表し、この中で70年以上の歴史を持つ鴨沂高校の夜間定時制を募集停止にしました。府教委はその理由を志願者減と説明していますが、2014年度入試では定員90名に対して49名が志願しています。2015年度入試では清明高校開校を理由に定員が30人へと大幅削減され、その結果志願者19名、入学者14名となりましたが、その原因は定員大幅減が受検生に不安を抱かせたからです。隣接の朱雀高校定時制では60~70人台で推移していた志願者が突如98人に増えています。 2015年度の鴨沂高校定時制の定員大幅削減の結果、朱雀・桃山定時制は定員いっぱいの入学生を受け入れ、再度一年生をやり直す生徒を加えると30名の学級定員を超えるクラスも出ています。今回の鴨沂高校定時制の募集停止はこの傾向に拍車をかけ、様々な課題を持つ生徒たちが少人数教育の中でじっくりと発達していく機会を奪うことにつながります。 3年目を迎える「前期選抜」入試の問題 導入から3年目を迎える「前期選抜」入試では、過去2回府内で5269名、6441名の不合格者が出ました。前期不合格者が「中期選抜」で同じ学校を志望し合格するケースも多く、高校不合格という一生残る体験を多くの生徒達に強いることには大きな問題があります。大阪府教委は大量の不合格者を出すことへの府民の批判を受け、2016年度入試から全校で実施する前・後期入試を廃止します。 民主的な学校運営をこそ 学校の閉そく性が進行しています。職員会議での発言者は少なく、トップダウンでことが決まる傾向が益々進んでいます。生徒の最善の利益を実現するためにみんなで知恵を寄せ合って物事を進めていくという民主的な学校運営が消え去ろうとしています。みんなで寄りあい、気兼ねなく自由に語り合える場を職場の中に作っていくことが極めて重要になっています。こうしたこともなしに主権者教育の推進などとてもできるものではありません。 5 大学改革問題 新自由主義的な大学改革は、近年いっそう加速化するとともにその矛盾は大学の危機として現われています。 政府予算の実質的な削減と競争化 従来から乏しかった政府予算は実質的な削減と競争化が進んでいます。国立大学では法人化以降、運営費交付金が10年間で1,000億円以上も削減され、私立大学の経常費補助金も国立大学との格差が是正されないままです。その一方で、政府や経済界の意向に沿った特定のプロジェクトのための競争的経費は増やされています。その結果、国立約80万円、私立約130万円(初年次)の世界一高い学費が学生を苦しめ、地方の中小規模の大学を中心に教育・研究・経営等の水準が悪化しています。 「国家戦略」としての大学改革へ これまで大学改革は文部科学省の主導の下、グローバル化と競争化を中心に進んできました。しかし、2012年頃より官邸主導の「国家戦略」として、より経済界の意向に結びついたものへと変化しています。2012年の「大学改革実行プラン」や13年の「国立大学改革プラン」は大学や学部の機能分化や再編を視野に入れ、大学を経済界に奉仕するための人材を供給する機関にすることを狙っています。さらに、これらの諸改革を実行するために学長や理事者のリーダーシップ強化を目的として、14年には学校教育法・国立大学法人法の改悪が行われ、今年4月に施行されました。これら一連の動きは、学問の自由や大学の自治と民主主義を破壊することに他なりません。 相次ぐ注目すべき動き 今年に入ってから、注目すべき動きが相次いでいます。 まず、4月に安倍首相が国会答弁で「(国立大学が)税金によって賄われているということに鑑みれば新教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべき」と述べたことを受けて、6月に下村文部科学大臣(当時)は国立大学に入学式や卒業式等における「日の丸」・「君が代」を求めました。しかし、多様な国籍の教職員・学生を抱える大学においては自主的に取扱うべきものです。 さらに同じ6月に文科省が出した通知では、国立大学に対してのいっそうの改革推進を要求し、人文・社会科学系の廃止・縮小を項目に掲げました。政府や経済界の「役に立つ」分野を重視し、それ以外を軽視し切り捨てる姿勢は絶対に許されません。 また、今年から防衛省による軍事研究費が大学に下りることになり、58大学が応募して東京工業大など四大学や宇宙航空研究開発機構(JAXA)など計9件が採択されました。10月に財務省が国立大学法人への運営費交付金を私立大学並みにまで削減する構想を発表したことも記憶に新しいところです。 「ローン事業」化する奨学金制度 大学生・大学院生は高学費に加えて不十分な奨学金制度にも苦しんでいます。日本学生支援機構(旧・日本育英会)の奨学金はすべて貸与制であり、このうち7割は利子を付けて返済しなければなりません。家計が厳しいなかで学生への仕送りは10年間で3~5割減少し、大学生の5割が何らかの奨学金を借りるようになりました。借入額は、学生では200~300万円が一般的で、大学院生では借入総額は4人に1人は500万円以上、10人に1人は700万円以上もの額が事実上の「借金」としてのしかかっています。しかも、厳しい雇用情勢下では卒業後の返済もままならず、滞納者のほとんどは経済的厳しさを理由として挙げています。追い打ちをかけるように取り立て強化も進められ、いまや奨学金は政府による「ローン事業」と化しています。 財務省の国立大への交付金削減計画は単純計算で40万円の学費増となり、この状況に追い打ちをかける可能性が非常に高く、断じて容認できません。政府は2012年に留保を撤回した「国際人権規約」社会権規約13条の学費の漸進的無償化に向けた、具体的な行動を起こす責任があります。 大学生・大学院生の働く権利・学ぶ権利の侵害 学生・大学院生をめぐる厳しい経済環境は、大学生・大学院生の働く権利・学ぶ権利を侵害しています。就職率は一時期に比べて改善したものの、若者の非正規雇用率は高く、違法な労働を強いる「ブラック企業」の問題も深刻です。そのため、若者の経済的自立の見通しは極めて不透明であり、一人一人の若者の尊厳が侵されています。 また、就職活動時期の変更により中小企業への就職環境が悪化や「オワハラ」問題も見逃せません。さらに、厳しい経済環境は大学および大学院への進学の機会を奪い、また長時間のアルバイトよって学習の時間も奪っています。厚生労働省の調査は、6割もの学生がアルバイトをめぐってトラブルの経験を持っていることを明らかにしています。 こうした学ぶ権利の侵害は教育と研究の質の低下を招いており、歴代のノーベル賞受賞者も基礎研究分野の弱体化を危惧する声をあげています。実際に、大学院生の数は2011年をピークに4年間で約1割も減っており、高度な専門職や将来の教育・研究の担い手が育たないことが懸念されます。 「軍学共同」には6割以上の研究者が反対しており、国立大への交付金削減には中央教育審議会や国立大学協会も反対の声を上げています。「文系廃止」通知には経済界からも異論が出されています。こうした中で、世論と運動の広がりは新たな展望を切り開いています。例えば、厚生労働省は「ブラックバイト」の調査を行い、結果を公表しました。加えて、文科省による大学での授業・研究補助アルバイトに関する調査が現在準備されています。また、不十分な点を含んでいるものの、就職活動時期の再見直しを日本経団連が発表したことも注目されます。 大学改革に対抗する自由と民主主義の回復を 安保法制をめぐっては、学者・研究者や学生・大学院生のあいだで安保法制反対の運動が大きく盛り上がり、「有志の会」は42都道府県130以上の大学に広がっています。9月の地方公聴会で広渡清吾・日本学術会議会長の「反知性主義」という批判は多くの大学人の共感を得ました。それは、戦争の危機が大学をめぐる矛盾と危機と結びついているという自覚に現われであると言えます。 大学改革に対抗する自由と民主主義の回復は大学人の切実な要求となっています。 6 震災・原発問題 いまなお約20万人の被災者 未曽有の東日本大震災から5年がたとうとしています。しかし、いまなお約20万人の被災者(福島県の被災者は103,500人)が避難生活を強いられ、先の見えない苦しみのもとに置かれています。 福島原発事故は、原発が抱える「異質の危険性」を明らかにしました。「収束」とは程遠い、事故の真っただ中にあります。放射能汚染水は増え続けています。安倍首相が言う「コントロールされている」状況とは程遠い事態です。 避難指示区域は約1,150平方キロメートル 香川県の面積の六割にあたいする広さです。(2014全国教研フォーラム)学校や友達を奪われ安心できる場を失った子どもたち、生業を奪われた住民たち、今後、いつになれば、元の生活に戻れるのか、見通しがつかない現状です。 許せない再稼働の強行 安倍内閣は、原発を「重要なベースロード電源」として将来にわたって維持・推進し、「再稼働を進める」とした「エネルギー基本計画」を閣議決定しました(2014年4月)。原子力規制委員会が定めた「新基準」をテコに川内原発(九州電力)の再稼働、20基以上の原発の再稼働をねらっています。 「新基準」は、福島原発事故の原因究明もないまま、再稼働を急ぐために「スケジュール先にありき」で決定したものです。重大事故(「炉心の著しい損傷」)への対策は部分的で、EUで義務づけているコアキャッチャ(溶融炉心を受け止めて冷やす装置)はなくてもよいとしています。活断層があっても表に出ていなければ、その真上に原発を建ててもよいなど、きわめてずさんなものです。火山対策も、火山学者が無理だと指摘しているのに、巨大噴火を予知できると強弁して、川内原発を「合格」させ再稼働を強行しました。電源が失われ燃料を冷やせなくなれば、一時間半で放射能が漏れだします。「万が一事故が起きた場合には、国は関係法令に基づき、責任をもって対処する」(「エネルギー基本計画」)としながら、避難対策は自治体任せです。アメリカでさえ住民の避難対策は稼働の前提とされています。 原発輸出の「トップセールス」に奔走する安倍首相 また安倍首相は、国内の再稼働で日本の原発の「安全性」を装いながら、原発メーカーやゼネコン、経団連と連れ立って、トルコや中東、東欧諸国、インドへ原発輸出の「トップセールス」に奔走しています。 再稼働を許さず「原発ゼロの日本」にすすむのかの大きな分かれ道に 福井地裁が2014年5月21日関西電力に対し大飯原発3・4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じる判決を言い渡しました。福島のような深刻な原発事故が再び起これば、周辺住民の人格権(個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益)が極めて広く侵害されるので、その具体的危険性が万が一にも存在する場合、原発の運転を差し止めるべきだというのが判決の主旨です。その上で3・4号機に係る安全技術及び設備が地震等に対して「確たる根拠のない楽観的な見通しのもとで初めて成り立ちうる脆弱なものであると認めざるを得ない」という専門技術的判断を下しました。 いま日本は、原発を再稼働させ原発依存社会を続けるのか、再稼働を許さず「原発ゼロの日本」にすすむのか、大きな分かれ道にあります。 「安全神話」ではなく、事実と科学に基づく私たちの原発・放射線教育の推進を 社会の在り方そのものを自分たちで考えていける学習が求められます。福島原発事故の実相を伝え、原発の危機性をきちんと伝える必要があります。現状は、新たな安全神話教育の推進、新副読本のバラマキ、教科書における部分的で不十分な記述、さらにエネルギー政策レベルの選択としか思わせない問題の矮小化などがあります。また安全神話への教師の取り込みのための講習会なども行われています。 各地の教職員の努力がある一方、個別の努力にとどまり、学校教育として積極的に行われていないのが現状です。教職員の力量をつけることが求められています。ぜひ「原発・放射能」のことを正しく教えるテキスト『原発・放射能をどう教えるか』(編集京都教育センター、発行京都教職員組合)や『原発事故!その時どこへ?』『原発再稼働?どうする放射性廃棄物―新規制基準の検証―』(「発行京都自治体問題研究所)を活用しましょう。そして、我々の学びと実践は、教育関係者にとどまらず、幅広くさまざまな人々と協力・共同することでより豊かに進み、広がっていくにちがいありません。 子どもの安全と学校給食 京都府内での「学校給食モニタリング調査」は、独自に検査機械を購入している、京都市、亀岡市、南丹市、長岡京市、京田辺市の五市が検査を続けているだけです。府の責任で安心して食べられる学校給食を保障すべきです。府や市町村に対して、「学校給食の食材は安全」の調査を要求していくことが大切です。 子どもの安全と安定ヨウ素剤 原発事故の際、子供への被害を少しでも減らすために、全地域で学校や保育園などにヨウ素剤の備蓄や事前配布の措置をもとめる必要があります。30㎞以遠の篠山市(兵庫県)はヨウ素剤の備蓄・事前配布を行うことを決めました。亀岡市も3月にヨウ素剤の備蓄を決めました。被ばくの影響を受けやすい子たちを預かる保育園や学校で30㎞以遠も含め、ヨウ素剤備蓄の指定場所にすることが必要です。保護者とも協力して自治体へ要求していきましょう。 7 障害児教育 一般校に在籍する支援の必要な子どもの教育の課題 2014年に「障害者権利条約」が発効し、「インクルーシブ教育」(どの子も排除しない教育、障害児者が健常者とともに学ぶ教育)と、それを保障するための「合理的配慮」の必要性が、学校現場にも少しずつ理解されつつあります。その一方で、学力テスト体制による競争主義が学校に持ち込まれたり、「規範意識」が強調され「ゼロトレランス」などの機械的な指導が広がったりする下で、学校生活に不適応を起こし、特別支援学級に入級する子どもが年々増えています。 特別支援学級在籍児童生徒数は、全国で174,881人と10年前の約2倍、通級指導教室の対象児童生徒数も、77,882人(いずれも2014年)と10年前の約2.3倍になっています。 その結果、学級の過大過密化、発達障害を含む障害の多様化、発達段階の差の拡大による、指導の困難な学級が激増しています。京都府内で特別支援学級に10名以上の子どもが在籍する学校は、2014年には小学校47学校、中学校26学校(7年前の3.65倍)にもなっています。子ども同士のトラブルや保護者の多様な要求に対応する困難さも増大しており、特別支援学級の本来のよさ(少人数の学級集団の中で、仲間との落ち着いた関係を築きながら、一人ひとりの子どもの発達段階に応じたきめ細かい指導ができる)を生かした実践、すべての子どもの発達保障が年々難しくなっています。 一障害種別8名まで一学級という国の基準を改めさせ、府独自での基準改善を求めること、自閉・情緒学級などの障害種別に応じた学級設置(京都府内でも市町村によって差が大きい)をいっそう進めることが必要です。 また、発達障害などによって支援の必要な子どものための、通級指導教室は、2007年以後徐々に全国の小中学校に設置されてきていますが、市町村によって設置状況に差があります。国の定数化や、府の独自施策によって、通級指導教室をすべての学校に早期に設置することが求められます。 特別支援学校の課題 中学校の特別支援学級在籍生徒が増加した結果、高等部を中心に特別支援学校の児童生徒数が急増しています。全国の特別支援学校で教室不足や校舎の老朽化が深刻な問題になっています。通常学校と同様の学校設置基準を、特別支援学校についても制定させ、校舎の増改築や支援学校の新増設を進めさせることが急務です。また、多くの教職員が常勤・非常勤の講師として、不安定な身分で働かされており、一般校に比べて非正規率が極端に高い状況が放置されていることも、大きな問題です。 京都府においても、南部地域での児童生徒数増、特別支援学校の過密・過大化が急速に進みました。その中で、八幡支援学校(2010年)・宇治支援学校(2011年)に続き、井手町への特別支援学校新設が決定したことは、これまでの保護者・教職員のとりくみの大きな成果です。5年後の開校までの、南山城支援学校の過密対策の実施を急がせる必要があります。 また近年、支援学校でも教育評価の観点として、計測できる「エビデンス」を求める傾向が強まってきており、指導のマニュアル化が進められています。高等部卒業後、民間企業へ就労することが最も望ましい進路であるように強調され、作業学習や事業所実習などに偏重した教育課程が押し付けられています。ベテラン教職員が大量に退職していく中で、一人ひとりの子どもの思いや願いを大切にした子ども理解、発達保障の観点に裏付けられた教育実践を引き継いでいくことが、大切な課題になっています。 高等学校での特別支援教育の課題 発達障害のある子どもたちは、小中学校の学習活動・集団活動に適応しにくく、学力不振や不登校などに陥っているケースが少なくありません。この子らの多くは、中学卒業時に希望の高校に進学することが難しく、高校入学後も学校生活に適応できず、不登校や中退を余儀なくされることが多くなっています。 文部科学省は2009年より、高等学校における特別支援教育の推進についてのワーキング・グループを立ち上げ、高校在籍生徒の約2%が支援を要すること、小中学校に比べて指導体制の整備が遅れていること、入試での配慮・教育課程の弾力的編制・キャリア教育・就労支援などが必要であることが報告されています。また昨年の11月には「高等学校における特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議」を発足させています。しかし、具体的な施策としては、校内委員会の設置や教員の研修の必要性を強調することが中心で、学校生活に適応できない生徒を支援するための教職員配置はほとんど進んでいません。 京都府内では、中学校特別支援学級卒業生のうち、20~50%(地域によって差が大きい)が、特別支援学校高等部でなく、高校(主に専門学科や定時制)に進学している、という実態があります。 しかし高校では障害に応じた特別なニーズに対応する基盤整備が整っていないため、単位取得や進級に大きな困難があり、個別の支援を学校として模索したり、福祉と連携した進路指導をおこなったりした例が出てきているものの、全府的にはまだまだ十分な配慮はおこなわれていません。 文科省は「高等学校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業」として研究指定をおこない、自立活動の取り出し指導や、通級指導学級のような形態での指導を模索しています。一方で、全国教研2015「教育のつどい」の教育フォーラム「高校の特別支援教育を考える」では、高校での特別支援学級の設置について議論が行われるなどしていますが、従来の高校教育の枠(入試制度や単位認定など)の中では捉えることの難しい、特別支援教育の方法論をそのまま導入することは、高校の教育現場に大きな混乱をまねく危険性もはらんでいます。 現在の高等学校における受験体制至上主義や、特別支援学校高等部での企業就労偏重政策では、本当に青年期の子どもたちの願いに答え、一人ひとりの成長や発達を実現する教育はできません。高校、特別支援学校、それぞれの実践に学びながら、それぞれの場での「合理的配慮」のあり方を検討し、生徒の願いを実現できる学校づくり、教育課程づくりを模索していくことが求められています。 8 地域と学校 文科省が統廃合推進の「手引」を発出 文部科学省は「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」を策定し、2015年1月27日、各教育委員会に通知しました。 そのポイントは、 *「学校規模の適正化」として、小学校で6学級以下、中学校で3学級以下の学校については、速やかに統廃合の適否を検討する必要があるとしたこと。 *「学校の適正配置」として、従来の通学距離について小学校で4㎞以内、中学校で6㎞以内という基準は引き続き妥当としつつ、スクールバスの導入などで交通手段が確保できる場合は「おおむね一時間以内」を目安とするという基準を加えたこと。 です。この「手引」を発出した背景には、学校統廃合をいっきに進めることにより、公教育費を削減したいという安倍内閣、特に財務省の思惑があります。 小学校で6学級以下という学校は、京都市内だけでも24校もあります。政府の地方切捨ての政策の下、財政難に窮する地方自治体では、この「手引」を利用して、さらなる学校統廃合を推進しようとすることが危惧されます。 一方、「手引」の中には、 「各市町村においては…学校が持つ多様な機能にも留意し、学校教育の直接の受益者である児童生徒の保護者や将来の受益者である就学前の子供の保護者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得るなど『地域とともにある学校づくり』の視点を踏まえた丁寧な議論を行うことが望まれます。」 「本手引の内容を機械的に適用することは適当ではなく、あくまでも各市町村における主体的な検討の参考資料として利用することが望まれます。」 などの記述もあり、「小規模校を存続させる場合の教育の充実」と章立てをして、「小規模校のメリット最大化策」「デメリット緩和策」などを例示しています。これらの記述は、「手引」の基準を機械的にあてはめた統廃合の推進にストップをかける取り組みに活用できる可能性があります。 「義務教育学校」(小中一貫校)を制度化する法改悪を強行 2015年6月17日の参議院本会議で、「義務教育学校」(小中一貫校)を制度化する、学校教育法の改悪案が可決され、2018年4月から施行されます。 これに先立つ、参議院の文教科学委員会の参考人質疑では、佐貫浩氏が、小中一貫校のメリットと言われるものには科学的根拠も具体的検証もない、と批判。藤田英典氏もいわゆる「中一ギャップ論」を批判し、「小中一貫校になれば、いじめ・不登校への対応でむしろ事態の悪化を招く」と指摘。自民党が招致した無藤隆氏も中学校生活への「ゆるやかな移行」が必要としながらも、小中一貫校が六・三制より優れているという明確な論拠を示すことができませんでした。 これらの批判を無視して、小中一貫校を制度化するねらいは、小中一貫校になれば優れた教育が受けられるかのような幻想を振りまき、一貫校設置により学校数を減らすこと、学校等配当に対する保護者・住民の抵抗感を薄めることにある、と言わざるを得ません。 また、佐貫氏が指摘しているとおり、同じ自治体の中で、小中一貫校と一貫校でない小中学校が並存することになり、公教育の平等性が大きく損なわれることになります。 京都府内の学校統廃合の状況 京丹後市では、統廃合によりこの5年余りで15校の小中学校なくなり、南丹市では、この4月に小学校六校がなくなり、来年4月にはさらに小学校4校が閉校になります。一方、福知山市では、地域ぐるみの運動が統廃合を一定押しとどめています。 京都市内では、東山区の13の小中学校が2つの小中一貫校に、南区でも3小学校・1中学が小中一貫一校に、それぞれ統合され、向島地域でも3小学校・1中学が小中一貫校に統合する計画が決定しています。今後、学年一学級程度の学校の統廃合がさらに加速させられる恐れがあります。 一方、京北地域のすべての小中学校(3小学校・1中学)を小中一貫の一校に統廃合する計画は、自治振興会の規約にもない会議での議決による「要望書」を、提出前に市教委が公表して既成事実化をはかるなど、市教委の強引な進め方が問題となり、保護者・住民のねばりづよい反対運動との綱引き状態が続いています。学校がなくなればこの地域で子育てができなくなる、という危機感が、多くの保護者や地域住民に共有されています。 WHO(世界保健機関)は「人間的教育のため学校規模100人以下」を勧めています。全校100人程度の学校の中では、一人ひとりの子どもにていねいに指導し学力を高められること、すべての子どもが責任ある役割を果たし学校の主人公として成長できることなどを、統廃合された東山区の小学校で勤務した教員は語っています。 ・学校統廃合のねらいは、教育条件を切り捨て、教育予算の削減にあること ・「切磋琢磨がない」などの小規模校への偏見を克服し、小規模校こそ一人ひとりの子どもの学力を高め、豊かな人格を育む場であること。 ・学校がなくなることにより、山間部地域では子育てが困難になり人口減少・地域の衰退を加速させること、都市部でも子育てに必要な地域のコミュニティの拠点が失われること。 などを、再度語り広げ、地域の学校を守ることが今求められています。 |
||
|