| 事務局 | 2013年度年報もくじ |
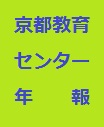 |
第6分科会 民主カウンセリング・ワークショップ 〜学校・職場・地域・家庭でよりよい人間関係をどう築いていくのか〜 芦田 幸子(民主カウンセリング研究会) |
|
3.11東日本大震災から早や3年が経とうとしていますが復興は遅々として進まず、福島第一原発事故はより深刻な事態となっています。 子ども達はいじめや過度の競争社会にさらされ傷つきを深くしています。多くの若者は不安定な非正規雇用の中で物のように扱われ、使い捨てられるという過酷な労働環境に苦しめられています。そして、消費税アップ、生活保護・年金の削減、特定秘密保護法の強行、首相の靖国神社参拝、米軍基地の辺野古移設などなど生活や命を脅かされる情勢が次々に押し寄せて、ますます人々の暮らし・命が脅かされています。 こんな誰もが安心して生きていく事が厳しくなってきている今だからこそ、人が人として尊重される社会を創っていきたい、お互いが尊重しあう人間関係を築いていきたいと私達は今回もエンカウンター・グループを開催しました。 今回も学校・地域・家庭で生活していく中で生まれる喜び・悲しみ・怒りや不安を言葉にして話してみる、聴いてもらって自分で問い直してみる、他の人の話しを共感的に聴いて経験や思いを拡げ自分の生きていく力にする中で、日常とは少し違った心地よい、次の日からの糧や心の支えになるようなエンカウンター・グループになったと思います。 全体では男性は5名、女性7名で12名の参加でした。教師(元・現)9名、障害児保育者1名、保護者2名という構成でした。午前中は簡単なオリエンテーションと自己紹介をしてひとりひとりが今ここにいる自分の気持ちを出し、午後からはいろいろな思いを出していきました。 ひとりひとりが主人公であり、全体の流れは参加者の自由な動きで決まります。例年に比べ情勢や教育の話が主になることが多かったのですが、それも今の世の中の動きを反映していて“今この話をしたい、しなくてはいけない、聴きたい”という参加者の思いが強かったからこそであると思います。またその中で “そんな時代だからこそ、話しあえ、聴きあえる人間関係が大切”“人々と繋がっていきたい”“人間ってすてたものではない”いというカウンセリングの原点に戻るような流れになりました。そういう意味でもカウンセリングは時代や情勢とかけ離れて存在しえないと改めて痛感できました。 ◎あいさつ 庶民は毎日、いろいろな喜怒哀楽を感じながら生活しています。ひとりで生きていくことは出来ず、誰かが一緒に感じてくれる、話を聞いてくれる、隣で佇んでくれるだけでも精神的に樂になります。今日はそんな気持ちが安らぐ経験を共にしていきたいと思います。 “優(やさしい)”という字は憂いの人に佇んで立つと書きます。今日は優しい経験を体験したいと思います。 ◎話しあい、聴きあいから(略) ○教育情勢や社会に動きなどについて ・ 高校の制度変わって大変なことになっている。地域の高校に行けない状況ある。 ・ 高校制度は完全な輪切りに。○○高は×点以上、○○高は×点以下とだけで高校決まる。交通の便の悪い所には行きたくない傾向あり、北通学圏に希望が殺到して、その地域の子は遠い高校に行かざるを得ない状況になった。点数さえとれば、自分の希望で好きな所に行けると思ったら大まちがい。高校3原則なくなって30年、1類2類の制度も崩壊して、また制度改悪一層ひどくなってきている。 ・ 不登校の子が定時制高校で救われてきた歴史あるがその定時制高校がなくなってきている。 ・ 政治が教育に関与している。教育の解らない人が政治している。 ・ 特別支援学校も就労が目的になり、教育の場とはいえなくなっている。子どもは居場所や求められている、頼られているという実感が必要なのに、学校がそんな場所ではなくなってきている。 ・ 生まれた時から格差社会にいる。貧困の問題大きく平等なスタートラインに立てない。どんどん格差つけられていく社会で子どもは人間らしく生きていく機会を与えられない。 ・ 自分の家の状況よくわかっていて「ぼくあほやし、大学行かへん」という子どもがいる ・ 小学生の子が「先生が一生懸命教えてくれるけど、わからへんし時間ばかりたってまわりに迷惑やし、わるいなあと思う」と話しているのを聞いてせつなくなった。 ・ 「ぼくアホキャラでやっていくから心配せんでいい」という子もいる。今の子どもは気を使い人の顔色を見て過ごしている、子ども社会を生きていくのは大変。 ・ 教育はITではなく、人と人との繋がり大切。生徒と教師、先生同士、親や地域の人との繋がりで成り立たないといけない。 ・ 学校現場もチャップリンの映画みたいに、機械に人間が振り回されている。人との対話が無くなり、機械の操作ができない人は時間ばかりかかる。ひとりひとりの子どもについて対面で話しあう機会なくなってきている。 ・ うちの学校では職員室で教員9名の話しあいを毎日している。子どもの話しだけでなく情勢の話や秘密保護法はおかしいという話もできる。それは、今までの伝統があるからで誰も止められない。こんな話し合いができるのは京都の教育の財産だと思う。 ・ 学校に格差できること単純に喜んでいる人もいる。A高校の同窓会で「今や府立高校のトップになり、出身校だと話す時に誇らしく思う」と副校長にあいさつしている人いた。 ・ 教育委員会から「どうしたら倫理を守れるか」という服務規定の研修会を開催するように通達があったようだ。“ならぬことはならぬ”以外することはない。教師を馬鹿にしている。そんな時間があったら子どもと接していたい。 ・ 教師の資格が軽く見られている。再教育の制度があるのは教員だけで医師、看護師、保育士など他の資格ではない。教師は教員免許講習を受けて再教育必要なのに、校長は民間校長制度で民間から登用。現場を知らない校長がうまくいくはずがない。 ・ 教育の影響力が政治にとって大きいことをわかっているから、教育の世界に関与しようとしているのだと思う。だからこそ教育と政治とは分離しなければならない。教育が利用されたり乗っ取られたりしてはいけない。利用されると戦争などの戦いがおこることは歴史的に証明されている。 ・ 教育など人間を相手にしている仕事は情熱と経験と人と合意することは必要。人格が大切。 ・ 新自由主義の行きつくまで所にきた。価値を生まない人はだめという社会。老人や障害のある人、働けない人は社会のお荷物という考え方。私達はもっと繋がって怒らないといけない。 ○こんな世の中で、私達は何をしたらいいのだろう、人の繋がりって何だろう ・ 日本の国民性は非常に健全であると思う。国民調査でも平和憲法を守ってほしい人が6割いて良識ある。若い人の感性はすばらしいが危ない所もある。高齢者の知性、論理性、こう生きるべきだという姿勢を、今社会に提供することが必要なのではないか。 ・ 戦前の教育勅語、治安維持法から太平洋戦争につながった道と、現在の特定秘密保護法成立、憲法改悪の社会状況とは全く同じ。そのことを知っている者が声をあげないといけない。瀬戸内寂聴さんが「私が長生きしてきた意味が今わかりました。“戦争はいけない”と伝えるためだったのです」と話されていた。全くその通りだと思う。 ・ 戦前、戦中を生き抜いてきた人は感覚でわかることある。戦争が怖いことが骨のずいまでしみついている。 ・ 若者の中には朝鮮人を排除する発言をしたり憲法を変えてもいいという者もいる。慰安婦問題をネットで検索するとそんな事実はなかったという意見が沢山出てくる。原発も反対している学者と推進している学者の割合は3:7で、明らかに推進の意見の発信の方が多い。うまく調べないと情勢に流される。新聞やテレビ、週刊誌などマスコミの問題も大きい。 ・ 自分の情報もダダ漏れ。ネットで繋がって殺人事件に繋がることある。ドコモの紙面での明細がなくなって家族がどれだけ携帯を利用しているかわからなくなった。子どもは友達と常に繋がってなくては不安、いつも群れていないと不安な様子。人間関係が希薄になりいつも不安な様子。 ・ ネットで繋がっている人は案外狭い情報でしかない。自分の好きな事しか知らない。それでは人の温かさや優しさ伝わらない。 ・ 国のトップが平気で嘘をつく。モラルのない国民が育って当然。民意が“何をしてもあり”になっても当然のような気がする。私達が人の多様性が認めること、お互いを尊重することを示していかなければいけない。 ・ 特定秘密保護法は大勢の国民が反対した。国会を通った後も反対の運動が続いている。もっともっと世論を高めていきたい。全国の弁護士会がまとまって反対した。それは今までなかったこと。マスコミも反対している。にもかかわらず安倍政権が通したのは日米安保条約や軍事産業が後押しをしているため。3年後の選挙で賛成した人は落とす、反対した人を通すという運動をしていかないといけない。 ・ 敬老パスの有料化・値上げ 年金の削減などお年寄りは死んでしまえといわんばかりの社会がある。その人達の働きがあるからこそ、今の社会の繁栄があることを大きな声で言わないといけない。 ・ 社会に貢献した世代が尊厳されないことおかしい。ヨーロッパでは老人が一人亡くなることは図書館が一つなくなることと同じだと言われている。日本にはそんな意識がない。 ・ 社会の年功序列にも意味があった。積み重ねがあるから若い人を助けることできる。 ・ 齢をとっても生きていることに意味がある。しゃべるために、伝えるために生きている。行き様を伝えていきたい。聴く人が学ぶ事多い。 ・ しかし、聴いてくれる人いないとしゃべらない。 ・ 老人で家族と一緒にくらしていても、孤独な人いる。家族の中の孤独は一人暮らしの孤独よりつらい。そうなるまでの関係が悪かったのだと思うけど、 ・ 自分の存在が認められない、無視されるほどつらいことはない。日常的な家族関係が大切。いろいろな話ができる関係、お互いを尊重し合える関係を築いていくこと必要。 ・ いじめも同じ。誰からも声をかけられないことほどつらいことはない。どんな子どもにも、まずは大人が声をかけることが必要。 ・ この1年間でいろいろな病気になった。病院通いでゆったりとした時間が全くない。世話をしている夫は「幸せやなあ」とは言わない人。でもずっと一緒にいていろいろな話をしている。 ・ 家庭、学校、職場など身近なところで話しあう聴きあう人間関係を作っていきたい。身近なところがむつかしいのではあるけれど。日頃から心にとめていかないとなかなかできない。 ・ 社会が厳しくなって、心の余裕も時間の余裕もなくなってきている。そのことから人間関係がよけいギスギスして・・・・政治の思うつぼになっている。私達の手で人間関係の修復しなければいけない。 ・ 心地良い人間関係、話し合い聴きあいを経験したものはそのことを知っている、忘れない。その経験を伝え、広めていきたい。 ・ このような場所に元気に出てこられるだけで幸せだと思う。生の声を聞いて話をする。話をしなくても顔をみるだけでも幸せな気持ちになる。 ・ 社会の情勢の中ではこれからな社会はどうなるのだろうと思うことが多いが、こうして話し合うと“人間も捨てたもんじゃない”と思える。あきらめずに人と繋がっていこう。人間の英知を信じようと思える。 ・ 今こそ、戦争を知っている者の出番。今、声をあげないでどうする!と思った。 ◎感想文から(略) |
||
|