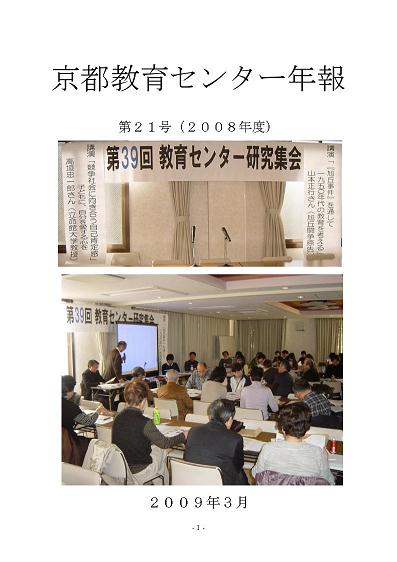
講演〈第39回研究集会 プレ集会〉
『旭丘事件』を通して1950年代の教育を考える(大要)
講師 山本 正行 さん
(「旭丘闘争」原告、前京都退職教職員の会会長)
日時 2009年1月24日(土)午前10時~12時
会場 京都教育文化センター302号室
| 本記録は2009年1月24日に行われた「京都教育センター第39会研究集会 プレ集会」で行われた山本正行さんの講演をセンター事務局の責任で修正編修したものです。見出し等は編集者がつけました。 |
1.はじめに
旭丘事件が起こった時は、私はまだ25歳の青年教師でありましたが、今や、今日は80歳で現れましたので、若いときの実践を、どれだけみなさんの心に届くように話が出来るかどうか、あらかじめ心配になったので、そういう手紙を差し上げた方もおられますが、どうぞ一つよろしくお願い致します。お手元に資料集「旭丘に光あれ」という青の表紙のものが入っていると思いますが、それから寺島さんの赤い色の紙で手紙があると思います。大平先生をはじめ、事務局の方に非常にご迷惑をおかけしていますが、資料が乱雑になっていますけれども、責任は私の方にありますので、一つよろしくお願いしたいと思います。このセンターの報告集の方に主文がありまして、あと資料が別にあるという事です。
「はじめに」ということで、「今日の子どもたちの状態」という欄をつくりましたけれども、なにしろ年もとったので、あまり余分なことをしゃべると持ち時間が切れてしまうと思いますので、さっそく2の「旭丘中学事件とは」というところに入りたいと思います。
2.旭丘中学校事件とは--道徳、学力、政治的「偏向」
世間では、1954(昭和29)年の3月に私たちが、私、山本や寺島、北小路という3人の先生が「異動勧告」を受けまして、それを拒否し、5月5日の子どもの日に首を切られました。その後市教委の手で5月11日に、「分裂授業」というのが行われまして、労使双方合意が成立し、6月始めに統一して再開する、このごく狭い時期のことを「旭丘事件」と言っております。けれども、実際は、その前の年から、ずっと前から起こってきているということなので、どうしても事件の話の前に、そんな「偏向教育をしている」というのは、全国で24例あげられましたが、そのトップが山口県の日記問題、それから旭丘と、小学校で大将軍小学校、京都に二つの学校が「偏向している」というふうにあがっています。
当時の吉田茂首相、国葬になった人ですが、その内閣の提案で「教育の中立性に関する法案」と「教員の政治活動禁止に関する法案」、「政禁法」と言いましたが、この二つの法案を政府が提出するにあたりまして、「こういう法律をなぜ出さねばならないか」ということで、山口の日記や、京都の旭丘のような「偏向した、赤い教育がある」ということで、問題がクローズアップされたわけであります。その主な理由は①「生徒の行儀が悪い」②「教科指導が充実していない」③「偏った思想、偏った政治教育をしている」と、いつでも彼ら権力が問題にするのは、道徳の問題、学力の問題、政治的に偏向しているかどうかという、こういう3点を中心に、いろいろ問題にすることが多いと思いますが、私たちの側にとっても、大事な柱であります。
事件はそのとき、といってももうこの話は55年ぶりということになりますので、若い先生方は、まだ生まれておられなかったので、「えーっ」ということになるかも知れませんが、私たち3人の教師が、懲戒免職という処分になり、50人近い全部の先生が配転になりまして、旭丘中学は「落城」するわけです。そして、事件の舞台は「懲戒免職取り消し」裁判に変わりました。裁判で1審、2審と、私たちが勝利するわけです。というのは、その当時の市教育委員会は、異動勧告などをするときには、5月5日子どもの日に首を切るわけですが、そういう時にだけ現れて、あとは隠れてしまって、「雲隠れ委員」というあだ名がついたように、教育委員は逃げ隠れして、私たちとは会わないんです。これが裁判に反映しまして、京都裁判所は「偏向教育という疑いをもたれているが、その証拠はない」「直前に、非公開で決めたのだから、」・・・・当時の教育委員会は公選制でもありましたので、皆に告知しなければいけないのに、「告知していないから、この決定は無効である」となったのです。その次は大阪に行きまして、大阪高裁は「教育委員会法では、三日前に告知をしなければならないのに、その日に告知をしている」「問題外である」ということで、これも勝つわけです。
ところが、最高裁に行ったら「あれだけ世の中を騒がせた事件なのに、手続きというのは単なる瑕疵にすぎない」「いったいどういうことでこうなったのか調べよ」ということで、差し戻しになりました。そして、差し戻しになってから、我々が破れるということになったわけです。いわゆる最高裁というのは、「憲法の番人」と言われていますけれども、実際上は、最高裁判所の裁判官は内閣総理大臣が任命するということになっているわけですから、政治権力のいいなりになったというのが話の大筋です。
3.旭丘中学事件とは--たたかいの経過
そこで、「旭丘事件とは」ということになるわけですが、当然私たちの側は、憲法・教育基本法にもとづく教育をしていたわけです。だから、それを正面に掲げて闘うわけですが、当時京教組が中心になりまして、旭丘の真相を訴えるパンフなどを作りました。学者・研究者の方がたのご協力もあったわけなのですが、その中心は①「生徒の気持ちになって教育を考える」②「お金のかからない学校」③「明るくて民主的な職員室」「先生と生徒・父母が手をつないでやる教育」・・・そして、その総まとめがみんなでつくった「綱領」であるということが、パンフや、「京教組40年史」にも書いてありまして、その40年史の中の旭丘に関わりのある所は、みなさんにも資料をお配りをしています。詳しくはまたそれを見て頂ければと思います。また、京都教育センターが1960年に発足してから、「季刊 教育運動」というのを出すようになりまして、その1~3号に「旭丘、何を受け継ぐか」ということを書いております。また、53年から始まったということがわかるような年表もあります。その他の資料も載せております。
当時の労働組合「京都総評」も満場一致で「支援する」という決定で、来てくれたのは良かったのですが、資料にありますように「赤旗」、労働組合の旗を持ってきたので、校舎に赤旗が「林立」したわけですね。労働組合が、「支持することは労働組合のシンボルである赤旗を持っていくことだ」と言って、赤旗を建ててきて、旭丘の教育を支持している父母もいろいろな方がいますから、おどろいたこともありました。ただでさえマスコミが「赤い学校」と書き立てている中でしたので、「これでは説明困難」ということで、京教組が支援団体への要請を行ってくれました。そうして赤旗が撤去され支援団体名にしました。すると、今度は、マスコミは「赤旗をおろして白旗を立てた」と書きたてました。日本の伝統では、白旗を立てるということは「降参した」ということですね。マスコミの役割はひどいものでした。
そういうことで、私たちに対して転任の発令があっても、市教委は「雲隠れ」して交渉に応じないから、学校の先生方は私たちを入れて授業をすすめているわけですね。そのあと、教育委員会が、「教育委員会立の」学校を急造して、生徒を奪い合いするようなことが起こりました。そのときの写真も資料にあります。ごらんのパンフの左側にマイクを握っているのが、寺島洋之助先生で、その横にぐっと若いのが私です。こういうことで、トラックの上から、真相を訴え、みんな学校に来ようということで呼びかけました。事実、教育委員会が生徒を奪うまでは、それまで生徒はみんな、毎日学校に来ていましたし、平穏に授業も行われ、毎日公開授業をしていました。写真にあるように学校を取り巻いて生徒を奪おうとしている連中の中には、暴力団「○○組」とか、「赤化防止団」とか、右翼の人がたくさんおりまして、私たちを応援するお父さん方、お母さん方も来られて生徒を守っているという、そういう激しい闘争になりました。全面的なアカ攻撃に負けず、登校した子ども、父母、支援者の方の苦労は大変でした
旭丘中学校の教育--真相
4.「戦争を教えた先生」「戦争を教えられた生徒」で成り立っていた学校
それでは、旭丘中学校はいったいどんな教育をしていたのか、どうしてそんな闘争になったのかということが一番大きな、また素直な疑問だと思います。
レジメの右に校歌がありますが、その裏側に「民主的な学校づくり」の三本柱を書いています。
一つは、旭丘の教師は、当時は、全国のどこの学校の教師もそうであったように「かつて戦争を教えた先生」、また「戦争を教えられた生徒」、こういうもので成り立っていました。年配の方には、こんなことをいちいち言わなくてもいいのですが、若い方もおられますので言いますと、資料に戦前の教科書が載っていますが、私の生まれは1928年生まれですが、小学校に入りましたら、国語の教科書は「サイタ、サイタ、サクラガサイタ」「コイコイ、シロコイ」「ススメ、ススメ、ヘイタイススメ」「オヒサマアカイ、アサヒガアカイ」「ヒノマルノハタ、バンザイ、バンザイ」と教えられてきました。やさしい女の先生が私の担任でしたけれども、「みなさん、日本の花は何でしょう?」「ハイ!桜の花です!」「そうです、桜の花は、パッと咲いてパッと散る。みんなも大きくなったら、天皇陛下のために、お国のために、パッと咲いて、パッと散る、・・・」(笑い)こいうことが、ちゃんと教師用テキストに書いてありまして、みんな一斉に教えたものです。
当時の私は気の弱い少年でしたけれども、私の名前は正行と言いますが、同じ正がつく人で有名な楠木正成という人がいますね。天皇陛下のために闘う忠臣、楠木正成の、その子どもが正行と言うんです。ご存じのように正行というのは二十歳で死んでいるんです。だから、私は「僕は二十歳になったら、兵隊に行って死なんならんな」「お国のために死なんならんな」と、思い込んでいました。私は比較的成績が良かったものですから、学芸会で先生が、「湊川の親子の別れの芝居」をするというのですが、そのとき「お前、正行をやれ」と言われて、稽古をしたのですが、なかなかセリフを覚えませんでしたので、女の子に尻をギュッとつねられたのを、今でも覚えています。まあ、なんとかそれで終わりましたけれど、みんな、なんらかの形で「死なんならんな」と思わされてきたわけです。その当時は、共産党のように戦争に反対する人がいるなどということは、思いもよりませんでした。
軍国主義教育の「教育の力」ということで、澤地久枝さんが書いておられます。「僕は軍人大好きよ、今に大きくなったら勲章下げて剣さげて、おうまにのってハイドウドウ」これは、子どもの歌ですが、こういう歌を歌うようになった。その中で、18歳になった中島正三という人が、特攻隊で飛行機に乗って、沖縄で戦死するんですが、その方の遺書を紹介しておられますね。途中を飛ばします、「中島正三は18歳の遺書に、まず『必勝』と書き、『父上、母上、長らくお世話になりました。私は桜の花と共に散っていきます。世の中に思い残すことはありません。さようなら』と書き残したそうです。ごく普通に考えて、『この世に思い残すことのない18歳』などというのがあるのでしょうか。すべてはこれから始まるところです。恋にさえ出会うこともなく、人生のよいことも辛いことも知らず、人生の入り口に立ったところで、死んでいかねばならなかった少年の一人が中島正三です」と、澤地久枝さんは告発されています。
こういう教育の中で私も軍国少年になりまして、あの戦争を迎えたんです。敗戦は、さきほどご紹介がありますたように、工業関係の学校(今の「京都工芸繊維大学」)でもありましたが、化学工業科と言っていまして、「学徒動員」で舞鶴の火薬庫に「日本の火薬の研究に行け」ということで、行きましたら、もう火薬はほとんど無くて、空箱が積んであるという状態になりまして、「火薬もないのに、これで日本は勝つんだろうか」と思いました。思いましたというより、ふっとつぶやいたんですね。それを軍人が聞きとがめました。「山本!きさまはどう思うのか!」「はい、日本は勝ちます!」、こう言って、私は今日あるのです。あのとき「日本は、もう負けそうです」などと言えば、軍刀がどこへ飛んだかわからないような、そういう暮らしをしておりました。
これは私の場合にしかすぎませんが、寺島先生は飛行機の整備士みたいな兵隊さんであったし、寺前さん、寺前巌というのちに衆議院議員になった人がいますが、かれも同僚で、一人乗りの魚雷で、一度乗ると船にぶつかる以外に、帰り道がなにもないというものに乗って、「特攻隊」ですね、いよいよ出撃、という時に8月15日(敗戦)が来たんです。そういう同僚もたくさんおりました。
5.旭丘中学校はいったいどんな教育をしていたのか
8月15日の戦争が終わったという時の放送を聞いていても、私などは、戦争が終わったとは思いませんでした。悲しい声が聞こえてきて、ラジオがピーピー言っていて、はっきりとは聞こえなかった。何と、連れて行った先生が、「諸君、いよいよ本土決戦の時が来た。もっとがんばれ、というお話や」と言って、「そうか」と思って寮へ帰りました。ところが、日本が負けたということで、「あれは負けたということやで」と言った友だちを、みんなで袋だたきをした覚えがあります。それほど、徹底した精神状態でおりました。そういう教育をされました。
それを教えた先生、それは全国どこにもありましたし、旭丘にもありました。そして、私たちの中にも、もう二度と、ああいう戦争を教えるということは避けたいという気持ちは、みんなの中にありました。特に旭丘中学は、小高い丘の上にできまして、東山三十六峰がきれいに見える学校でした。新制中学で、できたてでしたから、学校の名前、旭丘という名前も、校章も、校歌も、みんなで作ろうということだったんですね。校名の「旭丘」、何度言っても、「旭」と「丘」の間に「ガ」を入れられる。京教組のパンフでも、「ガはいらんのや」と言っても、入れてしまう。そりゃそうやね。寺島くんとも話していて、だいたい「旭」という字、これは当用漢字に入っていない。「ガ」がないのに、「あさひがおか」と読め、と。校長さんは国漢の先生で、「それは無理や」と。「無理でもきいてくれ」と。丘の上、当時「鐘の鳴る丘」というのがラジオでもありましたが、丘の上で「カーン、カーン」と鐘が鳴って、ロマンチックな、そういう学校にしたいんだと、「旭丘、どうしてもこの名前にしてほしい」と、言ったので、みんなは「名前ぐらいは校長さんに譲ろうやないか」ということに--。校章は、美術の先生の案が当選しました。校歌は寺島洋之助の作品が当選したんです。校歌の言葉も、曲もそれぞれ別個に先生方だけではなしに、生徒や親も、みんな含めて公募し、審査委員会も含めて作った歌です。あらゆる時に、運動会や、生徒大会や、卒業式の時にこの歌を歌いましたので、資料にデカデカと載っておりますのは、マスコミによって、この校歌が「インターナショナル(の歌)」ということになったりしていたんですね。新聞は「インターでマリつき、赤旗で授業」と、マスコミが平気で書いたんです。そういうことで「赤い学校」ということになったんですけれども。これが旭丘のありのままの姿です。
6.「お互いの自由を尊重しよう」が民主的な学校づくり
私たちは、そういう戦争の反省も、教えた人、教えられた人、双方でしました。校長さんの「お互いを名前『○○さん』と呼び合おう、『センセイ』はダメ、まして『小使いさん』はいけない」という提案も、みんな賛成しました。私と同い年で関矢くんという人がいますが、「私らは、教え子を戦場に送ったんとちがう、送られたんや」とか、ワイワイ言いながらも、学校づくりをやりました。校長さんは、そういうことですが、教頭や教務主任は皆公選制にして、当時の教頭さんに北小路さん、中学校の組合長の北小路さん、そしてわずか30歳ほどの寺島洋之助さんが、一番、学校の改革にいろいろ言うので「あいつにやらそう」といことで教務主任になりました。私は生徒会顧問になっていましたけれども、そいういふうに、みんななりたいものになる、言いたいことを言う。なかなか意見がまとまない場合は「丘をおりよう」、つまり「寝かそう」ということで「寝かして」、次の会議の議題にするということにしました。そういうことを繰り返してやりました。そうした中から「お互いの自由を尊重しよう」ということでやっていくのが、民主的な学校ということではないか、というのが私たちの言い分でありました。この校歌は時間があれば、のちほどみなさんにご披露したいと思います。
職員会議もそれまでは教頭さんが議長をしていましたが、輪番制にしまして、なごやかに行ってきました。今日の学校の先生から見れば「へえー!」ということになるかと思います。そういう経過の中で、一番頼みにしたのは生徒で、私は生徒会顧問として、今から思うと恥ずかしいようなことも多いんですけれども、いろいろな活動を生徒の気持ちになって徹底してやってきたと思います。私の思いは①「命、平和、大切」②「だまされない」③「手をつなぐ」でした。
まず運動会は、今日のオリンピック様式を採用しまして、生徒会主催で校長開会挨拶、生徒会長挨拶という形で行い、表彰は生徒会長というのが当たり前でありました。また仮装行列もやりました。女の体育の先生がどこかで習ってきたのか、「緑の山河」を全校生徒と共に歌い、おどり、当時の全校生徒は1600余名で運動場が埋まってしまうほどいて、みんなで「校歌」を歌い、最後はフォークダンスを先生も生徒もいっしょになって全員でやりました。親の中からも、飛び入りで何人もいっしょに入ってきて、フォークダンスをして、まるでオリンピックが終わった時のような雰囲気になりました。我々はとても喜びましたけれども、地域の来賓席にいる一部の人には「乱れた学校」と見られたようです。
ライブラリーも、図書委員会をつくりまして、生徒の意見で図書を買う。担当先生の指導もあり、もちろん委員会できちんと審査もするんですけれども、「そんなんしたら図書室はマンガばかりでいっぱいになるんと違うか」という校長先生のご心配をも乗り越えて、やはりすばらしい図書館になりまして、毎日子どもたちがたくさん集まるという、とても活気のある図書館になっていったと思います。
そういうことを一つ一つていねいに積み上げていったのが、旭丘中学校です。その中で、だんだん子どもたちがのびのびと、元気になりました。
7.お金のかからない学校にしよう
当時はまた、貧困の問題も非常に厳しい時代でしたので、「お金を集めない」「お金のかからない学校にしよう」というのは、「生活保護」での免除など非常に徹底してやったと思います。
そういう中で、ある日、学校帰りの子どもが、「自転車にハンドルがなかったら、どうなるやろう」と、話をしていましたら、ちょうど向かい側に警察官が来まして、「お前ら、わしを見て笑ったやろう。わしらをポリ、ポリ、と言って学校で習らっているんやろ」と言われて、派出所に連れ込まれて、さんざん絞られました。ところが、絞られて、それで終わりやなしに、その生徒らがすぐに生徒会新聞に投書したんやね。「私たちはこんな目に遭った。これはおかしい」と。何でも自由な意見を尊重する旭丘中学も、「警察に抗議に行く」ということになって、「これはちょっとなあ」ということになって、ためらう人も多かったんですけれども、非常に筋を通す男もおりまして、「もうちょっと、ソフトにできひんか」などと言いつつも、抗議に行き、最終的には曖昧な姿ではあったけれども、上鴨署の署長さんが学校へ来て、「指導に誤りがあった」。どこに誤りがあったとは言いませんけれども、謝りにきました。それが1953年でした。その年にメーデーがありまして、5月1日の前、4月29日の天皇誕生日に、メーデーの準備のために一部の先生たちが学校に集まってきたとき、学校の校舎の片隅から原因不明の火災が起こりまして、あっという間に、活動家の先生が警察にひっぱって行かれました。そして、いろいろと尋問を受けました。私は偶然、卒業生が遊びに来ていたので、夕方送りに行ったのです。「火事や」「どこやろ」と言っていましたら、自分の学校が燃えているんです。おどろいてすぐにかけつけました。みんな真剣に後片づけをしました。
そして、メーデーが終わった翌日ぐらいに、近くの小学校をお借りして、「旭丘中学校の火災問題について」というオープンにした地域の集会を持ちました。生徒や卒業生、親はもちろん、地域の民主団体(「洛北民主協議会」など)もできていてくれていて、集会は、従来通りの「寄付集め」から脱却して、大もめにもめましたが、最終的には「寄付は取らない」「運動で解決しようじゃないか」ということでまとまりました。
そんな中、生徒会新聞に投書がありました。読み上げます。
「わからない 父とおじさん」 わからない いつもくるメガネの おじさん きのうも父とお酒をのんで おそくまで 話していた となりのへやで 社会の勉強をしていた私 「旭丘」 「旭丘」という おじさんの声 「ワッハッハ」と笑う父の声 私は思わず耳をすました ぬすみ聞きは悪いことだ そう思ったけれど 何かしら気になる 「だいたい若い教員がいかん あいつらが生徒をおだて 卒業生をおだてているんですよ こんどの事もあんな風に メチャメチャにして 一体父兄有力者を無視して 何が出来ますか○○さんは来年市会議員に出るので 出来る丈みなさんと協調しようと、云いたい事も控えて いたが 今度こそガマンならんと云っているし ××さんはガラス1300枚のキフを取り下げるそう だし 結局困るのは学校じゃありませんか 何しろ「キフを受け取るな・・・」という教員がいるんで すからね それに父兄の中にキフを出すな と云って るのがいるそうでケシカランことです。 「我々の子供の学校だから、我々の真心のこもった金を出す のをどうして変に考えるのでせう」 そういう父 しかし私はおぼえている あの火事の日 もえ上がるほのほを二階から見ながら 「ああ 又キフか・・・・」といやそうに云った父を また小学校の給食場のキフを 「よそが出すならしょうがない」と いいながら出していた父を 私は覚えている 一体どちらが 本当の父なのか わからない おとなは皆 あんなのなのだろうか 私にはわからない・・・・・・・ (原文) |
こういう詩が旭丘の新聞のボックスに入ったんです。しかし、「人の迷惑になる」ということで、没にされました。それに対して、生徒は「諸君はどう思いますが、迷惑をこうむる者があると思いますか」と、没にされた文をのせて「これが没にされた。どうだろうか」と、なかなか知恵がありますね。そして実際に新聞には載ったんですね。これに対して「当然、新聞には載せるべきだ」という声がでてきて、みんなの目にふれるのです。
8.旭丘の平和教育
こういうふうにして、旭丘中学の火事問題は、親から一銭も金を取らない、みんなの署名運動でいくというふうになって、すでに旭丘は、生徒が伸び伸びとするようになっておりましたから、運動する委員会も、生徒の代表、卒業生の代表、PTAの代表、地域の代表、先生の代表、この5つの分野から実行委員会が開かれ、毎回相談をして、そしていろいろやるようになったわけです。こうしたことが、一部の有力者たちには非常に気に入らなかったわけです。警察にも抗議に行くし、寄付を断って教育委員会に要請に行くと。こういうことがなければ、もっと外の学校でも「私の学校はこうしている」「こんな実践をしている」というような学校はたくさんあったのではないかと思うのですが。
修学旅行でも、先生は別室に行って、ちょっとごちそうがでて、一杯飲んで、というような学校も多かったのですが、旭丘はいっさいそういうものはしない。生徒といっしょに同じものを食べて、お酒はいっさい飲まない。そして京都へ帰ってから、「ご苦労さん 乾杯」というようなことをやりましたし、「ヒロシマ」や「ナガサキ」、そういうところへ行くとか、平和教育もやっておりました。また、旭丘では映画鑑賞も大事にしまして、「京教組40年史」の資料にも書いていますが、「平和教育」として、「原爆の子」「ひめゆりの塔」「雲流るるの果て」「蟹工船」「禁じられた遊び」「ヒロシマ」などを見せました。「蟹工船」というのは最近注目をあびていますが、私たちの中でも「これは無理なんじゃないか」という意見もありましたが、しかし当時は中学卒業の3分の2は就職するという時代でもありました。3分の1が進学という状態です。たしかにたいへんだとは思いますが、働く以上は、これはやはり見せたほうが良いということで見せました。これらの取り組みが「偏向」とされたのです。私たちは生活綴り方で有名な「山びこ学校」も見せましたが、映画だけでなく、本も好評で10数冊も購入して図書室に置きました。しかしこれは彼等の偏向教育事例には書かれませんでした。
9.子どもたちの受験勉強や学力底上げ
このほか、寺島先生など、受験勉強に正月から取り組みましたし、子どもたちの学力底上げにも熱心に取り組んできました。3年になると「能力別編成」に英語科だけ踏み込むという行き過ぎもありましたが、先生方の相互批判、ことに生徒の差別への抗議で止めになりました。そういう中で寺島先生は1960年の日光でありました第一回教育研究大会に参加し、もともとそう組合に熱心なというよりも教育実践に熱心な先生だったのですが、帰ってきたら、全国の基地闘争、夏は内灘米軍基地反対支援闘争へ私も一緒に参加しましたが、それから日本がアメリカ支配でどうなっているかということなどを学習するようになってきました。
また、夏の補習授業などではイングリッシュ・グラマーなどと書いている副読本を自分でつくって、これは印刷されて出版もされていますけれども、これでみんなの学力を底上げするということにも取り組みました。みんなの英語の力をつけるということで必死になってやりました。学級文集の「入道雲」というのは、後に本になりましたけれども、毎週一度、月曜日に寺島学級3年6組というクラスが出した新聞ですけれども、とても新鮮なすばらしい通信でした。
山本学級の文集は、寺島先生が「ぼくが切ってやる」と言ってしてくれました。だから、私のクラスの文集「こころ」は、私が編集して、子どもたちの作品ですけれども、寺島先生の支援の中でできあがったものでした。このように何でも助け合って取り組むというのが、当時の様子でした。また、私の授業のない時間などには、寺島先生の授業に入って、空いた席に座って、授業を受けたりしました。「このザットは目的格か所有格か?」と生徒を次々と当てて、「そこの人」と私も当てられまして、「目的格だと思いますが」と言うと、「よし!」と言ってもらえて、生徒がニコニコっとして拍手をしてもらえて、そういう授業もありました。
資料に旭丘の生徒名簿がありますが、2年1組、私のクラスの名簿ですが、一クラス53名。名前を覚えるのもたいへんでしたが、名簿が女子を先にあげています。「男女同権というのだったら女子が前に来てもいいじゃないか」ということで議論の中でこういう形になったのです。男女混合名簿という意見もありましたが、それについては保健の先生から「身体計測など、やはり男女は分けてほしい」という意見もあって、最終的にはこのような形になりました。卒業証書も、一番先の女の子が名前を呼ばれました。一人ひとり校長先生の手わたしで感動的でした。旭丘の教育は、そういう教育だったのです。
10.助け合い、励まし合う教職員集団
53年の時に山城地方に風水害が起こりまして、南山城の茶畑などがつぶれ、死傷者も出ました。そのとき、「水害救援隊」で、S君は、救援に行ったんです。そして帰ってきたら、S君が「この原因はアメリカ帝国主義にある」と(笑い)どうつながるのか、私にはわかりませんでしたけれども。S君という人はおもしろい人で、帰ってきたら授業で、教室の窓を開けて、「この日本の空に、アメリカのヘリコプターが飛んでいるではないか」って言ってまわりました。2回目になったら、生徒が「先生、今日は曇っています。ヘリコプターは飛んでいません」と。(笑い)S君は困りまして、「私は寺島さんのように新聞をつくるのもできないし、山本さんのように文集をつくるのも苦手。どうしたらいいやろ」と。いろいろ考えまして「よし!」と、ザラ半紙を8分の1に切りまして、教室へ出て行きました。どうしたのかと言うと、「私は、今までこうして数学や理科を教えてきたけれども、どこかおかしい所がある。私の授業に意見があったら、書いてくれ。名前は書かんでもええ」と言って生徒に配ったんです。たくさんの子どもたちが書いてくれたようでした。「山本さん、ぎょうさん書いてくれたで」と読んでいて、「『その横はやめてくれ』これなんやろ?」。S君は、教室に行ったら、成績の良くできる子とか、かわいい子とか、やんちゃな子とか、こういう目立つ子はすぐに名前を覚えるけれども、そのあと、「○○さん」と言ったら、「その横」「その前」「その後ろ」と。(笑い)いつでも「その横」と呼ばれる子がいるんですね。「その横ではなく、私には名前があります」と。「痛い!」と言っていました。どのクラスもまわって読み上げて謝ったのは偉いと思います。
また、こんなものもありました、ある日、いっしょうけんめいに授業を教えたあとで、黒板を消す時に「今日の授業で教えたことは、全部ウソやった。どこが間違いか、わかっている人、言ってほしい」などがあって、「そんなんをやられたらどこでウソを言われたかわからないので、いつも緊張していなければならないので、やめてほしい」と言うのもありました。なぜそんなことをしたのかを聞くと、彼は言いました。「ぼくらの時代は『天皇は神様』と間違ったことを教えられていて、みんなそれを信じていたではないか。ぼくもたまには間違ったことを教えてしまうこともある。その時に生徒が『先生が言うから』ということで、信じてしまうのではなく、子どもたちに何が本当かウソか、事実に基づいて考える生徒に育てないとあかんのと違うか。そう思ってしたけれども、『うその授業をいつするかわからん』というようなやり方は考え直さなあかんな」ということで、反省しあったものです。そういう中で教職員組合運動の活動家も、教育実践を大事にする先生も、だんだんとお互いに心が通い合うようになってきました。
私などは学生時代に世をはかなんで戦争が終わったから、一年間、朝から晩まで碁を打っていた時代がありまして、今アマ6段で、明日も囲碁大会の世話をするのですが、当時は「民主教育をやらなければいけない。碁盤や碁石はさわらない」と決めておりましたけれども、ある運動会の終わりに年配の髭の生えた先生が「山本君、君、生徒会やらをやるのもいいけれども、碁ぐらい打たんとあかんで。碁を教えたろう。ちょっと持って来い」と言って、碁を教えていただいたことがあります。「君は、案外強いやないか」と言われて、それから節度を持って碁を打つこともありました。今まで意見が違ったら、木っ端みじんに相手の意見を切り捨てて「あー、すっとした」などと言っていたのですが、そうではなしにお互いを忠告し合い、励まし合うことが大事だと、石川啄木の好きな自称「センチメンタル・ヒューマニスト」の私も、明るく子どもにとけこむようになりました。理科ではトコトン事実を大切にし、発明発見の歴史など力を入れました。自然だけでなく「社会科学」でも、あんなに勉強したことはありませんでした。
11.「旭丘の赤い先生を追い出せ」の攻撃と抵抗
さて、旭丘中学校事件が1954年に起こったと言いますけれども、53年の暮れに急に「旭丘の赤い先生を追い出せ」「赤い魔の手から子どもを救え」「赤化防止団」と書いた大きな新聞が、ベタベタと町中に貼られたんです。またその日にきれいなプリントにした「旭丘中学は赤い」「旭丘中学を憂う会」というものが一斉に配られたんです。そういう事件が起こりまして、で、旭丘の真相を報告するんですけれども、なかなかうまくいかない。当時高山市長という、革新から当選して裏切った人ですが、この人たちが取り上げて、54年は知事選挙の年でした。「蜷川知事さんの下ではこういうことが起こるんや」ということを言われたんです。でも、真実は53年10月の「池田・ロバートソン会談」が真の根源だったと思われます。
(「池田・ロバートソン会談」:第二次大戦後のアメリカの極東戦略にもとづく日本の軍事基地化と再軍備計画、それに沿った人づくりを教育の課題とすることなどを日本の責務として確約した会談。1953年10月2日から約1カ月にわたってワシントンにおいて自由党政調会長池田勇人と国務次官補ロバートソンとの間で断続的に行われた)
真相を報告するんですが、その中で日教組の教研集会にも報告しなければ、ということになりまして、第3回の静岡教研大会、まだ当時は教育研究集会ではなしに「教研大会」でしたが、私が静岡へ行くことになりまして、レポートを正月返上で書きまして、「こう書いたら首になるかもわからんな、でもこれは本当のことだ。ああ、革命は近づけり」などと言いながら、若かりし頃ですから、何日か徹夜して書き「平和教育を守る旭丘中学の報告」というのを持って静岡に行きました。
ところがみなさん、日本全体の中では、「旭丘がいろいろがんばるから、せっかく教育二法反対でまとまりかけているのが、具合が悪くなっている。ああいう学校をつくるな」ということになっているというのです。そういうことを言われました。また、実際には、僕は知らなかったのですが、全国に行くと、たとえばKさんという生活綴り方の、私は心服して学級文集にも生かした方ですけれども、「そういう学校がありますね」と、こういうふうに言われたんです。「一体、どうなっているのかな」と思いました。しかし、Yさんという方や歴教協のTさん、Mさん、Oさんなどという方は、25歳の私に対して「いや、ごくろうさんです」と頭を下げられて、非常に親切に援助をしていただきました。当時は、日本共産党自体が割れていたんですね。労働運動も総評中心にありましたたけれども、社会党も右派社会党、左派社会党と割れていて、自民党も自由党と民主党に分かれていました。翌年、1955年に、それぞれが統一して新しい時代を迎えるという、時代が大きく変化していく頃だったと思います。日本の「太郎」「花子」--原水禁大会、母親大会など、この年にはじまりました。
その中で、私たちの中学校の問題があったわけですが、5月に日教組の大会が札幌でありまして、そこへ僕が行くことになったのですが、レポートを持って真相報告をしようとしたのですが、なかなか報告をさせてくれないんです。それで、府立高等学校のTさんという委員長が「5分間だけ」と言って、結局30分ほど旭丘の話をしました。夜は「旭丘の真相報告会」を連日開き、大反響でした。その結果、大会で満場一致で「旭丘を支持する」「教育委員会や教育長こそ雲隠れするな、その責任を問う」という決議があがったんです。感慨無量でした。
12.旭丘の生徒はどう変わってきたのか
そう言う経過の中で、旭丘の教育の話から、旭丘の事件の話になっていったわけです。 さきほど言いましたように、旭丘の生徒はどんどんと変わってきていまして、子どもたちの作文の中にもそれが見られます。
資料に生徒だった「S君の場合」というのがあります。彼は小学校の時は不良少年だったと言いますが、こう書いています。
「・・・・そして中学校、旭丘中学校は、できたばかりで建物も設備もずいぶんひどいものでしたが、毎日毎日、目を見はることばかりでした。ここには、成績や貧富による差別がまったくなかったのです。何より『お母ちゃん、オカネ!』という必要のほとんどない学校・・・・。それは、ぼくたちを解き放ちました。ぼくの生活は一変しました。何でも言える授業、気兼ねなく発言できるH・R。アダナで呼んでも怒らない先生。みんなの納得いくように運営できる生徒会やクラブ活動・・・・。ぼくはもう有頂天でした。毎日、陽が落ちるまで、帰るのを忘れてしまうのでした。そして何よりもぼくにうれしかったのは、『働くことの尊さ』をくりかえしくりかえし教えてくれた沢山の先生たちの授業でした。ぼくの母は、闇米のかつぎ屋をしていました。ぼくは新聞配達をする毎朝でした。ぼくの意識の底で、いつもこれがはずかしくて仕方がなかったのです。しかし中学校生活の中で、働く母親を頼もしいと思い、尊敬できるようになりました。小学校ではフダツキの非行児、問題児だったぼくは、あれほど毛嫌いしていた授業や宿題さえ楽しいものになりました。この中学校では、文字どおり、一人ひとりの生徒自身が主人公となることが目指されていました。それが劣等生のぼくにもよく感じとれました。そして、ついに引き起こされた『旭丘事件』・・・・。私たちは同窓生や先生、生徒、父母と一体に、本気になってたたかいました・・・・」と書いてくれています。
また、映画もつくられました。「記録映画 子どもたちの昭和史第5部 学校」東京都教組が「勤評の頃」という記録映画をつくったのですね。それに登場しています。旭丘のことは映画を作る監督さんが載せました。「真実をつらぬくために:京都・旭丘中学校」がそうです。
この資料の写真にのっている人たちは、寺島・山本以外はみな卒業生です。詩人Hさんも、憲法9条の会の働き手も、ここにいる保育園長のKさんもいますね。現在でも各方面で活躍しています。
13.50年代の教育が、どういう影響を与えたか
50年代の教育が、どういう問題であり、どういう影響を与えたかということですが、旭丘闘争が終わった時に、教え子や父母との「お別れ会」があった時に、賞状をもらいました。珍しいでしょう。その賞状には「激励状 先生 先生は私たちに 未来を信じ 明るい未来をつくるために 生きる事を教えて下さいました その教えを守って 私たちはがんばります 先生も がんばって下さい 昭和29年6月20日 旭丘中学校 同窓・生徒会」(左掲)という文章が書いていますが、それは今でも私の机の上に置いてあります。これは、オーバーな言い方になるかも知れませんが、私たちにだけではなしに日本の先生に送った激励状ではないかと思っています。そういう意味では、私たちの行ってきた実践を知っていただいて、生かせるものは生かしてほしいと思っています。
中国の魯迅の「もともと地上には道はない」という詩がありますね。「歩く人が多くなれば、それが道になる」という魯迅の言葉にもあるように、今、そういうことを改めて考えてみてほしいと思います。私の大好きな石川啄木が、考えてみると、もう100年も前になるのですが、「新しき 明日の来るを 信ずと言う 自分の言葉に 嘘はなけれど」という詩をうたっていますが、いかに新しき明日を、私も、私たちの誓った言葉に嘘はないけれども、やはり築いていくのは私たちじゃないかと思います。お互いに、信じ、頼り、高め合おう。
教え子は、最近も同窓会をやっています。寺島学級は、寺島さんの手紙にもありますように、最近は毎年一度は持っているといいます。昨年のある人からの年賀状では、2回も持っているとも書いてありました。手紙にあるように寺島さんも呼ばれて校歌を歌っているわけですが、あの校歌は、考えてみれば、その学校で懲戒免職になった人がつくったわけです。闘争の最中は、「校名もなくなる」「校歌も歌えなくなる」「女の子はお嫁に行けなくなる」などというデマ宣伝の中であったのですが、その後の旭丘の教師だった人が、この校歌がひょっとしたらもう歌えない校歌になるかも知れないと危惧して、3年生担任で卒業生を出すときに、記念製作として校歌を銅板にして体育館に貼り付けたんです。こうしてあるから、生徒も親しむし、あまりいわれを知らない子も歌っているし、出入口に「旭丘に光あれ」という石碑もあるということです。この石碑も後に卒業記念として製作してくれたものだとか。だから、そういう形で今日にも続いているわけです。私のクラスは、首を切られた時期の関係もあって、1年8組と2年1組の合同の同窓会をしています。こういう形の同窓会は全国でもめずらしいと思いますが、そういうことを通じて、今も教え子たちとの交流を持っています。
教え子たちは、卒業して労働者になっても、中小企業の経営者になった人たちと話をしても「今、不況でたいへん困っている。けれども、『しかたがない は 止めよう』ということで、がんばっているんや」ということでした。この「しかたがない は 止めよう」というのは、旭丘の綱領に入っている言葉です。また同窓会などでも「世界をつなぐ橋となれ 未来に輝く道となれ」という、こういう内容の校歌は日本の中でもあまりないと思う。誇りに思っている」と話してくれます。こういう形では、今日にも生きていると思います。
14.旭丘の綱領と校歌
最後に、みんなでつくった旭丘の綱領を読ませていただいて、話を終わっていきたいと思います。
旭丘綱領 誰もかれもが力一ぱいのびのびと生きていける社会、自分を大切にすることが人を大切にすることになる社会、誰もかれもが「生きていてよかった」と思えるような社会、そういう社会をつくる仕事が私たちの行手に待っている。 その大きな仕事をするために私たちは毎日勉強している。 私たちは次のことがらをいつも忘れず、大きい希望と自信とをもち、みんな力をあわせてがんばって行こう。 1.祖国を愛しよう 私たちみんなが幸福になるために、古いしきたりを打ち破り、美しい自然と平和な国土を きずきあげよう。 2.民族を愛しよう かくれたかがやかしい民族の歴史を学び、人間の強さと尊さを知り、自由で平和な社会を つくる人になろう。 3.労働を愛しよう 責任を重んじ、みんなのためにはたらくことの尊さを知り、いいことを進んで実行しよう。 4.科学を愛しよう 人間の幸福のための学問を尊敬し、なんでも、なぜ? と考える人になろう。 5.公共物を愛しよう 私たちの生活を豊かにするみんなの物を美しく大切に使い、平和な国、美しい町、明るい 学校を育てよう。 6.「r仕方がない」をやめよう 自分や友だちを見すててしまわず、いつでももっといい方法がないか考え、みんなの力で 一つ一つ解決して行こう。 7.しりごみをやめよう いじけたりかくれたりしないで不正を見のがさず、正しいことをどしどし実行する勇気を もとう。 8.いばるのをやめよう 生徒も先生も、女子も男子も、いばったりおどかしたりこわがったりしないで、親切にあ たたかくたすけあって行こう。 9.ひやかしやかげぐちをやめよう おたがいに親切に忠告しあい、よろこんで忠告をきくようにして、かげでこそこそするの をやめよう。 10.ムダをやめよう 時間や資源をムダにすることをやめ、みんなの幸福のため、役立てよう。 (1953.7 作成) |
この旭丘綱領は1953年7月に草案が出され、何度も議論され、こういう形に練り上げられたものです。最終決定はされませんでしたが、旭丘の綱領となっています。ご存じの人も多いと思いますが、この前文は雑誌「世界」の編集長(当時)をしていましたYさんという方の詩から引用されています。ほかは、中国の五愛運動ですね、それから「山びこ学校」の「何でもなぜ?と考えよう」という言葉や、なによりも旭丘の活動の中で取り上げたら良いという切実なものをまとめて、ここに載せられることになりました。「もっと生命と平和のことを」などという意見もありましたが、この綱領がもっと生かされたらと、校歌と共に誇りに思っています。
(プレ集会の最後に、山本正行先生は、当時の旭丘中学卒業生たちと共に「旭丘中学校校歌」を熱唱されました。)
旭丘中学校校歌 1 輝く丘に 草燃えて 比叡の風に 友を呼ぶ 希望を結ぶ 森かげよ 希望を結ぶ 春かげよ 若い心の ふるさとに 光は満ちて 野の花も はげむ我らの 胸にさく 2 みとせの夢の ゆりかごよ 苦楽を分かつ 丘の上 理想の光 もとめゆく 清い我らの 真心は 世界をつなぐ 橋となれ 未来に続く 道となれ 3 ああいつまでも 手をつなぎ 心ゆたけく すこやかに 学びに励む 我が友よ 緑あふれる あこがれの 旭丘に 光あれ 旭丘に 光あれ (作詩・作曲 寺島洋之助) |
| 質疑応答の後、10分間程度、山本正行先生にまとめの発言をしていただく予定でしたが、時間の都合でできませんでしたので、以下、山本先生からいただいた「おわりに」の部分の発言要旨を追記します。 |
15.おわりに
あれもこれも話したい事があったのですが、最後の10分が消えたのが残念です。
その思いを込めて校歌を卒業生と共に歌いました。
旭丘事件の頃は、特別な学校のように扱われましたが、勤評反対闘争で全国に燃え広がった平和と民主教育を守る灯は、60年安保闘争として大きな節をつくりました。さらには学力テスト反対闘争、高校全入運動など、草の根の広がり、生活要求に根ざした闘争として、60年代の教育、国民運動の大きな足跡を残しました。
今また21世紀に生きる教育と運動が求められていますが、私たち「旭丘」の「地図のない登山」のような逆コースと対決するたたかいから見れば、情勢は大きく変わっています。憲法9条を世界の宝として大きく燃え広がらせる運動をはじめ、世界を変える歴史的な激動期に私たちは生きています。
「生きていてよかった」と言える世の中にするため「わかる授業、楽しい学校、明るい未来」をつくるため、老若男女力を合わせて活動するチャンスが訪れています。「客観的条件は成熟している、主体的条件をどうつくるかがカギ」といわれています。そのカギは、私たち人間にあります。人間は「変える」ことができます。自分を変え、仲間を変え、子どもを変え、日本を変え、世界を変え、宇宙を変える気概を持って力を尽くそう。
全面発達、科学的認識、集団主義の旗をしっかり守り、創造的に生かした実践をしようではありませんか。新しい実践は無限です。「教え子を再び戦場に送るな」はゆずれない誓いです。
この機会をつくってくださった京都教育センターのみなさん、父母、国民のみなさんに心から感謝して私のお話とさせていただきます。
ノーベル科学賞を受けられた益川さんの「もし9条危機なら、運動に軸足を」という平和と科学への思いは、最近私の最も感銘を受けた言葉であり、未来に生きる言葉だと思います。ありがとうございました。
(2009.2.11 建国記念日反対の日に--)
| (本講演の詳細については「京都教育センター年報 21号(2008年度版)」をごらんください。) |