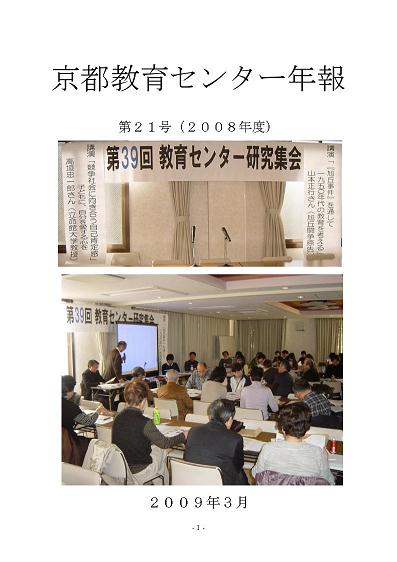
2008年度の活動のまとめと2009年度方針
築山 崇(生活指導研究会事務局)
Ⅰ. 2008年度活動のまとめ
1. 経過(2008年2月〜2009年1月)
2月例会 「生徒指導」をめぐる政策動向を考える
1.環境なき厳罰主義(ゼロトレランス)の問題性と規律規範の教育のあり方 テキスト 喜多明人「環境なき厳罰主義(ゼロトレランス)」(藤田英典編『誰のための「教育再生」か』岩波新書 2007)
2.新学習指導要領をめぐって(中教審答申、小・中要領改訂ポイントなど)
4月例会 現代中学・高校生の意識について -その生活世界の理解のために-
ゲストスピーカ(高校生)を迎えて、座談会形式。参考文献 土井隆義『友だち地獄』(ちくま新書)
【例会設定の趣旨】
生活指導研究会では、1997年11月に、学級崩壊問題についての小冊子「幼さを自分らしさに」を、99年11月にはその第2集「表現を励まし信頼を育てる学校を」を発行しました。「幼さを・・・」の編集過程で、学級崩壊現象に見られる“子どもと教師のずれ”の問題に関わって、「子どもから見た、大人・社会の見え方」という視点を提起しました。
教師・親など大人は、子ども達が見せる「問題行動」(例えば、むかつく・キレル)を、大人の文脈で読み取り、意味づけをしています。「子どもは変わったのか、変わっていないのか」と言った、素朴な議論を含め、「子ども(生徒)理解」は、生活指導・生徒指導にとって、常に実践の鍵となる課題です。
子ども相互、子どもと大人との、意思疎通、コミュニケーション(関係づくり)の難しさがいわれる中、次々と新しい(少なくとも外見的に)様相を呈する子どもたちの状況から、子どもたちの内面や、「子どもから見た、大人・社会の見え方」を、正確に読み取り、理解することは非常に困難になってきています。むしろ、子ども、大人それぞれの世界の相互の理解には、限界とずれがあることを前提に、それぞれ(全ての世代)がすみやすい世界を、連帯や協同の営みとして築いていくという、基本的な姿勢(構え・考え方)が求められているということかもしれません。
1996年に国連のユネスコの会議で提起された「学習の4本柱」には、「他者とともに生きることを学ぶ(learning to live with others)」という提起がありますが(他の3本は、知ること(to know)、為すこと(to do)、人間であること(to be))、この柱には、「違いを違いとして認めあって、平和的に共生を図る(社会的排除ではなく、社会的包摂)」という続きがあります。そこでイメージされているのは、グローバル化がすすむ現代にあって、様々な民族・文化が、その多様性ゆえに全体として豊かな世界を築いてくことですが、私たちの身近な社会生活や、学校生活にひきつけて考えるなら、“ちがう”こと(違和感)を理由に、排除するのではなく、「私はこう、あなたはそう、それがあたりまえ、無理にあわせようとなんかしなくていい。違ってる方がおもしろい」という、包摂する(つつみこむ)関係をつくっていくことが大事、「その方が、お互いうんと住みやすい」という世界を創っていくことでしょう。
「生活世界」という言葉について
ここでは、現象学や、ハーバーマスが使う「システムと生活世界」という概念などを厳密に適用しているわけではありません。上に書いたように、「子ども・青年から見た大人・社会、その見え方」、「対人関係、コミュニケーションの世界」と言った意味合いで使っています。
今日の社会状況として、格差の拡大や固定化とセットになった競争構造の強化、そのことによる“周辺(縁)化”や“社会的排除”よって、将来への希望や人間への信頼を奪われる青年という側面はしっかりとらえなければなりませんが、同時に、そのようなハード(社会のしく組み・構造)のもとで(も)日々結ばれている、“人々の”関係、その関係が作り出している世界−現代において、人々は、それぞれの性、世代、(所得・職業・学校)階層、地域などで構成される“世界”−に“棲んでいる”状況があります。そして、その様々な世界相互に、接点と重なりが存在し、そこでは摩擦や紛争が起こっていると考えることが出来ます。
6月例会 学習・意見交換 最近の無差別殺傷事件とその背景をめぐって
―分析・対応への意見交換― 以下の資料①〜③を読み合わせ、参照しつつ議論。
【参考・学習資料】
①土井隆義『友だち地獄―「空気を読む」世代のサバイバル』2008.3 ちくま新書 より
②山本敏郎「〈格差〉〈貧困〉問題と生活指導」 『生活指導』2008.7 より
③アエラ 秋葉原事件 特集記事/新聞記事コピーなど
*現代のエスプリ 2008.7 『ネットジェネレーション バーチャルな空間で起こるリアルな問題』
*藤川大祐『ケータイ世界の子どもたち』講談社現代新書 2008.5
9月例会 中学生の問題行動をめぐって―日韓の比較調査から―
報告者 京都府立大学大学院 上田光明さん
11月例会 教育センター冬季研究会 生活指導分科会の内容・運営について
1月 教育センター研究集会生活指導分科会(詳細は、別掲「分科会まとめ」参照)
テーマ 連帯と共同の関係をつくる生活指導の探求 基調報告
日本社会の窮状と生活指導実践の課題
(事務局より) 報告 ①「荒れ」の現象をこえて子どもとつながる (京都市内小学校)
②自治の力、集団の力を育てる生活指導実践 (府北部中学校)
③高等学校の生徒指導の現状から考える (府立高校 )
Ⅱ. 2009年度活動の方針
1.主な研究テーマ
①いじめ問題についての継続的研究
・実態のより正確な分析と子どもの内面の把握
②官製生徒指導の批判的検討と、自治と人間的共感を育む生活指導実践のあり方の探求
・ゼロトレランスの克服、規律・規範の教育のあり方の検討
③自治的諸活動の指導・集団づくりをめぐる今日の実践の到達点と課題について
・習熟度別学級編制など、学習集団と生活指導の関係の問題点の検討
④子ども・父母(住民)・教師の協同による学校づくりを支える“自治”の構築
⑤”荒れ”の背景にある生活の困難の検証と子どもたちをつなぐ教育的な働きかけの方法の探究
2.研究会の組織化のとりくみ
◇教組、各種サークル等へも呼びかけて、研究討議の輪を広げることを目指す。
◇研究例会、教組の教研、センター研究集会を相互に関連付けながら質的な発展を図る。
Ⅲ. 研究会の体制
代表 築山 崇(兼事務局)
会員 (略)