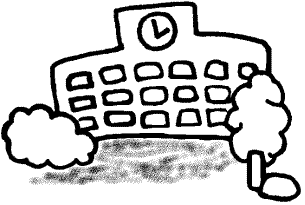 |
教育基本法・学習会・・・・17 04・7・3. 土野 友人 |
|
「公教育は・・・・」 ・ 今日、04・7・3(土)は、恒例の教育基本法・連続(月例)学習会での第7回、第6条「学校教育」であった。 哲学者:鰺坂 真 氏が語る「学校教育」・・・・・ 「公教育とは・・・・、学校とは・・・」と、今日的課題とも関連させての非常に興味あるものでした。 ・ 「公教育」というものを、フランス革命にまでさかのぼって、歴史的に追求されたこと・・・・・、しかも今日的課題でもある「管理と競争の学校現場のもつ基本的問題点」その背景としての「公教育のもつ二面性」にもふれられながらの分析! 日頃の多忙化の中で、「なにやら、おかしい・・・こんなことではいけない!」と感じつつもながされざるを得ない状況の中で、僅か2時間ほどではありますが、じっくりと「公教育」について考えるチヤンスは非常によかったと思います。 ・ 今日の教育基本法・第6条「学校教育」の前項には、まず「・・学校は、公の性質をもつものであって・・・」と「公教育」の理念が示されていること。これに対して、政府与党たちが示している”おそまつな改悪案”(04・6・16)には、同様に「学校教育」の項はあれども、「公教育」の理念は全面削除されている! これは何故か! これをどう考えるか! これが、今日の学校現場には既にどのような形で出現しているのか! などなど・・・・・ 今日の「公教育」は、国民のための教育ではなくて、国家のための教育ということで、学校現場や子どもたちを「管理と競争」で非教育的状況に追い込んでいる。このことから、親たちからは、「公教育不信感」が芽生え、「民営化傾向」を支持する「公教育」解体論的傾向さえ生じかねない状況もある。 ・ そもそも「公教育」についての考え方は、「天然・自然的に発生してきたものではなく、歴史的に成長してきたものである・・・」こと。18世紀後半に国家主義的・絶対主義的・プロイセン的傾向のものと、民主主義的・フランス共和主義的傾向の二つの流れがあった。後者はフランス革命の自由・平等の理念が求められていること。そして、民主主義実現のためには、「公教育」が必然的に重要であること。また、当時「公教育に対する4つの観点」として、「自由の原理、 非宗教性、 無月謝性、 義務性は主張されてない」があったことなど、述べられた。 ・ 第6条:「学校教育」のの第2項には、教員についての記述ああるが、これについては今回の学習会では、論じられずにまたの機会にということになったが、後半の討論時には、重要なポイントとして、今後問題にしていくことが求められた。 いやはや、いつもユニークな学習会となって、基本法の「深み」で感動である。 ひとこと感想まで・・・・。
|
| トップ | 教育基本法 | 事務局 | 雑感目次 |