| 前文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
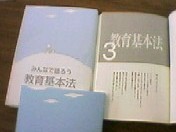 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
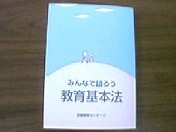 |
内容・執筆者(一部)紹介
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回学習会 教育基本法「前文」を学ぶ(要旨) 話題提供:野中一也(大阪電気通信大学名誉教授) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ 教育基本法を学ぶ今日の意義 わたくしたちを取りまく情勢は、平和と民主主義を基調とする憲法・教育基本法の精神から大きく離れていっています。自民党・公明党の連立政権は、排他的なアメリカの単独行動主義に卑屈なまでにのめり込んでいます。日本は、アメリカの植民地になり下がっているかのような状況です。戦後、アメリカの占領政策の転換により、「詭弁」を弄して自衛隊がつくられ、戦争ができる「普通の国」を目指してきました。そして、ついに、アメリカのイラク占領戦争に「共犯者」として自衛隊を派遣するところまで来ました。明らかに日本国憲法の精神と9条から一線を超えました。 このままでは日本の展望はありません。日本国憲法の理想の実現は、根本的には教育の力にまつと教育基本法は規定しました。多くの市民が教育基本法を学んで展望を探ることが今求められている緊急の課題であると言えるでしょう。 Ⅱ 主体的に学ぶために Ⅲ 前文からの考察 「前文」 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しょうとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。 【第1項】 ① 「われら」 「われら」は、戦前のような天皇ではなく、われわれ国民であるということを高らかに宣言した者であると言えるでしょう。まさに、「国民」の意思で、国民主権の憲法・教育基本法を制定したという表現です。 ② 「日本国憲法を確定し」 戦前の学校では、儀式にとき校長が白い手袋をはめて「教育勅語」をお経のように読み、生徒は意味もわからないまま頭を下げて聞いていました。天皇崇拝の刷り込みでした。戦後、日本憲法で「教育勅語」体制と決別・断絶して、主権在民の民主主義的な日本をこの憲法でスタートしました。このことを再確認することが重要であると思います。憲法の民主主義精神を常に確認・意識して、それが日本の「伝統」になっていく国民的努力をするように求めていると言えるでしょう。 ③ 「民主的で文化的な国家」 「民主的」とは、政治、経済、社会などのあらゆる領域で「民主的」であるということであり、「文化的」とは、真・善・美の文化的価値を内包し、それを実現する国家の建設をめざします。具体的には、戦争を放棄した文化であり、思想・良心・信教・表現・学問などの自由を保障する国家です。権力主義的国家主義「文化」とは全く無縁です。「資本主義の退廃文化」とも全く関係がありません。 ④ 「世界の平和と人類の福祉」 「世界の平和」は、憲法9条が描く世界であり、どんな争いであっても戦争で解決をはかることは決してしないということです。「人類の福祉」は、平和の中で一国だけの福祉ではなく、まさに人類の福祉を充実させようと日本国民は決意をしたのです。なんと高い理想を掲げたことでしょう。 ⑤「この理想の実現は教育の力にまつ」 わたくしたちは憲法で崇高な理想を決定しましたが、単に思想のままにおいておくのではなく、その理想を教育の力よって実現しようと決意をしました 教育に夢とロマンを託したのです。民主的な教育への期待の大きさが読み取れます。 【第2項】 ① 「個人の尊厳」 まず「個人の尊厳」とはどのように考えたらよいのでしょうか。それは憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される」という基本的な規定に連動しています。天皇や国家ではなく、一人ひとりの個人が人間らしく生きるように第一次的に尊重されなければならないと言うことです。今、激しい競争の導入により、人権侵害が多発し、民主主義の破壊である戦争に多くの国民が動員されようとしています。まさに個人的人間の尊厳が傷つけられています。 ② 「真理と平和を希求する人間」 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」、武力行使は永久に放棄する、という憲法9条の中核的規定に連動します。そして、両者を結合して「真理と平和」を「希求する人間」を人間像として描いています。 「真理」の対立概念は「虚偽」です。歴史的現実に真摯にむきあい、科学的認識によって真理を捉え、平和を希求する文化的存在としての「人間」が期待されています。 ③ 「普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化」 個と普遍と特殊の関係から考えてみましょう。人格は「個」、人類は「普遍」、民族は「特殊」、として位置づける。そして、個・普遍・特殊を串刺しにして捉えてみる。 務台理作氏は個人を「人類主義に裏打ちされた人格としての個人」、国家を「開かれた民族連帯としての国家」、国民を「誠実で真理と正義を愛する国民」として捉えています。人類主義に裏打ちされた個人・国家・国民という3者を串刺して考える重要性を指摘しました。 日本の文化は、日本の独自の個性をもつが、同時に人類主義に裏打ちされ、世界に広がる普遍性をもつものです。決して偏狭なナショナリズムを内包してはならないのです。 ④ 「教育を普及」 以上のような教育を実現するには民主的な教育実践を発展させる以外にはありえません。 特に教職員の深い自覚を促していると言えるでしょう。 【第3項】 ① 「日本国憲法の精神に則り」 教育基本法は、まさに憲法と一体のものであることを再確認したものです。 ② 「教育の目的を明示」 教育の理想的な目的は、いわば「当為」(sollen)の世界の提示です。理想のもつ意義は現実の矛盾を「止揚」していく情熱的な行動に駆り立ててくれるところにあります。 ③ 「新しい日本の教育の基本」 「新しい」の意義は、1945年の“敗戦”からのスタートです。 「新しい日本」は、排他性をもたないし、「共生の思想」で教育をすすめる、それが教育の基本であるとうたっています。 Ⅳ 未来の展望 以上考察してきたように、日本国と教育の在り方を前文は示しています。情勢が困難であっても理想は必ずや人々のこころを掴み実現されていくものでしょう。努力しましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
「みんなで語ろう 教育基本法」お申込の方は、こちらまでお願いします。 |