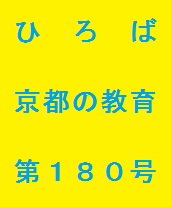
特集2 教職員の専門性をいかした教育
総論 教職員の専門性の向上と成長
中田 康彦(一橋大学)
教師がおかれている勤務実態
経済協力開発機構(OECD)の国際教員指導環境調査(TALIS)が2013年に実施された。2008年調査に続く2回目の調査だが、日本が参加するのは今回が初めてである1。日本では、全国の国公私立の中学校・中等教育学校前期課程から200校を無作為抽出し、校長と在籍教員に対して質問紙調査が行われた。
国際調査は条件をそろえて数値を準備することになっているが、実際には数値の算出方法や制度の大前提がそもそも異なることがあり、単純に比較できない。勤務時間やその内訳にしても、各国の平均値(それはしょせん平均値にすぎない2。
とはいえ、このたびの調査では、①全体として長時間労働の傾向にある、②部活動に充てる時間が長い、③事務処理に充てる時間も比較的長い、といった特徴が浮かび上がっている3。全教が2012年に実施した長時間労働勤務実態調査でもそのことは明らかになっているが、こうした多忙な状況は、専門性の成長を阻害する要因となっている可能性が高い。
国際社会と比較した研修状況
TALIS調査は、専門性の成長に関する調査も行っている4。
初任者研修については、公式の初任者研修への参加率は83.3%と参加国中第二位(平均48.6%)なのに対し、非公式の初任者研修活動への参加は18.4%(平均44.0%)と最下位である。組織内の指導者(メンター)の支援を受けているのは33.2%(第四位、平均12.8%)で、職能開発の形態としては他校の見学が51.4%(第二位、平均19.0%)である。職能開発の参加の障壁としては、「自分に適した職能開発がない」「参加する誘因がない」という回答は参加国平均を下回っているが、「仕事のスケジュールと合わない」が86.4%と韓国と並んで突出している(平均50.6%)。また職能開発のニーズとしては「多文化・多言語環境での指導」「新しいテクノロジー」が参加国平均を若干下回る以外は、多くの項目で他国より高い数値を示している。
こうした数字から読み取れるのは、日本の教師文化の自己省察的性格である。自己効力感の低さ、職能開発ニーズの高さは、日本の学校の困難な現実をそのまま反映しているというよりも、目標は高く自己評価は低いという教師文化の反映とみるべきであろう。もっと研修をしたいという意識は強く持っていながら、それを満たすだけの機会が与えられていない、というもどかしさが浮かび上がってくる。
「実践的指導力」要請の強まり
教員の資質向上に関する近年の特徴の一つは、「実践的指導力」が入職前から強く求められるようになってきた点にある。
新卒採用でも、「実践的指導力」を備えた一人前の教師として子どもや保護者と向き合わねばならない。しかし民間企業でも長期研修期間を経てから顧客と対峙するとは限らない。だから「実践的指導力」自体は、教職で固有に求められるものとはいえない。
「実践的指導力」への要請が強まっているのは、即戦力として目の前の職務を遂行「できる」ことへの期待の強まりを意味している。さらにいえば、「できない」教師は職場で育てるという発想を捨て、個人の自己責任に還元していく、ということである。
中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」(2006年7月11日)は、免許更新講習とともに教職課程に「教職実践演習」なる必修科目を設置することを提言した。この教職実践演習には、1.使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、2.社会性や対人関係能力に関する事項、3.幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項、4.教科・保育内容等の指導力に関する事項、を含めるものとされ、2010年度入学者以降には必修科目となっている。
「学校や教育委員会等との協力により、実務実習や事例研究、現地調査(フィールドワーク)、模擬授業等を取り入れる」など、「理論と実践の有機的な統合が図られるような新たな授業方法を積極的に開発・工夫」してみたところで、即戦力に必要な実践的指導力の獲得を入職前の時点で行うのには限界がある。それにもかかわらず、入職前の最終段階として「教職実践演習」を設けなければならなかったあたりに、即戦力志向の強まりがうかがえる。
7月3日に発表された教育再生実行会議第五次提言は、「実践的な力を備えた教師を養成し採用する」ために「インターンシップやボランティア活動など学生に学校現場を経験させる取組を推進するとともに、採用前又は後に学校現場で行う実習・研修を通じて適性を厳格に評価する仕組み(教師インターン制度(仮称))の導入を検討する」としている。あわせて大学に対しては「実践型のカリキュラムへの転換」を要請している。教員免許更新制度の現状をみれば、非効率的な負担が課されるだけとなる危険性が高いが、それにかまわずすすめられそうな気配である。
個人能力還元主義
もう一つ指摘できる傾向は、実践的指導力に限らず、「~力」あるいはスキル(技能)というかたちで、職務遂行上求められる特性を個人の能力に還元したがる点である。
内閣府が掲げる「人間力」(2003年)、厚生労働省が掲げる「就職基礎能力」(2004年)、経済産業省が掲げる「社会人基礎力」(2006年)、はいずれも、職業社会への準備教育としてのキャリア教育で、学生・生徒に身につけさせるべき能力とされている。これらに共通しているのは、いわゆるコミュニケーション能力を重視している点である。
コミュニケーションをスキルの獲得の問題だとすることは、人間関係に由来する問題の原因を個人の能力の欠如に還元する傾向を生み、自己責任とみなす空気を生む可能性がある。教員文化でいえば職務の個別化・私事化を推進し、組織体制としては協業なき分業が促進されるということである。これが、学校教育の目的を達成するうえで望ましい方向といえるだろうか。
教職の専門性とは何か
教育活動の各領域に即して要請される知識・技能は存在する。それらが教職の専門性の構成要素の一つであることはまちがいないだろう。
そうした専門性は今日においてもなお必要とされるものだが、今特に求められているのは、さまざまな関係主体の教育要求をコーディネートできることではないか。
コミュニケーションを築けること自体は、人間関係の中で主体的に行われる性格が強い教育活動において重要である。ただしそれは個人の「能力」として蓄積されるものではなく、人間関係のうえに成立するものである。そこに生み出されるのは、関係主体相互における信頼であったり、ネットワークであったりといった、学校における社会関係資本とでも呼ぶべきものである。個人に蓄積される知識・技能も、子どもや保護者の声をくみとり、それに応じることで初めて十全に発揮される。学校に寄せられる願いは、特定の教師個人に対するものばかりではない。教職員が組織化され、集団として教育要求に対応することも、教職が発揮すべき専門性であろう。
油布佐和子は1995,1999,2009年に実施した教師の意識調査を通じて、高度な知識・技能と人間的素養を必要とし、使命感がないとできない職業だという教職観をより強く肯定するようになっている一方で、組織の中の教師であることを強く意識する「組織へのスペシャリスト」指向が強まっていると指摘する。そして、その変容には加齢(組織内の位置の変化)と社会の変化の双方が作用しており、教育改革がこの変容を加速させているという5。ただし本稿がいう組織化とは、組織の構成員という自己規制をかけることではなく、組織を主体的につくりあげることを指す。
専門性の向上の場はどこに
それでは、教師の専門性はどこで向上させられるのだろうか。
林寛平は、TALIS調査結果をみて、「学校内でのインフォーマルな学び合いに参加している教員ほど仕事に対する満足度が高い…教員の満足度を高めるには、勤務時間の増減よりも、学校現場におけるインフォーマルな学びを促進するような政策の方が筋が良いということになる」と指摘している6。そのうえで、職場の過酷さを強調するよりも、日常の仕事の中で感じているやりがいや魅力に着目するかたちで政策的示唆をひきとるべきだという主張している。
専門性の向上という課題に即してみるならば、職場満足度・職業満足度だけでなく、自己効力感を見ておく必要があろう。TALIS調査では、学級運営・教科指導・生徒の主体的学習の促進の領域について4項目ずつたずねているが、どの項目でも日本の回答はずばぬけて低い。教育文化や教師政策で類似性が高いといわれている韓国と比べても、かなり差がある。
意識調査はあくまでも教員の主観を尋ねるものであって、教員がおかれている客観的状況を示すものではない。したがって自己効力感のずば抜けた低さも、かなり割り引いて受け止める必要がある。
とはいえ、こうした意識状況そのものが現実である以上、自己効力感を高めるような実践ができるための条件整備と専門性向上の機会が用意されねばならない。
学校外での民間教育研究運動への積極的な参加ももちろん喜ばしいことではある。自分の課題にあわせ、実践の豊かなアイデアを手に入れるうえで、勤務地を離れて自主的に研修を行う条件が整えられることが望ましい。
重要なのは、それを自分と自分をとりまく環境でそれをいかに活かせるかである。パッケージとして流通する実践アイデアや教育技術は、万能の処方箋ではない。目の前の現実からたちあがる要請に応えているかといった診断は、教師個人の中で自己完結したものではなく、身近なところでの情報交換・意見交換によって、より効果あるものとなっていくのではないか。
そのためにはまず、自分の実践を消費してしまわないよう記録し、対象化することである。記録された実践や実践への自己のまなざしが、課題を共有する<同僚>に検証されることで、新たな示唆を得ることができる。
専門性が個人の能力に還元され、専門性の成長プロセスがパッケージ化あるいはシステム化されがちな昨今、人間関係に基づいたふり返りを行うことがますます重要な意味を持つようになるだろう。
1 第1回OECD国際教員指導環境調査の結果については、OECD編著、斎藤里美監訳『OECD教員白書』明石書店、2012年、を参照。
2 TALIS調査から何を読み取るべきかについては、山本宏樹「国際教員調査TALISは現代の黒船か? 教育的信念をめぐる闘争のゆくえ」『SYNAPSE』2014年3月号、30~35頁、を参照。
3 この側面を強調するものとして、井上伸「駅前トイレで寝泊まりするトリプルワークの女子高生、世界ワースト長時間労働で鬱病激増する日本の教員」2014年6月27日、http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20140627-00036818/
4 第2回OECD国際教員指導環境調査の結果については、国際教育政策研究所編『教員環境の国際比較』明石書店、2014年、を参照。
5 油布佐和子「教職の変容―「第三の教育改革」を経て」『早稲田大学大学院教職研究科紀要』第2号、2010年3月、51~82頁。
6 林寛平「教員は「忙しい」なんて言ってない ―国際教員指導環境調査(TALIS)をどう読むか―」2014年6月30日、http://blogos.com/article/89461/