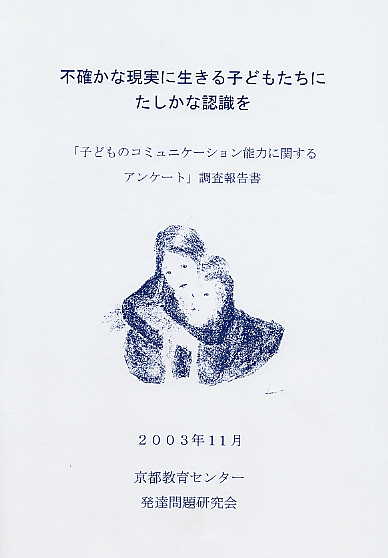 |
Ⅱ.友人における対人関係の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)児童の発達的特徴について
①交友関係の成立と仲間への同調 実践的な研究においては、小学校低学年~中学年にかけての児童の交友関係の成立の動機は、主として「家が近い、クラスが同じ、席が隣・・・・」などの外部的な条件で成立するのに対して、小学校高学年~中学生にかけては、「趣味や関心事が同じ、勉強・スポーツ・性格の共通性・・・・」などの、内部的な条件により成立する傾向が強い。
児童の仲間への同調は、従来の研究によれば、仲間への同調は、児童前期から児童後期または青年前期まで増大し、それ以後減少する傾向があり、また女児は、男児よりもいっそう同調的であると指摘されている。同調行動は、児童期を通して増大し、その頂点は児童後期から青年前期にかけてであり、それ以後は減少するという曲線的変化を示すと考えられる。また一般に、女児は男児よりもいっそう同調的であるといえる。
今回の調査では、(中学生の調査結果と併せて検討してみなければならない面もあるが)少なくとも小学校の段階では、従来の研究と同様、同調傾向は年齢が上がるに従って増大していき、男子では小学校6年生が、また女子では小学校5年生がピークを示している。
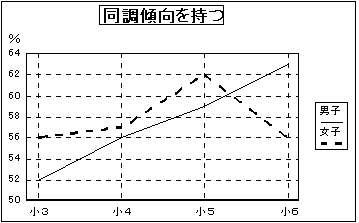 ②同輩による受容と拒否 児童期における同輩からの受容と拒否についての従来の研究によれば、同輩による受容と拒否を決定する重要な要因は、知能水準や学業成績よりも、むしろ人格特性や行動特性であることを示している。
従来のこの種の研究結果では、小学校の時期に同輩から受容される児童は、一般に、積極性(活動的,熱心,勇敢など)、社交性(明朗,親切,友情的など)、身体的優位性(容姿がきれい,運動能力が優れているなど)という特性をもっている。男児の場合には、「勇敢」「活動的」「指導的」などの特性が、女児の場合には、「親しみがある」「友情的」「親切」などの特性が強調される傾向があるとされている。今回の調査でも、ほぼ同様の結果を得ている。
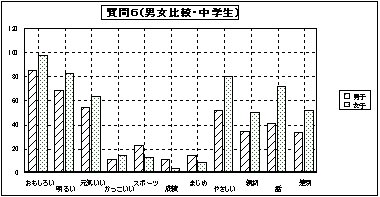 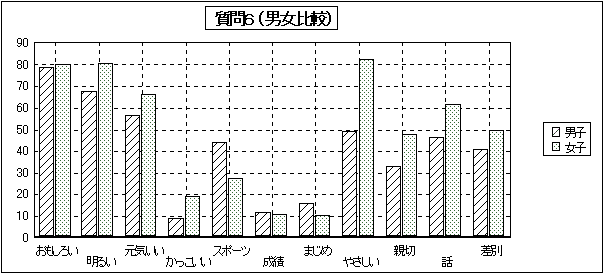 (2)調査項目から見られる特徴
(質問番号5)「あなたの仲の良い(またはよく遊ぶ)友だちは何人ぐらいいますか?」の結果は、次の通りである。
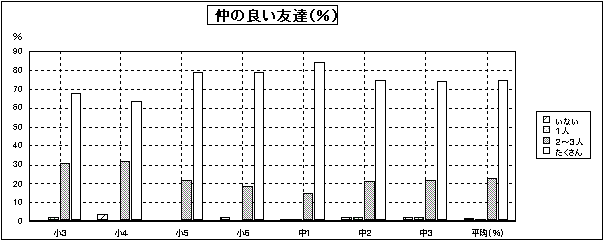 少数ではあるが「友だちがいない」子どもの存在は気になる。また、友だちが1人~ 3人という少ない 友達関係の中でコミュニケーションしている
子どもが2割~3割お り、その関係がくずれ た時に「孤立」してしまう可能性は高い。この友達の人数は、 同時に「いつも誰と遊んでいるのか」という点や、「友達とのコミュニケーション能力」 の発達という面からも大いに関係しているのではないか。3・4年生の中学年と、5・ 6年生の高学年とを比較してみると、やや高学年の子どもたちの方が友達が増えている と思われる。
(質問番号6)「あなたの好きなタイプの友だちはどれですか?」の結果は、次の通りである。
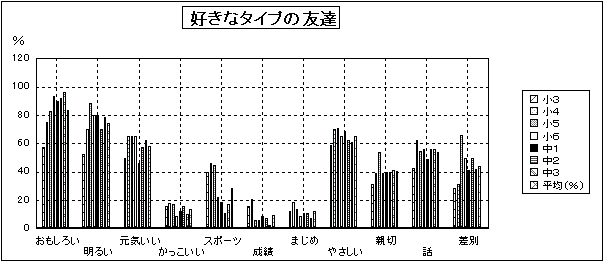 「好きな友だちのタイプ」は、面白い・明るい 元気・スポーツができるなどの表面的に目立つ面を 見せる子どもに人気が高い。関谷健は、これを「個人性を好む傾向が強く、関係性の弱さを表す」(2002,11)と指摘している。また「やさしい」 「話を聞いてくれる」など、自分を受け入れて くれる存在として友だちを求めている面もうか がえる。しかし、このような「人間関係的な面」(その人の内面的な側面を求める)は、前者の表面的に目立つ面よりも相対的には少数である。また、「成績がよい」「まじめ」などの子どもを好きなタイプと思う子どもが少ないのは「先生にとってよい子」が必ずしも子どもの支持を得ているわけではないことを示している。また、男女別の比較をしてみると次のようになる。 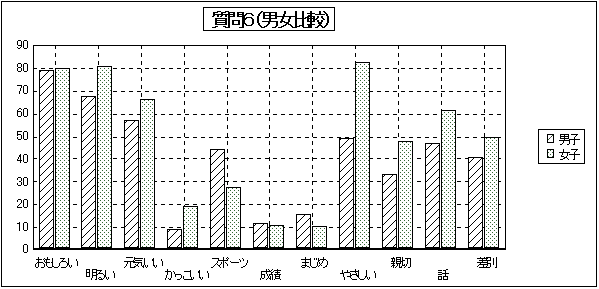 男子に比較して、女子は「やさしい」「親切」などの数値が高い。これは、友達に対して競争的ではなく「同一性」「親密さ」のようなものを要求しているのではないかと思われる。男子は「スポーツ」が高く活動的であるが、女子は「話を聞いてくれる」など「おしゃべりを通して自分を受け入れてくれる存在」を求めていることに特徴があると考えられる。また、女子に「明るい」「元気いい」の数値が高いのは、友達に対して積極的で前向きな関係を求めている期待感の表れではないかと考える。
次に、男子ごと、女子ごとに小学校と中学校の比較をしてみると、全体として、男女とも小学校・中学校では大きな変化が見られない。これは、この時期の子どもたちが、小学校3年生~中学校3年生に至るまで、同じような価値観で友達を見ていることを表している。
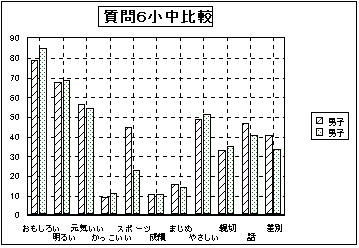 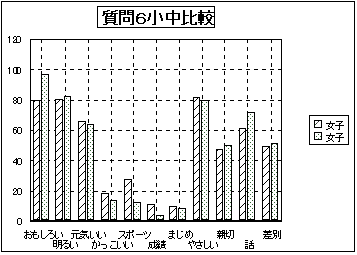
泉真理子(2002.2.4.)は、この項目について、次のように分析している。
「まず1つめに、男女ともに「面白い」「明るい」という項目において高数値を得た。これは、何も子どもだけにみられる特徴ではなく、大人であっても同じではないかと思う。2つめに、小学校、中学校ともに女子に共通して、「やさしい」が高数値を得た。しかし、なぜ男子においては数値が低かったのであろうか。女子は、同性にも異性にも「やさしさ」を求める一方、男子は、異性には「やさしさ」を求めても同性には求めないという傾向があるのだろうか。3つめに、「かっこいい」「元気がいい」という項目において、男子よりり女子のほうが数値が高かったことがあげられる。これは、私自身にとっては、少し意外な結果となったのであるが、こうなったことの要因について次のようなことが考えられる。今日、女子においては「女性的な性格」に加えて、「男性的な性格(特徴)」も求められるようになったのではないだろうか。これは近年、盛んに言われている「男女の平等」「女性の社会進出による女性の男性化」のあらわれのように思う。一般的に男子よりも女子のほうが内面的な発達が早いと言われていることもあわせて考えると、そのような考え方が早くも小学生・中学生の女子に浸透しているのではないだろうか。一方、男子で数値が低かったことについては、「自分よりかっこいい友達だと、一緒にいても自分が目立てない」といった嫉妬心が少なからず関係しているのではないかと思われる。4つめに、「スポーツが得意」という項目では、男女ともに中学生になると割合が減少することと、「成績がよい」という項目において、男子では小学生・中学生でほとんど割合が変わらないのに対して、女子では中学生になると割合が減少しているということがいえる。加えて、5つめに、「話を聞いてくれる」という項目において、女子では中学生になると割合が増加していることがあげられる。4つめと5つめから、中学生になると、友達に求める要素が、「スポーツが得意」「成績がよい」などの外見的なものから、「話を聞いてくれる」などの内面的なものへと移り変わり、その傾向は男子よりも女子の方が顕著であることがわかる。」
(質問番号7)「あなたは、友だちからいやなことを言われたり、たたかれたり、けられたりした時どうしますか。」の結果は、次の通りである。
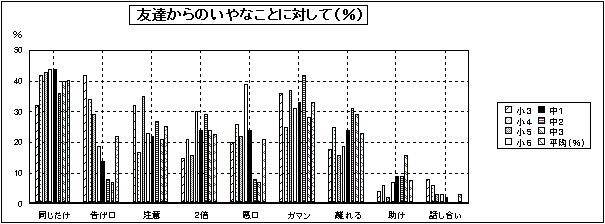 「同じだけ仕返しをする」「2倍の仕返し」「悪
口を言う」などが学年が上がるに従って増え
ている。これは一面「自分達で問題を解決しよう」という傾向である共に、暴力を背景とした「目には目を」論が子どもの世界に根強くあることを物語っている。またこれは「親や
先生に言う」が高学年になるに従って減少していることからも伺える。
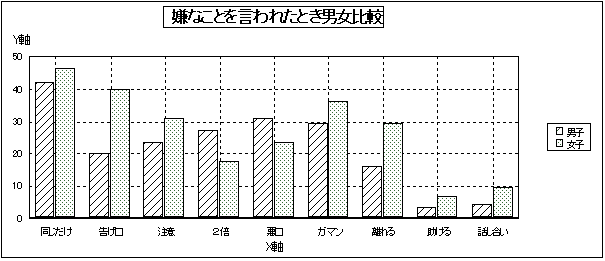 「口で注意」「クラスで話し合う」などが少数で ある点から見ても、子ども達は民主的な手続 きで問題を解決することに期待を持っていな いのではないかと思われる。 少なくない子どもが「がまんする」と答えてお
り、トラブルの民主的な解決の必要性と方法
への指導が重要な課題になっているのでは ないか。今日、子どもたちの世界が「弱肉強食」「ジャングルの掟」と言われる世界になっている中で、子ども世界の中での「生き方」を子どもが模索しているのではないかと思う。
また、男女別で比較してみると、男子に比べて女子の方が「同じだけ」「告げ口」「注意」などに多く、「2倍返し」が少ない。これは、暴力よりも「ことば(口)」で、反論し、自己の主張を貫こうとしている姿勢が現れている。また、「告げ口」「離れる」などが、同様に女子の数字が特に高いのは、当事者同士で解決を図ると言うよりも、相手との距離をさらに広げる形で事態に対応しようとする傾向があるということを示しているのではないか、と考えられる。
(質問番号16)「あなたになやみごとや困っていることがあったら、だれかにそうだんしますか?」の結果は、次の通りである。
結果は学年においてあまり差は見られない。約3/4の子どもが相談すると答えている。1/4の子どもたちは「いいえ」と答えている。この背景には「信頼し、相談する相手を持っていない」という孤立した状態が子どもにあるのではないかと思われる。
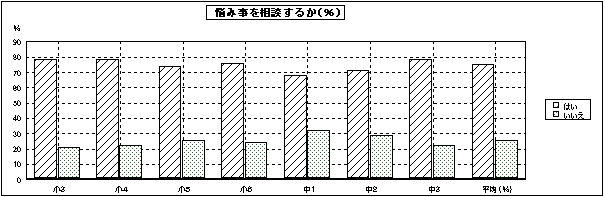 (質問番号16-2)「「はい、だれかにそうだんする」とこたえた人に聞きます。それはだれですか?」の結果は、次の通りである。
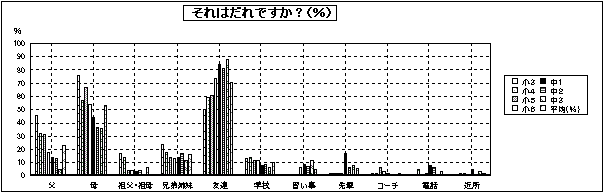 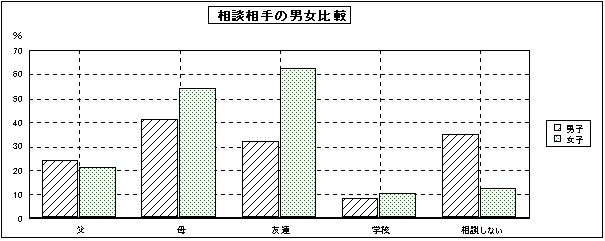 「悩み事の相談相手」のベスト3は、1位 母親、2位 友だち、3位 父親である。しかし 学年があがるに従って、父母への相談が 減り、代わって友だちが増えている。 相談相手としての父親は、母親に比べてその半数にも達していない。多忙等の理由により、必ずしも子どもとは日常的に「親密ではない」状態があると考えられる。また、学校の先生や習い事の先生に対しては、悩み事の相談相手としてほとんど、期待されていないことがわかる。「相談相手」は、日常的なつきあいの中での「親密さ」が反映しているものと考えられる。
(質問番号16-2)を、男女別にすると上記のようになる。これを見ると、男子のベスト3は、1位 母親 2位 相談しない 3位 友達 であり、女子は、第1位 友達 第2位 母親 第3位父親である。男子では「相談しない」というのが高く、もし、母親や友達の中に相談相手を持たないとしたら、孤立を深めていくことになる。女子は友達・母親により比重がかかっているのがわかる。この点でも、女子にとっては、友達や母親との良い関係の形成が重要であると言うことがわかる。
(3) クロス集計から見える特徴的な事柄
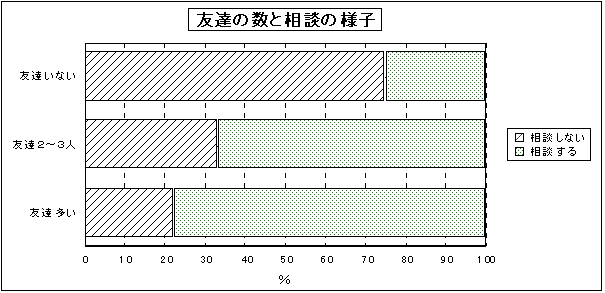 「友達の数と」、「悩み事を相談するか」の関係について(質問番号5と16との関連について)の結果は、次の通りである。 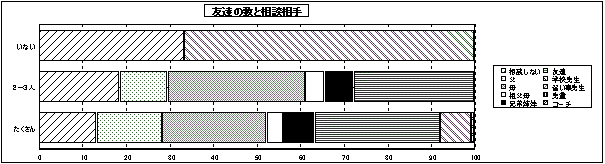 対象となる数字が少ないので、一概には言えないが、傾向としては「友達が少ないほど、悩み事を相談しない」傾向があることがわかる。同時に「相談相手」との関係について言えば、ひとりぼっちほど「がまんする」ことが多く、相談相手に「教師」が重要な役割を果たすことが示されている。 沢山の友達がいるほど、相談相手も多彩であり、救いの手があることがわかる。 友達の数と、折り合いの付け方(質問番号5と質問番号7)の結果は、次の通りである。
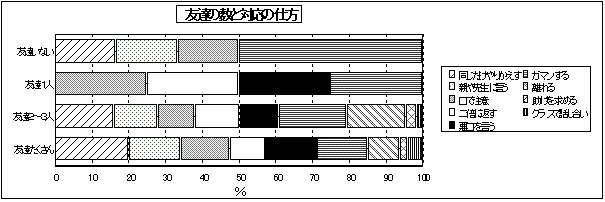 この結果から見て、友達の数が少ないほど、「ガマンする」子どもの率が高いということがわかる。また反対に、友達がたくさんいる子どもでは、多くの選択項目が平均的に選択されており、多様な「折り合いの付け方」があることがわかる。友達の少ない子どもには「2倍返し」の率が高いが、これにより「ガマンするか、強い反撃に出る」という極端な方向に動く傾向のあることが分かる。
また、折り合いの付け方と相談相手(7と16)との関係は、次の通りである。
友達にいやなことをされたり、言われたときに、誰かに「相談する」とした層と「相談しない」とした層との比較では、相談するとした層の方が、「やり返し」「2倍返し」「悪口」などが少なく、「口で注意」「親や先生に言う」「離れる」「クラスで話し合い」といった点が多くなっている。相談相手がいることが、友達との関係をより敵対的なものへと発展することを防ぎ、解決への前向きに姿勢につながっていることが分かる。
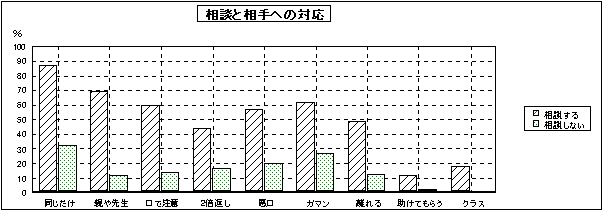 |