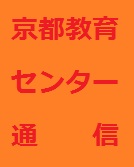
 |
●京都教育センター通信 復刊第136号 (2020.4.10発行) |
4月は「さようなら」と
高垣 忠一郎 (京都教育センター代表)
何かが終わり、何かが始まる移行期は、混乱や苦悩の時期でもあります。変わりたくないのも真実だし、変わりたいのも真実ですね。そのせめぎあいを経験し、精神的にも身体的にもバランスを崩して症状を出すことも少なくありません。今年はまたコロナ騒ぎがあり、さらにお疲れになったことだと拝察いたします。くれぐれも心身のメンテナンスを忘れず、ご自愛のほどをまずお祈りします。
人間がその基盤の上に生きる絶対的事実が3つあります。「必ず死ぬ」「自分の人生は自分しか生きられない」「すべての生命はつながっている」の3つです。
人生を旅にたとえれば、この旅にのみ有効(途中下車無効)と書かれた切符をもって、それぞれ独自の旅をしています。「裏をみせ表を見せて散るもみじ」という良寛さんの句があります。80年~100年の人生の前半生と後半生を「表」と「裏」とすれば前半生は獲得の人生、後半生は喪失と自己実現の人生とも言われます。
そして獲得の裏には喪失があり、喪失の裏には獲得があるのです。表からだけ見ないで、陰になる裏からも見る。複眼で人生をみる。人生を奥行きもって見る作法ですね。否定的に見えることの裏に肯定的な契機が潜んでいることに気がつきます。気がつけば「お陰さまで」とも言えます。あの苦しいことがあったお陰で、今日の自分があると言えるようにもなります。
「社会内存在」としての自分、「宇宙内存在」としての自分、二つの自分を中心にして生きる「楕円形」の存在が人間なのではないでしょうか。その人間は「世間相場」のモノサシと「生命相場」のモノサシと二つのモノサシをもった目で人間や世の中をみることも必要でしょう。大人になるとは、「働く」ことと「愛する」ことができるようになること(フロイト)と言い
バリバリ働い
子どもたちの ねがいにこたえる 学校づくり
ー「京都府高 障害児教育運動の歴史」学習会の記録よりー
このほど,府高障害児教育部で、見出しの学習会のまとめの冊子を出されました。その紹介をさせてもらいます。
はじめに
いつの頃からでしようか、職員会議での発言が聞かれなくなってしまったのは・・・。
只々指示と提案を聞き入れるだけの形式的な場となり、異論は喉の奥にしまい込まれていきます。高圧的な会議運営がされているのかというと、必ずしもそうでもありません。意見が出せない雰囲気が漂っているのです。また、校内の研究会では、下ろされてきたテーマと方針に沿って統一された 指導案の様式に合わせた作文を作ることに大きなエネルギーが注がれています。一人一人の子どもの実態を語り合う中で教育課題と
授業を練り上げるのではなく、卒業時に必要となる力を目標として逆算された生活課題を獲得させるための授業が求められています。「人生を生きぬく力」ではなく「生活に生きる(役立つ)力」をつけることが障害児教育の目的なのでしょうか?素直な子が良しとされ、反発する子は否定されていきます。特別支援教育の現場の中で、かつて溢れていた先生と子どもたちの生き生きとした笑顔や人格を磨き合うぶつかり合いがとても少なく なってきているように感じます。それは何故なのでしようか。![]() 「発達は要求(願い)からはじまる」「子どもをまるごと(能力・生活・家庭・生育歴・集団・心)つかん
「発達は要求(願い)からはじまる」「子どもをまるごと(能力・生活・家庭・生育歴・集団・心)つかん![]() で、その成長に寄り添う」「高まり合う目標を持った集団の中でこそ、子どもたちは育ち合う」「学び合
で、その成長に寄り添う」「高まり合う目標を持った集団の中でこそ、子どもたちは育ち合う」「学び合![]() う教師たちの中でこそ、子どもたちは学び合うことを知る」「教育の目的は人格の発達である」、実践の中から導き出されたこのような言葉が、かっての障害児教育の中にはたくさん生まれていました。
う教師たちの中でこそ、子どもたちは学び合うことを知る」「教育の目的は人格の発達である」、実践の中から導き出されたこのような言葉が、かっての障害児教育の中にはたくさん生まれていました。
教職員の世代交代と軌を一にして障害児教育の大きな路線転換の中で行われた「言葉狩りと共![]() 通言語化」(文書作成の徹底添削と検閲)によって、それらの言葉と教育理念はかき消し、教育の現場の中には、踏まれても踏まれても芽を出し花を咲かせる雑草のように、子どもたちを中心にした教育実践と仲間と共に育ち合おうとする教師の姿が、強く暖かく優しい光を放っています。
通言語化」(文書作成の徹底添削と検閲)によって、それらの言葉と教育理念はかき消し、教育の現場の中には、踏まれても踏まれても芽を出し花を咲かせる雑草のように、子どもたちを中心にした教育実践と仲間と共に育ち合おうとする教師の姿が、強く暖かく優しい光を放っています。
この冊子は、その歴史の転換点を見つめてきた世代と新たな輝きを見せている若い世代の架け橋となることを願って行った学習会の内容をまとめたものです。
そして、すべての教職員の皆さん訴えます。
「発達の主人公は
教育活動の主人公は
そんな学校を
「学校がすき!」と大人も子どもも言えるようになってほしいとの願いを込めて、この冊子![]() ます。
ます。
2020年1月
以前から、これまでの障害児教育部の歴史をまとめようという話がありました。具体的に検討を始めた![]() のは2017年度からでした。京都府内の支援学校ではベテラン世代の教職員が毎年大量に退職し、各校の世代交代がほぼ完了した時期でした。京都府で初めて養護学校として開校した向日が丘や与謝の海は50年の歩みを記念する行事が行われていました。これまで50年以上にわたる「ゼロからの学校づくり運動」、そして「教育の自主性・主体性をめざした障教部運動の取り組み」の歴史をベースにし、現在の支援字校の課題である「卒業後の進路に向かう青年期教育」を中心的な内容とし、50年間の障教部運動の歴史を現在につなげようと話しました。
のは2017年度からでした。京都府内の支援学校ではベテラン世代の教職員が毎年大量に退職し、各校の世代交代がほぼ完了した時期でした。京都府で初めて養護学校として開校した向日が丘や与謝の海は50年の歩みを記念する行事が行われていました。これまで50年以上にわたる「ゼロからの学校づくり運動」、そして「教育の自主性・主体性をめざした障教部運動の取り組み」の歴史をベースにし、現在の支援字校の課題である「卒業後の進路に向かう青年期教育」を中心的な内容とし、50年間の障教部運動の歴史を現在につなげようと話しました。
この話し合いの後、2018年2月に行われた府立特別支援学校長会の研修会で参加者に配布された府立特支校長会発行「最後の晩餐」という冊子の存在が明らかになりました。この内容は、養護学校義務制前後から障害児学校の教職員が努力を積み重ねてきりひらいてきた京都の障害児教育の歴史や成果の蓄積を誹謗するとともに、当時の教職員や教職員組合などの活動を一方的に中傷するものでした。障害児教育部の各分会ではいっせいに各校の校長と対応し、京都府高、京教組は京都府教育委員会と対応しました。
この校長会発行冊子は「過去を引き継がない」と、これまでつくりあげてきた教育の歴史をすべて否定し、不当労働行為など野蛮な行政権力を使ってトップダウンの学校運営と教育内容に転換させようとするものでした。より豊かな教育や障害のある子どもたちに即した新しい教育内容の創造のためには過去の下地や膨大な蓄積に深く学ぶことが求められます。「過去を忘れてください」とその歴史を無かった![]() ように進める方法では進歩も発展も望めません。
ように進める方法では進歩も発展も望めません。
これまで障害児教育部が中心となり、多くの教職員や関係者と進めてきた障害のある子どもたちのた![]() めの教育課程づくりや学校づくり、寄宿舎の生活教育、共同教育の発展、「医療的ケア」の体制づくり、教職員定数改善の取り組み、教職員健康問題、スクールバス通学問題、施設設備老朽化・過密問題、寄宿舎増設運動、子どもたちの放課後問題など、その時々の国際的な障害者理念を学習しながら進めてきた「これまでの教育」とすべての面について今、子どもたちや保護者、教職員との矛盾が現れています。
めの教育課程づくりや学校づくり、寄宿舎の生活教育、共同教育の発展、「医療的ケア」の体制づくり、教職員定数改善の取り組み、教職員健康問題、スクールバス通学問題、施設設備老朽化・過密問題、寄宿舎増設運動、子どもたちの放課後問題など、その時々の国際的な障害者理念を学習しながら進めてきた「これまでの教育」とすべての面について今、子どもたちや保護者、教職員との矛盾が現れています。
私たちは教職員組合として「あらためて障教部運動50年間の学校づくり運動を再確認し合い、今後![]() の分会活動を一層前進させる契機とする」こととし、障教部運動の新たな歴史を若い世代の先生方とと
の分会活動を一層前進させる契機とする」こととし、障教部運動の新たな歴史を若い世代の先生方とと![]() もに前に進めることを目指します。この取り組みは単に「歴史をまとめる」ことだけにとどまらず、2018年度から3回にわたり学習会が企画されました。その内容は、ベテラン教員の歴史の話を聴くだけでなく、現在の職場で取り組んでいる教育課題や教職員組合員としての思いを交流し、話し合うことを中心としました。学習会の半分くらいの時間は参加した若い世代の先生方の発言を確保する時間配分を行い
もに前に進めることを目指します。この取り組みは単に「歴史をまとめる」ことだけにとどまらず、2018年度から3回にわたり学習会が企画されました。その内容は、ベテラン教員の歴史の話を聴くだけでなく、現在の職場で取り組んでいる教育課題や教職員組合員としての思いを交流し、話し合うことを中心としました。学習会の半分くらいの時間は参加した若い世代の先生方の発言を確保する時間配分を行い![]() 進めましたが、予定時間を遥かに上回る多くの発言で豊かに学習し合うことができ、今後の学校づくりの課題や運動の進め方についても話し合われました。
進めましたが、予定時間を遥かに上回る多くの発言で豊かに学習し合うことができ、今後の学校づくりの課題や運動の進め方についても話し合われました。![]()
50年以上前、京都の障害のある子どもたちと保護者の「私たちも学校で友だちと勉強したい」という![]() ねがいを受けとめ、教職員組合の中心的な運動の課題として多くの教職員や関係者とともに取り組んできた「学校づくり」の歴史は今後も途絶えることなく、教職員集団の協働の力で新たな前進を始めて
ねがいを受けとめ、教職員組合の中心的な運動の課題として多くの教職員や関係者とともに取り組んできた「学校づくり」の歴史は今後も途絶えることなく、教職員集団の協働の力で新たな前進を始めて![]() います。
います。
2020年1月
「京都府高障害児教育部運動の歴史」 学習会担当
電話075-751-1645