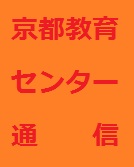
 |
●京都教育センター通信 復刊第126号 (2018.8.10発行) |
不満は減り、不安が増えた子どもたち
―「学校」と「勉強」に取り込まれた子どもたちの生活 ―
山岡 雅博(立命館大学大学院教職研究科・教職大学院)
少し前のNHKの調査では(1)、約95%の中・高生が「幸せだ(とても+まあ)」と回答している。また、ベネッセの調査(2)では「自信が持てない」という子どもが減ったという報告もある。不登校やいじめなど、子どもたちのしんどさの指標となる行動が減る兆しを見せていない現状を考えると、にわかには理解しがたい数値である。
先述のベネッセの調査では、2008年から2013年までの5年間の子どもたちの生活の変化を調べている。小学5年生から高校2年生まで、すべての学年で学校にいる時間が増えている。小学生では約10分、中学2年生では約18分も長くなっている。その結果、「遊び」や家族や友人などの「人とすごす」時間が短くなった。また、寺崎は2006年以降高校生の家庭学習の時間が増加傾向にあることを指摘し、「脱受験競争」から新しい「受験競争」が到来したと述べている(3)。学習時間の変化だけではなく、「学校の勉強の万能観」という学習観の変化もあるという。2006年までの「学歴と自己実現は相いれないものだ」と考えていた傾向がへり、「将来のすべての満足度の向上を学校の勉強が保証してくれる」と考える傾向が強くなった。生活を学校に取り込まれ、「学校の勉強の万能観」という価値観に、子どもたちは縛り付けられている。
こんな子どもたちは自分に対する期待値を下げれば、生活満足度は高くなルと土井は述べている(4)。土井はその背景に、子どもたちが「努力したら報われる」と考えなくなったためとしている。勉強万能の競争原理に浸され、さまざまな格差が拡大し、子どもたちはあきらめやすくなっている。また、尾木は生活満足度の上昇を「身辺化が進んだ」からだと述べている(1)。広がり続けるネット社会とは逆に、「身近なところに意識が集中している」と、子どもたちの意識が身近な狭い関係の中にとどまっていることを指摘した。生活圏を狭めることで不満も減少させているのである。
身辺化が進むと、逆に身近な人との波風を立てない関係づくりに腐心し、そのため他者の視線が気になってしまう。また、競争原理による「学校の勉強の万能観」という価値観では、負け組は自己責任で片付けられてしまい、あきらめの傾向は増えていく。かくして、子どもたちの不満は減り、不安は増え続けている。自分に期待せず、範囲を限定した幸福感には、不安と表裏一体で、少しでも失敗すればすべてをあきらめざるを得ない危うさがある。「自分はダメな人間だ」と思い込むと、がんばることを受け入れ、管理されやすくなってしまう。「ゼロトレランス」のような管理強化と「道徳の教科化」などは、これに拍車をかける可能性がある。
【文献】
(1)(『NHK中学生・高校生の生活と意識調査・2012』NHK放送文化研究所,2013)
(2)(「第2回 放課後の生活時間調査-子どもたちの時間の使い方[意識と実態]」ベネッセ教育総合研究所初等中等研究室,2013)
(3)(寺崎 里水「新しい“受験競争の時代”の到来 ―学習の量的拡大と質的変化―」『第5回学習基本調査報告書』ベネッセ教育総合研究所,2015)
(4)(土井隆義「子どもたちはどんな社会を生きているのか-社会的格差の進行と幸福感の上昇が意味するもの」「人間と教育」97号 2018春主教育研究所)
みんなで21世紀の未来をひらく教育のつどい 教育研究集会2018IN長野
美術教育分科会「表現が苦手な児童に寄り添って」
絵本 努 (府内小学校教諭)
はじめに
教師になり京都の北部で2年、そして南部の現任校で8年が過ぎました。現任校でとあることをきっかけに図工の研究会で学ぶようになり7年が過ぎました。教材研究や学びの大切さを改めて感じ実践を行い、本年度は5年生を担任しています。
「先生今日の図工何するの?」と子ども達全員が表現を色々な意味で楽しめるようにと右往左往しながら進めてきました。その中で昨年度担任したAとBという表現が苦手な児童への関わりについてまとめました。
基本的な姿勢
①子どもに無理がないように指導を行う。 (大きさ・内容・日常的)
②「やりたい」「描きたい」という意欲が湧く題材選びや指導
③子どもが納得できる作品を仕上げられる指導。
Aについて
不安感が強く、生活の中で劣等感が積み重なってきているようでした。字形がとれない、発表(特に自分の思いなど)ができない、会話の中身はAが好きなミリタリーと戦国の事ばかりでした。中学年では、一日に1時間程別室(図書室)に行き落ち着くという形をとっていました。
Bについて
感情をコントロールすることが不得手で、苦手なことや嫌いなこと、自信がないことには向き合えない。一方でプライドが高く、自分が認められる活動(工作、算数)には意欲的に取り組める。感情が高ぶると攻撃的になる傾向もあり、薬を服用している。
2人とも図工の時間は描きだすのがとても遅く、時には作品を出さずに終わる時もありました。表現をすることに自信がなく、表現することを避ける傾向があり、それがさらに表現への自信をなくすという悪循環に陥っていました。
国語「やまなし」
読み取りの学習をしたあと、読みとったイメージを毎時間絵で表現していきました。水彩色鉛筆を使い抵抗感なく水彩を楽しめるようにしました。最初、Aは出てくる物を1つ2つ描<だけ、Bは挿絵をまねるといった具合でしたが、周囲の友達の絵などを参考に毎回グレードアップしていき、最後のまとめでは、八つ切りの半分の大きさの絵を描<ことができました。
円福寺の絵(写生)
6年生は毎年地域にある円福寺で写生をしています。AやBを含め学級全体が、いきなりの四つ切り作品には抵抗(不安?)を感じるだろうと、小さい作品として校舎を描いた後に写生に行きました。
今回は大き<描く等指定せず「自分が選んだ場所をみんなに自慢するつもりで描いてみよう。」という形で進めました。どうなるかと思いましたが、全体的には今までの学年での積み上げのおかげか、下書きはそれぞれが納得できる作品になったようでした。しかし、AとBの二人は全く描かない状態だったので、とにかくどんな構図で描きたいのかを聞き、写真を撮りました。
教室に帰りみんなが彩色の段階で、周りの友達の作品がどんなものかを見る中で、2人が安心して描きだしました。写真があったこともあり、いったん描きだすと2人とも集中してやりきるので、みんなと同じころに作品を完成させることができました。
飛び出すクリスマスカード
Aは手先が不器用で工作系も苦手です。(Bは工作系は得意)3学期に版画、粘土工作、卒業制作として写真立て(カッターを使ったステンドグラス)を計画しており、そこへ向けて12月にカッターの作品に取り組むことになりました。Aが難色を示すことが目に見えていたので「1年生と家族に送るクリスマスカードを作ろう」という形にしました。Aは家族も1年生も大好きなので、きっと頑張るだろうという考えがありました。ただ、作品が完成するように、市販の立体グリイーティングカードを使い「基本的な形として、これを使ってもいいよ。でも自分で考えたい人は色んな工夫をしたらいいよ。」という声かけをしました。
未来の自分(粘土工作)
Bは工作系が得意で、バスケも好きなので、自分でも納得できる作品を黙々と作っていましたが、Aは何を作ったらいいかで何時間も悩んでいました。A「未来の自分なんて分からないと」とテーマの出し方が悪かったようで「将来したいこととかない?今好きなことでもいいよ。」と声かけすると、「戦艦」とかえってきたので「じゃ、船に乗る人なんてどう?かっこいいな。」と言うと、図書室に行き、船乗りの資料を自分で集めてきて課題を進めることができました。特に、自分が好きな船をつくるところは集中し、こだわって取り組んでいました。
卒業制作(写真立て)
カッターの習熟ができたAは冬休みも家で練習し、「飛び出す年賀状」を学校にもってきてくれました。Bもお家で写真立てのデザイン等を考えてきていたようで、2人とも驚<ほどスムーズに作品を完成させていました。それを校内図工展に出したところBの母から「絵も工作もそろって出しているなんて、1年生の時以来です。」と、卒業を前に喜んでもらうことができました。
まとめ
この間の指導を自分なりにまとめる中で、この2人が表現に向かいあうには、
① 自分でやろうと思えるまでの試行錯誤の時間。
AもBもこれまで多<の失敗体験を繰り返しています。その中には、教師として自分が関わって感じさせた失敗体験もあります。そして、とてもデリケートでした。そのため、笑われることに非常に敏感で「○○で笑われるんじゃないかな。」と時には固まり、時には逃げるといった手段をとってきました。そんな2人が表現という行為を行う時、他の児童よりも大きい抵抗を感じるのだと推測されます。2人がやろうと思えるまで待て、その幅や2人なりの頑張りを受け入れられる学級であれば、安心して表現していけると思います。
②周りの作品を見ることで安心感を持つ。
2人とも、周囲から浮いてしまうことに憶病です。国語のやまなしの絵では、第1場面の絵は本当に描けませんでした。でも、毎時友達の作品を見る中で、「そんな絵でいいんだ、自分の描<ものでいいんだ。」と思えたあとは、表現に向き合っていました。
③自分でできると思える支援、話し合う。
2人の大きな武器は、家族と友達でした。どちらの母親も、2人に対しての理解が深く、良い所もできないことも、悪い所も全て受け入れ、その上でどう支援していくのかを本人を交えしっかり話し合うことができた時は、紆余曲折あるにしても最後まで作品を仕上げることができました。そして、2クラスである学年の友達みんなが2人に対して一定の理解をしており、協力もしてくれました。
④最後まで作品づくりに付き合う。
卒業をひかえた最高学年である6年生のタイムスケジュールはかなりタイトでした。他教科の課題の中には話し合った結果やらずに終わったものもあります。しかし、いったん本人達が「やる」と言ったものは、必ず最後まで付き合い完成までもっていきました。時には家に持ち帰りというものもありましたが、そのことが次の表現へとつながっていったと思います。
円福寺の写生のように、「毎年しているから今年も」と安易な考えで題材を選んでしまったことなど、反省点も多い1年でしたが、今後もていねいな指導を心掛け図工(表現)を楽しめる、そんな集団(児童)を育てていきたいと思います。
(紙面の都合で、写真をすべて載せることができませんでした。)(註:HPでは写真を掲載しておりません・・・・編集部)
第56回近畿・東海教育研究サークル合同研究集会
第57回兵庫県民間教育研究団体協議会合同研究集会
語り合おう地域・学校・教育。平和を!
子どもたちと共に よりよく生きる確かな学力と、
平和な未来を切り開く力
◆日時 8月25日(土)~26日(日)
◆会場 神戸市勤労会館
◆25日 記念講演
「なぜ学校へ行くの?」から「通いたい学校づくり」へ
講師 山下 晃一氏(神戸大学准教授 教育行政学)
25日全体会・講座 26日分科会が企画されています。
第23回登校拒否・不登校問題 全国のつどいin大阪
◆日時 8月25日(土)~26日(日)
◆会場 エル・おおさか(主会場)・ドーンセンター
講演 「いのちと自己肯定感は愛で育つ」
講師 高垣忠一郎さん(心理臨床家、立命館大学名誉教授)
25日特別講座・分科会
26日基礎講座・分科会が企画されています。
主催:登校拒否・不登校問題全国連絡会
地方教育行政研公開研究会
テーマ 子どもの貧困 お話 仙田富久さん
◆日時 10月13日(土) 13時30分
◆会場 京都教育文花センター 205号
主催:京都教育センター地方教育行政研究会
京都子どもネット結成1周年 学習会&総会
◆日時 9月20日(木)18時30分~20時
◆会場 京都教育文化センター301号
・「子どもの権利条約とは?」
お話 本田 久美子さん(子どもの権利・京都代表)
・「子どもの権利条例を制定している札幌市への視察報告」
日本共産党京都市市会議員
「これからの日本、これからの教育」
~日本と教育の未来を示す憲法の輝き~
前文部科学事務次官
前川 喜平さん 講演会
第一部講演 第二部質疑応答
◆日時 9月29日(土)17時~19時10分
◆京都教育文化センターホール・第2会場
※入場は先着順です。満員の場合入場をお断りする場合があります。
参加費 500円 (京都市教育研究集会全体会)
共催:地域子育て教育ネットワーク京都・京都市教職員組合
2018年度 改訂指導要領を問う 第3弾
道徳教科書の問題点と道徳教育のあり方を考えよう
◆日時 11月10日(土)13時30分~16時30分
◆会場 京都教育文化センター302号
主催:京都教育センター・京都教職員組合・京都教科書問題連絡会
新日本婦人の会京都府本部・京都退職教職員の会