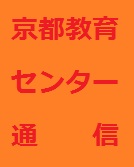
 |
●京都教育センター通信 復刊第125号 (2018.6.10発行) |
教科の魅力・みんなで学ぶことが楽しい授業づくりを
~ 新学習指導要領に向けて ~
安井 芳幸(京都教職員組合教文部長)
私は教育実習指導教官に実習が始まる前、「京都府はこの本のような教え方をしているので、指導案を書く前に読んで勉強しなさい。」と言われました。一時間授業をする度に「形成評価」という小さなテストを自作し、次時の指導案を書くという繰り返しの毎日でほぼ徹夜状態だった私でしたが、昼間の生徒さんたちとの授業や活動がとても楽しく、必ず教員になろうと思いました。
後からその本は「到達度評価」と呼ばれる教育実践で、「質の高い、わかる・楽しい授業」、「すべての子どもに基礎学力をつけること」を目指す教え方・学校のあり方でした。私は理科の実習でしたが、「理科の基礎がわかる」だけでなく、「生徒たちみんなでわかることが楽しい」、そんな授業づくりを先生たちの協働の力で進められているのだと感動に近い思いをしました。このような体験から私の学校での教育実践がスタートしました。
この時期、私はあまり学習指導要領を意識したことはありませんでした。なぜなら通常学校では教科書の内容を、特別支援学校では子どもたちの障害や発達の観点を「指導原案」として、同僚の先生方と話し合ったり各種研究会、サークルでの議論をもとに、自分が毎日行う学習指導を積み重ねていたように思うからです。
私が小学校で働いているとき、たまたま「算数」の研究指定となり、発表会をすることになりました。しかし、私と同僚の女性教員の二人のクラスだけは研究授業を外されました。私たち二人は日常、「水道方式」と呼ばれる指導方法で「タイル」を使って算数を教えていたからでした。教育委員会から視察に来る研究授業の日だけは二人は校庭で「算数ゲーム」の授業を「公開」しました。
教科書の単元を子どもたちの実態に合わせて組み替え、教科書にない教具で毎日教えていたことが「学習指導要領違反」だということでしょうか・・・。こんなことがあっても私たちは毎日元気に、楽しく働いていました。なぜなら子どもたちとの授業や活動がとても楽しく、やりがいのあるものだったからです。
改訂学習指導要領は、告示された当初から新聞などで「学習目標が態度目標になっている・・・、教え方まで規定した縛りのきついもの・・・。」など、さまざまな論点で語られています。これまでの「教育内容の規定」から「資質・能力の規定」へと改変され、「何ができるか、どう使うか、どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか・・・」と、今の日本社会での「生き抜き方」までを規定してしまっています。
近年、学校職場が「ブラックだ」と言われ、教員のなり手が無く、「教育に穴が空く」問題も広がっています。これに輪をかけるように新しい「教科」や活動が提案されています。
教科や「合わせた指導」の内容が子どもたちに合っていて、その基礎・基本がみんなに分かる授業を目指すとき、子どもたちは教科を学ぶ面白さ・学ぶ魅力を体験し、関わり、つながり合って楽しい授業になります。
こんな授業づくりを仕事にする教員こそ、「ちょっとしんどいけど、仲間と一緒にがんばろう」と思える楽しい職業なのではないでしょうか。改訂学習指導要領の言葉に惑わされ、振り回されない授業づくり、学校づくりが求められています。
とまどう先生や子どもたち ―道徳の教科化と授業の実際―
NHKクローズアップ現代+(4月23日放映)
道徳が正式な教科に 密着・先生は? 子どもは?
衣笠 信一(元小学校教員)
NHKが道徳の教科化を取り上げ、小学校の授業(4年・6年)に密着して放映しました。問題点を的確についた優れた内容でした。本稿は番組で浮き彫りになった問題点を整理し、〝現場はどうすればよいか″を考えます。
番組は冒頭で次のように問いかけます。
「―お母さんの愛は無償?監督の指示は絶対?子どもたちは教科書に沿って、家族愛や規則の尊重などについて学んでいきます。でも授業をのぞいてみると、戸惑う先生や子どもたちの姿が…。価値観が多様化する中、国が定めた価値をどう教え、評価するのかー」(傍線筆者)
・(家族愛)4年「お母さんのせいきゅう書」。
・(規則の尊重)6年「星野君の二塁打」。
どちらも8社の教科書会社すべてが掲載している定番教材です。
1.「家族愛」小4「お母さんのせいきゅう書」
| ある朝男の子はお母さんに請求書を渡した。お使い代・お留守番代・お手伝い代など合計500円。昼食時お母さんはその金をくれたが、同時にお母さんの請求書も置いてあった。親切にしてあげた代・病気をしたときのかん病代・洋服やくつやおもちゃ代・食事代と部屋代…合計0円。それを読んだ男の子の「目にはしだいには涙があふれて、お母さんの書いた字がぼうっとかすんで」きた。 |
「お母さんの子どもに対する気持ち・思い、無償の愛を考えさせたい」とする新人の先生は、授業で、「お母さんは、どんな気持ちで、たかし(男の子)に請求書を渡した?」と問いかけます。子どもたちは、「私はたかしにいろんなことをしている。それでもたかしにはお金をもらってないよ。」「私の宝物はたかしだから、お金なんてもらわないよ。」「お金はいらないから、そのかわり、たかしの成長を見せてね。」これらの意見が大勢を占めるなか、1人の男の子が異なる意見を言いました。「子どもっていいな。えらいことするとお金がもらえるから、私も子どもがいいな。」
予期せぬ意見に笑い、ざわつく子どもたち。男の子の机の上のメモには、「私は0円なのよ、お母さんの気持ちになってみなさいよ。せっかく家事とかをしているのに。子どもっていいな。えらいことをするとお金をもらえるから」と書いてあります。お母さんは、家事に対してお金をもらいたいのではないかと言うのです。しかし、先生は男の子に対して、「でも、お母さんは0円の請求書を渡した。お金がほしい、いいなと思うんだったら…」と言葉を返します。他の子どもたちも「たしかに、1円、10円、100円でも書いて渡せばいい」と発言し、この子の意見は残念ながら受け入れられませんでした。家事労働と報酬の問題も含まれる内容でしたがー。男の子はそれ以上発言せずに下を向いて泣いてしまいました。
授業の後、手洗い場で涙の顔を洗った男の子は「お母さんは家事とかしているから、お金をいつももらえないから、お金をもらいたいって気持ちがあってこれを書いた」と言いました。男の子の家庭は共働き。仕事も家事もこなす母親の心を思いやる発言でした。自分の思いを先生にも友だちにも受け止めてもらえなかった悔しい、悲しい涙だったのです。罪深い道徳の授業と言わねばなりません。
授業後、男の子の頭を優しく撫ぜながら話しかけていた新人先生は「普段の生活とか価値観が、子どもたちの中から無意識に出ていると思う、道徳の時間は。一人一人見ていないと(授業が)さばけないと思うので難しい。」と言いました。(傍線筆者)
2.(規則の尊重)6年「星野君の二塁打」
| 星野君は少年野球の選手。チャンスで打席が回ってきたとき、監督に呼ばれました。監督は、確実に1点を取るため送りバントを指示。しかし、星野君は得意なコースにボールがきたため、監督の指示を守らず打ちました。結果は二塁打、勝利に貢献しました。ところが、試合の後、星野君は監督の指示に従うというチームの約束事を守らなかったとして、とがめられます。「チームの統制をみだした」「ぎせいの精神のわからない人間はー」と言って、監督は次の試合の出場禁止を命じます。星野君は深く反省し、なみだで光った目をあげて「異存ありません」と罰を受け入れます。 |
番組の中で、授業を前に先生が同僚と話し合っています。ベテランの先生(授業者)は「『規則尊重・きまりを守る』というところ、そこに収束しにくい」。同僚の若い先生は「星野君の打った気持ちもわかる。ただ、チームとしてはまずいのか考えさせたい。やっぱり最後は、その価値観で落とし込まないといけないと思うと、『星野君の二塁打』は、きまりって大事だと落とし込むのは難しい」。
はたして授業では意見が分かれます。「僕なら送りバントー」と言う子。「―せっかくのチャンスを逃すわけにはいかない。」と言う子。そして、きまりは常に尊重されるかと言う問題になって一人の女子が穏やかな表情で発言します。「地震の時、先生の言うことを聞いてと言ってるけど、自分で判断しないと命に関わることもある。きまりは大事だけどどんなときも守るのはいけないと思う」。「犠牲精神」「上からの指示に絶対服従」「統制を乱すな」とするこの教材の古い道徳思想を超えた見事な意見で授業は締めくくられました。
『規則尊重・きまりを守る』では「収束しにくい」と迷い悩みながら、価値を押しつけない姿勢で授業に臨んだからこそ、子どもたちの柔軟な意見を引き出すことが出来たといえるでしょう。
*「お母さんのせいきゅう書」「星野君の二塁打」両教材の問題点(個人の尊重・家族観・意見表明など)にも言及したいのですが紙面の都合で叶いません。後日、別稿で論じたいと思います。
では、現場ではどうすればいいのか。
まず、中教審・文科省は道徳教育についてどう言っているかを知っておく必要があります。(たとえそれが建前だとしても)「道徳―改善等について」(2014.10中教審答申)「―道徳教育の本来の使命に鑑みれば、特定の価値観を押し付けたり、主体性をもたず言われるままに行動するよう指導したりすることは、道徳教育が目指す方向の対極にあるもの」とし、それを受けた学習指導要領解説では、「答えが一つではない道徳的課題を一人一人の児童が自分自身の問題ととらえ」る道徳へ「変換を図る」としています。
〇私たちが目指す道徳の授業 三つの提言
1.一つの事象を多面的にとらえる授業を。
学年会や研究会で、授業が「価値観の押しつけ」になっていないかと立ち止まって論議をすることから始めます。教職員間の論議を活発にします。
2.多様な意見や考えを自由にの下合う授業を
本当のことを言ってもいい授業。子どもの声を本気で聴き取ります。安心と信頼にもとづく授業の原則です。
3.子どものリアルを大切にする授業を。
事が起こった。そんな時、『キミたちはどうする?どう生きる?』それを考えるのが道徳です。子どもたちは現実生活やリアルな体験にもとに考え出します。多様な意見が出てきて当然であり、どんな発言にも意味があります。そもそも一つの答え(徳目)に絞り込まそうとすることが間違いなのです。
前出の二人の先生から「さばく」とか「最後は―その価値観で落とし込む」とかの言葉が出てきたときには驚きました。しかし問題はその先生個人にあるのではありません。子どもたちが色々意見を出し合っても、結局は国が用意した徳目を教え込むことが道徳の授業だと上から指導されてきたからです。
番組は「道徳の授業の現場では、価値の押しつけにならないかと、戸惑い、悩む先生たちの姿がありました」と締めくくりました。悩まない先生より「戸惑い、悩む先生」の方が良心的です。そこからさらに一歩前進して「論議し、新しい授業に向かう先生たち」になってほしいと思います。(ひろば194号より)
※中学校道徳教科書採択の年です。教科書展示会は、京都市6月1日から、京都府6月15日からの開催です。(詳しくは、市教委・府教委のHPに掲載)現場の先生や保護者、地域の人たちが、教科書を実際に手に取って意見を伝えることが大切です。
憲法改悪を許さず
子ども・教職員が人間らしく生きていける学校と教育を
―2018年度の京都教育センターの活動方向―
1.(1)基本方向
・憲法改悪を許さず、憲法を学校・教育・社会にいかす取り組みを推進する。
・新自由主義と特別な教科「道徳」に象徴される安倍の教育政策に抗して、子ども・教職員が人間らしく生きていける学校と教育はどうあるべきか探究する。
(2)活動の重点
・安倍内閣の教育再生に抗し、憲法と子どもの権利条約の理念にもとづいた教育のあり方を探究し、広める。
・子どもの現状を把握し、子どもの人格形成上の課題を探求する。
・改悪教育基本法の具体化である新学習指導要領のねらいと問題点を学習し、自主的・自律的な教育実践の創造を普及する。
・高大接続、大学入試制度とあわせ、高校教育のあり方について探究する。
・学校・教職員とはどうあるべきか、教職員の働き方も含めて課題を探る。
・地域における学校・教育のあり方を父母・教職員・住民とともに考え、共同を広げ・課題を探る。
-学校統廃合・小中一貫校などの問題―
・原発再稼働・核兵器の危険性と教育のありようを検証し、平和教育を広める。
2.センター体制
・顧問:野中一也・代表:高垣忠一郎・研究委員長:高橋明裕・事務局長:本田久美子・事務局 下田正義
・運営委員(上記含めて16人)川地亜弥子、倉本頼一、西條昭男、築山崇、富山仁貴、中西潔、原田久、深澤司、山岡雅博、安井芳幸、得丸浩一、西田陽子
・「ひろば」編集委員:西條(編集長)、倉本、本田、下田 ・HP管理 浅井
◎ 各研究会事務局 地方(我妻) 生指(横内) 学力(市川) 発達(浅井) 地域(姫野) 高校(原田) カウンセリング(原木) 国語(西條) 障害児(西城)
3.とりくみ
・第49回センター教育研究集会・第27回全国教育研究交流集会合同
2018年12月22日(土)、23日(日)教文センター
・学習会:テーマ「今を生きる教師像を考える-困難な状況の中で-」
6/9(土)13:30~ 職員会館「かもがわ」2階大会議室
・「センター通信」の発行:隔月10日 教育実践の紹介
・季刊誌「ひろば」の発行:5月、8月、11月、2月 定期読者募集中
京都教育センター学力・教育課程研究部会 6月公開学習会
●テーマ: 新学習指導要領のもとで、多様で豊かな学びを実現する条件とは
―学力恵生上の課題と深い学びの追及―
●日時 6月24日(日) 13:30~16:30 京都教育文化センター301号 (参加費不要)
●基調報告 鋒山 泰弘さん(本研究部会代表・追手門学院大学)
●実践報告「深い学び」に関する実践的検討―小5社会科を例に― 瀬川千裕さん(奈良・小学校)
●実践報告「専門職を育てるための基礎学力を」 小野英喜さん(元立命館大学講師)
京都の 子どもたちの今と未来を考える シンポジウム パート2
●6月30日(土) 13:30~16:00 京都教育文化センター 103号
●シンポジスト ・保健師 ・保育園 ・学校 ・養護施設 ・子ども支援の現場
●コーディネ―ター 藤井伸生さん (京都華頂大学)
●主催 : 子どもの今と未来を考えるネットワーク―京都市に子どもの権利条例を―