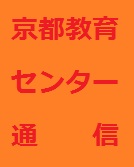
 |
●京都教育センター通信 復刊第123号 (2018.3.10発行) |
センセイたちの京都ふぇすたを通して学んだ
「平和を求めるという当たり前のこと」
高橋 響子(京都教職員組合・青年部部長
先日、2月10日と11日に「センセイたちの京都ふぇすた」を開催しました。この2日間で私が学び、心に残したのは「平和を求めるという、当たり前のこと」と「世の中んじついて無関心にならないこと」です。
全体講演会は、絵本作家長谷川義史さんの「こどもたちに伝えたいこと~〇〇ってすてきだね!~」でした。お話だけにとどまらず、「絵本お読み聞かせ」「ウクレレ弾き歌い」「ライブ紙芝居」とわくわくするような構成と、長谷川さんの「平和に対する強い思い」を感じさせる内容で、本当に時間が経つのがあっという間でした。
「絵本の読み聞かせ」は全部で7冊。その語りは魅力たっぷりで、読んだことがある、知っている絵本なのに、まるで初めて読んだかのような感覚になりました。
全体を通して「当たり前にある毎日」への深い愛がありました。毎日の何気ない家族のやりとり、生活のにおい、家族のおもい、そういったものは特別なものではなく、本当に「日常」の中にあり、その当たり前にある毎日を、当たり前に大切にしよう、というやわらかくも強い思いを感じました。
実践交流会では11の分科会で毎日の教室や職場での実践が報告され、それぞれの実践について語り合い、学び合いました。たくさんの学校で、たくさんの「毎日」があり、そこに生きる先生と子ども達がそれぞれにいるだ、ということを実感しました。それは当たり前のことですが、日ごろ仕事に埋没していると、自分のことだけを考えがちです。たくさんの「毎日」の実践に励まされ、学んだ交流会でした。
2日目の学習講座では、8の講座がありました。ヨーロッパにある日本人学校に勤務された先生のお話は、前日の長谷川さんのお話とつなげ、「平和」への思いを考えさせられました。現地に勤務していた時代に、ヨーロッパ各地を巡って見た戦争の爪痕と、その負の遺産から学び、後世に伝えようとする諸国の様子を教えてえいただきました。思わず目を覆いたくなるような事実の前で、私はどれだけこのことに向き合い、何ができているのだろうかと考えました。自分のことだけに囚われ、行事を「こなす」ことに追われ、社会情勢の変化より明日の授業、そんな風になっている自分が怖くなりました。
私たちの目の前にある「日常」という平和とは、当たり前にあるものではなく、当然、私たちが考えて創っていくものです。長谷川さんは、「人が生まれて、いずれ死んでいくのは自然の摂理です。けれど、その命にはたくさんの命の元に在って、そしてそれが次の命につながっていくーーものすごい時間と、ものすごい命の数の中にいる自分も、周りの人も、それだけでスゴイ」とお話されました。特別なことは何もない、ふつうの日常を大切にする「平和」を子ども達に残すために、誰も殺されず、誰も殺さないという「当たり前なこと」を「当たり前にする」ために、憲法9条の改憲はしてはならないと改めて思いました。そして、そのために世の中のことに関心を持ち続け、「当たり前の平和」を求め続けていこうと思いました。
京都ふぇすたを運営してくださった実行委員のみなさん、参加していただいたみなさん、本当にありがとうございました。
第48回京都教育センター研究集会 第1分科会
《テーマ》「教職員の長時間労働と働き方改革」
報告 京都南部中学校のとりくみ
九条 守(京都府・公立中学校)
はじめに
宇治市に勤めて三四年となる。その間、多くの教職員が、激しい残業、持ち帰り仕事、過密労働に耐えながら、学校と子どもたちのために誠実に仕事に向き合ってきた。「仕事だ」と割り切りながらも、自分たちの家族をも巻き込み、過労による自らの疾患にたえながら、薬を飲みながら、黙々と勤務する多くの仲間、同僚をみてきた。悲劇の頂点は、一九九五年の荻野さんの過労死であろう。しかし、それは、今でも隠れた様々な苦しみの氷山の一角である。それは、今すぐ宇治市の深夜のどこかの中学校を訪れてみればわかることだ。煌々と電気が付き、残って仕事をしている職員が必ずいる。
「労働組合」の意義
私が発言した内容は、「労働安全衛生委員会に、労働組合の代表が入れるはずなのだが…」という内容だった。
学校長は即答を避け、教育委員会に問い合わせ、労働安全衛生委員会の構成メンバーに、労働組合の代表が入れることを確認し、協議の上、私を構成メンバーに入れてくれた。企画の中では、「あの人は日教組なのですか」という発言もあったようだが、「まあまあ、法に基づいて存在している組織なのだから」と管理職から説明がなされたという。ここでも、長年、行政と組合が信頼関係を構築してきた成果が反映しているように感じる。宇治の中学校で、全体としては、各校で労働安全衛生委員会の枠が作られているが、その内実が問われている。労働組合の構成員が少なくなっている中、積極的に関わりを作れている学校は少ない。それでも、私は各中学校の若い人たちに何かを感じてほしいと発信を続けている。
「労働安全衛生委員会」の開催
どこの中学校も、深刻な残業の中身に、クラブ活動がある。一昨年転任して最初の夏が過ぎようとしていた頃、管理職から申し入れを受けた。労働安全衛生姜委員会を開きたい、と。かねてより、学校長は、クラブ活動について「教育課程外の教育活動である」、と主張してきた。
「クラブは、先生の主たる仕事ではないこと、教職員の前でも子どもたちの前でも話しをしていた。ちょうど折しも、地域から、「なぜもっとクラブをやらないのか、賞を取れないのは校長の責任である」という趣旨の批判が寄せられていた。「土日にクラブをして普通」という感覚に学校長が首をかしげた。様々な意見や議論を踏まえ、この件について、クラブ活動を原則として、土、日のどちらか半日とする、という原案を労働安全衛生委員会で確認した。文科省の働き方改革の追い風を受けているとはいえ、まだ、府の方針が下りてくる一年前の出来事である。まだ、クラブ活動を学校の柱として熱心に推しすすめる管理職が少なからずいる中、計り知れない影響を及ぼしたものと思われる。
学校長曰く、「クラブを熱心にやることが子どものためという時代ではなくなっている」のである。私は、三〇数年前、この学校で競い合って朝から晩までクラブ活動をおこなってきた。勝たなければ、学校での発言権もないように感じた。家族を犠牲にし、自分を犠牲にして、過酷な競争に身を投じ、クラブをやり続けた。もう、このような時代ではなくなっている。何という大きな変化だろうか…。
残業、過密労働の解消のために
学校ができることは何か
労働組合との協議の中で、クラブだけではなく校務そのものを見直すことを学校長とかねてから意見交換してきた。その内容は、企画委員会でも協議された。夏の研修会で、校務分掌ごとに削減できる内容がないか議論しよう、というものであった。夏休みの研修で、このような内容を議論したことはない。結果、実際にはあまり成果はなかったが、それでも、削減できるものはカットの方向に動いた。このような議論ができる場がもてたこと自体が画期的なものであった。
続いて昨年度一〇月、府の方針ではじめて本格的な残業時間の精密な調査が全小中学校でおこなわれた。私の記憶する中で、出勤時間から、退勤時間まで、土日も含めて全員を対象に調査したのははじめてのことではないかと思う。
この調査の結果、本校で、八〇時間を越えたものが四割、さらに一二〇時間を越えたものが六名に及んだ。
その申し入れを受け、労安委員会が開催された。八〇時間を越えたものを上記と同じ内容で公的に確認し、その解消のための手立てを具体化した。私たちはクラブ以外の残業の内容にも踏み込み、微々たるものではあるが、職員討議の上、テスト前の放課後、生徒を残さない日を二日間設定することにした。残業記録も継続されることになった。
今後の課題は何か
私たちが学校でやれる活動は微々たるものである。問題の抜本的な解消は四〇人学級そのもの、そして、膨大な量の残業を公的に認めさせることである。なぜ、残業代が支払われない労働が存在するのか、調整手当とは何か、次から次へと若い教職員から疑問が寄せられるようになった。できるだけ丁寧に疑問に答えながら、膨大な量の過密労働、残業が解消し、子どもたちをゆったりとみることができるようになってこそ、真の働き方改革となり、地域父母の学校や教師への信頼を高めることにもつながると訴えている。まだまだ不十分な状況の中、日々の残業、過密労働は続いている。宇治久世教組は毎年の定期大会で荻野さんのコーナーを企画し、若い人たちに事実を伝え、二度と過労死を起こさせない誓いの場としている。ここを出発点に、職場づくりを進めているところである。
京都教育センター 2017年度活動の報告
新学習指導要領の問題点を明らかにし、発信しました
1.第48回京都教育センター研究集会
・12月23・24日(土・日)、集会テーマ「憲法施行70年、今こそ憲法を生かす」を掲げ、「いまこそ語ろう!憲法、核兵器、教育―“個人の尊厳”を手がかりに」冨田宏治講演、「教育ってなんだろう」をテーマに教職員が現場の状況や思いを語った。参加者は全体会72人、分科会113人。
2.公開研究会の開催
各研究会が企画開催した研究会は10回開催した。センターとして以下の学習会に取り組んだ。
「学校・教師の今、苦悩と希望を考える」久富善之(一橋大学名誉教授)6/10
「自治の力で、地域を守る―今に生かそう、番組小学校」11/19(京都教育センター・自治体問題研究所共催)
新学習指導要領連続学習会を、京教組、教科書連絡会、新日本婦人の会と共催で取り組んだ。
第1弾 「どうする!子ども不在の新学習指導要領」 俵義文さん 3/20
第2弾 「特別の教科 道徳は、どんな子どもを育てようとしているのか?」石山久男さん 5/27
第3弾「新学習指導要領による人格支配と選別的教育制度作り」 中嶋哲彦さん 7/22
第4弾「教科化された道徳への向かい方」 碓井敏正さん 10/21
第5弾「新学習指導要領改訂と総選挙後の教育をめぐる情勢のゆくえ」 中田康彦さん 11/25
第6弾「学習指導要領が変わると子どもと学校はどうなる?」 1/27
3.教育研究集会・民教委、民研などへの参加
・ 第67次京都教育研究集会(「教育のつどい2017」)(1/27~28:教文センター他)には共同研究者・世話人として二日間でのべ80人が参加し各分科会での任務を果たした。
・ 8月の「全国教育のつどい(岡山)」に2人が参加しました。
4.季刊誌「ひろば・京都の教育」の発刊
・190号(5/1) ①教育をどう変えようとしているのか-改訂学習指導要領の問題点
②悩んで、笑って、子どもに学ぶ
・191号(8/1) ①地域で育つ子どもたち ②障害児教育の今
・192号(11/1)①学校・教師の今、苦悩と希望を考える
②「特別の教科 道徳」は、どんな子どもを育てようとしているか
・193号(2/1) ①憲法施行70年、今こそ憲法を生かす ②教職員の長時間労働と働き方改革
5.「センター通信」の発行 今年度より隔月発行とした。〈2017年度執筆者一覧〉
116号
117号 高垣忠一郎/仙波尚子(事務職)
118号
119号 西城信幸/兼田 幸(京生研)
120号 富山仁貴/堀 徹也(市高)
121号 西條昭男/野中明子(栄養教諭)
122号 高垣忠一郎/センター研概要
123号 高橋響子/九条 守(府内中学校)
6.出版活動
森友学園の幼稚園児が教育勅語を暗唱が話題になり、今の教育情勢を知らせる「最近何かヘンではないですか?」教育緊急パンフレットを発行した。教職員、地域での学習会などで活用された。これまでの出版物の普及。
7.研究活動
「地方教育行政」「生活指導」「学力・教育課程」「発達問題」「子どもの発達と地域」「家庭教育・民主カウンセリング」「高校問題」「教科教育・国語」「障害児教育」の9つの研究会があり、それぞれ独自に研究活動を展開している。研究会員募集中。
8.事務局・運営委員会体制
代表:高垣忠一郎 顧問:野中一也 研究委員長:高橋明裕 「ひろば」編集長:西條昭男 事務局長:本田久美子
運営委員(上記含め): 築山 崇、 川地亜弥子、 倉本頼一、 下田正義、 原田 久、 中西 潔、 大平 勲、
深澤 司、 富山仁貴、西田陽子、得丸浩一、 團野三千代