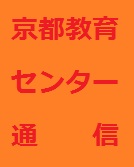
 |
●京都教育センター通信 復刊第119号 (2016.7.10発行) |
「特別支援学校の学習指導要領改訂の論点」
~「京都の障害児教育が大切にしえいること」~「京都障害児教育研究センターの5年間の活動と目指したこと」~より~
西城 信幸(京都障害児教育研究センター)
平成32年度から「新学習指導要領の円滑な実施」が言われていますが、井手町に新設される「南部新設支援学校」は、新学習指導要領とともに生まれ、その実施の基幹となる学校といっていいでしょう。その開校コンセプトは、「インクルーシブ教育システムの構築を実現する特別支援学校」、「共生社会の推進や地域振興を担う特別支援学校」です。
「地域振興」という言葉や「共生社会の実現」は特別支援学校の在り方の具体化であり、地域に貢献する学校を目指すことの現れです。施設設備の基本方針で示されている事柄は、中央教育審議会「特別支援教育部会における審議のまとめ」で示された、「交流および共同学習」で示された「地域社会の人達とのふれあい」や「オリンピック・パラリンピック」、「開かれた教育課程」の構想を具現化したものです。又「遊ぶ力」、「生きる力」は、学習指導要領が示す教育の目的や教科領域を合わせた指導を意識したものです。
問題となるのは、開校コンセプトでは示されていない、目標に準拠した評価という課題にこの学校がどのように迫るかです。既存の学校でも、すでに次期学習指導要領に向けた取り組みが始まっています。京都府立八幡支援学校が行った2016年度の公開研究会では、「次期学習指導要領への展望を踏まえ、これからの特別支援学校の教育課程や授業」を考える機会とするとしています。また、京都府内でも指導案の作成において、観点別学習状況の評価を盛り込んでいる学校が出てきています。
今、問題となっていることは、学習の形態(合わせた指導、教科領域別の指導)ではなく、教育内容であり目標なのです。言い換えれば、実践を考える始まりはどこなのか、準拠すべきはどこなのかということです。判断の材料は、教育実践であり、教育的事実であると考えています。
目標に準拠した評価は、学習指導要領等で示した教育目標にしたがって授業を行うということであり、授業作りの出発点が、学習指導要領に示された教育目標にどのように到達するのかが始まりとなるということです。
京都の教育実践は、子どもを丸ごととらえ、そこからその子どもたちの発達上の課題はどこにあるのかを考え、教育目標を立て授業つくりをしてきました。その出発点が全く違ったものにしていくことがこの学習指導要領の改訂では明確に示されているのです。この点が一番重要な問題点ではないかと考えています。このことは、教育における評価というものを根本的に変えていくのではないでしょうか。子供たちが示すパフォーマンスを評価基準に合わせて評価をする、児童生徒は評価の対象、教師は評価者という二極化した構造を教室内に持ち込むことになります。本来、教育評価は、教育実践の評価でもあり、教育実践を総括していく役割も果たしていくべきものです。一方的に子供たちを評価していくものではないのではないでしょうか。
また、教職員の実践に対して、それぞれの授業の目標は学習指導要領の示す目標と関連しているのか、実践の過程でどのようなパフォーマンス課題を設定し、児童生徒が示すパフォーマンスを評価基準に合わせてその出来・不出来で評価をしていきます。結果として、目標に児童生徒を到達させることができたのか、できなかったのかということが、教師に対する評価の基準となっていくのです。日々の実践は管理され、自由な発想は委縮していくのではないでしょうか。
支え合いながら、自立へ向かって
~絵里子と歩んだ二年間~(後半)
京生研 市内サークル 兼田 幸
■絵里子の自立へ向けて
学習環境づくりとして、フリースクールの付近にある施設を絵里子との学習の場として解放して頂く手続きを管理職に頼み進めた。絵里子の家に学習環境がないため、学習支援が難しかった。六月より自宅付近に学習部屋が確保でき、木曜日の放課の時間に、絵里子の学習支援をはじめた。
また、夏休みはプール補習でF子と一緒になり、昨年後半の不和を解消するきっかけになった。週末にF子が高校見学に行く話しをしたので、二人をつなぎ進路を考えさせる良いチャンスだと思い、私が案内するから、絵里子も一緒に行こうと誘って、三人で高校見学へ行った。
動物好きというところが、二人の共通点でトリマーの講座を楽しんで受け、振る舞われたカレーを食べて帰った。それ以降は、自分たちで約束して高校見学に行くようになった。
夏休みの課外活動では、昨年からつながりを作ってきたお菓子作りの会のH男、R太と絵里子とF子が再結集し、川遊びとバーベキューを満喫した。前日は、「遠いし行きたくない」と連絡があり、「疲れたらH先生の車で先に帰ってもいいんやで!」と応答した。当日はR太がカバンに水風船を、H男が水鉄砲を入れて、ワクワクしている様子。気の乗らない女子を前向きなムードに変えてくれた。私を散々川に引きずり込んで水をかけてくるなど、普段はおとなしい四人だが川辺では大はしゃぎだった。
■小集団を本拠地として
その後、放課後取り組みで、「アイスクリーム作りの会」、「ラングドシャ作りの会」などを実施し、四人にA男やY男やA子も交えて和やかに取り組んだ。アイスクリームは、塩と氷でボールの中身を凝固させていく企画だったが、なかなか固まらずA男と絵里子がひたすら混ぜ続け、企画者H男は「みんなごめん~先生も材料買ってくれたのに無駄にした~」と懺悔していたが、タイムアップ直前に、「固まってきた~」と絵里子が叫び、みんな「わぁ!すご~!」と歓声をあげた。
役割分担も自然とできるようになり、ラングドシャの会では焼けるまでの時間、A男とR太がお笑いの芸を披露していた。お菓子作りの会のメンバーは学年の中でも、二年間ほとんど全欠のF子、長欠のY男、学級で浮いてしまい休みがちなR太、母子家庭で学習低位のA男、家庭の不和により家出を繰りかえしてきたH男など、バラエティー豊富な顔ぶれだ。
そのメンバーの普段見られない表情が見られると、学年の先生方もたくさん覗いて下さって協力して下さり、安定した取り組みとなっていった。自分たちのLineでもつながり、互いに誘い合うようになり、九月以降、絵里子は週に数回別室での学習に登校するようになった。そして、放課後の学習会にF子とA男と参加するなど、大集団は苦手だが、小集団では活動するようになってきた。
十月は進路に向けて本命のT高校(通信制)の見学に、駅前で待ち合わせ絵里子と二人で出かけた。説明を聞きながら、絵里子の顔が明るかったので「どうだった?」と聞くと「ほとんどここで決まりやな。」と言った。そのことが動機となり、毎週とは行かないがフリースクールが休みの水曜日を中心に学校へ足を運ぶことが増えた。昼休みはいつものメンバーと和やかに過ごしており、他にも友人が少しずつだが広がっていった。
進路写真の撮影は、絵里子は前日「行きたいし行けんねんけどなんかゆわれたらどーしようとか、行きたないって気持ちが強なって行く。それでも撮りたいって気持ちはあんねん絶対撮りたいってゆう気持ちな?みんなで写真撮れるのもあと少ししかないし、正直焦ってる」といった。「焦ることない。チャンスはいっぱいあるよ。」と伝え、「翌日が無理でも、放課後撮影会をしような」と約束した。
翌日は「フリースクールに行きます。みんなには一緒に写せへんかったけどまた教室に行ったら普通に接してって伝えて。」と絵里子から連絡があった。N男とR太の欠席もあり、再撮影の一週間後にみんなで取り直そうということになった。前は「やっぱり不安。嫌になってきた」と言っていたが、評議員のS子が作った撮影ポーズのメモを見て、「行けそう。」と言い、当日は昼頃に登校した。
別室にいる絵里子に、「教室でビデオの最後だけ一緒に観て、みんなと写真を取りに行こう。」と呼びかけた。絵里子が「もう心は教室に行ってる。身体が動かへんねん。」と言ったので、「無理にとは言わへん。けど、教室行ってから写真撮りたいって絵里子言うてたやん。」と声を掛けると、自分で教室へ向かって歩き出した。
ビデオを見終わると、N男とR太が再撮影の場所へ絵里子を連れて行った。卒アル用は笑顔の写真を撮るのだが、写真嫌いのR太はちっとも笑えない。絵里子と一緒に変顔をして必死に笑わせようとした。引きつって不自然な笑顔だったがなんとか写せた。すると仕返しに、R太が絵里子の撮影時に「ウーパールーパー」とお笑いネタを披露。あまりに意外な行動に絵里子は大爆笑。私はR太の変化に驚いた。その後、みんなでグループ写真を撮ることができた。撮り終わってからも女子のグループで「先生、もっかい撮って~」と楽しそうな笑顔の絵里子が見られた。
■絵里子のケンカと仲間関係の深化
いつもの企画、今回はプリンの会。いつも通り和やかに過ごした。しかし、帰り際に絵里子は泣きながら怒っている。F子は「A男が悪いねん。絵里子にひどいことばっかり言ってた。」と絵里子を弁護。A男も呼び、話すと絵里子はすごい剣幕でまくしたてた。A男もカッとなり一触即発。そこに我関せずという行動をしているR太。絵里子の怒りはR太へも向く、しかしR太は取り合わない。
H男はなんとかその場をとりもとうとするが、よけいごちゃごちゃになる。時間は最終下校をとっくに過ぎ、あたりは真っ暗。私は仕方なく、論点だけ整理して、ケンカは持ち越しになった。絵里子が初めて、本気で怒ってぶつかったことに、この集団がやっと仲間になりつつあると思い、R太の無関心な行動を批判し、時間がかかっても、自分たちで解決して行こうとH男とF子と約束した。
A男と絵里子は、その後も個人でケンカを継続した。冬休み前に、メンバー全員で話し合う場を持ったが、絵里子は参加できず、F子が電話でのやりとりをすることとなった。その場で、これまでのお菓子作りの会で一人一人が考えていたことが出された。A男は、「やるからにはみんなで分担とかもちゃんとしてやりたい。手伝わずに自分勝手に過ごすのは違う。絵里子の言い分は半分分かるけど、納得してない。」と言う。H男は中心となりケンカの経緯を整理していく。R太は「受験がめっちゃ不安やし、勉強はストレスたまる。お菓子作りの会の時間はテンション上がりまくってて、周りみてなかったし、今の聞いてて悪いと思った。」と言って謝った。それぞれに相互批判し合いながら、いつまでも話し合っていた。そして、私の心配をよそに、彼らは冬休み中に、自分たちで絵里子をカラオケに誘い出し、話し合いを持ちこの一連のもめごとを解決した。
お菓子作りの会は、はじめは学級の有志の仲間で取組んだが、次第にこの会を自ら居場所とする生徒たちに移り変わっていった。それぞれに、生きづらさを抱え葛藤している子どもたちだ。生育史の中で、ネグレクトや虐待による人に対する基本的信頼感の欠如。それゆえ、他者への交わりの力の脆さが気になっていた。
人間関係のぶつかり合いは疲れるししんどいし、なるべくなら避けたいものだ。関係を断絶すれば傷つかずに済む。絵里子自身はこれまで、些細なことでもすれ違うと関係が途切れてしまっていた。そんな絵里子が初めて、自分たちの力で修復し、関係を積み上げることができた。
■旅立ちの時
絵里子への最後の学活は、もう誰も居なくなった教室で、八人の学年の仲間と共に。二年間の思い出ムービーには、お菓子作りの企画のたびに写してきた、絵里子とこの仲間たち。アイスクリームが固まらず苦戦する表情、出来上がったお菓子を囲む幸せそうな笑顔、一瞬一瞬を捉えた写真に懐かしみながら、みんなの笑顔が弾ける。
その後のスピーチでは、一人一人が仲間へ向けて、思いの丈を打ち明ける。一緒に最後まで参加して下さった、H先生が、「あの子たちが、こんなに喋るとこ、初めて見た。」とつぶやいた。
校長室で、八人の友人と学年教職員に見守られ、絵里子に卒業証書が授与された。校長室に響く、ささやかな校歌斉唱。私は、「卒業おめでとう。絵里子の未来に、幸せをいっぱい創っていこうな。」というと、涙がとめどなく流れた。
「一人で卒業証書を貰って、一人で卒業する。」と宣言していた絵里子。今、絵里子に対して、「お前は自己中なとこあるし、気分の波が激し過ぎやしな。でもな、絵里子が笑ってないと、俺らおもんないねん。」と、ストレートに言ってくれる仲間がいる。
| 京都教育センター「家庭教育・民主カウンセリング研究会」 公開研究会 民主カウンセリング・ワークショップ ◆日時 7月日(月)海の日時~時(受付9時分~) ◆場所 京都教育文化センター 204号室 ◆内容 エンカウンター・グループ 人間中心の出会い・ふれ合いのグループ経験によって、人間信頼・受容的態度・教官的理解などの集中的体験学習を行います。 |
| 新学習指導要領を問う!第3弾 どうなる?こどもと教育 ~人格の完成でなく、人材の育成で、日本の子どもたちは?~ ◆日時 7月日(土) PM1:30~4:30 ◆会場 京都教育文化センター302号 ◆内容 講演 新学習指導要領による人格支配と 選別的教育制度づくり 講師 中嶋 哲彦氏(名古屋大学教授) ✱全国学力テストの内容分析の報告もあります。 ✱小学校英語・全国学力テスト体制についても討論しましょう。 主催: 京都教科書問題連絡会・京都教育センター 京都教職員組合・新婦人の会京都府本部 |
| 音楽教育の会第回全国大会 ◆日程:7月28日(金)~7月30日(日) 後援:福知山市 ◆会場:福知山市三段池公園総合体育館 京都府教育委員会 内容:※歌います(参加者みんなで歌う) 福知山市教育委員会 ※子どもたちの歌を聞きます。 ※リズム表現をします。 ※演奏を聴きます。 《詳しくは音楽教育の会ホームページ参照》 |
| 第48回全国臨時教職員問題学習交流集会in京都 つながろう広くつなげよう未来へ ~“正規が当たり前”に!!~ ◆とき 2017年8月10日(木)~12日(土) ◆ところ ホテル・ルビノ京都堀川 主催: 臨時教職員制度の改善を求める全国連絡会 京都集会現地実行委員会 《詳しくは京教組ホームページ参照》 |
| 第6回京都障害児教育夏季研究集会 ◆とき 2017年7月29日(土)~30日(日) ◆ところ 京都教育文化センター ◆内容 29日13:00~13:30 開会の集い 13;40~16:30 講座①「わたしとあなたをつなぐ発達を考える。」 講座②「発達障害の児童生徒に対する実践や保護者の抱える課題」 30日 10:00~16:00 分科会 主催:京都障害児教育研究センター 問い合わせは府立高教組 ℡ 075-752-1645 |
| 近数協2017年夏季研究集会&数教協全国中学校研究集会 ◆とき 8月26日(土)~27日(日) ◆ところ 京都 同志社中学校 ◆内容26日 ①小学校・中学校講座 高校レポート報告 ②講演 カタカナ語教育学と数学教育の現況 小島 順氏(早稲田大名誉教授) ③シンポジュウム 「どう創る?わかって楽しい算数・数学の授業」 27日 校種別分科会 《詳しくは近数協ホームページ参照》 |