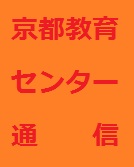
 |
●京都教育センター通信 復刊第111号 (2016.9.10発行) |
「オリンピック」が学校の中にもやってくる?
大味 祥恵(京都市教職員組合書記長)
去年の春ごろ、同じ学年の先生たち5人で雑談をしているときに話題が「東京でオリンピックすることどう思う?」ってなって、被災地支援に足繁く通っている青年がまず「そのために東北の復興がますます遅れるのが許せない。」と言い、他の人からも「福島原発がアンダーコントロールされているなんて大嘘!」など…結局「やめたらいいのになあ。」と5人で一致したことを覚えています。
今、リオのオリンピックが閉幕し、2週間後からパラリンピックが始まるというタイミングでこの原稿を書いています。開催期間中は、テレビはどこをつけてもオリンピック。メダルラッシュに沸き、選手だけでなく家族までもが大きく取り上げられる報道ぶり。「君が代」を声高らかに歌う姿や決勝戦で負けて「ごめんなさい。」と泣く吉田選手の姿に違和感を覚えながらも、手に汗を握って試合の様子を見守ったり、夜中まで見てしまったりしてしまう自分もいて、知らず知らずのうちに次の東京オリンピックへの期待が高まっています。
さて、学校の中にもこの東京オリンピックが入ってきていることを知りました。すでに東京では、「オリパラ教育」といって年間35時間の授業が義務づけられ、取り組んだ学校には予算が下りてくるということになっているのだそうです。始まったばかりで手探り状態と言われていましたが、この「オリパラ教育」は、きっと日本中に広がり、「日本の伝統を重んじる」「国民の団結」などが、学校の中でも強調されることが考えられます。
オリンピック憲章の中には、「オリンピニズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会を奨励することを目指し、スポーツを人類の調和の取れた発展に役立てることにある。」「スポーツをすることは、人権の一つである。(中略)オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる。」と書かれています。
「リオのオリンピックの開会式。地球の裏側の日本では、8月6日の午前でした。8時15分という時間に合わせて日本を紹介する出し物がされました。ブラジルの演出家は当初その時間に黙祷することも考えられていたそうです。」そのことを教室で子どもたちと話し合った先生がおられます。押しつけの「オリパラ教育」が下りてくる前に、平和やフェアプレーの精神を伝えるようなわたしたちの「オリパラ教育」の実践を先行することが必要だと思います。
みんなで21世紀の未来をひらく教育のつどい 教育研究集会2016
美術教育分科会 3年の「かさこじぞう」
乙訓教職員組合 H・M(青年教師)
1.絵の題材を決めるまで
夏休み明けの学年会。「9月と言えば絵」ということで、何を題材にするか学年で話し合った。しかし、「全国美術展に出品しなければならないから」という考えが土台にあるため、子どもの生活からではなく見栄えのする題材ばかりを探す傾向かあった。
学年会で候補にあがったのは、「かさこじぞう」だった。理由は、「全時の指導内容が載っている資料があるから」。教師主導の授業で、果たして子どもたらは生き生きと描けるのかと不安になった。自分が描きたい場面を描きたいように描いてほしい。自分の絵の良さを知り、絵を描くことを楽しんでほしい。
学年とは方針が一致しないまま、残暑厳しい京都で真冬の絵を描く授業が始まった。
2.授業の流れ
第1時 読み聞かせ
| 「かさこじぞう」は、2年生の時に文学の授業で学習している。「知ってる~」と言う子がたくさんいたが、読み聞かせのときはみんな真剣に聞いていた。 読み聞かせの後は、イメージを深めるため話し合いをした。友達の意見を聞いて、新しい見方を見つけてほしいと思った。 |
「どの場面、誰が何をしたところが好きですか。その理由は?」
→あまり意見が出なかったので、班での話し合いに。
「班で、どの場面がすきか話し合いましょう。」
「では、好きな場面を教えてください。いくつでもいいです。」
・かさを売りに行くところ。ぱあさまのために一生懸命で、優しい。
・じぞうさまの雪をはらってあげるところ。雪は冷たいのに、手袋もなく雪を落としてあげるのは優しいから。
・じそうさまに、かさこをかぶせてあげるところ
・じぞうさまに、手ぬぐいをかぶせてあげるところ
・家に帰っても、ぱあさまが怒らなかったところ
・もちつきのまねをしたところ。二人が優しそうだから。
・じぞうさまがお礼をしにきたところ
「その場面を絵に描きます。1つ決めてください。」
・後で変えてもいいの?
「いいよ。今、絵に描きたいと思っている場面を教えて。」
| 最後の場面で、お地蔵さまがお礼をしにきたところが一番多かった。 理由は、「お地蔵様がやさしいから」とのこと。 |
第2時 お地蔵さまを描く
| 「子どもはお地蔵さんなんて知らんから、そのまま描かせたらアニメみたいなお地蔵さんになるで。」とアドバイスを受け、慌てる。 授業時間を使って子どもと一緒にお地蔵さんを見に行くことを提案したが通らず、仕方なくお地蔵さんを描く練習をすることにした。 |
「白い紙に、自分の思うお地蔵様を描きましょう。」
・え~、わからん!
・お地蔵さまって、手ってどうしてだっけ?
・手に何か持つてるかな?
「予想でいいから描いてごらん。」
「何人かに黒板に描いてもらいます。」
→顔・耳・手・体など、違いを見ていく
「友達の絵を見て、直したいところがあったら描き加えましょう。」
「お地蔵様の写真を見て、自分の絵と比べます。」
「写真を見て、自分の絵に描き加えます。裏に描き直してもいいです。」
・おでこに丸いのがある!
・人の顔みたい。
・鼻すじが長い!
「学校の近くに、本物のお地蔵さんていたっけ?」
・いるよ!古墳の上!
・大通りから病院に入る曲がり角の所。
・うちの裏のお墓にいる。何人かいる。
「見に行ってみようか?」
| この日の放課後に、近くのお地蔵さんを見て回った。急な提案にもかかわらず、7~8人くらい集まった。子どもたちはお地蔵さんに触って、「つるつるしてる~」と言っていた。 お地蔵さんに足があることを発見した。中にはカメラを持ってくる子もいた。次の授業のときに、写真を持ってきてくれた。学童の子や用事があって行けなかった子は、後日おうちの人と一緒に見に行ったようである。 |
第3時 好きな色作り 黒の画用紙(色画用紙)に絵の具がどのようにのるかをためす。
「色の感じがいつもの白画用紙と違うので、小さい黒画用紙に色を塗る練習をしましょう。自分の好きな色を見つけましょう。」
・先生、見て見て!こんな色ができた!
・なんか、汚くなってきた。
・これ、お地蔵様の色にすんねん。それで、これはじさまの服の色。
第4時~ 色塗り
「大切なところから塗りましょう。お話の中で大切なところはどこですか。」
・かさこ。題名にあるから。
・じぞうさま。題名だから。
・雪。たくさん降っているから。
| 集中力を持続させるため、「今日はもう終わり」と決めた人は、片づけて読書の時間にした。毎回授業のはじめに時間をとって、全員の絵を1枚1枚紹介した。頑張って塗ったところや、本人の思いが学級に伝わるように心がけた。 |
第7時 絵を文章として記録に残す。
「なぜこの場面を選んだか、心をこめたところなどを、文章に書いてください。できたら絵の裏に貼ります。」
「何年かたって絵を見た時に、どんな思いで描いたか思い出せるように。せっかくがんばって描いた絵だから、言葉でも記録に残そう。」
・(最後の場面で)お地蔵さまが笑って喜んでいるようにした。
・じさまとばさまが地蔵様を見送っているのがわかるように、後ろ姿にした。
・地蔵さまとじさまを大きく描いた。かさの色を工夫した。
・ない
・これ書いてるのって、うちのクラスだけなの?来年もあったらいいのになあ。
3.全国美術展のこと
美術展の審査の結果、自由に描いた私のクラスの絵はすべて落選。すぐに絵が戻ってきた。しかし、教師主導で描いたクラスの「上手な」絵はすべて通り、次の審査へと進んだ。
「絵を描く」とはどういうことなのか。教師が思う絵を子どもに描かせ、上手に仕上げることが私達教師に求められているのか。
ここでいう全国美術展とは、良いか悪いかの単なる「評価」でしかないと思う。「美術展に出品されたら、子どもは嬉しいし自信をもつ。」という人がいるが、その陰にはたくさんの選ばれなかった子どもたちがいる。その子が絵に込めた思いは、「どうせ自分なんか選ばれない」で終わってしまう。
絵は、「評価」ではなく「共感」でありたいとつくづく思う。絵を見ながら「よく描いたね」「これは何を描いたの?」「とてもいい顔をしているね」と声をかけてあげあたい。子どもにとって、それはどこか遠くの審査員ではなく、先生やお父さんお母さんであってほしいのではないか。
4.振り返って
「どこの場面?」「これは何?」などと声をかけると、子どもだちからいつもたくさん答えが返ってきた。「先生見て!上手に描けた!」という子どもの声に応えるだけで、毎回の授業は終わっていった。
三十三人の子どもの絵には、三十三通りの思いが込められていた。好きな場面を選ぶのに時間をかけた子、かさこの紐の色を十分ちかくかけて悩みやっと納得できる色を作れた子、吹雪を表現するために全面真っ白に塗った子。
学年が終わり四か月が過ぎた今でも、絵を見ると一人一人の顔や描いている様子が浮かぶ。もしこれが、一斉に同じ絵を描かせていたら…。見栄えを重視していたら…。
この「かさこじぞう」は、私にとって忘れられない実践となった。
2016年度 第2回 京都教育センター地方行政研 拡大学習会
テーマ 「18才選挙権と主権者教育の課題」
◆日時 9月3日(土)13時30分~16時30分
◆場所 教文センター 203号室
◆内容 報告
①2016年参議院選挙の状況と今後の課題 市川 哲
②主権者教育の具体的展開を構想する…杉浦 真理
③高校生の政治的教養と「政治的中立」を考える…我妻 秀範
2016京都市教研実行委員会&学習会
講演 「自民党改憲草案と強まる教育介入」
講師 渡辺輝人弁護士 〈京都第1法律事務所〉
◆日時 9月3日(土)13時30分~15時30分(講演及び質疑)
15時40分~16時30分(各分科会打ち合わせ)
◆場所 教文センター 203号室
講師紹介
「渡辺輝人弁護士は、全教弁護団・市教組弁護団の一員として、新採者の文言免職処分取り消し裁判(全面勝利)。また、18歳選挙権の問題や今回の自民党の「密告フォーム問題でも、積極的に発言されています。
京都教育文化センター第52回公益事業 子どもの育ちを考えるつどい
◆日時 9月25日(日)13時~17時
◆会場 教育文化センター ホールほか会議室
◎全体会
ミニコンサート 出演 MOONDAY
講演「子ども・若者の生きづらさと自己肯定感」
おはなし 高垣忠一郎(心理臨床師・京都教育センター代表)
◎語り合う分科会 ①小学校 ②中学校 ③高校 ④青年
2016年 第1回 京教組・京都教育センター地方行政研 合同学習会
テーマ 「子ども達とともに、こんな教育・学校をつくりたい」
―新学習指導要領移行期前に取り組むことを考えるー
◆日時 10月15日(土)13時30分~16時30分
◆場所 教文センター 会議室 101号室
◆内容
講演「中教審の『審議のまとめ(案)』を検討する」
講師 中田 康彦氏(一橋大学教授)
報告 中教審「審議まとめ(案)」の資質・能力」の強調を批判的に検討する
安倍内閣「憲法改正」の動きを教育現場から考える
他(検討準備中)