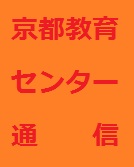
 |
●京都教育センター通信 復刊第110号 (2016.7.10発行) |
地域に根ざした学校づくりが地域の未来を切り拓く
中久保 弘志(京都教職員組合書記長)
美山町が南丹市に、京北町が京都市に合併され、「北桑田」という呼称が薄れゆくなか、私の母校でもある「府立北桑田高校」は、北桑田地域にとって極めて重要な存在である。
私は、12年ほど前に北桑田高校のPTA本部役員を務めた。高校のPTAではあるが、子どもたちを全力で応援しようとさまざまなとりくみをすすめた。その一つとして、北桑田高校の存続・発展を願う地域の思いを発信するため、「北桑田高校の未来(あす)を創る会」を発足させた。地域に根ざした北桑田の教育を推進するという、先人が北桑田高校設立時に託した思いを受け継ぎ発展させるために、今日まで年1回の集会を続けてきている。地元の中学生による発表、北桑田高校・美山分校生によるとりくみの発表、卒業生による講演など、地域の教育力を確認し再発見するとりくみとして、行政をふくむ地域ぐるみですすめてきている。小規模校であっても、いや、小規模校であるからこそ、キラリと光る教育をすすめている北桑田高校への地域住民の思いは熱い。府教委が府立高校の統廃合をすすめようとしている今日、このとりくみの意義はいっそう大きくなっていると思っている。
北桑田地域における学校統廃合問題は、常に「北桑田の教育はどうあるべきか」という根本的な課題を住民に投げかけてきた。その課題を住民は真正面から受け止め、考え、私たち教職員とともに地域づくりの観点からとりくんできた。とりわけ美山町では、小学校分校の統廃合にあたっても、住民が何度も話し合い、運動をおこし、教育行政も住民との話し合いを重視し、時間をかけて結論を出してきた。
ところが、1980年代の京北町小学校統廃合問題や美山町中学校統廃合問題は、いずれも行政が一方的に、あるいは形式的に計画をすすめた。そこには、かつての地方自治のあるべき姿はみられず、その姿勢は今日の学校統廃合問題へと続いている。
美山町の八ヶ峰中学校統廃合問題で、私たちは住民とともにたたかい、3度にわたる統廃合阻止をかちとった。当時私は、北桑田教組専従書記長として連日の新聞折込ビラを作成し、住民合意がないままであること、北桑田のへき地教育のすばらしさ、学校は地域の宝であること、学校があってこそ地域づくりがすすむことなどを訴えた。統廃合は4度目の提案により強行されたが、八ヶ峰中学校が育んだ「地域に根ざした教育」は統合後の美山中学校に引き継がれている。声をあげること、最後までたたかうことで、その後の教育のあり方が変わることを私は学んだ。
今年度から美山では小学校が1校に統廃合され、広大な校区をもつ小学校となった。京北でも1校統合がすすめられようとしている。統廃合に未来はない。今後も、一教職員として、一住民として、北桑田地域が培ってきた「地域ぐるみの教育運動」を受け継ぎ、地域の未来を切り拓く教育をすすめていきたい。
京都市教組 下京・南支部 「せんせのがっこ」(中西教室)実践報告7月8日より
小さな一歩だけど 大きな一歩
~友だちとの関わりの中で~
京都市立小学校 K・Y(青年教師)
1. はじめに
現任小学校で2年目、4年3組(男20人 女11人 計31人)を担任、3年生時の担任4人が持ち上がりの学年、クラス替えがありました。
2. 支援を必要とするSくん
昨年から学年での活動では,とても目立っていました。集団に入れず,大きな声で叫んで怒っている様子をよく目にしていました。
☆出会いの日
体育館でのクラス発表の時。クラスごとに集合しているのにそこへ来ないで,「なんでぼくだけが!」と大声で叫んで怒っていました。理由を聞くと,ささいなことでした。
じっくり話を聞いて,整理してあげると納得したのか、だんだん落ち着きを取り戻し,みんなのところへ行きました。(ていねいに話を聞いて,困っていることを解消できる手立てを教えてあげることが大切と感じました。)。
☆次の日から激しい日々が続く
朝から人ともめる。思い通りにいかなかったり気にいらなかったら,大声でさけぶ。ロッカーをける。物を投げる。上ぐつははかない。ランドセルはほったらかし。ぼうしや体育服入れも投げたまま。本を読み始めたら切り替えられない。授業中、うろうろ、後ろで寝転がる。パソコンをつけたらずっとさわって離れない。めがねくわえる。 体育服に着替えない。体育で外に集合なのに教室から出てこない。「次は~します」と声をかけたら,「うるさい!」と怒りの返事だけ。友だちとの関わりをすごく求めているが…もめて暴言はきまくる。授業中,隣りの席の友達に近すぎる。休み時間は,一番に教室を飛び出していき,クラスの友だちと遊ぶが,遊びの中でトラブル多い。「なんでぼくだけをねらうんだ!」
☆4月初めての参観日
いつもと全くちがう様子、朝から上靴をはいて,かばんを片付け,席に座っています。両親が教室に入ってくるとノートをひろげ,板書をうつし、手を挙げて発表しました。(→両親の存在の大きさを実感しました。)
3 やってみたこと
○がんばりカード できたらシールをはる。喜んで貼っていたが…。結局長続きしませんでした。
○みさきの家(6月2日~4日)の取組
班長をやりたい!絶対にやりたい!」と大声でさけぶ。他の子はすんなりOK。
・当日までに…
父親と話す「Sくんもみんなも楽しいみさきの家になるために」。父「班長はみんなのことを考えられなあかん。自分勝手な人はできひん。」
班での役割決めや水族館の周る順序を決めるとき,もめることなく話し合うことができました。(Sくんも爆発しそうになりながらも,ぐっと我慢、同じ班の友達のやさしい声かけやあたたかく見守り待つ姿)
荷物準備は両親といっしょに
家に行き,しおりを読みながら,どんな活動をどんな服装でするかいっしょに確かめました。
・当日
「班長やから,ぼくがしっかりしなあかんねん。
お父さんと約束してん!」お父さんから渡されたメモ帳(班長とは…が書かれている)をお守りのようにずっと持っていました。入所式では堂々とあいさつをして、みんなから拍手をもらいうれしそうでした。班の友達と譲り合いながら活動することができ、笑顔いっぱいでした。
帰りのバスの中でお父さんへお手紙を書きました。書いた内容をSくんにも伝えると喜んでいました。
○怒りのコントロールのしかたを伝授
「イライラをおさえられないとき,かべのこの部分だけはけってもいいよ」
はじめはかべをけって怒りをぶつけていたが,だんだんなくなってきました。
○周りの子への声かけ
・攻撃的な言い方はしない
・過度な声かけはしない
・我慢している分,たくさんほめる
・Sくんへの理解
○父親といっしょに
・毎日連絡帳のやりとり。よかったこと・悪かったことをすぐに伝える。おうちでの様子を知ることができる(毎日帰宅後の様子や週末の様子)父親がすぐに対応 Sくんから話を聞いたり,アドバイスをしたり→Sくんは素直に聞き,改善が見られました。
・必要なときは,家庭訪問
・校内で顔を合わせたときには,がんばっていることをたくさん伝える「おうちに帰ったらほめてあげてくださいね!」次の日 Sくんはほめられたことを私にうれしそうに報告します。「今日もがんばるぞ!」につながります。△母親とはあまり話をできなかった。
4 年度末には
◎やるべきことを少しずつできるようになってきた
読書から切り替えられるようになった。登校したらすぐにかばんの片付け・提出物を出す。授業中は,自分の席につくのが当然。移動教室、声かけなしで自分で行く『かぎ係』。給食当番、声かけなしで着替え・後片付け。『先生と競争』
◎友達との関わりでだいぶ我慢してがんばれるようになってきた
『お楽しみ会』マジックショー みんなから拍手をもらう。
『大なわ大会』ひっかかっても怒らない 何度も挑戦する姿。友達の声かけが大きい 「ドンマイ」「おしい! 次はもっと早く入り」
『学習発表会』練習中は舞台そででけんかがたえなかったが本番が近付いてくるとせりふもダンスも歌もばっちり。本番インフルエンザのため欠席
「Sくんの分もがんばろう」「歌声とどけよう」
「先生,Sのためにちゃんと写真撮っといてや」
◎周りの子たちの変化
「Sくんもがんばってるやん。もうそれ以上言うなや」「最近,大声で叫んでへんなあ。がまんしたはるなあ」「いっしょにがんばろうやあ」
批判の声じゃなくて,はげましの声かけが増えてきた。よいところを認めようとしている姿がたくさん見られるようになった。
5 一対一の関わりがとても大切 子どもの心をつかむ
一人ひとり抱えているもの・課題・背景が違う。その子にあった声かけ、その子にあった指導。まずは,しっかり話を聞く。何に困っているのか。
6 集団を育てることが大切
◎歌・ダンス 中山譲(ゆずりん)
ダンス部結成 Sくんもダンス部の一員
『スタートライン』『DO MY BEST』 『みんなを浴びながら』『目覚める力』
『とっておきの一人』
『空が空であること』(学習発表会)
『スキスキ 大好き』(誕生日)
誕生日の人のすてきなところを見つけてみんなで歌って伝える。Sくんのすてきなところをクラスの子たちはちゃんと見つけていました。
◎学級通信『スタートライン』
100号 (2冊の本)
作文をのせて読みあいました。
7 おわりに
☆最後の参観日
10歳の節目の年 『2分の1成人式』
一人ずつ発表(今までにできるようになったこと・将来の夢・家族へのメッセージ)
原稿をなかなか書けなかったSくんも,大きい声で自分の夢を語り,両親への感謝の気持ちを堂々と伝えることができました。(両親そろって参加)親からの手紙(事前に書いてもらったものを手渡す)
歌『10才のありがとう』
親からの手紙を読んだ後,歌いながら涙をながしている子どもたち。子どもの成長を目の前に涙をながしている保護者。私も子どもたち一人ひとりを見ていると涙があふれてきました。その後の懇談会でたくさんの絶賛の声が聞かれてうれしかったです。
☆4年3組解散の日
クラスの全員と握手をして「一年間ありがとう」「楽しかったね」の気持ちを伝えよう。握手が無理でも,必ず相手の目を見ること!→ ほとんどの男女が握手をして話をしていました。たくさんの子がなみだを流しています。
「ほんまに楽しかった。」「4年3組のままがいい。」「みんなと離れたくない。」「ありがとう」
わたしも涙があふれだしてとまらない。最後の話ができない。でも最後はえがおで「ありがとう!」
この一年間,去年以上に叱ることが多く、けわしい顔をしていることが多かったです。毎日大声で叫ぶSくんがいることで,クラスの子たちにたくさん我慢させていたと思います。それでも,クラスの子たちは,「4年3組が楽しかった。クラスがえをしたくない。終わりになるのがさみしい。」と言ってなみだを流していました。そんな子たちの顔を見ると涙があふれ出して止まりませんでした。
支援の必要な児童がとても多く,しんどい毎日だったけれど,今振り返ると,毎日が新鮮でとても楽しい毎日だったように思います。そして私自身の子どもたちへの関わり方や保護者との関わり方を見直し,よい方法をさぐりながら見つけられたとても成長できた一年でした。
京都教育センター「家庭教育・民主カウンセリング研究会」
公開研究会 民主カウンセリング・ワークショップ
◆日時 7月23日(土)10時~16時(受付9時30分~)
◆場所 教育会館別館 1階奥 2号室
※教育文化センターの裏側(南側)建物 駐車場のところ
◆内容 エンカウンター・グループ
人間中心の出会い・ふれ合いのグループ経験によって、人間信頼・受容的態度・教官的理解などの集中的体験学習を行います。
日本生活教育連盟第68回夏季全国研究集会〈京都・滋賀集会〉
研究主題 世代をつなぎ 他者とつながり 希望を紡ぐ
◆日時 8月6日(土)~8月8日(月)
◆会場 アヤハレイクサイトホテル滋賀県大津市におの浜3‐2‐25
開会全体会 8月6日(土)13時~16時
・「浦島浩司と仲間たち』歌の世界を一緒に広げよう!
・講演「生きづらい時代と自己肯定感」
高垣忠一郎(立命館大学名誉教授)
・パネルディスカッション
「生きづらい時代に学び、育つ~若者からの発言~」
◆6日~8日 分科会・講座。閉会全体会
詳しい内容は、『日本生活教育連盟』にて検索
全国障害者問題研究会
第50回全国大会京都2016
◆日時 8月6日(土)7日(日)
◆会場 6日全体会 国立京都国際会館
7日分科会・学習講座 龍谷大学深草キャンパス
大会テーマ
プラスワン あなたと次の一歩を
※詳しい内容は「全障研京都」のホームページにて検索
全国到達度評価研究会
第33回全国研究集会
◆日時 8月6日(土)~7日(日)
◆会場 京都教育文化センター
全体会
基調提案 鋒山 泰弘(追手門学院大学教授)
実践・問題提起
3. 「平和をテーマに子どもたちとつくった授業と学級担任集団の議論―戦後70年をめぐる動きの中でー」 小学校からの報告
4. 「18歳選挙権と高校生の政治的教養ー「現代社会」の授業でどのように取り組んだか」 高校からの報告
※詳しい内容は「全国到達度評価研究会」のホームページにて検索
第54回近畿・東海教育研究サークル合同研究集会
テーマ 教育に憲法を子どもに平和を
日時 8月27日(土)28日(日)
会場 京都府立大学
27日 全体会 12時30分~15時15分
・女性僧侶シンガー鈴木君代ライブ
・講演「憲法・平和と子どもたち」
藤原辰史(京都大学人文科学研究所准教授・
自由と平和のための京大有志の会)
理論実技講座 15時30分~17時30分
28日 分科会・移動講座など
※詳しい内容は「さんすうしぃ!」のホームページにて検索