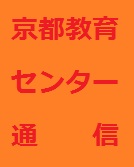
 |
●京都教育センター通信 復刊第109号 (2016.6.10発行) |
歴史と現在、雑感-米大統領広島訪問と「安保関連法」から-
高橋 明裕(京都教育センター研究委員長・立命館大学非常勤講師)
私たちは日々、世界史のなかで展開する日本の政治情勢とこれに対する変革の波のなかで生活している。
五月二七日、オバナ大統領が広島を訪問した。アメリカ大統領の初の訪問を画期的と見る向きもあるが、核兵器廃絶の具体的中身がなく、核兵器禁止条約に背を向けている日米両国のパフォーマンスであると批判的に見る人が多い。韓国内では、当時の帝国臣民として被爆した韓国人犠牲者の慰霊碑に哀悼の意を捧げることを期待したが、日米両首脳が容れるところではなかった。実現していれば日本が植民地支配国であったことが鮮明になり、原爆投下による無差別な虐殺が日本国民だけでなく植民地支配下の人々をも襲った構図が浮かび上がったであろう。昨年暮れ、締切間際に間に合わせるかのように合意された日韓両政府によるいわゆる従軍慰安婦問題の「不可逆的かつ最終的解決」についても同様に多くの問題点が残されている。為政者は歴史問題を曖昧に決着させることで国民が変革の原動力とならないよう眠り込ませようと、歴史を忘却させ、歴史から切り離された存在へ貶めようとする。教科書・歴史教育をめぐって歴史修正主義の攻撃が激しいこともそう考えれば納得がいくし、この問題はゆるがせにすることができない。
米大統領の広島訪問という半ば棚ボタ的な「得点」稼ぎを果たした安倍内閣は、来年の消費増税を先送りすることで、憲法改正に向けた議席と首相任期確保のための選挙日程をにらんでいる。昨年九月、多くの反対の声を無視して「安全保障関連法」が強行採決されたが、法律施行後も廃止運動がやむことがない。昨年来、シリアなど中東の難民が大量に欧州に押し寄せ世界を驚かせているが、石油が入って来なくなったら大変だからと、国民の幸福追求権を理由に集団的自衛権を行使することが想定されたのがホルムズ海峡封鎖だったことは記憶に新しい。「安保法制」は中東の問題とつながっていることがわかる。日本では「IS」と呼称されるテロ組織が諸悪の根源と報じられるが、実際には欧米各国による空爆が事態をますます悪化させ、ISの台頭自体が欧米の中東政策の所産であった。こうした中東の混乱の淵源は、社会主義圏が崩壊して以降、アメリカを先頭にした先進資本主義諸国が中東に直接軍事介入するようになったこと(集団的帝国主義)に由来すると見なければならない。社会主義圏が存在した冷戦の時代には、欧米が中東に直接軍事介入することはなかった。むしろエジプトのナセル政権のように社会主義的な政策を採り、対欧米従属からの脱却を進めた国民な政権が中東に存在した時期もあった。これをつぶす役目を果たしたのが欧米の番犬、移民国家イスラエルによる中東戦争だった。中東では欧米の集団的帝国主義支配の矛盾が集中し、一九九〇年代以降、日本の軍事大国化は常に中東問題を対象に進展してきた。日本の中東研究者たちの多くはそのように現代を見ている(最新刊、長沢栄治・栗田禎子編『中東と日本の針路 「安保法制」がもたらすもの』大月書店)。歴史のなかの現在の位置と構図を意識しながら、社会変革の歩みを進めていくことが求められる。
京都教育センター公開研究会
☆再来年度からはじまる・・・・道徳の教科化を考える
-大平 勲さんの基調提案に学ぶ-
5月28日の教育センター公開研究会での大平勲さんの基調提起を紹介します。
1、道徳教育のあゆみ(紙面の都合で省略)
2、道徳教育をめぐる最近の動向
(1)2000年(H12) 教育改革国民会議「教育を変える17の提言」 家庭教育の重視、「学校は道徳を教えることをためらわない」
: 「人間科」「人生科」
(2)2002年(H14) 文科省「心のノート」全小中学生に
配布: 民主政権下で中止したものの、H25年に改訂版を再配布
(3)2006年(H18)「教育基本法」改定
(第一次安倍内閣) :
「国と郷土を愛する」
2007年(H19)「教育再生会議」が提言 : 「徳育」名称で正式教科に
中教審が受け入れず実施は見送りに
(4)現行学習指導要領実施2011年(H23から) : 総則
で「道徳の時間を要として」を挿入、
解説で「道徳教育推進教師」を位置づける。
(5)013年(H25)「教育再生実行会議」(第二次安倍内
閣)の提言を受け、文科省の「有識者会議」報告
: 道徳を「教科外の活動」から「特別な教科」に
検定教科書 記述式評価
(6)2014年(H26)中央教育審議会が「教科化」答申、
文科省が『私たちの道徳』作成・配布(10億円)
使用義務はない。
(7)2015年(H27)3月27日「改訂学習指導要領」告知
道徳の教科化を2018年4月から小学校、
2019年4月から中学校で先行実施。
今年の4月から教材使用も含めて前倒し実施も可。
一般教科の改訂全面実施は2020年(小)、2021年(中)、2022年(高)
(8)2015年(H27) 3月 文科省補助教材選定基準に
関する「通知」
3.「道徳の教科化」の問題点
「道徳の特別教科化」の推進論者の押谷由夫氏(昭和女子大教授、日本道徳教育学会長、文科省教育課程委員)はその根拠を次のような「珍妙な論拠」で述べています。
「教科とは人格の形成を目指して必要な知識や技能などが分野ごとにまとめられ専門分化していくもの」であるのに対し「道徳は,人格の基盤となるものであり,専門分化したもの全体にかかわり人格の基盤づくりにつなげていくもの」であるから「道徳は各教科とは性格を異にするが,各教科と密接にかかわることによって成り立つという特性を持つ。その意味において,教科の範躊に入れて考える必要がある。それは,本来の教科の概念を超えて成り立つものであること」から,更に道徳は「特別活動や総合的な学習の時間など学校の教育活動全体,及び家庭や地域社会での道徳教育と密接に関わる」という意味でも特別の教科(スーパー教科)となる」
(1) そのねらいと本質の破綻
教科化のねらいは、国民の思想や価値観、人格的な価値意識そのものを国家によって統制、管理、教化することにあります。そのことによって、日本の学校教育は今までとレベルの違う国家統制下におかれる危険性があります。新設「道徳科」では国家権力が教育内容を直接決定する仕組みが容易に働きます。社会科の日本史には歴史学が対応しますが、道徳科に対応する「科学」が存在しないからです。それは学習指導要領での道徳の「項目」(徳目)を見れば歴然です。
「従来『読み物道徳』と言われたり、軽視されたりした道徳から、教科書を使って子ども達が答えが一つでない問題を道徳的課題として捉え、考えたり、議論したりする道徳へと質的に転換を図ってまいります。」
この見解は道徳が本来の教科となりうるには無理があることを自認するものです。また、教科の存立条件としては現行の指導要領でも、「教科書」、「評価」、「免許」の3つが不可欠とされていますが、この点でも問題点がたくさんあります。
(2) 検定教科書 小学校は2016年度中に「検定申請」、2017年度に「検定合格・採択」「指導書作成」、2018年度「使用開始」(中学校は1年遅れ)の日程で、5月末「8社の申請があった」と報道されました。告示から1年間での申請も異例です。また「答申」ではバランスの取れた多様な教科書を認めると言いながらも、この日程では一様性に追い込む(文科省配布の『わたしたもの道徳』を教科書のベースに?)ことの策略とも思いかねません。また、文科省の教科書調査官による検定作業が「公正・中立」に行われる担保はありません。彼等が学習指導要領と教科書検定基準をものさしとして審査する以上、多様な教科書が出来てくる可能性は薄いと言わねばなりません。育鵬社の『はじめての道徳教科書』(小学校版)が指導要領に最も準拠したものとして合格・採択される危険性が高いです。
(4)免許の義務化は不要
中学校では教科ごとの教員免許が必要とされるのと同様に、道徳も教科扱いにするのであれば当然免許取得が義務づけられるはずです。しかし、短期間に教員が免許取得できる条件整備もなく、大学などの受け入れも不十分なもとで猶予せざるを得ないのが実態でしょう。むしろ、免許を設定しない方が研修の強化で全ての教員を統制することが容易になることも睨んでいるかも知れません。
4.「教科化」改訂の内容と問題点
(1)徳目の強要では道徳性は涵養されない
道徳が教科化される大きな背景になった出来事として、2011年の大津でのいじめ自殺事件があります。この事件の事実関係や背景の分析にはかなりの時間を要したが、安倍政権は「いじめ防止対策推進法」を制定(2013年9月試行)し、各自治体では「いじめ防止条例」制定で各学校では「いじめ防止対策計画」策定で、いじめは許されないという規範意識を徹底するために「道徳教育の強化」を誘導しました。
用した読み物があり、そこでは加害生徒が被害生徒の心情を綴った文集を読んで30余年を経過した今も謝罪しなかった罪業を思い出し、悔い、忍び泣くという筋書きです。ここでは「いじめは絶対にダメ」という徳目に迫るために個人の心情に訴える手法ですが、いじめは個人の心がけで解消するほど単純な問題ではありません。現実にいじめが支配している空間の力学を組み替える。生活指導なくしていじめは克服できません。教師が正確な事実関係を把握した上で個別指導と共にいじめ事件を「生きた教材」として、クラス集団の論議に託し集団的に行われるいじめを集団の問題としても解決していく道筋を求めない限り根絶されません。道徳性の涵養は各個人の「心がけ」の中にあるのではなく、自らの判断や価値意識を集団議論の場に提示し「共に生きる」という共同性の土台の上で反省的に吟味し続けることにあります。「心理主義」や「徳目主義」は子どもの心に道徳性を育むことが出来ないどころか、「体制に順応し、社会の矛盾に目をつぶって生きることを暗に強制するもの」と言えます。(佐貫浩・法政大学教授)
(2)新指導要領に見る間題点
梅原利夫氏(和光大学)は「指導要領の新旧対照」(表は略)によってその問題点のポイントを次のように指摘しています。
① 学年段階別項目]の変容
・現行の4類型から、新4類型に。A(自分自身―6項目)B(人との関係―5項目)C(集団今社会との関係―7項目)D(自然や崇高なものとの関係―4項目)
類別と項目数は何を根拠に指定したのか?
・A「善悪の判断、自律、自由と責任」は同一のカテゴリーか?
・C「伝統と文化の尊重」と「国や郷土を愛する態度」は違う次元?
② 内容項目の批判的分析例
から設定された「感謝→尊敬→応答→人間愛」という4段階に無理がある。
・「国々郷土を愛する」では、重要視や大事という認識から「愛する」という一元的な心情で包括できない。
③[指導計画の作成]について 「アクティブ・ラーニング」や「教材選択の基準(法令遵守)」を挿入
5.文科省『私たちの道徳』批判
O「私たちの道徳」その特徴
①
人物伝:多くの「偉人や有名人」(9割が日本人)が登場し、その大の業績や著述の一部を「徳目」に沿って取り上げ、その努力と精神を学ばせる。その人の果たした社会的、歴史的役割についての検証のないままに。
②繰り返される「自己責任」:不安や葛藤で悩み苦しむ自分を横に置いて、自己責任で頑張れ、もっと反省しろ、とのメッセージが降り注がれ、[書き込み]を通して「徳目」に準じる「よい子」像に誘導する。
③社会の側の[道徳的価値]の衰退には一切ふれず:平和の堅持や基本的人権擁護が疎かにされている現状に目をつぶり、生きづらさなどを個人の道徳性の問題に緩小化して、自己責任として認識させる枠組みを設定している。
○各学年ブロック別の批判的検討〈京都教育センター刊「冊子」参照〉
6.私たちの課題と実践
(1)今日的状況の批判的理解を深める学習を
・道徳の「教科化」についてその背景、構造、内容などを熟知すること
・「立憲民主主義を取り戻す」ためにも有効な道徳実践
・「道徳教育」を機械的に否定するのでなく、目指すべき「道徳教育」のヴィジョンを
・地に着いた道徳教育の実践推進者とも共同して
(2)市民的な議論の場を広げよう(内容は省略)
(3)私たちの実践:「市民道徳」の実践プランを(内容は省略)
※資料も含めて文書がほしい方は連絡ください。
戦争への道ゴメン!メディアの萎縮を憂える京都アクション
戦争への道。憲法9条の道、メディアはどちらに向かっているか。
監視するのは私たち…。
講演とシンポジュウム
◆日時 6月18日(土)13時30分~
◆会場 京都教育文化センター103号 (会費800円)
◆講師
河野慎二さん(ジャーナリスト、元日本テレビ社会部長、JCJ運営委員)
コーディネーター 隅井孝雄(NHKを憂える運動センター・京都共同代表)
パネリスト 新聞関係 日比野敏陽さん(新聞労連近畿地連委員長)
若いお母さん 姫野美佐子さん(5年生のお母さん)
SEALDs 寺田ともかさん
全障研第50回全国大会in京都 プレ企画
×
京教組障教部・市教組障教部学習会
◆日時 6月19日(日)13時30分~16時50分
◆会場 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館 第2会議室
◆講演 人間を大切にするしごと
~「教育」という名に値するもの~
講師 三木 裕和氏(鳥取大学教授)
子どもの発達と地域研究会学習会
「ママ友」だけではない子育てのつながり
―雑談から共同の子育てへー
◆日時 6月25日(土)13時30分~15時30分
◆会場 ウイングス京都 中京青少年活動センター和室
アドバイザー
右京子育てネット代表 後藤米江さん
京都教育センター学力・教育課程研究会 6月公開研究会
テーマ 現代社会を批判的にとらえ、
未来を創る主権者をどう育てるか
―憲法・子どもの権利条約を子どもたちに培う授業・活動―
◆日時 6月25日(土)13時30分~16時30分(13時開場)
◆会場 京都教育文化センター 301号 (参加費は不要)
基調報告
「生徒にとって意義ある主権者教育をどのように創りだすか」
鋒山泰弘氏(本研究会代表・追手門学院大学)
実践報告
①
高校生に対する主権者教育の試み」山根直さん(西乙訓高校)
②
平和主義と憲法9条―憲法9条に関連する政府見解を歴史的に振り返る―」山口 洋さん(修学院中学校)
教科書問題学習会 京都教科問題連絡会議
新しい検定で
高校教科書はどのように変えられたのか
◆日時 7月9日(土) 13時30分~16時30分
◆会場 京都教育文化センター301号
報告 どのような教科書検定が行われたのか
講演「新旧日本史教科書の比較から見えてくるもの」(仮題)
講師 原田敬一氏 (佛教大学教授・日本史研究会代表)