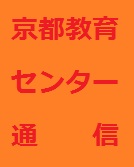
 |
●京都教育センター通信 復刊第105号 (2016.2.10発行) |
「小中一貫」で学校が消える
大平 勲(京都教育センター・立命館大学非常勤講師)
広がる学校リストラ
「子どもの数が減った」「小中一貫校ができる」などを理由に100年以上も地域に根づいた学校が急速に消えていく。それは、「お客が減った」「近くに大型店ができる」などを理由に店舗を閉めるのとはわけが違い、教育問題に矮小化してはならない。少子高齢化で子どもが減っているのは事実だが、学校という「場」は学齢児の学習の場にとどまらない地域の生活・文化のセンターであり、そこに住む人々の「原風景」の一つでもある。戦後1950年代の「昭和の大合併」(自治体数が3割に)の時に国の方針で学校統廃合が強行されたが、昨今の統廃合も「平成の市町村合併」が背景にあり、1992年から2007年の15年間に全国で4,706小中高校が廃校になり、それ以降も毎年400~500校の公立学校が消えている。京都にあってもこの20余年の間に京都市内で51校、それ以外の府内で100校が統廃合された。
突出する京都市と京丹後市
とりわけ私が調査して驚いたのは京都市と京丹後市の実態です。京都市では、中・上・下・東山の各区にある「番組小学校」(明治の初めに町衆の寄附でつくられた64小学校)の殆どが消えて、小中一貫校などに統合された。その手法が巧妙で、市教委は「黒子」として自治連やP連からの「要望」に応える形をとり、父母や住民は青写真ができてから知るという「仕組まれた住民合意」でした。特に東山区では、小中学校11校を一貫校の「東山開睛館」と「東山泉」に統合し、一貫校を「アメ」にして人口4万弱の行政区で公立校が2校だけという他地域では見られない異常なリストラ。しかも廃校となった学校跡地を京都市が「経営資源」としてホテルなどの民間に転用するとして今の市長選でも大きな争点になっている。京丹後市もこの数年で異常な学校つぶしを行った。この地の教育実践や教育運動は「丹後の教育」の名で、青森の津軽や岐阜の恵那と並んで地域に根ざした教育のメッカと言われた歴史を残している。2004年に六町が合併し、天下りの官僚市長が着任以降、「学校再配置計画」に基づいてこの五年間で31小学校を19校に、9中学校を6校に整理し、地元教組や住民組織の「待て!」の声も無視して半減近くまで減らすという全国的にも突出した統廃合。他にも南丹市や福知山市等でも強行され、亀岡市等でも昨年の文科省「適正配置手引き」によって単学級校を機械的に整理する動きが出ている。また、これまで他県のように手を付けなかった府立学校にあっても府教委が「北部の高校再編」の検討会議で北部の数校に焦点を当てた統廃合を目論み、現地を中心とした反対運動が展開されている。こうした中で注目されるのは合併せず自立をめざし、義務教育費無償を具体化させた伊根町です。2009年に、町教委は小中学校を各1校にする方針を出したが、教委による「保護者アンケート」で中学校は統合するが小学校は2校とも残すことを文字通り「住民合意」で決めたのです。
「小中一貫」は学校つぶしと「6-3制」破壊
施設一体型の小中一貫校は年々増え、全国で100校をゆうに超えているが、京都はここでも東京や九州と並んで突出している。市内には「東山開睛館」「東山泉」「凌風」の目玉校に加え、左京山間部の「花脊」「大原」があり、伏見の向島や京北にも計画している。府内では「夜久野」(福知山市)、「上林」(綾部市)、「川東」(亀岡市)の各周辺部にあり、宇治市の「黄檗学園」は小学校に中学校を積み上げた統合なしの特異な形態である。いずれも文科省が進める「新自由主義的な教育改革」の先取りを自負するものだが、学習指導要領が小中別々のもとでメリットがあるのか、和光大などが実施した実態調査では一貫校の子どもは非一貫校よりも「自信や自己価値が低い」「疲労感が強い」などのデメリットが検証されている。この4月から認められる小中一貫の「義務教育学校」は先の中高一貫校とともに戦後の「6-3-3-4」制度をなし崩し的に崩壊させ、競争の教育に拍車をかけることが危惧される。
第46回京都教育センター研究集会生活指導分科会レポート
今じゃなくていいよ、あまえてもいいよ(前半)
府内公立小学校 瀬戸 有佳子
1 はじめに
今年、四年生を担任することになった。(二年前に二年生で担任した子どもたち。三〇人のうち二年の時担任した子どもは九人。その中に明と俊がいる。)二年のときは学年全体が落ち着かず、キレる・殴る・からかう・泣く・教室に帰ってこないなど、毎日いろいろなことが起きた。しかし3年生ではずいぶんと落ち着き、成長したんだなあと思っていた。
明は二年生の春に弱視であることが分かり、「視神経萎縮」という診断が降りた。それまでの経験や学習の積み重ねが乏しく、やりたくないことはしない。立ち歩く。注意されるとキレて殴る蹴る。反面。機嫌がいいときは1対1での関わりを求めてくる。家庭環境はとても複雑だ。
俊は、不安が強く、初めてのことやできるかどうか分からないこと、負けそうなことを前にすると「無理!」「いや!」と拗ねてしまう。俊も立ち歩く、キレる。殴りこそはしないが、物を投げる、教科書を破る。一つずつにそうやって不安になっていたらしんどいだろうなあと思う。
2 重石がとれて
四月、教師にとっては何とも気持ちのいいスタートだった。全員チャイムが嗚る前に席に座る。私語はしない。明も俊もちゃんと座っている。しかし、四月も半ばを過ぎる頃、まずは明が荒れ始めた。立ち歩き、授業で使っている掲示物をとったり、クラスで飼っているトカゲをさわりに行ったり。
私「明君、座ろ。」
明「無理!うっさいんじゃ!ほっとけ!」
私「いやいや、授業中やで。」
明「だまれ!殺すぞ!」
私「だまりません。座って。」
明「だまれって言ってるやろ!」
(殴りに来る)
周りで見ている子からは、「明、三年生の時はそんなんしてへんかったやん。」という声が出た。別の日、「明君、なんで授業中にうろうろするん?三年生の時はちゃんと座ってたんやろ?先生は成長したんやなって思ってたけど、そうじゃなかったん? A先生が怖いからおとなしくしてただけ?」図星だった。その後のキレっぷりは、過去最高だった。泣きわめいて殴りかかってくる明を押さえながら、一年間がまんし続けた分を今出しているように感じた。
それは俊も同じだった。明が荒れ出したのを見て、「無理!」を連発するようになった。教科書やノートは出さない。常にしゃべるか音を出す。私が話すことにいちいちカチンとくる合いの手を入れる。立ち歩きも始まり、自由奔放な真美とつるんで、三人で教室の後ろで遊んだり帰ってこなかったりと、何度も非常電話のお世話になった。「やっぱり俊もそう来るか~」と思った。
3 学年団のしんどさ
学年会で明や俊の話をすると、三年生の時に俊を担任していた先生には「それ甘えてるだけですよ。去年はそこまでじゃなかったのに。」、主任の先生には「大変やけどあれを許したらあかん。」と言われた。そして、明や俊がうろうろし始めたら教室から出して、三人で囲んで指導するという方針が立った。対処療法でうまくいかないと思ったが。自分のクラスが一番ガチャガチヤしている負い目があり何も言えなかった。
実際に三人で囲んでの指導を何回かしたが、その場しのぎにもならなかった。このままではだめなことは分かるけれど、自分がしていることはただの甘やかしではないかと悩んだ。今までは学年でそういった話ができたのだが、今年はそれができないのがしんどい。
4 方針を持って 明とのかかわり
五月の合同生指サークルでそれまでのこと話した。たくさんアドバイスをもらい、自分のやるべきことを整理した。
① 分析をする(明の生い立ち、家庭環境、背負っているものは何か。)
② 明のための授業(見ることへの支援)
③ スキンシップ(人に甘えるとはどういうことか教える。)
方針を持ったとたんに気持ちが軽くなった。まずは見ることへの支援を徹底的にした。視覚機器をフル活用し、四年生補助の先生による個別指導も毎日行うことにした。
(明の生い立ち)一人目の父親が、母や明に暴力をふるっていたこと。保育園の時はいろいろなことができなくて困っていたこと。小学校入学前に母が一回目の離婚をしたこと。一年生の時は自由なクラスで自由に過ごしていたので特に困ることはなく、キシることもなかったこと。二年生まで弱視に気づかれていなかったこと。二年生で母が再婚し、妹ができたこと。三年生で母が二回目の離婚をしたこと・・・。たった九年だが、明は山あり谷ありの人生を歩んできていた。特に気になったのは、一人目の父親の暴力だ。
私(明のクールダウン中)「明君、なんでそんなに殴ったり蹴ったりするん?もしかして明君も誰かに殴られてんの?」
明「殴られてるし!」
私「えっ!誰に?」
明「お母さん・・・まちがえた、お父さん。」
私「お父さんつて、一人目のお父さん・?」
明「うん。」
私「そうかあ。痛かったやろ?」 明「うん、お母さんも殴られてた。」
私「そうなんや。殴られた時って。明君はどうしてたん?」
明「逃げたりやり返したりしてた!」
私「やり返してたん!?」
話しながら、明はなぜか得意気になっていく。見えていないので相手の表情や雰囲気が分からず、恐怖心が薄かっためだろうか?それでも殴られたら痛くて怖かっただろうに・・・
明は小さい頃に親に甘えやわがままを受けとめてもらう経験が乏しかったことが分かった。経験していないなら、開き直って甘えさせればいい。(と、五月のサークルで教わった。)人に頼ったり甘えたりすることが、明の成長には必要だ。学習など、やりたくないことはとことん手伝うようにすると、「先生、手伝って!」と自分から言うようになった。そして、「金曜日は毎週残るから宿題教えてな。」と言って、六月から本当に毎週残っている。また、「イライラする。」と言ってきたときは何かを職員室まで持って行くなどの手伝いをしてもらっている。お礼を言うと、満足して椅子に戻れることも増えてきた。キレたときは、前から腕を押さえるのではなく、後ろから抱きしめるようにして腕を持つと、「ボケ!死ね!」という暴言が減って、赤ちゃんのようにしくしく泣くようになった。そして、手をつないだり膝に乗ったりしてくるようになった。私が明にとって少しでも信頼に値する大人になれてきたかな?と思う。一進一退だが・・・
5 俊とかかわり
(俊の生い立ち)父親が母や姉に暴力をふるい、俊が保育園の時に、母が二人を連れて逃げるように離婚した。その後母が不安定になり、姉も情緒面のケアで通級指導教室に通っている。三年生の時はやるべきことはしていたそうだが、後半は不登校気味になり、母が毎日送ってきていた。それは六月頃まで続いたが、遅刻はほとんどなくなった。
俊は、小さいときにたくさん失敗して助けてもらってできるようになるという経験をしてきていないように感じた。自信は無いがプライドは高く、素直に助けを求めることができない。俊の返事は「無理!」なのだが、それを「手伝って!」に自動翻訳して、机の上を整えたりカードを少し書いてあげたりしている。そして、用事があるときはなるべく俊にお願いして、「ありがとう!助かったよ!」を言うようにしている。
俊のお母さんは、不安定ながらも俊をなんとか学校へ行かそうと必死だった。そのためにお母さんが宿題をやることもあった。開き直って俊の宿題を減らすことにした。
1日日
私「どれやったらできそう?おすすめは算プリやで。」
俊「全部してくる。」
結局一つもしてこなかった。
2日日
私「やっぱり算プリがおすすめやけど。」
俊「・・・算プリしてくる。」
今度はちゃんとしてきたので、花丸をしてたくさん褒めた。
3日目
この日も算プリをしてきた。
私「今日もできてるやん。えらい!」
俊「うん。でも漢字はやってへんから、残ってやるわ。」
私「ええっ!残るの」
居残りが何より嫌いな俊が・・・まさかの展開でびっくりするやら嬉しいやら。俊は本当に居残りをして、漢字ノートに花丸をもらい、大満足で帰って行った。しかし、その後二日は算プリすらしてこなかった。こちらも一進一退だ。
(以下3月号)
学校統廃合と小中一貫教育を考える 第6回 全国交流集会
〇主催/学校統廃合と小中一貫教育を考える第6回全国集会実行委員会
◆日時 2月21日(日)10時~16時30分
◆会場 たかつガーデン(大阪府教育会館) 大阪市天王寺区東高津七番十一号
◆内容
《午前》10時~12時 全体会
1 全国の学校統廃合、小中一貫校をめぐる情勢と課題 山本由美(和光大学)
2 シカゴ教員組合からの報告 サラ・キャンバースさん(シカゴ教員組合)
*父母と結びつき、学習を重ね、学校統廃合反対の空前のたたかいを作り出したシカゴの教訓に学びます。
《午後》1時~4時30分 分科会
第1分科会「学校統廃合・地域の運動」共同研究者/佐貫浩
第2分科会「教育課程・発達」 共同研究者/梅原利夫・都筑学
第3分科会「地域再開発と小中一貫校」共同研究者/室﨑生子
特別分科会「シカゴ教員組合との交流」共同研究者/山本由美
◆参加資料代/五〇〇円
全国障害者問題研究会 第回全国大会京都 プレ企画
◆日時 2月21日(日)13時受付開始/13時15分講演開始/17時終了
◆会場 京都教育大学 京都市伏見区深草藤森町1/京阪「墨染」より徒歩約7分
◆内容
1 加藤由紀さん(『思春期をともに生きる 中学校支援学級の仲間たち』《クリエイツかもがわ》の著者)の講演
*支援学級の実践やこども観、授業で大切にしていたことなどの熱い思いを語っていただきます。
2 パネルディスカッション
(パネラー)福田洋子先生(府内小学校教員)
石田 誠先生(府内特別支援学校教員)
谷口藤雄先生(府内高等学校特別支援・進路支援教員)
加藤由紀先生
◆参加費 (一般500円)/(全障研会員 無料)
第35回 より豊かな全国学校給食をめざす京都集会
〇主催/より豊かな学校給食をめざす京都連絡会
◆日時 2月27日(土)10時~16時
◆会場 京都テルサ/JR京都駅より南へ徒歩約15分
◆内容
1 記念講演(午前)「食べること」をとらえなおす--ドイツの台所に歴史から
講師 藤原 辰史(京都大学人文科学研究所准教授)
2 分科会
第1分科会 「学校給食の充実と食育」 東館3階会議室A
第2分科会 「食の安全から学校給食を考える」 東館3階視聴覚研修室
◆参加協力券/500円/できるだけ事前にお申し込みください。
(連絡先)京都自治労連 ℡075-801-8186
2015年夏の 教科書採択報告学習会
〇主催/京都教科書問題連絡会議
◆日時 3月12日(土)13時30分~16時30分
◆会場 キャンパスプラザ京都4階第4講義室
◆内容
1 講演「平和憲法擁護の教科書こそ、子どもたちに~今度は育鵬社を採択しなかった東京都大田区のとりくみ~」
講師 森 峯太郎さん(大田子どもの教育連絡会世話人)
2 報告「2015年夏の教科書採択の結果と今後のとりくみ」
意見交流
◆参加費/500円