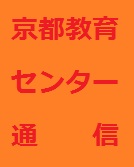
 |
●京都教育センター通信 復刊第102号 (2015.11.10発行) |
主権者教育に名を借りた教育支配を許してはならない
原田 久(京都教育センター高校問題研究会)
世界では既に九割が十八歳選挙権
今年六月一七日に公職選挙法が改正され、十八歳・十九歳の青年、約240万人が新たに選挙権を手にすることになった。法の施行後初めての国政選挙から適用されるため、来年七月の参議院選挙からとなる。世界では約九割の国・地域が既に十八歳選挙権で、日本の政治的後進性は際立っていた。
一九六九年通知は廃止
十八歳選挙権成立に伴い、高校生にも有権者が誕生する。こうした事態を前にして、文科省は「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動について(通知)」を発出した。
この中で政治的教養の教育を、校長を中心に、公民科のみならず総合の時間や特別活動の時間も利用して行うことを記すと共に指導の中身まで具体的に例示している。教員の個人的主義主張をさけ、公正中立の立場での指導を強調している。生徒の政治的活動については校内では必要かつ合理的範囲内で制約を受けること、校外であっても場合によっては禁止することも有り得るとしたうえで、家庭の理解の上で生徒が判断し行うものともしている。高校生の政治的活動を禁じた一九六九年通知は廃止した。
早くも副読本・指導書が作成される
文科省は早くも「副読本」を作成し、二月までに在籍生徒への確実な配布と学校における有効活用を要請する文書(九月八日付)を発出している。副読本には指導書もあり、その中で全体の四分の一を使って、「指導上の政治的中立の確保に関する留意点」を詳述している。一読では「『できないこと』が多い。この問題には深入りしない方が無難だ」という印象が強く残る。
政権与党による「提言」
一方、自民党は七月八日に政務調査会名で「選挙権年齢の引き下げに伴う学校教育の混乱を防ぐための提言」を公表し、「高校生の政治活動は基本的に抑制的であるべき指導を高校が行えるよう政府としての責任ある見解を学校現場に示すべき」「教員の日々の指導や政治活動については政府としてその政治的中立性の確保を徹底すべき。政治的行為違反に罰則を科す」などとしている。
憂慮される主権者教育の形骸化
このような政権与党や国家機関の動向は学校現場に委縮効果を及ぼし、主権者教育の形骸化を招きかねない。主権者教育を通して、学校、教職員を政治的に締め上げ、教育内容や方法にまで事細かく介入する、むき出しの意図が見える。
こうした下で私が憂慮するのは、教職員が真理真実を大切にし、子どもたちや国民の方を向いてその最善の利益のために力を尽くすのではなく、自分の実践が自分以外の人や管理的立場に人たちからどう思われているのかを絶えず意識する思考回路を自らの内部に形成してしまうことだ。
「政治的中立」とは
さらに、政治的中立ということばが教職員に向かって執拗に投げかけられているが、元々は政府や権力機関の教育介入を防ぐために彼らに向かって投げかけられたことばであることを忘れてはならない。教職員が自らの実践が政治的に中立かどうかという問題設定するのではなく、子どもたちに学問的に裏打ちされた真理真実をきっちりと提示できているかどうかという問題設定こそが必要なのである。
平和で民主的な社会の主人公を育成する教育実践はこれまでも現場で地道に積み上がられてきた。その豊かな蓄積の上に立った主権者教育の展開こそが今求められているのであって、主権者教育に名を借りた子どもと教職員支配は許してはならない。
教育研究全国集会in宮城 生活指導・自治的活動分科会分科会レポート
えがおきらきら二年生
京都府内公立小学校 海田 勇輝
1.はじめに
一年生時にネグレクトのS子がいた。懸命にS子に寄り添い彼女の居場所づくりを軸に据えて学級集団作りに取り組んできた。二年生へ進む直前の三学期の修了式当日、S子が児相に保護され、結局転出した。自分の力不足を痛感した一年となった。同じクラスを持ち上がり、S子がいつ戻ってきても安心して過ごせる、そして全員が安心して過ごせる、みんなの居場所になるクラスづくりを目指し、二年生のスタートを切った。
2.一年時のこと
○体育でおにごっこ
肌と肌の触れあい、身体と身体のぶつかり合いの少なさが幼年期での課題であると思っている。「みんなで遊ぶと楽しい」ことを実感できるように、体育の時間の初めに必ず鬼ごっこをした。初めはⅠ男がよくパニックを起こすなど、鬼ごっこ自体が成立しなくなったことも何度もあったが、次第に子どもたちの歓声が大きくなりみんな大喜びの体育へとなっていった。ゲームや鬼ごっこでのトラブルは話し合って解決している。(詳細略)
○遊びのお店屋さん
配慮しなければならない児童が多く、一、二学期は、集団の遊びが成立しづらい日々が続いていた。こだわりが強く遊びのルールが理解できないⅠ男。さらに強いこだわりのY男、そして「おもんない!」と叫び雰囲気を壊してしまうS子。子どもたちは子どもたちの中でこそ子どもになれるということを胸に、三学期はより積極的に集団的なとりくみを意識して展開することにした。
給食時間に「お店屋さんを開くよ」と言うと、その日遊びたい遊びを子どもたちが言う。
ルールは、「三人以上で成立。三人集まらないときはその日はあきらめて違う遊びに参加する。誰でも入れる。やめるときはその遊びをしているみんなにわかるようにする。」にした。
給食時間は大盛り上がり。自分たちで考えた遊びも生まれ始めた。一人で昼休みを過ごす子がいなくなった。(後半略)
3.一学期の二年二組
「えがおきらきら二年生」を学年目標にして、二年生がスタートした。
子どもたちには、「めっちゃおもろいクラスにしよう」と呼びかけた。
○遊びのお店やさんのその後
一年生時と変わらず、給食時間になると教室は大盛り上がり。妖怪ウォッチごっこ、虫取り、鉄棒、折り紙や粘土など、いろんなお店が開かれた。
一人のおみせもOKというルールになっているが、一人は嫌なようで、一人遊びは影をひそめた。「今日は諦める」と言ってちがうお店に入ったり、「一組さんをさそってくる!」と言って一組の友達に入ってもらったりして遊びの広がりが定着してきている。悩んでる人がいると、「入って!入って!」と大合唱が起こる。
Y男
偏食、気に入らないことはしない、友達とのつながりが苦手、初めてのことは特に苦手、つばをはく、たたく、支配的ものの言い様、会話は一方的。これが幼稚園からの引き継ぎ事項であった。
大変な偏食で、苦手なものは食べさせようとしても絶対食べない。おかずを減らしに来たときに「どれ頑張る?」と聞き、頑張ると言ったもの一つは食べようと根気強く励ますことにした。「しっぶー!」「まず〜〜!」と大声を出しながら食べる。一度おかずが余りすぎたので、全員少しずつ増やし、Y男にも入れてみると案の定泣き出した。そこで「なぁみんな。みんなにも苦手な食べ物があると思うけど、Y男はその苦手レベルがめっちゃ高いねん。だから今は一口は頑張ってるやろ。おかずがいっぱい余ったとき、Y男だけは増やさないときがあるかもしれません。先生はいつかこの一口チャレンジが二口になり、三口になっていくのを待っています。みんなも一緒に待ってあげてくれる?」とY男に聞かせるように話した。クラスから「Y男!待ってるよ!」の声が響いた。たまにコーンを十口頑張ると言うと、拍手が起こる。いろいろトラブルがあったり、できないことも多かったりするが、私との関係も少しずつつながり始め、彼なりに一生懸命頑張った一年間であった。
そんなY男の二年生一学期。イスにきちんと座らずに前の席のM男とずっと話している。注意すると、自分で口をおさえるが、一分持たずにしゃべりだす。ときどきM男に関係なく一人で大声でしゃべっている。グループ学習をすると、ふざけるか、友達と一緒にできないかのどちらかである。
同じ班のN男とC子を呼んで、「Y男のことで困ってることない?」と聞く。二人は「ある。しゃべるし、ちゃんとしてくれへん」と言うが、顔を見るとそれほど怒っているようではなく我慢の限界ではなさそうである。
「みんな苦手なことってあるやろ?(うなずく二人。)C子は野菜が苦手やろ?N男も苦手なことあるよな?それと同じでY男はちゃんとするのが苦手やねん。せなあかんことがわかっててもついついふざけてしまうねん。それでちゃんとしてってきつく言われると余計にちゃんとできなくなってしまうねん。一年生の時と同じでおしゃべりしてるときはちょんちょんしてあげてくれないかなぁ。三回してもだめやったら先生も頑張ってみる。できてないことがあったらここをやるんだよ、とか一緒にやろう、とか声をかけてあげて。先生と二人が優しく話していったらいつかY男も頑張れるようになると思うんだけどなぁ。先生と一緒に頑張ってみてくれないかなぁ。無理やりはしなくてもいいからね。」
二人は一年生の時を思い出して、頑張ってみると応えてくれた。
その後、M男とおしゃべりしていると、ちょんちょんしたり小さい声で注意してくれているが、あまり効果はない。授業中Y男が大声で「先生、何すんの?」と言った時や、「わからん!」と言った時には、C子が優しく教えてくれていた。
国語「かんさつ名人になろう」の学習でのこと。作文が苦手なY男は、「無理!」と言って書かない。絵も描こうとしない。Y男と作文が苦手なⅠ男以外の子どもたちは、順調に観察記録文を仕上げていった。班の子どもたち同士で互いに記録文を読みあい、付箋に書いて評価し合っていく活動の時間、当然Y男とⅠ男は参加できなかった。すると二人がやってきて、「先生、Y男がまだ書けてないから一緒に書いてもいい?」と聞いた。「ありがとう。でも書けなかったらしかたないし、無理やったらいいしな。」と答え、様子を見ていた。案の定Y男はふざけている。やっぱり厳しいかなと思ったが、二人は諦めない。粘り強く「トマトを見てどう思った?」などと聞いてくれている。C子が私のところに来て、「先生、Y男は赤鉛筆しか持たはらへん。もしかしたら赤鉛筆やったら書けるかもしれへんと思うねんけど、赤鉛筆で文書いてもいい?」と聞いてきたのでいいよと伝える。しばらくすると、「先生、Y男絵も描けたで!」と嬉しそうにC子が教えてくれた。見ると赤鉛筆で二行だけ文を書き、絵も描けている。Y男も気持ち嬉しそうな表情に見える。二人がY男にかかわってくれている間、私がⅠ男にかかわり、Ⅰ男も観察記録文を完成することができた。
二人を呼んで、「ありがとう。途中腹立つこともあったかもしれへんけど、二人が優しく手伝ってくれたからY男も書けた。友達に優しくできるってとっても素敵なことやから、これからも誰にでも優しい二人でいてな。」と話す。二人ともいい顔をしていた。授業のまとめで二人の頑張りをクラスでも紹介し、こんな優しさいっぱいのクラスになったらいいねと話した。
話し合い
七月初め、N男が、みんなで円になって給食を食べたいと言ってきたので、B男と一緒に翌日の朝の会で、提案することになった。
「今日の給食をみんなで円になって食べませんか。なぜ円になって食べたいかと言うと、そのほうがみんな楽しく給食を食べられると思うからです。」
班ごとに聞きたいことや意見を考えさせた。
「並び方はどうするんですか?」
などの質問に二人は丁寧に答えていった。全体的に円で食べることに肯定的な雰囲気の中、
「円で食べてもいいですか。」
と、二人が聞いたとき、A男が手を挙げた。
A男・・・自閉傾向があり、こだわりが強い。嫌なことが頭に残りやすい。環境の変化に弱く、移動教室での学習になると異様にテンションが上がり、抑えられなくなる。学力は高いが、相手の気持ちを考えるのは苦手。
「ぼくはな、実はな、円で食べるのが嫌やねん。」
「実はな、ぼくは給食を時間内に食べたいねん。でも円にしたら、落ち着かなくて食べられないかもしれないから円は嫌やねん。」
と言う。
「じゃあA男はどうしたい?」と聞くと、A男は、
「みんなは円になって食べたらいいよ。ぼくは一人で食べるし。」と言う。
周りから「一人はかわいそう。」という声が聞こえてきたので、A男もみんなも安心して給食を食べるにはどうしたらよいか、もう一度班で話し合わせた。
・みんな円になってA男と先生は真ん中で二人で食べる。
・A男のいる 五班だけ班の形にして、ほかの人は円になる。
・A男が安心できるように仲良しの人を隣にする。
などの考えが出た。A男に聞くと、五班だけは班の形なら大丈夫かもという。五班のほかの二人に聞くと、「いいよ。」といってくれたので、A男に、それでいいか確認すると、
「二人は円で食べたいやろ。無理しなくていいよ。」と言うので、同じ班の二人に本当は円で食べたいのか聞くと、「どっちでもいいから、大丈夫!」と言ってくれる。それを聞いてA男も安心したようである。
N男とB男が「五班は班の形で食べて、ほかは円になって食べるでいいですか。」と聞くと、みんなも賛成をし、その日の給食は5班だけ班の形、ほかはみんなで円になって食べることになった。みんな楽しそうに給食を食べていた。その中にA男の安心した顔があった。
第46回京都教育センター研究集会
日時 12月19日(土)・20日(日)
会場 京都教育文化センター
テーマ「戦後年、戦争と平和を考える〜戦争をくぐった生き証人から学ぶ〜」
全体会 12月19日(土)13時〜17時 302号室
開会あいさつ 高垣忠一郎/京都教育センター代表
河口隆洋/京教組委員長
基調報告 京都教育センター事務局
記念講演 「戦争責任をどうとらえるか〜教育の観点から学校の戦争責任を問う〜」
講師/佐藤広美氏(東京家政学院大学教授・教育科学研究会副委員長)
報告 戦争をくぐり、教師として戦後を生きた証人の語り
安井 亨さん(86歳)
京都師範学校の学徒動員で舞鶴海軍工廠へ。45年7月、空襲で九人の学友を失う。
49年より母校で教壇に。丹後と山城で教鞭をとり、「はぐるま研・文芸研」の実践家。
井手小の校長として定年退職。
黒田寿子さん(89歳)
京都女子高等専門学校の学徒動員で島津へ。45年3月、姉宅で神戸大空襲。49年
より明徳高女で教鞭をとりながら劇団活動にも参画。市立北野中で学テ闘争。京教組
婦人部長など専従役員七年。
閉会あいさつ
分科会 12月20日(日)10時〜16時 教文センターの各部屋
※研究会毎に以下の九つの分科会が行われます。
第一分科会 地方教育行政
テーマ 「学校の組織・運営を検証する〜『学校の自主性・自律性確保』はどうなったか?」
報告① 「市立高校における職員会議の状況と課題」
② 「学校における『新しい職』と学校運営」
③ 「京都市教委の学校管理」
第二分科会 生活指導
テーマ 「子どもたちの生きづらさをこえる生活指導・教師の仕事」
報告① 「今じゃなくてもいいよ、甘えていいよ」(小学校)
② 「本音で語り、信じあえる集団づくり」(中学校)
第三分科会 学力・教育課程
テーマ 「国際化時代を生きる学力とは―国際相互理解のために、英語教育と歴史教育に
何が必要か―」
報告① 「中学歴史教科書記述と植民地・戦争認識の関係」
② 「安易な早期教育に未来はあるか」(小学校)
③ 「何のために英語を学ぶのか」(高校)
第四分科会 発達問題
テーマ 「学校・地域で平和を伝え、すべての子ども・青年の豊かな発達を」
報告① 「戦争を語り継ぎ、平和な未来を」(戦争遺跡に平和を学ぶ会)
② 「緊急保護される子どもたち」(児童相談所)③「進路保障と就修学支援のとりくみ」
(高校)
第五分科会 子どもの発達と地域
テーマ 「子どもにとってすべてが育ちの場」
報告 二人の保護者から、学校について思うこと、地域の活動を通じて見えてきたことを
お話いただきます。
第六分科会 家庭教育&民主カ ウンセリング
テーマ 「生き生きとした温かい人間関係をつくるために」
内容 民主的カウンセリング・ワークショップを行います。
第七分科会 高校問題
テーマ 「若者の声から主権者を育てる教育を探る―どうする!18歳選挙権PART2―」
報告① 「若者の声」18歳選挙権について府内の高校生、戦争法制反対の運動に参加した
SEALDs KANSAIの大学生からレポート
② 18歳選挙権に関する実践レポート
第八分科会 教科教育・国語部会
テーマ 「真実のことばを子どもたちに」
報告① 小学校・中学年の作文教育
② 小学校・二年文学教育
③ 高校〜日本・イギリス・アメリカの文章から戦争を考える
第九分科会 京都障害児教育
テーマ(仮)「実践を通して考える『教科別の指導』『教科・領域に分けない指導』」
報告 京都府立特別支援学校及び京都市立総合支援学校より(仮)