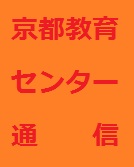
 |
●京都教育センター通信 復刊第101号 (2015.10.10発行) |
国民の安全より原発を優先する「新規制基準」の欺瞞性
市川 章人 高校非常勤講師・日本科学者会議会員)
福島原発事故から四年半、被害も事故も続く中、川内原発の再稼働が強行されました。今、再稼働の法的根拠である新規制基準をはじめ、原子力政策の問題点を具体的に明らかにすることが重要です。
原発においては万が一の危険も許されない
杜甫の詩に「国破れて山河在り」の一節がありますが、原発事故は山河も残しません。原発事故の破滅性・甚大な被害から導かれる結論は、原発においては「万が一の危険も冒してはならない」ということです。これは2014年5月の大飯原発運転差し止め訴訟福井地裁判決においても、生命を基礎とする「人格権」に至高の価値があることと合わせて示された最も重要な見地です。
政府は“原発の重大事故は起きない、放射性物質は5重の壁で閉じ込められ絶対漏れない”として原発を推進してきましたが、福島事故が起きるとこれを反故にしました。原子力規制委員会は「新規制基準は重大事故が発生しうる前提で作られ、対処をしていれば事故は起こらないという従来の考え方を大きく転換した」と言い放ちました。
原発技術そのものが本質的に危険
そもそも原発は異質の危険性をもつ装置です。
第一に、燃料が異質で、運転すれば放射能の強さは一年間で一億倍にもなります。運転を止めても熱の発生が続くため何年もの冷却が必要です。
第二に、エンジンの燃焼室に当たる原子炉内に燃料を入れっ放しにする異質な装置です。短時間での燃料取り出しはできず、事故が起きれば止めることができない特性を備えています。
従来の規制を撤廃した新規制基準
従って原発の再稼働は危険を冒すしかなく、新規制基準は再稼働のために可能なあらゆる手立てを講じる悪質なものになりました。
その典型は、被害の根源である放射性物質の放出を事実上野放しにしたことです。従来、「原子炉立地審査指針」では、事故の際に原発敷地境界での被ばく線量の目安は250mSv以下でなければ稼働できないという規制がありました。しかし再稼働のためにこの規制を廃止しました。
他にも新規制基準には、原子炉本体の改造も重要設備の耐震性強化も求めないなど、安全より再稼働優先の基準が満載です。
被ばく前提の原子力災害対策指針、さらに改悪
避難計画に関する原子力災害対策指針も規制委員会が決めています。
30㎞圏内住民の避難計画は被ばく前提です。
月にさらに改悪し、㎞圏外住民にヨウ素剤を準備するPPA区域を廃止し、30㎞圏外の被ばく回避を個人責任にしました。
京都北部に狙う使用済み核燃料中間貯蔵施設
今、各原発の使用済み核燃料貯蔵プールが満杯に近づいており、再稼働を続けるためには原発敷地外に中間貯蔵施設を作る必要があります。関西電力は多分宮津か舞鶴に建設を狙っています。
これは300トンの核燃料を最長50年貯蔵といいますが、永久貯蔵になる危険性があります。しかし建設を阻止すれば再稼働も困難になります。
★これらの問題について詳しくは、冊子『原発再稼働?どうする放射性廃棄遺物―新規制基準の検証―』(京都自治体問題研究所発行A4版50ページ700円)をぜひご覧ください。
★市川章人・・・京都大学理学部で原子物理学を専攻。府立高校で物理を教え、定年退職後も非常勤講師。「原発問題研究家」として活躍。学力・教育課程研究会事務局長。
教育研究全国集会in宮城 国語分科会レポート
作文を書き、読み合うこと(後半)
京都公立小学校 伊藤 正信
(前号からの続き)
6.作文のパワー
さいこうのともだち B(年三月)
おもしろくしてくれる人、ないている人をなぐさめてくれる人、いろいろあります。
よくあそんでいるのは、つきしまはやたくんともも木さやかちゃんが一ばんよくあそんでる。よく学どうでもあそんでくれる。うれしい。
こたけひろみちゃんは,すなおにきいてくれる。Cくんはふなっしーのモノマネをしてくれる。
かわばたゆうなちゃんは、わたしがないたとき、やさしくなぐさめてくれる。今は,本がかりのリーダーをしている。やさしい。
ゆかちゃんは,しんせつに、してくれる。
みずきじゅんたろうくんは、いつも、きゅうしょくを、おかわりしてくれる。
すきな人がいる。一年一くみの人だけのひみつ。
いとう先生は、みんなのことを、おもってくれる。
みんなやさしい。
一年生の最後の作文でした。読み合うと,Bちゃんはすかさず、
「名前書いてへん人もちょっと書けへんかっただけで、さいこうのともだちやで。」
とか、
「ぜんいんとくべつなともだちです。」
と付け足していました。周りの友達も
「一番なんていいひん。」
と言っていました。こんな風にみんなのことを大切に思いながら一年を終えられたのも,この作文の力でもあると思います。
面白いことに、二年生になって引き続き作文をしていくと、いろんな友達の『さいこうのともだち』という作文が生まれました。
さいこうのともだち G(二年五月)
四月に,図工のとき、つきしまさんとDさんと、Bさんが、G(自分)にずこうするでってゆってくれました。
それでつきしまさんは、紙をもってきてくれて、Bさんはのりとはさみをもってきてくれました。Dさんはえんぴつをもってきてくれました。
図工の授業の日に、休んでいたGちゃん。後日休み時間に作品を仕上げようとすると、三人の友達が作品の仕上げ方を教えてくれたのと同時に、いろいろな道具も用意してくれたのです。とても嬉しい出来事だったんでしょうね。
Dの大せつなともだち D(二年五月)
Dの大せつなともだちは、みんなです。なんでみんなやとおもう? みんなやさしいからみんな大すき 二年一くみのぜんいんともだち。 パパもママもこうまもはなちゃんもみんな大すき 先生も大−−−−−−すきです またねーばいばい。おしまい
7.楽しく読み合いつながり合う
マリオカートずきのあつしと、あつしがおもしろいこと(おとうと)(おもしろい)(かわいい) D(二年一月)
いつもあっしは、おもしろい。なにがおもしろいかというと、いろいろおもしろい。それでいちばんおもしろいのが たとえば それちょこぱんやでーていったら,ちょこぱんちゃうやんかいっていわはるのが むっちゃかわいくておもしろい。それで月日もそのことばをいわはった。ついでにあつしは男の子 あとわたしのおとうとです。むっちゃかわいいです。どこがかわいいかというと( )がかわいいです。それではな子きょう子がじかんわりしてるときマリオカートをしています。それでおねえちやんいっしょにマリオカートしようよ〜っていわはる。それできょう子とはな子がそのコースおわってからなっていう。それでおわった。それで三人か二人でやる。それでしょうぶがきまって それで夜ごはんたべるでーていわはった。それでたべおわって みんなでおふろはいって、みんなであ〜きもちかったっていう。それできがえて、かみのけかわかしてジュースのんで、はみがきがあつしきらいやから いややいややいわはる。それでおわってねました。たまにみんなでいっしょにねます。
まず( )の中に入る言葉を考えると、
・わらっているところ
・顔
・ふく
・食べているところ
・ゲームをしているとき
・あ〜きもちかったって言うところ
・おこっているところ
がかわいい。ということで出てきました。怒っているところもかわいいなんて、素敵です。自分に弟がいるAくんは「りょうた(弟)はこうやっておこらはんねん♪」とかわいい様子を実演してくれます。
さて、正解はなんと「ぜんぶ」がかわいいだったのです。そこで作文からDちゃんがあつしくんのことをかわいいと思っているところを探します。すると、
・チョコパンちゃうやんかい,とつっこむところ
・おねえちゃんいっしょにマリオカートしようよ〜つて言わはるところ
・いややいやや言わはるところ
などが出てきて,「かわいいよな〜♪」とまだ見ぬあつしくんを想像しながらの言葉が。そんな風にDちゃんの作文を通して温かい空気に包まれながら、自分の家族についても見つめる時間をとりました。
・あつしくんは、めっちゃくちゃかわいいんですね。いっかいあつしくんとあいたいです。
・2ばんめのいもうとをたたくと「#△口ox!?*@$★」っていわはる。
へんでおもしろいしかわいい。
・ぼくも、にいにゲームかしてとか、にいにあそぼとかいってくるし、かしたりやったりあそんだりしてる。
・たくみとあそぶのがすき
ぼくはたくみとあそぶのがすきです。キャッチボールや中あてや やきゅうやサッカーやおにごっこやかくれんぼやだたかいごっことかをします。
・わたしはいもうととか弟はいいひんけど、おにいちゃんもおもしろい。へんなマジックをしてくれたり,おもしろいどうがを見せてくれます。
・ママといっしょにしゃべってたらパパがビデオとってきはってやめてって言ってるのにやめてくれやおらへんのがおもしろい。
・おとうとがいていていいなー。いもうとがいていていいなー。おとうといもうとどっちかほしいのにおかあさんがうまへんからじぶんがおとうとやねん????。かなしいわ。
いいなー。 うらやましいなー。いもうとおとうといてていいなー。
自分が弟と。(Cくん)
最後にDちゃんが付け足しがあるということで、
「じつは〜あっしはわたしがおねつをだしたとき、おねえちゃんいっしょにマリオカートする〜?つていう。それがめちゃめちゃかわいい。これからもよろしくね!あつし!」
と書いたものを読んでくれました。
8.一人の子の作文を通して
(紙面の都合で省略)
9.生活を綴ること(作文)
作文は、我々大人が子どもたちを知ることの手助けにもちろんなります。しかし、子ども理解のためだけではなく、もっと子ども目線でその意味を考えてみることが大切なのではないでしょうか。
私が今考える生活を綴ることとは、「自分を知ること」にあたると思います。
人は話をすることで自分の考えがまとまったり、矛盾に気づいたりすると言われます。カウンセリングのような要素が、作文には多分にあるのではないでしょうか。多忙さを極める日々、子どもたち一人一人にしっかり向き合おうと思っても、難しいこともあります。だからこそ一人一人が自分白身に向き合い、自分を知るために、私が今大切にしたいものの一つにこの作文があります。
しっかりと受け止めてくれる相手がいるからこそ、子どもたちもそれだけしっかり自分に向き合います。作文を通して子どもたちとじっくり会話をしていき、子どもたちの心の内を一緒に探っていきたいです。
10.読み合うこと
作文は書いて終わりではなく、読み合うからこそ友達の思いや考えを知り、つながり合うことができます。しかし、そこには共感的に受け止める姿勢が欠かせません。批判的に受け止められては、安心して作文を書くことも、教室で過ごすこともできないでしょう。
聞いてくれているみんなが、「そう思っていたんだね。」と理解してくれるだけでも、何だか認められたような気がします。それ故に、無理に感想は求める必要はなく、ただただ寄り添う気持ちが大切なのだと思います。
*レポートの全文がほしい方は、教育センター までご連絡ください。お届けします。
秋の学習会
京都教育センター・自治体問題研究所合同学習会
日時 11月6日(金18)時30分〜20時30分
会場 京都教育文化センター ホール
テーマ「歴史と京都のまちをまもろう〜まちづくりと学校統廃合と跡地〜」
基調報告/池田豊さん(京都自治体問題研究所事務局長)
シンポジウム
◆コーディネーター/本田久美子さん
◆シンポジスト
研究者から/室崎生子さん(新建築家集団)
学校から/京都市教組
地域から/新日本婦人の会
第46回京都教育センター研究集会
日時 12月19日(土)・20日(日)
会場 京都教育文化センター
テーマ「戦後年、戦争と平和を考える〜戦争をくぐった生き証人から学ぶ〜」
全体会 12月19日(土)13時〜17時 302号室
開会あいさつ 高垣忠一郎/京都教育センター代表
河口隆洋/京教組委員長
基調報告
記念講演 「戦争責任をどうとらえるか〜教育の観点から学校の戦争責任を問う〜」
講師/佐藤広美氏(東京家政学院大学教授・教育科学研究会副委員長)
報告 当時の教師から/当時の子どもの体験から
閉会あいさつ
分科会 12月20日(日)10時〜16時 教文センターの各部屋
第一分科会 地方教育行政研究会
第二分科会 生活指導研究会
第三分科会 学力・教育課程研究会
第四分科会 発達問題研究会
第五分科会 子どもの発達と地域研究会
第六分科会 家庭教育&民主カ ウンセリング研究会
第七分科会 高校問題研究会
第八分科会 教科教育研究会・国語部会
第九分科会 京都障害児教育センター
による 九つの分科会
発達問題研究会《公開研究会》
テーマ:子ども・青年の「発達の芽」を育てるために
◆日時 10月10日(土)13時30分〜16時30分
◆会場 京都教育センター室
◆報告 「広域通信制高校の実態と課題」
報告者:秋山吉則さん(仏教大学大学院・元市高委員長)
「発達課題を持つ子ども・青年の支援に関わって」(学校現場・支援センターから)
学力・教育課程研究会《例会》
◆日時 10月18日(日)13時30分〜16時30分
◆会場 京都教育センター室
◆内容 「公共・道徳は滅私奉公へ、では英語は? 巧みに仕組まれた戦への道」…滋賀の杉浦和彦さんによる教育課程(特に小学校)にかかわる問題提起
学力・教育課程研究会《公開研究会》
テーマ:地域に生きる人々の力がどのように発揮されているか、教育の役割を考える
◆日時 11月15日(日)13時〜
◆会場 京都教育文化センター205号
◆報告 *基調報告:鋒山泰弘さん
*報告/①島貫学さん ②原田久さん
生活指導研究会《公開研究会》
テーマ:子どもたちがかかえる痛みと不安にどう向き合うか
◆日時 10月18日(日13)時30分〜16時30分
◆会場 京都教育文化センター 一階会議室
◆報告 「岩手中二いじめ・自殺を考える」
報告者 倉本頼一さん(立命館大学・滋賀大学非常勤講師)
*実践報告 「T先生の全国教研レポート」(府内小学校)